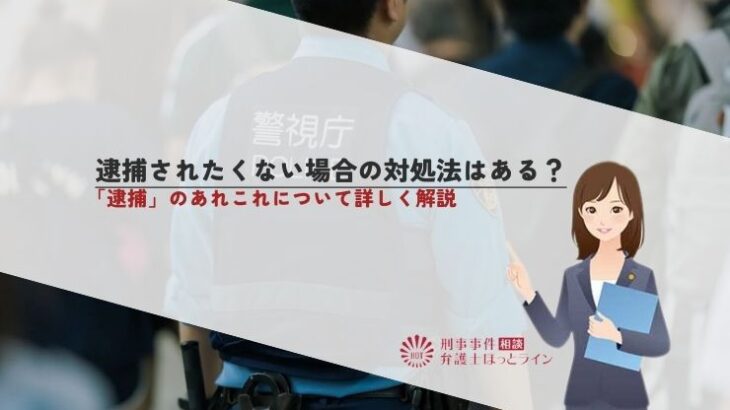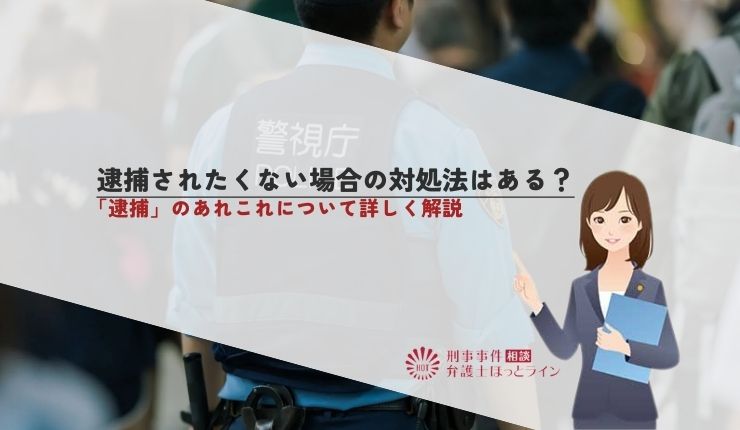
「逮捕」という行為は、罪を犯した疑いのある人の身柄を強制的に拘束するための手続きです。逮捕が認められるためにはいくつかの条件を満たしていなければいけず、満たせていなければ逮捕されることはありません。
この記事では、「逮捕されたくない」と考えている人向けに逮捕を回避できる方法や逮捕された場合であっても、早期に釈放されるためにできることについて解説しています。
罪を犯してしまい、「どうにかして逮捕を回避したい……」と考えている人は、本記事で解説している内容をぜひ参考にしてください。
逮捕とは
逮捕とは、罪を犯した疑いのある人(被疑者)の身柄を強制的に拘束するための手続きです。罪を犯したからと言って、必ずしも逮捕されるわけではなく、幾つかの条件を満たしている必要があります。
まずは、そもそも「逮捕」とは何か?について詳しく解説します。
被疑者の身柄を拘束するための手続き
「罪を犯したら逮捕される」と思われている人が多いのではないでしょうか。実際は、「罪を犯した=逮捕される」わけではありません。
そもそも、「逮捕」という行為は、罪を犯した疑いのある人の身柄を拘束するための手続きを指します。身柄を拘束するというのは、簡単に言ってしまえば「牢屋に閉じ込めておくこと」と考えれば良いです。
逮捕された被疑者(罪を犯した疑いのある人のことを「被疑者」と呼びます)は、警察署内にある留置所と呼ばれる場所に収監されます。留置所は、外から鍵を閉められる場所です。刑務所とは異なりますが、「外から鍵を閉められて部屋から出られない」という点では同じです。
逮捕をされた被疑者は、最長で48時間にわたって留置所の中で生活をしなければいけません。日中は、1日8時間を超えない範囲で事件に関する取り調べを受けます。
もちろん、衣食住に困らない環境ではあるものの、外へ出ることはできず、留置係員と呼ばれる警察官の監視下のもとで生活を送らなければいけません。当然、逮捕されている間は、学校や会社へ行くことはできず、自宅へ帰ることもできません。
逮捕をする目的は、罪を犯した疑いのある人の逃亡や証拠隠滅を回避するためです。そのため、これらの可能性がない被疑者に対しては、原則逮捕は認められていません。
罪を犯しても必ず逮捕されるとは限らない
罪を犯したからと言って、必ずしも逮捕されるとは限りません。多くの人は「罪を犯した=逮捕される」と考えているのではないでしょうか。しかし、そういったことはありません。
逮捕をするためには「逃亡の恐れ」や「証拠隠滅の恐れ」がなければいけないためです。そもそも、逮捕という行為自体、被疑者の身柄を拘束するための手続きです。罪を犯していない可能性がある人の身柄を拘束すること自体、本来であればあってはいけません。
また、最終的に刑事裁判で有罪判決を受けるまで、被疑者は推定無罪の原則に従う必要があるのです。推定無罪の原則とは、刑事裁判で有罪判決が下されるまでは、無罪であると推定されている状態を指します。
そのため、理屈上は無実の人の身柄を拘束している状態となります。このことから、罪を犯したからと言って、すぐに逮捕できるわけではないのです。
とはいえ、連続殺人鬼のように凶悪犯罪を犯している被疑者を野放しにしていれば、新たな被害者を産んでしまう原因にもなり得ます。このことから、推定無罪の人であっても逮捕をする必要があると認められなければ、逮捕をすることはできないのです。
もし、逮捕をする必要がないと判断された被疑者は、在宅捜査という形で捜査を行います。在宅捜査とは、自宅にいながら捜査に協力することです。
たとえば、なんらかの罪を犯した人であっても、逮捕する必要がないと判断されれば、逮捕はされません。つまり、身柄の拘束はされません。しかし、被疑者であることに変わりはないため、警察や検察官からの呼び出しには応じなければいけないのです。
当然、身柄拘束が発生していないため、会社や学校、自宅に帰ることが許されます。しかし、警察や検察からの呼び出しに応じなければ、「逃亡の恐れがある」などと判断されてしまい、結果的に逮捕されてしまう恐れがあります。
上記のことから、「罪を犯してしまったけど逮捕されたくない」と考えている人は、逮捕する必要性がないことを訴え、在宅捜査を目指していくことになります。
なお、以下に該当するような場合は、積極的に逮捕をせずに可能な限り在宅捜査となるような努力がなされます。
- 扶養家族がいる
- 定職があり、勾留が続くことで失職するおそれがある
- 学生である
- 入学試験がある
- 病気を患っている
等
上記の場合に「必ず逮捕されない」というものではありません。あくまでも、犯した罪の内容や過去の前科・前歴等も考慮し、逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れについても判断したうえで最終的に裁判官が決定します。
「逮捕=前科・刑事罰の確定」ではない
万が一逮捕されてしまったとしても、前科や刑事罰が確定しているわけではありません。詳しくは後述しますが、前科が付く条件は「刑事裁判で有罪判決が確定した場合」です。
逮捕をされたとしても、その後に不起訴処分となったり微罪処分となったりして、そもそも刑事裁判を開かれないケースもあります。また、仮に起訴されて刑事裁判を受けたとしても、最終的に無罪となれば刑事罰を受けることもなく、前科もつきません。
逮捕という行為は、証拠隠滅や逃亡の恐れのある被疑者の身柄を拘束するための手続きであり、必ずしも前科や刑事罰が確定しているわけではないことを覚えておきましょう。
逮捕の条件
罪を犯したからといって、誰でも逮捕できるわけではありません。逮捕するためには、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。
罪を犯したと疑うに足りる十分な証拠があること
- 逃亡の恐れがあること
- 証拠隠滅の恐れがあること
- その他逮捕する必要があるとき
次に、逮捕するための条件について詳しく解説します。
罪を犯したと疑うに足りる十分な証拠があること
逮捕をするための大前提として、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる十分な証拠がなければいけません。なぜなら、罪を犯したかどうかわからない人の身柄を拘束するわけにはいかないためです。
もし、罪を犯したと疑うに足りる十分な証拠がない場合は、逮捕せずに任意聴取という形で話を聞き、容疑が固まり次第逮捕状を請求する流れとなります。もし、少しでも罪を犯していない可能性がある場合は、逮捕状を請求することはありません。仮に、逮捕状を請求したとしても裁判官が逮捕状を発布することはないでしょう。
とはいえ、現実的に誤認逮捕が発生してしまっているのも事実です。絶対にあってはいけないため、警察官等の捜査機関や裁判官は証拠等をよく確認したうえで「罪を犯したと疑うに足りる十分な証拠がある」と判断された場合のみ逮捕状が発布され、逮捕されます。
逃亡の恐れがあること
逮捕するためには、被疑者が逃亡をする恐れがあることが条件です。逃亡されて所在がわからなくなってしまえば、罪に問うことができなくなってしまうためです。そのため、逃亡の恐れがある場合は、被疑者の身柄を拘束して取り調べを行うための「逮捕」という行為が必要となります。
たとえば、指名手配犯のようにずっと逃げ回っているような被疑者の場合は、現在進行形で逃亡をしているため、「逃亡の可能性が高い」と判断されてしまいます。
他にも、なかなか罪を認めない被疑者についても、「逃亡の恐れがある」と判断されやすくなってしまいます。なぜなら、たとえば素直に罪を認めて謝罪している被疑者と比較して、罪を犯した証拠があるにも関わらず「何もやっていない」といっている被疑者は、客観的に見ても逃亡の可能性が高いと思われるでしょう。
そもそも、警察等の捜査機関はあなたが罪を犯したと疑うに足りる相当な証拠を揃えているため、「あなたが罪を犯している」という前提で話を進めます。
そういった状況下で被疑者は「何もやっていない」といえば、「この人は何もやっていないと言い、罪を免れようとしている」と考えるのは当然です。そのため、逃亡の恐れがあると判断され、逮捕の要因となるでしょう。
証拠隠滅の恐れがあること
証拠隠滅の恐れがある被疑者についても、逮捕することができます。証拠は、裁判において非常に重要なものとなります。証拠がなければ、たとえ罪を犯したことが明らかであっても罪に問うことができません。
そもそも、日本の刑事裁判では1%でも無実である可能性がある場合は、罪に問うことができません。そのため、被疑者自ら証拠を隠滅してしまうことによって、罪に問うことができなくなる可能性があるのです。
そのため、証拠隠滅の可能性がある被疑者については、身柄を拘束したうえで罪に問うための証拠を隠滅されないようにします。
具体的には、たとえば罪を認めていない被疑者の場合は、証拠隠滅の可能性が高いと判断されます。なぜなら、実際に罪を犯していることを前提に考えると、「罪を犯しているのに否定している=罪を免れたいと考えている」となるためです。
罪を免れたい人は、逃亡を企てたり証拠を隠滅したりして、自分が罪に問われないように動こうとします。そのため、一例を挙げるとすれば、否認している被疑者は逃亡・証拠隠滅の恐れが高いと判断されやすいでしょう。
その他逮捕する必要があるとき
その他に、警察等の捜査機関が逮捕をする必要があると判断した場合は、逮捕されてしまう可能性があります。たとえば、住所が不定である被疑者の場合は、所在がわからなくなる恐れがあるため、逮捕されやすいと言えるでしょう。
上記のようにさまざまな事情を考慮したうえで、逮捕の必要性を考慮したうえで逮捕状の請求をし、裁判官が逮捕状を発布する流れとなります。
逮捕されたくないときの対処法
逮捕されたくない場合は、以下の対処法を検討すると良いでしょう。
- 直ちに弁護士へ相談をする
- 自首・出頭を検討する
- 監督者を定めておく
- 素直に罪を認める
- 被害者と示談交渉を進める
逮捕されたくない場合は、大前提として「逮捕の必要性がないこと」を主張することがとても大切です。逮捕の必要性がないことを主張するためには、逮捕の要件を満たしていないことを証明しなければいけません。
おさらいをすると、逮捕をするためには「証拠隠滅の恐れ」もしくは「逃亡の恐れ」がなければできません。つまり、これらの可能性がないことを証明できれば、逮捕を回避できるということになります。
とはいえ、逮捕の回避方法は絶対ではなく、最終的には裁判官が決定します。そのため、あくまでも可能性のある対処法として、これから解説する内容をぜひ参考にしてください。
直ちに弁護士へ相談をする
まずは、弁護士への相談を検討してください。弁護士へ相談をしたうえで、逮捕の必要がないことを主張していくのです。何度もお伝えしているとおり、「証拠隠滅の恐れ」や「逃亡の恐れ」がなければ逮捕は認められません。
そのため、弁護士へ相談をしたうえで逮捕の必要性がない旨を主張してもらうことが大切です。
なお、刑事事件における弁護士は、「逮捕後」や「勾留確定後もしくは起訴後」に無料で付けられる国選弁護人制度というものがあります。しかし、逮捕を回避したい人は、逮捕前の段階であるため、自分自身で弁護士を選任する必要があります。
自分自身で弁護士を選任した場合は、自分で弁護士費用を支払わなければいけません。また、弁護士へ相談をしたからといって、必ずしも逮捕を回避できるとは限りません。そういった注意事項を踏まえたとしても、まずは弁護士へ相談することを強くおすすめします。
弁護士は法律の専門家であり、刑事事件においても専門家としての知見を強く主張できます。そのため、自分自身で逮捕回避を検討するよりも、弁護士へ相談をして適切な弁護活動を行ってもらうことによって、逮捕回避の可能性は高まります。
自首・出頭を検討する
実際に罪を犯した事実があるのであれば、自首や出頭を検討しましょう。自首や出頭をするということは、前提として「罪を認めている」ということです。
先ほども解説したとおり、罪を認めている被疑者は否認している被疑者と比較して、証拠隠滅や逃亡の可能性が低いと判断されます。結果的に、逮捕を回避できる可能性が高まります。
ただし、自首と出頭は異なる点に注意しましょう。自首・出頭はいずれも、「警察や裁判所に自ら罪を犯したことを申し出ること」を指します。しかし、自首と出頭には大きな違いがあります。
自首は、犯罪が発覚していなかったり犯人がわかっていなかったりする状況で自ら出頭することです。自首の場合は、法律によって減刑が認められています。
一方で、出頭は犯罪が発覚していたり犯人が特定されている状態で出頭した場合のことを指します。出頭の場合は、法律による減刑は認められないものの、「自ら出頭してきた」という事実が良い影響を与え、結果的に減刑されるケースが多いです。
また、自首や出頭をしていることによって、「罪を認めて反省している」と判断されやすくなります。さらに、自首や出頭をしている人の多くは、自ら証拠を提示するケースも多く、結果的に逮捕を回避できる可能性が高まります。
監督者を定めておく
監督者を定めておくことによって、逮捕を回避できる可能性が高まります。監督者とは、罪を犯した人を監督する人を指し、基本的には同居している親や配偶者等がなります。
監督者がいることによって、「逃亡したり証拠隠滅をしたりする可能性が低い」と判断されやすくなり、結果的に「逮捕の必要がない」という判断になり得るでしょう。
なお、親や配偶者といった家族が被疑者を匿っていたとしても、犯人隠避罪や犯人隠匿罪といった罪に問われることはありません。その点は安心して良いでしょう。とはいえ、だからといって罪を犯した人を匿う行為を肯定するわけではなく、自分自身も取り調べの対象となる可能性があるため注意しましょう。
素直に罪を認める
逮捕されたくない場合は、素直に罪を認めましょう。罪を認めることによって、「証拠隠滅」もしくは「逃亡の可能性は低い」と判断されやすくなります。
先ほども解説したとおり、逮捕するためには「証拠隠滅もしくは逃亡の恐れがあること」が条件です。そのため、罪を認めて自ら証拠となるような発言をしたり、物品を提出したりしている場合は、あえて逮捕をする必要はないと判断されやすくなります。結果的に、逮捕を回避できる可能性が高まるでしょう。
とはいえ、罪を認めているからといって必ずしも逮捕を回避できるとは限りません。そもそも、自首や出頭をしていなければ、「逮捕→取り調べ」となるのが一般的です。つまり、初めに逮捕されてから取り調べを行い、罪を認めるという流れになります。そのため、逮捕の回避として有効な手段ではありません。
しかし、軽微な犯罪である場合や逮捕できるほどの証拠が集まっていない場合は、「任意聴取(取り調べ)→逮捕」という流れになるケースがあります。この場合は、初めから罪を認めておくことによって、「逮捕する必要がない」と判断される可能性は高いです。
ただし、罪を認めたからといって必ずしも逮捕を回避できるとは限りません。やはり、犯罪の態様やこれまでの前科・前歴等を考慮したうえで逮捕の必要性を判断されます。
とくに凶悪犯罪である場合や組織犯罪である場合は、証拠隠滅や逃亡の可能性が高いと判断されやすく、逮捕されてしまう可能性が高いので注意しましょう。
被害者と示談交渉を進める
被害者がいる事件の場合、被害者との示談交渉を早めに進めておくことも大切です。そもそも、罪を犯したからといって直ちに逮捕されるとは限りません。まずは任意聴取を行ったり、その他の捜査を行ってから逮捕をするかどうかを判断し、逮捕状の請求→発布というのが一般的な流れです。
もし、罪を認めて素直に償いたいという意思があるのであれば、被害者と早めに示談交渉を進めておくのもひとつの手段です。
被害者と示談交渉が済んでいる場合、被疑者側としては「罪を認めて反省している」という見方ができます。被害者目線で見ると、「被疑者と示談交渉が成立し、今回の事件に関して許している」ということが明らかになります。
そのため、示談が成立している事件であれば、罪を認めている事実があり、被害者も許していることから「あえて逮捕をしたり身柄を拘束したりする必要はない」と判断されやすくなります。
上記のことから、被害者が明らかであり、自分自身でも罪を認めているのであれば、早めに示談交渉を開始しておいたほうが良いでしょう。
なお、示談交渉は弁護士を介して行うのが一般的です。被害者対被疑者で交渉を行おうとすると、なかなかスムーズにはいきません。なぜなら「被害者」という立場と「犯罪加害者」という立場であるためです。
被害者から見ると「加害者が怖い」と感じるのは当然です。加害者にそのようなつもりがなかったとしても、脅しのように捉えられてしまい、「本当は示談をしたくないけど示談を成立させた……」ということがあり得るかもしれません。
そのため、第三者である弁護士が間に入って示談交渉を行い、お互いにとって良い解決案を提案し、和解を目指します。もし、現時点で被害者がわかっており、逮捕を回避したいと考えるのであれば、早めに弁護士へ相談をしたうえで示談交渉を進めていきましょう。
逮捕されたくないときの注意事項
逮捕されたくないときに注意すべきことは以下のとおりです。
- 逮捕状が発布されてからでは遅い
- 逮捕回避方法は絶対ではない
- 重大な犯罪ほど逮捕の可能性は高まる
次に、逮捕されたくないときの注意事項について詳しく解説します。
逮捕状が発布されてからでは遅い
逮捕状が発布された場合は、逮捕されてしまうため注意しましょう。逮捕状が発布されたかどうかは、被疑者本人にはわかりません。そのため、罪を犯した場合は、早めに自首もしくは出頭を検討したほうが良いです。
逮捕状が発布されるということは、警察官等が「逮捕の必要がある」と判断して裁判官へ請求し、裁判官が「逮捕の必要がある」と判断して初めて発布されます。つまり、警察等の捜査機関と裁判官が「逮捕の必要がある」と判断している状況であり、この時点で逮捕を回避することはできません。
逮捕状発布のタイミングや逮捕のタイミングは、被疑者の状況等によっても大きく異なるため一概にはいえません。そのため、できるだけ早めに行動することがとても大切です。
何度もお伝えしているとおり、逮捕状が発布されても被疑者等に通知されることはありません。そのため、逮捕の可能性がある場合は、早めに弁護士へ相談をしたうえで自首や出頭を検討してください。
逮捕回避方法は絶対ではない
先ほど逮捕を回避する方法についていくつか紹介しました。しかし、いずれの方法を行ったとしても、必ず逮捕を回避できるとは限りません。少なからず逮捕をされてしまう可能性があることを覚悟しておきましょう。
そもそも、罪を犯した時点で逮捕の可能性は誰にでもあります。とはいえ、逮捕の条件を満たしていなければ逮捕できないというだけです。
そのため、「そもそも逮捕の条件を満たしていない」「逮捕をする必要がない」ということを主張していく必要があります。被疑者自身が罪を認めて反省していたとしても、その旨を伝えて逮捕を回避するのは難しいでしょう。
上記のことから、まずは弁護士へ相談をしたうえで「逮捕の必要性がない」ということを主張していくことが効率的です。ただし、弁護士へ相談をしたとしても絶対に逮捕を回避できるものではないため覚えておきましょう。
重大な犯罪ほど逮捕の可能性は高まる
基本的に、逮捕の条件を満たしていなければ、たとえ殺人犯であっても逮捕をしたうえで身柄拘束することはできません。しかし、重大な罪を犯している人は、逮捕の可能性が高まるのが現実です。
なぜなら、たとえば連続殺人鬼を例に取ると、逮捕をせずに在宅捜査となってしまえば、遅かれ早かれ自分自身が逮捕されてしまうことが明らかとなっています。そういった状況下で野放しになっていれば、殺人に使った道具を隠滅したり、新たな被害者を発生させたりすることが考えられます。
上記のことから「逮捕の必要がある」と判断されやすく、結果的に逮捕されるケースが多くなるのです。とはいえ、建前上は「逮捕の条件」を満たしていなければ、逮捕はできません。
組織犯罪・共犯者がいる場合は逮捕の可能性が高まる
組織犯罪や共犯者がいる場合は、逃亡や証拠隠滅の恐れが高いと判断されやすく、結果的に逮捕される可能性が高まります。たとえば、詐欺や暴力団の犯罪の場合です。
詐欺容疑で逮捕された場合は、組織壊滅につながる重要な手がかりを持っていることも多く、逮捕をしたうえで可能な限りの情報を聞き出そうとします。たとえば、詐欺で逮捕をせずに在宅捜査をしていた場合は、組織の上のほうから連絡があり、「何も言うな」などと言われてしまう可能性が高いです。
結果的に犯罪の重要な証拠を得られなくなってしまう可能性もあるため、逮捕する可能性が高まります。そのため、組織犯罪や共犯者がいる場合は、逮捕回避の対処法をすべて行ったとしても、回避は難しいでしょう。
逮捕の種類とは
「逮捕」と呼ばれる行為には、以下の3種類があります。
- 現行犯逮捕
- 通常逮捕
- 緊急逮捕
いずれの場合も「逮捕」であることに変わりはなく、その後の手続きにも差異はありません。しかし、逮捕をするための条件が大きく異なります。次に、逮捕の種類について詳しく解説します。
通常逮捕
通常逮捕とは、令状の発布に基づいて逮捕することを指します。警察等の捜査機関が捜査を進めて逮捕状を請求し、裁判官が内容を確認したうえで逮捕状を発布し、その後に被疑者を逮捕することです。通常逮捕は、他の逮捕と比較して一般的な逮捕手段であると言えます。
裁判官から逮捕状が発布される前後で逮捕の対象となる被疑者の生活サイクルを確認し、逮捕するタイミングを伺います。
そのため、被疑者からすると「ある日突然、逮捕状を持った警察官が現れ、逮捕された」ということになるでしょう。通常逮捕する場合は、逮捕状を被疑者にしっかりと見せたうえで罪の内容を告知したり、逮捕の理由を説明したりする必要があります。
現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、犯罪を行っている最中もしくは直後であり、誰がどのような犯罪を犯したか明らかである場合に認められている逮捕方法です。「現行犯」とは、「現に犯罪を行った」という意味です。
現行犯逮捕は、通常逮捕に必要となる逮捕状の請求が必要ありません。なぜなら、現行犯(犯罪の行為中もしくは直後)であり、誰がどのような犯行を犯したか明らかとなっているためです。つまり、「罪を犯したと疑うに足りる十分な証拠がある」ということです。上記のことから、現行犯の場合は逮捕状が必要ありません。
たとえば、電車内で痴漢を行った人が周囲にいた人に取り押さえられた場合、現行犯逮捕(私人逮捕)できます。なぜなら、その人が痴漢を行ったことが明らかであり、痴漢行為は立派な犯罪であるためです。
私人逮捕とは、逮捕権を有していない一般の人でも逮捕できることを言います。私人逮捕が認められるためには、現行犯であることや軽微な犯罪の場合は罪を犯した者が身分を明かしていないことなど、いくつかの条件を満たしている必要があります。
緊急逮捕
緊急逮捕とは、緊急を要する場合に限って裁判官の発布する逮捕状がなくても逮捕できる方法を指します。
逮捕という行為は、人の身柄を強制的に拘束するための手続きであるため、憲法によって「事前に裁判官の発布する逮捕状を提示したうえで逮捕をしなければいけない」と定められています。
しかし、緊急を要する場合は逮捕状がなくても逮捕することができます。これを「緊急逮捕」と呼びます。緊急逮捕は、たとえば指名手配犯のようにすぐにでも逮捕しなければ逃げられてしまうようなケースに認められています。
現時点で逃亡している指名手配犯の場合、「ある日突然街中で発見した」ということもあるでしょう。この場合、いちいち裁判官に逮捕状を請求してから発布されるのを待っていれば、また取り逃してしまう可能性があります。
通常、逮捕状を請求してから発布されるまでには、半日程度の時間がかかってしまうためです。尾行をしていたとしても、気付かれて逃げてしまう恐れもあるでしょう。そのため、このようなケースでは「緊急性がある」と判断され、緊急逮捕が認められています。
ただし、緊急逮捕するためには「遅滞なく逮捕状を請求して発布すること」が条件です。取り急ぎ逮捕することはできるものの、すぐに逮捕状を請求しなければいけないということです。
なお、緊急逮捕するためには以下の条件を満たしている必要があります。
- 一定の重大犯罪であること
- 罪を犯したと疑うに足りる十分な証拠があること
- 急速を有し、裁判官に逮捕状を求めることができない場合
以上の3つです。一定の重大犯罪とは、法定刑が「死刑もしくは無期懲役または3年以上の有懲役・禁錮」に該当する犯罪を指します。殺人罪や強盗罪、詐欺罪や窃盗罪といったさまざまな犯罪が該当します。
罪を犯したと疑うに足りる十分な証拠とは、通常逮捕や現行犯逮捕と同様です。逮捕という行為は、強制的に人の身柄を拘束するための手続きであるため、必ず罪を犯したと疑うに足りる十分な証拠があることが条件です。
たとえば、指名手配犯の場合は現時点で逮捕状が発布されています。しかし、指名手配犯はどこにいるか所在がわからないため、すべての警察官が常に逮捕状を持っているわけではありません。とはいえ、「罪を犯したことが明らか」であるため逮捕可能です。
急速を有し、裁判官に逮捕状を求めることができない場合とは、すぐにでも逮捕しなければ証拠を隠滅されたり、逃亡したりする恐れがある場合を指します。この場合は、緊急逮捕の条件を満たしていることになります。
上記すべての条件をすべて満たしている場合に限って、緊急逮捕が可能なのです。逮捕は、人の身柄を強制的に拘束するための手続きであるため、基本的には逮捕状の発布および提示が必要です。しかし、緊急逮捕と現行犯逮捕に限っては、例外であることを覚えておきましょう。
逮捕の前兆
逮捕は、ある日突然行われます。もし、逮捕することが被疑者に知られていた場合、逃亡したり証拠隠滅を図ったりされてしまう恐れがあるためです。しかし、逮捕前には以下の前兆があることもあるため、覚えておくと良いでしょう。
- 自宅周辺の下見
- 家宅捜索に来た
- 警察からの連絡
次に、逮捕前の前兆について詳しく解説します。
自宅周辺の下見
通常逮捕の場合、タイミングを伺うために被疑者が住んでいる場所の近くで張り込み捜査を行います。なぜなら、被疑者の生活サイクルを把握し、確実にいるタイミングを見計らって逮捕をするためです。
そのため、普段見かけない車が自宅近くに停まっていたり、捜査員らしき人がいる場合であって、逮捕に心当たりがある場合は逮捕間近であることを覚悟しましょう。ただし、張り込み捜査が行われているからといって、必ずしも逮捕されるとは限りません。
逮捕以外にも家宅捜索や任意聴取などさまざまな事情で話を伺いにくるケースがあるためです。しかし、もしも心当たりがあるのであれば、逮捕される可能性を覚悟しておいたほうが良いです。
なお、早めに弁護士へ相談をしたうえで、逮捕後のアドバイス等を確認する方法を検討しても良いでしょう。
家宅捜索に来た
逮捕をする前に警察等の捜査機関が、家宅捜索に来る場合があります。家宅捜索とは、裁判官が発行する「家宅捜索差押許可状(いわゆるガサ状)」に基づいて強制的に自宅等を捜査・差押をすることを指します。
たとえば、何らかの罪を犯した疑いのある人の自宅の中を強制的に捜査し、犯罪の証拠となるようなものを押収するとしましょう。その後、一般的には任意聴取をしたうえでその後の処分等が決定します。
また、家宅捜索と同時に逮捕状が発布されている場合もそのまま逮捕されます。もし、家宅捜索時点で逮捕状が発布されていなければ、逮捕されない可能性もあるでしょう。しかし、家宅捜索を行った結果、証拠が集まり、任意聴取中に逮捕状を請求・発布してそのまま逮捕というケースもあります。
そのため、家宅捜索が行われた場合は、そのまま逮捕されてしまう可能性があることを覚えておきましょう。
警察からの連絡
現在任意聴取されている場合や捜査対象となっており、携帯番号等を知られている場合は、警察から直接連絡が来ることがあります。この場合、あくまでも任意聴取という形であり、「〇〇の事件について聞きたいことがあるので出頭してもらえますか?」のように言われます。
当然、任意であるため必ずしも応じる必要はありません。しかし、何度も呼び出しを受けても応じなければ、「逃走の恐れがある」と判断されて逮捕される恐れがあるため注意しなければいけません。
そして、仮に任意聴取に出頭をしたとしても、任意聴取の家庭で容疑が固まればそのまま「逮捕状請求→逮捕状発布→逮捕」となることもあります。
任意聴取であり、その日のうちに逮捕状が発布されていなければ、一度は自宅へ帰ることができます。その後逮捕状が発布されれば逮捕、逮捕状が発布されなければ在宅捜査となるでしょう。
ただし、警察から連絡があった場合は、逮捕の可能性があることを覚えておいたほうが良いでしょう。
逮捕後の流れ
逮捕されたくない人は、さまざまな対策を講じて逮捕回避を目指します。しかし、必ずしも逮捕を回避できるわけではなく、捜査機関や裁判官が「逮捕の必要がある」と判断すれば、嫌でも逮捕されてしまいます。
もし、回避できずに逮捕されてしまった場合、その後はどのような流れで事件は進んでいくのか?と不安や疑問を抱えている人も多いでしょう。逮捕をされたとしてもその後に早期に釈放される可能性もあるため、そこを目指していくのもひとつの手段です。
次に、逮捕されてしまった場合の流れについて詳しく解説します。
逮捕
本記事で何度もお伝えしているとおり、逮捕という行為は「被疑者の身柄を強制的に拘束するための手続き」です。そのため、逮捕された場合はそのまま警察署内にある留置所と呼ばれる場所に収容されます。
逮捕によって身柄拘束が可能となる期間は、「逮捕から48時間以内」です。つまり、逮捕による効力は48時間しか継続しないということです。
48時間の間は、留置所と呼ばれる場所に収容されたうえで事件について取り調べを受けます。取り調べは、原則1日8時間を超えない範囲でなければいけないと定められています。
警察も時間に制限があるため、短い時間内で被疑者から事件について詳しく聞き出すために努力をすることでしょう。一方で被疑者には「黙秘権」という権利があるため、言いたくないことは言わなくても良いです。ここまでが「逮捕」という手続きによって生じる効力です。
事件の送致
逮捕された被疑者は、48時間以内に検察官へ事件を送致されます。原則、すべての事件について送致する必要があり、これが「全件送致の原則」です。
そして、逮捕された被疑者をそのまま送致することを「身柄付送致」と呼びます。身柄付送致された被疑者の場合は、引き続き被疑者の身柄を拘束する必要があるかどうかを検察官が判断します。検察官が勾留の必要性を判断をする時間は24時間以内と定められています。
つまり、この間で最長逮捕から72時間(3日間)経過しており、その間は当然に自宅へ帰ることができないため、社会的な影響も発生してくるでしょう。
なお、逮捕された被疑者であっても検察官が「引き続き身柄拘束をする必要がない」と判断した場合は、即時釈放されます。その後は、在宅捜査となり、自宅にいながら警察や検察官の呼び出しには応じ、取り調べに応じていく流れとなります。
そして、引き続き勾留(身柄拘束)をするためには、逮捕時同様の条件が必要です。たとえば、証拠隠滅の恐れがある、逃亡の恐れがあるといった理由がなければいけません。
そのため、逮捕された人であってもすぐに釈放を目指したい場合は、素直に罪を認めて証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを主張していくことが大切でしょう。
勾留請求の判断
事件が送致され次第、検察官は24時間以内に引き続き被疑者の身柄を拘束するかどうかを判断します。勾留の必要がないと判断されれば、即時釈放しなければいけません。
もし、引き続き勾留する必要があると判断された場合は、裁判官に対して「勾留請求」というものを行います。勾留請求が行われた場合は、被疑者を連れて裁判所へ行き、勾留質問を経て勾留の必要性を裁判官が判断します。
勾留が認められた場合は、初めに10日間の身柄拘束が可能となります。さらに勾留延長されるのが一般的であり、+10日、合計で20日間の身柄拘束となり、逮捕時からで考えると23日間もの間、身柄拘束が行われることになるでしょう。
当然、自宅へ戻ることができないため、学校へ行けない、会社へ行けないといったことによるさまざまなリスクが発生します。なお、勾留期間中は引き続き留置所と呼ばれる場所に収容され、検察官等からの取り調べに応じる必要があります。
起訴・不起訴の判断
勾留されている被疑者の場合は、勾留期間中に起訴するか不起訴とするかを判断します。不起訴となった場合は、即時釈放されて事件は終了します。
起訴は「正式起訴」と「略式起訴」の2種類があり、正式起訴は通常通り刑事裁判を開いて判決が確定する流れです。略式起訴とは、100万円以下の罰金に対してのみ行うことのできる起訴方法であり、略式命令が言い渡されて納付することによって事件は終了します。
刑事裁判が開かれないため、被疑者にとってはデメリットとなり得ることもあるため、弁護人とよく話し合ったうえで決定すると良いでしょう。
そして、起訴された被疑者は引き続き身柄拘束が続きます。期間に定めがなく、刑事裁判で判決が確定するまでです。ただし、起訴された被疑者の場合、保釈請求を行うことができます。
保釈請求とは、保釈金を支払って一時的に社会へ戻ることを請求することです。必ずしも保釈請求が認められるとは限らないものの、認められれば一時的に戻って来れるため検討する余地はあるでしょう。
刑事裁判
正式起訴された場合は、刑事裁判が開かれます。刑事裁判にて罰金刑が確定すれば罰金を支払って終了します。懲役刑や禁錮刑といった自由刑であれば、一定期間刑務所に収容されて刑期をまっとうして終了します。生命刑であれば、自分の死をもって罪を償わなければいけません。
逮捕されたくない場合によくある質問
逮捕されたくない場合によくある質問を紹介します。
Q.逮捕されたら学校や職場、家族へ連絡が行きますか?
A.ケースバイケースです。
逮捕されたからといって、学校や職場、家族等へ連絡をする義務はありません。しかし、被疑者自身が希望をした場合は連絡をするのが一般的です。
また、公務員である場合や大企業に勤務しているような人である場合は、逮捕されて突然連絡を取れなくなったり出社しなかったりして混乱を招く恐れがあります。そのため、こういった場合は警察から連絡をする場合があります。他にも裁判官が必要があると判断した場合は、連絡をすることがあるでしょう。
いずれにせよ、逮捕によって数日間自宅へ帰れなくなってしまうため、警察等に依頼をしたうえで逮捕された旨を伝えておくのが賢明でしょう。
Q.未成年でも逮捕される可能性はありますか?
A.当然逮捕の可能性はあります。
未成年者が起こした犯罪の場合、14歳以上であれば逮捕の可能性があります。しかし、14歳未満の者が起こした事件の場合は、逮捕されることはありません。なぜなら、14歳未満の者を処罰することができないためです。
なお、14歳未満の者であっても歩道をしたうえで児童相談所へ連絡し、身柄拘束と同様のことが起こり得ます。当然、自宅へ帰ることはできなくなってしまうため、「逮捕されないから大丈夫」などと思わないようにしましょう。
Q.逮捕されなければ、今後罪に問われることはありませんか?
A.逮捕されなくても罪に問われる可能性があります。
逮捕とは、逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがある被疑者の身柄を強制的に拘束するための手続きです。そのため、逃亡や証拠隠滅の恐れがないなど、逮捕する必要がないと判断された場合は、逮捕せずに在宅捜査となります。
在宅捜査であっても、正式起訴されれば刑事裁判を受けなければいけません。刑事裁判の結果、懲役刑等が確定すれば、当然刑務所に収容されます。そのため、逮捕されなかったからといって、罪に問われないといったことはありません。
Q.逮捕されるとどのような影響が発生しますか?
A.さまざまな影響が発生すると考えられます。
具体的にどういった影響が出るかは状況次第で異なるでしょう。しかし、以下のような可能性があることを覚えておきましょう。
- 長期勾留リスク
- 社会的リスク
- 前科・前歴が残るリスク
逮捕されることによって長期間の身柄拘束が発生する可能性があります。当然、学校や会社へ行くことはできません。留置所や拘置所、刑務所といった外から鍵を閉められる場所で生活をしなければいけません。
そして、長期勾留によって学校へ行くことができない、会社へ行くことができないといったリスクが生じます。結果的に、退学処分となったり解雇処分となったりする可能性があります。
社会復帰を目指すうえでも、逮捕された事実が尾を引いてさまざまな弊害・リスクとなり得るでしょう。
逮捕された場合、前歴が残ります。前歴とは「犯罪被疑者として捜査対象となった」という事実です。前歴が残ることによって、今後新たに事件を起こした場合に厳しい処分が言い渡される可能性が高まります。
そして、最終的に有罪判決が下された場合は、前科が残ります。前科が残ることによって、就職に影響を与えたり、海外に行くことが難しくなったり、一定の職業に就くことができなくなったりします。他にも、状況次第ではさまざまなリスクが考えられるでしょう。
Q.逮捕されたら解雇されたり退学になったりしますか?
A.必ずしも解雇・退学となるとは限りません。
逮捕されたからといって、解雇や退学となるとは限らず、会社や学校によって異なります。
そもそも「会社」と「学校」を別々で考える必要があります。会社の場合は、社内規則に従う必要があるものの、それ以上に法律が強いです。法律では、逮捕された事実のみで直ちに解雇することは認められていません。
社会的な影響等を考慮して妥当性を主張しなければ解雇することはできません。よって、逮捕した事実のみで直ちに解雇されるとは考えにくいでしょう。しかし、たとえば業務上横領罪で逮捕されたなど、会社に大きな損失を与えている場合は解雇となるでしょう。つまり、ケースバイケースです。
学校は学校の規則に従う必要があります。秩序を乱すような行為があった場合など、会社と比較して退学処分は下しやすい傾向です。
そもそも、会社は「働いてお金を得る場所」です。働き口をなくしてしまえば、生活を送ることも難しくなってしまいます。そのため、労働者は法律によって守られているのです。
まとめ
今回は、逮捕されたくない場合の対処法について解説しました。
逮捕を確実に回避する方法はないものの、逮捕の必要性がないことを主張することによって回避できる可能性があります。逮捕するためには「逃亡の恐れ」もしくは「証拠隠滅の恐れ」あるいはその他逮捕の必要性があることが条件です。
上記いずれもないことを主張するためには、まずは弁護士へ相談をしたうえで「逮捕の必要性がない」という事実を主張していかなければいけません。逮捕された場合は当番弁護人、勾留・起訴された場合は国選弁護人を選任することはできるものの、タイミングは遅いです。
そのため、実費ではあるものの、私選弁護人を選任したうえで逮捕の回避を目指していくことを検討しましょう。なお、逮捕された場合であっても勾留を回避できたり保釈請求を認めさせたりすることができるため、検討してみてはいかがでしょうか。