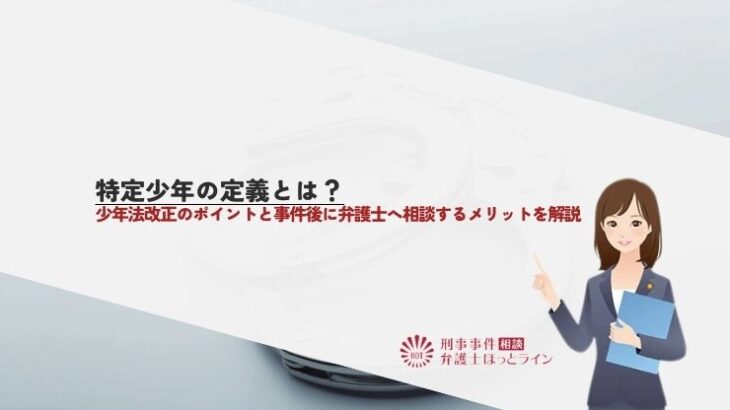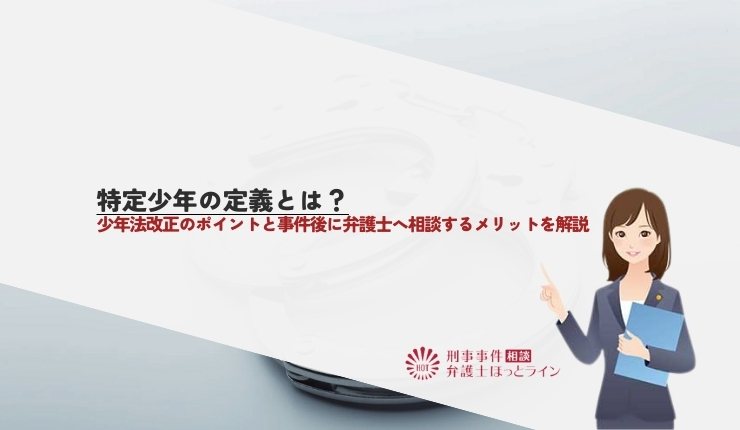
2022年(令和4年)4月1日に施行された改正少年法では「特定少年」の概念が新設されました。
特定少年は、「犯罪行為に及んだ18歳、19歳の少年」と定義されます。民法で成人年齢が引き下げられたこととのバランスをとる目的で新設されました。18歳、19歳の少年は成人とは違って少年法が適用されますが、18歳未満の少年よりは成熟しているため、いくつかの特別なルールが制定されます。
そこで、この記事では、18歳、19歳の子どもが事件を起こして不安を感じているご家族や、今般の少年法改正について知りたいと考えている方のために、以下の事項について分かりやすく解説します。
- 特定少年の定義
- 特定少年に関する少年法の改正ポイント
- 特定少年に適用される手続きの流れ
- 特定少年が事件を起こしたときに生じる可能性があるデメリット
- 特定少年が事件を起こしたときに弁護士へ相談するメリット
少年事件・刑事事件は、手続きの初期段階から丁寧に防御活動をおこなわなければ、想像以上に不利な処分を下されかねません。当サイトでは少年事件・刑事事件の実績豊富な弁護士を多数紹介しているので、できるだけ早いタイミングで信頼できる専門家までお問い合わせください。
目次
特定少年の定義とは
まずは、少年法の改正によって導入された「特定少年」の概念や、少年法の改正ポイントについて解説します。
特定少年とは罪を犯した18歳、19歳のこと
特定少年とは、「犯罪行為に及んだ18歳、19歳」のことです。
18歳、19歳の特定少年については、17歳以下の少年とは異なる取り扱いがされるものの、少年法が適用されます。
特定少年は少年法改正で新設された概念
2022年(令和4年)4月1日、改正少年法が施行されました。これは、同年同日に民法が改正されて、成人年齢が18歳に引き下げられたことの影響です。
従来、民法では20歳未満が未成年と扱われていました。ところが、18歳以上の年齢ならある程度の分析力・決定力がありますし、現実社会でも数多くの人が就労をしているのが実情です。このような年齢層の人材について、「未成年者」という理由だけでさまざまな権利上の制約を課すのは適切ではないといえるでしょう。
そこで、2022年4月1日に民法が大幅改正されて、18歳まで成人年齢が引き下げられました。これによって、私法上は18歳未満が未成年者として法的にさまざまな制約を受けて、18歳以上は完全な成人と扱われるようになりました。結果として、18歳、19歳の若者の自己決定権が尊重されて、積極的な社会参加が促進されてします。
ここで注意を要するのが、少年法との関係です。というのも、少年法は20歳未満の「少年」に適用されるものだからです。つまり、改正民法によって、私法上は成人と扱われる18歳、19歳が、刑事法制上は「少年」に位置づけられるということです。
もっとも、少年法が20歳未満に適用されるのは、この年齢に至るまでの少年には未熟なところがあり、成人に適用される刑事手続き以外の方法での更生・教育サポートが必要だと考えられているからです。ということは、民法改正によって私法上は成人と扱われることになった18歳、19歳であったとしても、刑事法制上はあくまでも少年の未熟成に配慮したケアが必要だといえるでしょう。
そこで、民法改正に合わせたタイミングで少年法が改正されて、18歳、19歳が「特定少年」と位置付けられて、20歳以上の成人とも18歳未満の少年とも違うルールが適用されるに至りました。
特定少年に関する少年法改正のポイント
少年法の改正によって、18歳、19歳は「特定少年」に分類されるようになりました。民法上は成年と扱われる年齢層ですが、あくまでも刑事事件の領域では少年法が適用されます。ただし、今般の改正では、特定少年に適用される制度に一定の改正が加えられました。
2022年(令和4年)4月1日に施行された特定少年に関する少年法の主な改正ポイントは以下のとおりです。
- 原則逆送対象事件の拡大
- 実名報道(推知報道)の解禁
- 家庭裁判所の保護処分に関する特例
- 刑事事件の特例
原則逆送対象事件の拡大
今般の少年法改正では、特定少年について適用される原則逆送対象事件の範囲が拡大されています。
原則逆送事件とは、家庭裁判所が検察官送致の判断を下すことが原則とされている一定範囲の少年事件のことです。本来、少年事件はその未成熟性などを考慮したうえで家庭裁判所が保護処分などを終局的判断として下すものですが、悪質性・凶悪性が高いタイプの事件類型については、事件が家庭裁判所から検察官に送致されて(逆送)、成人と同じ刑事手続きでさまざまな審理がおこなわれます。
まず、原則逆送事件については以下のようなルールが設定されています(少年法第20条第2項)。
(検察官への送致)
第二十条 家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。
出典:少年法 | e-Gov法令検索
つまり、改正前の少年法及び改正少年法における16歳、17歳の少年については、「16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合」が原則逆送事件として扱われます。
そして、改正少年法では、特定少年のみに適用される原則逆送事件の範囲が以下のものまで拡大されました(少年法第62条第2項)。
(検察官への送致についての特例)
第六十二条 家庭裁判所は、特定少年(十八歳以上の少年をいう。以下同じ。)に係る事件については、第二十条の規定にかかわらず、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、特定少年に係る次に掲げる事件については、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。
一 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るもの
二 死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であつて、その罪を犯すとき特定少年に係るもの(前号に該当するものを除く。)
出典:少年法 | e-Gov法令検索
つまり、特定少年については、「16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合」「死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪を犯した場合」が原則逆送対象事件と扱われるということです。
たとえば、殺人罪、強盗罪、強盗致死傷罪、不同意性交等罪、現住建造物等放火罪などが適用される犯罪行為に及んだときには、検察官送致の処分が下されて、刑事裁判にかけられることになります。
実名報道(推知報道)の解禁
原則として、少年が犯罪に及んで家庭裁判所の審判に付されたり公訴提起されたりしたとしても、氏名、年齢、職業、住居、容貌などによって少年の身分を推知することができるような記事・写真を新聞紙などの出版物に掲載することは禁止されています(少年法第61条)。
この点について、今般の少年法改正では、特定少年については実名報道禁止の原則が以下のように修正されました(少年法第68条)。
第六十八条 第六十一条の規定は、特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合における同条の記事又は写真については、適用しない。ただし、当該罪に係る事件について刑事訴訟法第四百六十一条の請求がされた場合(同法第四百六十三条第一項若しくは第二項又は第四百六十八条第二項の規定により通常の規定に従い審判をすることとなつた場合を除く。)は、この限りでない。
出典:少年法 | e-Gov法令検索
つまり、特定少年が罪を犯して公訴提起された場合(家庭裁判所から逆送されて起訴された場合)、実名報道の対象になるということです。
ただし、略式起訴(略式命令・略式裁判)されたケースについては、従来どおり実名報道禁止の原則が適用されます。
家庭裁判所の保護処分に関する特例
特定少年について家庭裁判所が少年審判において保護処分を下すときには、犯情の軽重を考慮したうえで相当な限度を超えない範囲で、以下の決定をしなければいけません(少年法第64条)。
- 6か月の保護観察所の保護観察に付すること
- 2年の保護観察所の保護観察に付すること
- 少年院に送致すること(3年の範囲内で)
刑事事件の特例
特定少年が起こした事件について、少年審判において検察官送致の判断が下されたときには、以下の刑事事件に関する特例は原則として適用されません(少年法第67条)。
特定少年が刑事事件を起こしたときの手続きの流れ
特定少年が犯罪行為に及んだことが発覚したとき、以下のような手続きの流れを経るのが一般的です。
- 警察が捜査活動を展開する(逮捕される可能性もある)
- 微罪処分の対象にならない限り、事件が検察官に送致されて捜査活動が実施される(逮捕・勾留される可能性もある)
- 検察官が少年事件を家庭裁判所に送致する
- 家庭裁判所で少年審判が開かれる
- 家庭裁判所が少年に対する処分内容を決定する(保護処分、検察官送致処分など)
- 家庭裁判所が検察官送致処分を決定した場合、検察官が事件を引き継いで捜査活動を展開する
- 検察官が公訴提起するか否かを判断する
- 検察官が起訴処分を下した場合、特定少年が起こした事件は公開の刑事裁判にかけられる
以下では、特定少年に適用される手続きのポイント・特徴を解説します。
特定少年が事件を起こすと逮捕・勾留されるリスクがある
特定少年が事件を起こしたときには、成人と同じように逮捕・勾留される可能性があります。
逮捕されたときには72時間以内、勾留されたときには10日間以内(再交流によりさらに10日間)、刑事施設に身柄が押さえられた状態で強制的に取り調べなどを受けなければいけません。
ここで注意を要するのが、特定少年には「検察官は、少年の被疑事件においては、やむを得ない場合でなければ、裁判官に対して、勾留を請求することはできない。(少年法第43条第3項)」の規定が適用されないという点です(少年法第67条第1項)。つまり、特定少年は、17歳未満の少年が刑事訴追されたケースよりも勾留されるリスクが高いということです。また、特定少年には「分離収容ルール」が適用されないので、逮捕・勾留期間中は20歳以上の成人と同じ施設に収容される可能性があります。
逮捕・勾留されると一定期間社会から完全に隔離された状態が発生するので、学校生活などのさまざまな面に支障が生じかねません。ですから、特定少年が逮捕されたときには、身柄拘束自体を回避して在宅事件処理を目指すこと、身柄拘束期間を短縮化することが重要だといえるでしょう。
特定少年が事件を起こすと家庭裁判所に全件送致される
特定少年に限らず、少年が起こした事件について検察官が捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると判断されるときには、全ての事件が家庭裁判所に送致されます。また、犯罪の嫌疑がないと判断できる事案であったとしても、家庭裁判所の審判に付すべき理由があると考えられるときには、検察官は家庭裁判所に送致をして、家裁の判断を仰がなければいけません(少年法第42条)。これを「全件送致」と呼びます。
犯罪行為に及んだ少年に対する処分内容を決定するときには、教育的・矯正的・福祉的な視点が必要です。ところが、通常の刑事手続きでは少年の環境や性格を汲んだうえでの教育的なケアを施すことができません。そのため、特定少年を含む少年事件はすべて一度は家庭裁判所に送致をしたうえで、各少年に適した処分を下すという運用がとられています。
特定少年に対する処分は家庭裁判所が決定するのが原則
特定少年が事件を起こして家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所が少年審判で特定少年に対する処分内容を決定します。
少年審判で下される処分の種類として以下のものが挙げられます。
- 保護観察:保護観察官や保護司から適宜生活や交友関係などについて指導・監督を受けながら家庭などで日常生活を送る保護処分のこと。
- 少年院送致:少年院に収容して矯正教育を受けさせる保護処分のこと。再非行のリスクが高かったり、社会内での更生が難しいと判断される場合に下される。
- 児童自立支援施設等送致:日常生活ではなく児童自立指導施設などの開放的な施設での生活指導が相当と判断される場合に下される保護処分のこと。比較的低年齢の少年や家庭環境などに問題を抱えている少年に対して下されることが多い。
- 検察官送致:家庭裁判所から検察官に送致(逆送)される処分のこと。少年法に規定される原則逆送対象事件に加えて、少年の非行歴・心身の成熟度・性格・事件の内容などを総合的に考慮した結果、刑事裁判による処罰が相当と判断される事件が含まれる。
- 知事または児童相談所長送致:児童福祉機関の指導を受けながら更生を目指すのが相当と判断される場合に下される処分のこと。
- 不処分、審判不開始
家庭裁判所の少年審判では、少年本人が起こした犯罪の悪質性だけではなく、犯行に至った動機、学校や日常生活での様子、生活環境、交友関係などの諸般の事情が総合的に考慮されます。少年院送致や児童自立支援施設等送致、検察官送致などの重い処分を下されると社会生活から隔離される期間が生じるので、保護観察のような比較的軽い処分を獲得するために早期に弁護士の力を借りるべきでしょう。
家庭裁判所が検察官送致の判断を下すと成人と同じ刑事手続きが適用される
家庭裁判所の少年審判で「検察官送致」の判断が下されると、特定少年が起こした事件はふたたび検察官に送致されます(逆送)。
検察官は、家庭裁判所から送致を受けた事件について、公訴を提起するに足りるだけの犯罪の嫌疑があると判断できるときには、必ず起訴処分を下して、特定少年に関する事件を刑事裁判にかけなければいけません。その一方で、犯罪の嫌疑がない場合、犯罪の情状などに影響を及ぼすべき新たな事情が発見された場合、検察官送致後の情況によって訴追が不相当と判断される場合には、不起訴処分を下すことができます(少年法第45条第5号)。
特定少年に関する刑事裁判は成人と同じ形式で実施されて、有罪判決が確定すると、成人と同じように懲役刑などに処されます。また、有罪判決を受けると前科がつくので、今後の社会生活にさまざまな支障が生じることになります。
特定少年が事件を起こしたときに生じる可能性があるデメリット5つ
特定少年が事件を起こして捜査対象になったときに生じるデメリットについて解説します。
手続きが進行している間に身柄拘束される可能性がある
特定少年が事件を起こしたことが発覚すると、一定期間身柄拘束されるリスクに晒されます。
たとえば、逮捕されると「72時間以内」、勾留されたときには「10日間~20日間」の範囲で強制的に身柄拘束されたうえで取り調べを受けなければいけません。また、鑑定留置された場合には「数か月程度」、社会生活から隔離された状態が発生します。
捜査機関などに身柄拘束されている間は、学校生活・社会生活から完全に遮断されてしまいます。拘束期間が長期化すると仕事や進学などに支障が生じかねないでしょう。
最終的に重い刑事罰や保護処分が下される可能性がある
特定少年が事件を起こすと、重い処分が下される可能性があります。
たとえば、少年審判で少年院送致の決定が下されると、収容期間中は厳しい教育訓練を受けなければいけませんし、収容期間中は学校に通ったり仕事をすることもできません。また、悪質な犯罪を起こした事案では、逆送されて成人と同じように刑事裁判にかけられて、懲役刑・禁錮刑などの重い刑事罰を下される可能性があります。
「特定少年はあくまでも少年法が適用されるから厳しい処分は下されない」というのは間違いなので、特定少年段階で事件を起こしたケースでも、できるだけ早いタイミングで弁護士へ相談をして、少年院送致や逆送回避を目指した防御活動を展開してもらいましょう。
前科がつくリスクに晒される
事件を起こした特定少年に対して少年審判で検察官送致の判断が下されると、前科がつく可能性が極めて高まります。
前科とは、有罪判決を下された経歴のことです。日本の刑事裁判の有罪率は極めて高いので、逆送された結果、検察官が起訴処分の判断を下して刑事裁判にかけられることが決定した時点で、事実上有罪判決が下されることが決まってしまいます。特定少年に関する刑事裁判では、非行に及んだ経緯や家庭環境・交友関係などの諸般の事情が考慮されるものの、成人と同じように、刑事裁判で無罪判決を獲得するのは難しいでしょう。
そして、前科がつくと、今後の人生は以下のようなデメリットに悩まされ続けます。
- 前科情報は履歴書の賞罰欄に記載しなければいけないので、就職活動・転職活動の難易度が高くなる(前科を隠して入社したことが発覚すると懲戒処分の対象になる)
- ビザやパスポートの発給制限がかかる可能性があり、海外旅行・海外出張に支障が生じかねない
- 前科は法定離婚事由に該当するため、配偶者から離婚を求められると拒絶できない(親権・養育費・慰謝料などの諸条件も不利に扱われる可能性が高い)
- 前科が理由で就業できない資格・職種がある(士業、金融業界、警備員など)
なお、前科がつくのは「有罪判決が確定したとき」なので、少年院送致などの保護処分が下されただけでは前科はつきません。
これに対して、「有罪判決」は無罪判決以外の全ての判断が含まれるので、懲役刑・禁錮刑だけではなく、罰金刑や執行猶予付き判決も前科として扱われる点に注意が必要です。
実名報道されるリスクが生じる
今般の少年法改正では、特定少年が逆送されて公訴提起された場合の推知報道が解禁されました(略式起訴を除く)。つまり、18歳、19歳の特定少年が起訴されるとテレビやネットニュースで実名報道がされる可能性があるということです。
実名報道されると特定少年が事件を起こした事実と身元が世間に公開されますし、インターネット上に当該情報が半永久的に残ってしまいます。身近な人に刑事事件を起こしたことがバレるだけではなく、新しい交友関係や学歴・職歴を築く際にも悪影響が生じかねないでしょう。
特定少年の家族にも迷惑がかかる可能性がある
特定少年に限ったことではありませんが、ある人物が刑事事件を起こすと、その家族・親族や知人などにも迷惑がかかる可能性があります。
たとえば、特定少年が事件を起こした噂が広がるだけで、親や兄弟も職場や学校で冷たい視線を向けられかねません。場合によっては、今の職場や学校に居辛くなって退職・退学や引っ越しを余儀なくされることもあるでしょう。また、特定少年の事件が実名報道されるに至ると、知人などにもマスコミが押し寄せて迷惑がかかる可能性があります。
このように、特定少年の非行が刑事事件化して周囲に発覚すると、関係者にも迷惑がかかってしまいます。ですから、特定少年が事件を起こしたときには、できるだけ早いタイミングで弁護士の力を借りて、刑事事件化の防止を目的とした防御活動を展開してもらうべきだといえるでしょう。
特定少年が事件を起こしたときに弁護士へ相談するメリット5つ
特定少年が刑事事件を起こしたときには、できるだけ早いタイミングで弁護士へ相談することをおすすめします。
というのも、少年事件・刑事事件を得意とする弁護士の力を借りることで、以下のメリットを得られるからです。
- 早期に被害者との示談交渉に着手してくれる
- 身柄拘束処分の回避・短縮化を目指してくれる
- 軽い刑事処分・保護処分などの獲得を目指してくれる
- 実名報道のリスクを軽減してくれる
- 社会復帰や更生に向けたアドバイスを提供してくれる
被害者側との示談交渉を円滑に進めてくれる
刑事事件を起こしたときには、できるだけ早いタイミングで被害者との間で示談交渉を開始する必要があります。
示談とは、刑事事件・少年事件の加害者・被害者間で紛争の解決方法について合意形成を目指す民事的な交渉のことです。たとえば、「加害者が被害者に対して一定額の慰謝料・損害賠償金を支払う代わりに、被害届を取り下げる」などの和解条件が盛り込まれることが多いです。また、被害者側が警察に被害申告をする前の段階なら、示談契約の締結によって刑事事件化自体を回避することも可能です。さらに、「被害者との間で示談が成立していること」「刑事事件について被害者の処罰感情がないこと」という要素は刑事処分の内容を決定する際に考慮される要因なので、示談成立によって軽い刑事処分(保護観察や起訴猶予処分)を獲得できる可能性が高まります。
ところが、少年事件・刑事事件が発生したケースでは、被害者側が加害者側と直接話し合いの場を設けることを嫌うことが少なくありません。怒りや恐怖心、不安感を抱いている被害者側からすると、加害者側と直接やり取りをするのを避けたいと思うのは当然のことです。
刑事事件や少年事件を得意とする弁護士に示談交渉を依頼すれば、感情的になっている犯罪被害者との間でも冷静な話し合いを期待できます。また、被害者側からの過大な要求にも粛々と対応してくれるので、相場と乖離した示談金を請求される事態も防ぐことができるでしょう。
身柄拘束処分の回避や拘束期間の短縮化を目指してくれる
特定少年の事件が捜査機関に発覚したときに意識するべきポイントのひとつが「身柄拘束期間」についてです。というのも、身柄拘束期間が発生したり長期化したりすると、周囲に事件を起こしたことがバレたり社会生活に支障が出る可能性が高まったりするからです。
刑事事件・少年事件を得意とする弁護士に相談・依頼をすれば、逮捕・勾留されないための効果的なアドバイスを期待できるでしょう。
少しでも軽い処分内容獲得を目指してくれる
特定少年が事件を起こして捜査対象になったときには、できるだけ軽い処分獲得を目指した防御活動が不可欠です。
まずは、特定少年の事件は家庭裁判所に全件送致されるのが原則なので、「いかに少年審判で有利な判断を獲得できるか」がポイントになります。少年院送致や検察官送致の判断が下されると一定期間社会生活から断絶された状態が発生することを踏まえると、審判不開始や保護観察を目指すのが合理的な戦略といえるでしょう。
次に、少年審判で検察官送致の判断が下されたときには、「起訴猶予処分を獲得すること」「執行猶予付き判決や罰金刑を獲得して実刑判決を回避すること」が防御目標になります。
そして、このような有利な処分内容を獲得するには、特定少年が置かれた状況や捜査活動の進捗状況などを総合的に分析したうえで、警察や検察で実施される取り調べへの対応方法・供述内容、少年審判で実施される質疑応答への対応に工夫を凝らす必要があります。少年事件・刑事事件を得意とする弁護士に相談・依頼をすれば、特定少年本人や家族へのアドバイスを通じて有利な処分内容獲得の可能性を高めてくれるでしょう。
実名報道によるリスク軽減を目指してくれる
一定範囲で特定少年に関する推知報道が解禁されたため、18歳、19歳が逆送されて公訴提起された場合には、ニュース報道などのリスクに晒されてしまいます。
一度でも実名報道されると社会復帰の難易度が格段に高くなるため、弁護士はさまざまな方法で実名報道回避を目指して尽力します。たとえば、少年審判で検察官送致の判断回避を目指した防御活動を展開したり、少年の社会復帰・更生のために実名報道を自粛するように報道機関に働きかけたりしてくれます。
特定少年の社会復帰や更生に必要なサポートをしてくれる
事件を起こした特定少年が本当の意味での社会復帰を達成するには、少年審判や刑事裁判で軽い処分を獲得するだけではなく、生活環境や交友関係、仕事などの面でのサポートが欠かせません。
少年事件・刑事事件を得意とする弁護士に相談すれば、提携しているNPO法人や非行歴のある少年を受け入れている企業などに紹介してくれたり、家族とも丁寧に話し合いをしながら少年の更生に役立つ施策などについてアドバイスを提供してくれたりするでしょう。
特定少年が犯罪行為に及んだときには少年事件を得意とする弁護士へ相談しよう
今般の少年法改正では、「特定少年」の概念が新設されて、原則逆送対象事件の範囲が拡大されたり、実名報道が解禁されたりしました。その結果、特定少年が事件を起こしたときには、18歳未満の少年よりも厳しい処分・手続きを強いられるリスクがあります。
ですから、特定少年が刑事訴追された場合、事案の状況を踏まえた効果的な防御活動が不可欠です。当サイトでは特定少年の弁護経験豊富な専門家を多数紹介しているので、未成年者の子どもが何かしらの非行に及んだときには、できるだけ早いタイミングで信頼できる弁護士までお問い合わせください。