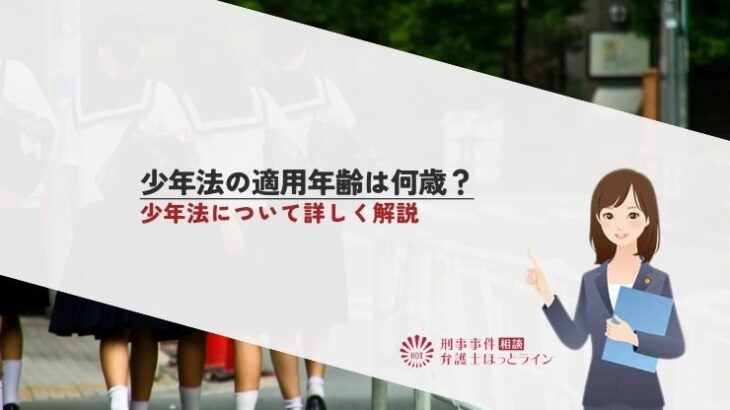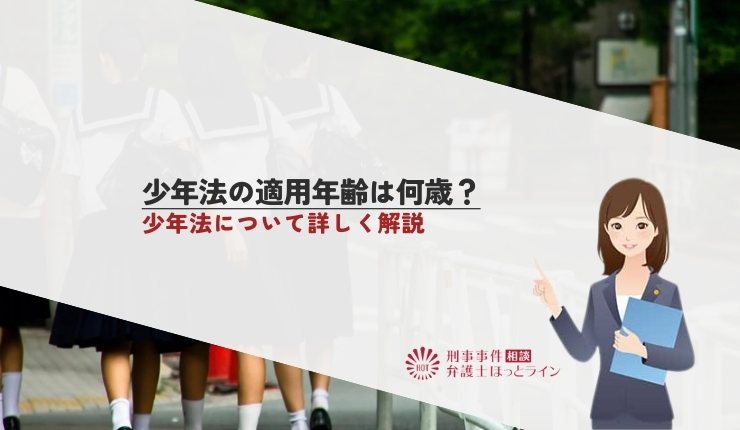
少年法の適用年齢は、基本的には20歳未満の少年です。少年法の適用を受けることによって、減刑されたり保護処分が下されたりなど、大人と比較して甘い処分が下されるケースが多いです。
凶悪な少年犯罪が増える中、「本当に少年法は必要なのか?」と思われている人も多いでしょう。また、中には「20歳未満の少年だから何をしても良い」と考えている人がいるかもしれません。
この記事では、少年法とは何か?少年法の適用年齢にある人が罪を犯すとどうなるのか?について詳しく解説しています。少年法について詳しく知りたい人は、本記事を参考にしてください。
目次
少年法とは
少年法とは、少年が犯罪や非行を行った場合に矯正をするために、特別な措置を講じることを指します。大人が犯罪を犯した場合は刑事罰を与えるのが一般的です。これは「罰」です。
一方で、少年については「罰」を与えるのではなく、矯正・更生を促すために何らかの特別な措置を講じます。
まずは、少年法とは何か?や、少年法の目的、必要性、処遇について詳しく解説します。少年法について詳しく知りたい人は、本記事を参考にしてください。
少年が起こした刑事事件についての処罰について定めた法律
少年法は、少年が起こした刑事事件について処罰を定めた法律です。刑事事件における少年の定義は、20歳未満の者です。ただし、20歳未満であっても処罰が異なるケースがあります。具体的には以下のとおりです。
| 14歳未満 | 触法少年 |
| 14歳以上18歳未満 | 犯罪少年 |
| 18歳・19歳 | 犯罪少年(特定少年) |
まず、触法少年とは14歳未満の少年を指します。触法少年が犯罪を犯した場合は、刑事罰を受けることはありません。14歳以上の場合は、刑事罰を受ける可能性はありますが、大人とは別の手続きで事件が進んでいきます。
そして、18歳および19歳も犯罪少年に該当しますが、原則として大人(20歳以上)と同じ扱いを受けます。
少年が事件を犯した場合は、大人のように刑事裁判を受けずに、まずは「審判」というものを受けます。これが大人と少年の大きな違いです。審判に付される少年については、少年法に以下のとおり定められています。
- 罪を犯した少年
- 14歳未満の少年のうち、刑罰法令に触れる行為を行った
- 保護者の正当な監督に服しない
- 正当な理由がなく家庭に寄りつかない
- 犯罪性のある人もしくは不道徳な人と交際している
- 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖
まず、何らかの罪を犯した少年は、少年法に従って家庭裁判所にて審判を受けます。また、14歳未満の少年については、刑事罰を受けることはないため、家庭裁判所で審判を受けることとなります。いずれも「何らかの犯罪を犯した少年」であることが前提です。
そして、他にも保護者の正当な監督に服しない、正当な理由がなく家庭に寄り付かないなどのいわゆる「非行行為」を行っていた場合も審判を受けます。
大人であれば、上記のような非行行為によって処罰されることはありません。しかし、少年の健全な育成を目的としている少年法では、上記のような内容によっても審判を受ける可能性があるため注意しましょう。
なお、少年であっても、少年本人の自立状況などを考慮したうえで非行行為に該当するかどうかが決定します。たとえば、18歳・19歳の少年が一人暮らしをしていたとしても非行行為には該当しません。
しかし、14歳未満の中学生が家に寄り付かないで深夜徘徊を繰り返している場合は、非行行為として処罰されます。
審判は大人で言う裁判と同じです。審判は家庭裁判所で行われ、これまでの非行事実や事件内容を考慮したうえで、どういった処分を下すことで更生を促せるかを判断して処分が言い渡されます。
少年法の目的
少年法の目的は、少年の健全な育成を図ることです。少年犯罪については、その重大性を鑑みて、時には刑事罰を与えることも必要ではあるものの、基本的には処罰ではなく、更生を促すための矯正等を検討すべきという考え方です。これを「保護主義」と呼びます。
14歳以上の少年については、刑事罰を受ける可能性があります。しかし、罪を犯したからといって直ちに刑事罰を確定させるのではなく、保護の可能性等を模索し、これまでの生活環境、背景等を考慮したうえで決定することを目的にしています。
先にも解説したとおり、少年法は悪魔でも「少年の健全な育成を図ること」を目的としているため、上記のような主義を取り入れています。
少年法の必要性
少年は、1人で生活をすることが難しく、基本的には監護者(親等)と共に生活を送ります。そのため、生まれ持った家庭環境等の影響を受けやすいです。
そのため、少年法という法律によって保護し、必要な矯正等を行うことによって更生を促すことを目的としています。生まれ持った家庭環境や周辺環境によっては何らかの罪を犯したり、非行行為を行ったりしてしまった少年に対して、直ちに刑事罰を与えるのは酷です。
そのため、まずは保護主義のもとで保護をしたうえで、更生を目指しましょう。という目的があるのです。少年の健全な育成を図るうえでとても大切な法律であると言えます。
とはいえ、少年犯罪が凶悪化する中で、「少年法は必要ない」との見方があるのも事実です。少年法によって凶悪犯罪であっても減刑されたり、刑事罰に問われなかったりするのも事実です。このことにより、不安を感じている人も少なくはないでしょう。
しかし、少年法によって救われている少年がいるのも事実です。同じことを繰り返す少年に対しては、その状況を鑑みて厳しい処分を与えるなど、さまざまな方法が取られています。
また、18歳・19歳の少年に対しては、特定少年として原則大人と同じく処罰されることとなっています。これは、2022年に法改正した少年法によるものです。今後もさまざまな少年犯罪を考慮したうえで改正が行われていくこともあるでしょう。
少年法による処遇
犯罪少年および触法少年、虞犯(ぐはん)少年(罪を犯す恐れがある少年)の処遇については、少年法によって定められています。基本的には、家庭裁判所での調査を受けて鑑別所へ入所し、家庭裁判所の審判で処分が決定する流れです。
実際、どのような流れで事件が進んでいくのか?については、少年の状況や事件の内容によって異なります。詳しい処遇・流れについては後述していますので、ぜひ参考にしてください。
少年法の適用を受けられる年齢
少年法の適用を受けられる年齢は、20歳未満の少年です。ただし、18歳・19歳は特定少年となるため、大人と同様の扱いを受ける可能性があります。また、14歳未満の少年については、刑事罰を受けることはありません。次に、少年法の適用を受けられる年齢について詳しく解説します。
基本的には20歳未満の者
少年法は、20歳未満の少年に対してのみ適用される法律です。年齢の基準は、罪を犯した時点で20歳未満かどうかで判断されます。たとえば、19歳で罪を犯し、20歳になったときに逮捕された場合は少年法の適用を受けます。
18歳・19歳は特定少年に該当
18歳および19歳は、特定少年に該当します。基本的に、20歳未満の者は少年として扱われるため、これまで同様に18歳・19歳の者も少年法の適用を受けます。
そのため、基本的に特定少年が罪を犯したとしても、まずは家庭裁判所へ送致されて処分が決定する流れです。ただし、原則逆送される対象事件の拡大や逆走決定後は、20歳以上のものと同じ扱いを受けるなど、特定少年に関する法律が変わりました。
逆送とは、検察官へ事件を送致して大人同様の裁判を受ける手続きのことを指します。逆送された場合は、大人同様に刑事裁判を行って刑事罰が下されます。
特定少年における逆送対象事件は「死刑もしくは無期懲役、1年以上の懲役・禁錮刑に当たる罪」が追加されています。また、特定少年が逆送された場合は、報道機関の判断で実名報道が可能になりました。
14歳未満は刑事罰を受けない
14歳未満の者は、罪を犯しても刑事罰を受けません。極端なことを言うと、14歳未満の少年が殺人事件を起こしたとしても、刑事罰に問うことはできないのです。
ただし、何らお咎めがないわけではなく、児童相談所に保護されたうえで家庭裁判所へ送致され、何らかの処分(少年院送致等)が決まります。その後、更生を目指す流れとなります。
【触法少年】少年法適用年齢の者が罪を犯した場合
14歳未満の少年のうち、刑罰法令に抵触する行為を行った少年を「触法少年」と呼びます。先ほども解説したとおり、触法少年は刑事罰を受けることはありません。つまり、逮捕されることもありません。
とはいえ、14歳未満の少年は何をしても良いのか?何らお咎めなしなのか?といえば、そうではありません。
では、どのような流れで事件が進んでいくのでしょうか。まずは、触法少年が罪を犯した場合の流れについて詳しく解説します。
警察による調査
触法少年が犯罪を犯したり、非行行為を行ったりした場合、初めに警察に補導されるケースが多いです。触法少年が逮捕されることはないものの、犯罪が発生した場合の初動は警察が対応するケースが大半であるため、初めは「補導」という形で調査が行われます。
警察による調査は、あくまでも任意による調査です。事件の内容や動機、交友関係等、事件に関することのみならず関係のないことも詳しく話を聞きます。
簡単に言えば、これまでどのような環境で生活してきたのかを把握し、触法少年が犯罪行為や非行を行わないようにするためには、どうすれば良いのか?について確認をします。
児童相談所への通告もしくは家庭裁判所送致
次に、犯罪事実や非行事実が認められる場合は、警察から児童相談所もしくは家庭裁判所へ送致します。
児童相談所は、少年の状況に応じて必要な福祉上の援助を行うためにあります。触法少年をいきなり家庭裁判所へ送致するよりも、まずは福祉上の援助が必要であると判断された場合は、児童相談所へ送致されます。
児童相談所へ送致された場合は、児童相談所にて一時保護されます。一時保護とは、とりあえず児童相談所の中で生活を送って、少年にとってどのような環境が福祉上最適なのかを調査します。
その後、監護者やその他の環境の元で更生を見込めると認められた場合は、自宅へ帰ることができます。
ただ、犯罪の内容によって矯正が必要であると判断された場合は、家庭裁判所へ送致される流れです。また、警察から児童相談所を介さずに家庭裁判所へ送致されるケースもあるため覚えておきましょう。
審判・審判不開始の決定
家庭裁判所送致が決定した場合、初めに審判を受けるか観護措置を行うか決定します。審判不開始となった場合は、その時点で終了します。
審判の開始が決定された場合は、審判が行われて処分が決定する流れです。その前に、証拠隠滅や逃亡の恐れがあると判断された場合、その他必要があると判断された場合は、観護措置の決定がなされます。
観護措置決定を受けると、少年鑑別所と呼ばれる場所に収監されて調査が行われます。少年鑑別所は、外から鍵のかけられる場所であり、刑務所に近い場所であると考えておけば良いでしょう。
ただ、刑務所とは違い、刑罰を与える場所ではありません。当然、刑務作業を行うわけでもありません。面会や運動の時間を除いて、部屋の中で1人もしくは複数人で過ごすこととなります。
保護処分
その後、審判が行われます。審判では、不処分もしくは何らかの処分が決定します。不処分は、いわゆる無罪判決のようなものです。犯罪事実や非行事実がなかった場合は、不処分となります。
そのため、大半のケースで何らかの処分が下されます。処分は、少年院送致や児童自立支援施設送致、保護観察処分や試験観察処分などさまざまです。触法少年は、検察官送致(逆送)はありません。そのため、何らかの保護処分が下されると思っておきましょう。
【犯罪少年】少年法適用年齢の者が罪を犯した場合
14歳以上の少年が犯罪を犯した場合は、犯罪少年として処分を受けます。大まかな流れは、触法少年と同様ですが、細かい部分で違いがあります。次に、14歳以上の犯罪少年の処遇について解説しますので、参考にしてください。
逮捕・調査
触法少年同様、初動として警察による調査が行われます。大半のケースで補導という形ですが、14歳以上の場合は刑事罰を受ける可能性があるため、逮捕されてしまう可能性がある点に注意が必要です。
逮捕された場合は、48時間以内の身柄拘束が行われます。この間は、当然自宅へ帰ることはできません。学校へ行くこともできないため注意しましょう。その後、勾留された場合は最長で20日間の身柄拘束(勾留)が認められます。
家裁送致・検察官送致
事件の内容によって、家庭裁判所送致もしくは検察官送致となります。家庭裁判所送致となった場合は、触法少年同様に審判の開始・不開始および観護措置の決定がなされます。
検察官送致となった場合は、大人同様に刑事裁判を受けることとなります。ただし、少年法の規定により、原則、家庭裁判所に送致されます。相当悪質なケースである場合や、少年の年齢、環境等を総合的に判断してどちら絵へ送致するか決定する流れです。
なお、検察官へ送致された場合であっても、家庭裁判所へ戻される可能性もあります。家庭裁判所へ戻された場合は、何らかの保護処分が下されると思っておきましょう。
保護処分の決定・逆送
家庭裁判所へ送致された場合は、少年鑑別所で観護措置を受け、最終的に審判を受けます。審判の開始が決定された場合は、下された処分に応じて対応します。少年院送致であれば、一定期間少年院へ入院しなければいけません。
ただし、何度もお伝えしているとおり、14歳以上は刑事罰を受ける可能性があります。保護処分ではなく刑事罰が相当であると判断された場合は、検察官へ事件を送致(逆送)します。
逆送となった場合は、大人と同様に刑事裁判を受けます。刑事裁判を受け、刑事罰を受けることとなります。懲役刑となった場合は、少年刑務所へ収監されますが、16歳未満の者は少年院への入院です。
なお、少年法により刑法の規定による刑事罰が下されるわけではありません。将来性等を考慮し、不定期刑が科されるケースが多いです。
逆送された場合は刑事裁判を受ける
逆送された場合は、刑事裁判を受けます。本来、少年に対しては「更生」を促すための保護措置が行われます。しかし、犯罪の内容次第で刑事処分を与えることが相当であると判断された場合は、逆送となるため注意しましょう。
【特定少年】少年法適用年齢の者が罪を犯した場合
18歳および19歳の少年は、特定少年と呼ばれます。しかし、基本的には犯罪少年と同じ内容で事件が進んでいきます。次に、特定少年が罪を犯した場合の流れについても詳しく解説します。
基本的には犯罪少年と同じ
特定少年が罪を犯した場合も、基本的には犯罪少年と同じ流れで事件が進んでいきます。逮捕もしくは補導され、その後家庭裁判所送致もしくは検察官送致となります。家庭裁判所に送致された場合は、審判の開始・不開始決定がなされ、審判にて何らかの処分が決定する流れです。
犯罪少年と特定少年の大きな違いとは
犯罪少年と特定少年の大きな違いは、逆送対象となる犯罪の種類です。犯罪少年は、家庭裁判所への送致が原則です。しかし、特定少年の場合は、多くの事件で逆送対象となります。
また、逆送された場合には、報道機関の判断で実名報道が可能となった点も大きな違いです。民法改正により18歳以上は成人です。そのため、少年法も改正され、より厳しく処罰される可能性が高まっているため注意しましょう。
少年法適用年齢に関するよくある質問
少年法適用年齢に関するよくある質問を紹介します。
Q.少年法の適用を受けるタイミングは犯罪を犯したときですか?罰せられるときですか?
A.基本的には「罪を犯したときの年齢」で判断されます。
少年法の適用を受ける年齢は、基本的には「罪を犯したときの年齢」で判断されます。たとえば、あと1カ月で14歳になる少年が殺人事件を起こした場合、刑事罰を受けることはありません。
ただし、注意しなければいけないのは「年齢切迫」にある人です。年齢切迫とは、主にもうすぐ20歳を迎える19歳の者を指します。
19歳であるため、基本的には家庭裁判所で事件を処理します。しかし、少年法では、審判の時点で20歳になっている場合は、逆送しなければいけません。
たとえば、19歳のときに事件を起こし、観護措置を経て審判を受けるとしましょう。審判の時点で20歳に達している場合は、逆送となり大人と同じく刑事裁判を受けなければいけません。たとえ、19歳のときに犯した犯罪であっても、刑事罰を受けるため注意しましょう。
Q.なぜ少年法があるのですか?必要ですか?
A.少年を守るために少年法があります。
少年法は、少年の健全な育成を図るためにある法律です。少年は、さまざまな環境の影響を受けやすく、流されやすい側面を持っています。少年1人で良し悪しを判断する能力は乏しく、周辺の人の影響を受けやすいのです。
たった一度の過ちで人生を棒に振ってしまうようなことがあってはいけません。そのため、さまざまな事情を考慮したうえで、矯正し、更生を促すことを目的としています。
一般の人からすると「少年とはいえ大人だ」と思うかもしれません。しかし、さまざまな少年がいる中で、少年法に救われている少年も少なくはありません。少年の凶悪犯罪が増える今、必要のない法律であるとの見方もありますが、必要な法律であることに変わりはありません。
Q.死刑になる可能性があるのは何歳以上ですか?
A.犯行時の年齢で18歳以上です。
犯行時点の年齢で18歳以上の少年は死刑になります。つまり、18歳未満の者がどれだけ重たい罪を犯したとしても、死刑になることはありません。18歳未満の少年が死刑に値する罪を犯した場合は、無期懲役刑が科されます。
Q.少年法適用年齢は引き下げられないのですか?
A.現在、引き下げに関することは決まっていません。
少年法は、現在20歳未満の少年を対象にしています。しかし、民法上の成人年齢は18歳であり、少年法引き下げの声も多くあります。
しかし、現在は20歳未満のままです。とはいえ、18歳および19歳は特定少年として扱われます。大人同様に裁かれるケースも増えてきているため、今後、少年法適用年齢引き下げの可能性もゼロではないでしょう。
Q.14歳未満の触法少年が連続殺人を行った場合はどうなりますか?
A.何らかの保護処分が下されることになるでしょう。
本記事で解説しているとおり、14歳未満の少年が刑事罰を受けることはありません。あくまでも何らかの保護処分が下されます。
少年の生い立ちや家庭環境等によって下される保護処分の種類は異なりますが、少年院送致や児童自立支援施設送致等、何らかの矯正施設への入所となる可能性が高いでしょう。
まとめ
今回は少年法の適用年齢について解説しました。
少年法の適用年齢は、基本的には20歳未満です。20歳未満の者が罪を犯した場合は、少年法によって保護処分となるケースが多いです。ただし、14歳以上の少年が罪を犯した場合は、刑事罰を受ける可能性があるため注意しなければいけません。
「少年だから何をしても良い」というわけではなく、何らかの保護処分や刑事罰を受ける可能性があることを覚えておきましょう。
もし、不安なことがある場合や少年が罪を犯して罪に問われている場合は、まずは弁護士への相談を検討されてみてはいかがでしょうか。