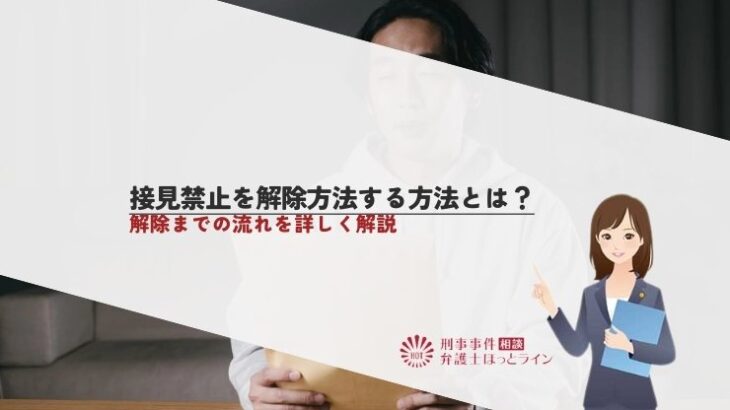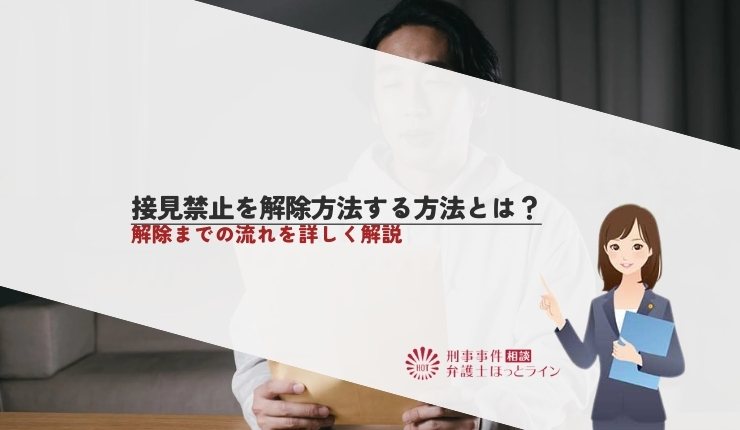
接見禁止とは、勾留されている被疑者が家族等との面会や手紙のやり取りを禁止されることです。突然逮捕されて家族や本人もさまざまな不安を抱えていることでしょう。
すぐにでも接見禁止を解除し、早期に接見を実現して少しでも不安を解消したいと考えているのではないでしょうか。この記事では、接見禁止を解除するための方法について詳しく解説しています。接見禁止解除について知りたい人は、本記事を参考にしてください。
接見禁止とは
接見禁止とは、その名の通り「接見」が禁止されていることを指します。接見とは、面会のことを指すため、面会が禁止されている状態であると思っておけば良いでしょう。
まずは、接見禁止とはどのような状況を指すのか?について詳しく解説します。
面会を禁止されていること
接見とは、刑事事件における「面会」のことを指します。つまり、接見禁止とは、面会が禁止されている状態であることです。
通常、逮捕された被疑者は留置所や拘置所と呼ばれる場所で身柄を拘束されます。身柄の拘束をされている間は、携帯電話の所持はもちろんできません。また、誰とでも会えるわけではありません。とくに逮捕された直後は、すべての被疑者が接見禁止となります。
その後、勾留された場合も引き続き接見禁止となる可能性があります。接見禁止となった場合は、家族や友人、会社の同僚であっても面会することはできません。
ただし、接見禁止はいつまでも許されているわけではありません。日本の法律では「推定無罪の原則」という原則があります。
この原則は、刑事裁判で有罪判決が下されるまでは無罪の人として扱わなければいけないという原則です。つまり、無罪の人を不当に拘束したり人との接見を禁止したりする行為は、原則許されるべきではありません。
とはいえ、さまざまな事情から接見を禁止せざるを得ない状況もあるのです。接見禁止となった場合は、誰とも面会できないことを覚えておきましょう。
逮捕後72時間以内の接見は不可能
逮捕された被疑者は、初めに48時間の身柄拘束が行われます。その後、事件を検察へ送致され、勾留の必要性を判断する(24時間以内)流れとなります。この間の最長72時間は、誰とも接見はできません。
逮捕後72時間の接見禁止は、すべての被疑者が対象です。そのため、接見禁止の解除という概念自体がありません。
そもそも、逮捕後72時間は接見が禁止されている理由は逃亡や証拠隠滅の恐れがあるためです。逮捕後の場合は、初めに取り調べが行われます。初動の取り調べが非常に重要であるため、この間に接見を行って証拠隠滅を図ってしまうと立件が難しくなる恐れがあるためです。
そのため、すべての人を対象に逮捕後72時間以内の接見は不可能であることを覚えておきましょう。
弁護人の接見は可能
接見禁止が付いている場合であっても、弁護士との接見は可能です。そのため、家族等に伝言がある場合は、弁護士を介して伝える方法があります。
なお、逮捕後72時間以内は、私選弁護人を選任しない限り弁護人は付きません。勾留確定後に接見禁止となっている場合は、国選弁護人がついているため、国選弁護人を介して伝言等を伝えると良いでしょう。
なお、証拠隠滅や逃亡の手助けとなるような伝言をしたとしても、弁護士からその旨を伝えることはできません。万が一、そのようなことがあった場合は、弁護士資格を失う恐れがあるため、上記のようなことは絶対あり得ません。
接見禁止の解除方法とは
接見禁止の解除方法は、基本的に準抗告もしくは抗告を行うしかありません。もし、準抗告・抗告を行っても接見禁止が認められなかった場合は、接見禁止の一部解除を求めたり勾留理由開示を行うなどの方法があります。次に、接見禁止の解除方法について詳しく解説します。
準抗告・抗告を検討
初めに準抗告・抗告を検討しましょう。準抗告や抗告とは、裁判所が下した決定に不服がある場合に不服申し立てを行うことができる制度です。
接見禁止が違法であると思われる場合は、裁判所に対して準抗告を行います。接見禁止が違法と判断されるためには、接見禁止の必要がないことを証明しなければいけません。
そもそも、接見禁止とするためには、逃亡または証拠隠滅の恐れがあると疑うに足りる相当な証拠がなければいけません。この事実がないにも関わらず、接見禁止となっている場合は違法となり、直ちに接見禁止は解除されます。
詳しくは後述しますが、否認事件である場合や組織犯罪である場合、共犯がいる場合は接見禁止となる可能性が高いです。なぜなら、口裏を合わせたり証拠を隠滅されたりする恐れがあると判断されやすいためです。そのため、裁判所が下した判断に違法性がないと判断されれば、接見禁止解除はされません。
接見禁止の一部解除を求める
接見禁止の一部解除を求めることも検討しましょう。一部解除は、本人や代理人(弁護人)以外でも行うことができます。そして、接見禁止が違法ではなくても行える申し立てです。
準抗告は接見禁止が違法である場合に接見禁止を解除するよう求める手続きです。一方で、接見禁止の一部解除は、違法ではないものの接見禁止解除を促す手続きであるという点で大きな違いがあります。
勾留理由開示を行う
勾留理由開示は、勾留されている理由を法廷で明らかにする場所です。接見を解除する方法ではないものの、法廷であるため家族等と顔を合わせることができる手続きです。
そのため、少なからず家族等の不安を解消できる手続きとなり得るため、接見禁止がついている場合は検討してみても良いでしょう。
接見禁止になる事件の特徴
接見禁止となる事件は、基本的に裁判官が「逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当の理由がある」と判断した場合です。具体的には、以下のような事件が該当します。
- 否認事件である場合
- 組織犯罪である場合
- 共犯がいる場合
次に、接見禁止になる事件の特徴について詳しく解説します。
否認事件である場合
否認事件である場合は、接見禁止となる可能性が高いです。そもそも、警察等の捜査機関は、あなたが犯人であると仮定して捜査を進めています。そのため、否認している=証拠隠滅もしくは逃亡の恐れがあると判断されやすくなります。
本当に罪を犯していないのであれば、否定し続けたほうが良いですが、罪を犯した事実がある場合は素直に罪を認めてしまったほうが良いケースが多いです。
なお、接見禁止中であっても弁護人との接見は可能であるため、まずは弁護人とよく話し合ったうえで今後の方針を検討したほうが良いでしょう。
組織犯罪である場合
組織犯罪である場合も証拠隠滅もしくは逃亡の可能性が高いと判断されやすいです。接見禁止が解除されることによって、基本的には友人や知人等とも接見が可能となります。
そのため、同じ組織に属している人と接見をしたうえで、証拠隠滅や逃亡について話をするのではないか?といった疑いが残ります。結果的に、組織的犯罪である場合は、接見禁止となる可能性が高まってしまうのです。なお、組織犯罪とは反社会的勢力が行った犯罪や特殊詐欺等が該当します。
共犯がいる場合
共犯がいる場合も接見禁止となる可能性が高いです。仮に、共犯者が逮捕されていない場合は、共犯者が接見に来たうえで口裏合わせをされてしまう可能性があります。
あなた自身にそのようなつもりがなかったとしても、その疑いが払拭できない限りは、証拠隠滅や逃亡の恐れがあると判断されやすくなってしまうのです。結果的に、接見禁止となる可能性が高まります。
接見禁止解除の流れ
接見禁止解除は弁護士を介して裁判所に対して行われます。大まかな流れは以下のとおりです。
- 被疑者・被告人が弁護士へ接見禁止一部解除の相談をする
- 接見禁止一部解除の申立てを行う
- 裁判官が検察官へ意見を求める
- 裁判官が接見一部解除の判断
- 被疑者・被告人へ呈示
基本的には上記の流れで接見禁止解除が進んでいきます。ひとつひとつの流れについて詳しく解説します。
弁護士に接見禁止一部解除の相談をする
まずは、弁護士に接見禁止解除の相談をしておきましょう。接見禁止中で弁護士が付いていないということはないため、自分の弁護人に「接見禁止を解除してほしい」と伝えましょう。
そもそも、逮捕〜勾留確定までの最長72時間はすべての人が接見禁止です。その後、勾留が確定した場合は国選弁護人が選任されるため、選任された弁護人に対して「接見禁止解除を求めたい」と伝えましょう。
なお、弁護士へ相談をしたからといって必ずしも接見禁止が解除されるわけではありません。先ほども解説したとおり、逃亡もしくは証拠隠滅の恐れがあると判断された場合は、接見禁止が解除されない可能性もあることを覚えておきましょう。
そして、通常は接見禁止一部解除の申立てを行う前に、準抗告を検討します。準抗告は、裁判所が下した接見禁止命令が違法である場合に行える手続きであり、違法性が認められれば接見禁止は解除されます。
もし、違法性が認められなければ、接見禁止の一部解除の申立てを行う流れです。いずれの場合も、弁護人が対応してくれる(自身での対応も可能)ため、まずは「接見禁止の解除を希望する」という旨を弁護人へ伝えれば良いです。
接見禁止一部解除の申立てを行う
弁護人が裁判所に対して接見禁止一部解除の申立てを行います。接見禁止一部解除を求める申立書には、接見禁止の解除を求める対象者や接見禁止を解除すべき理由等を記載しなければいけません。
接見禁止の一部解除が認められる傾向としては、以下の場合が挙げられます。
- 罪を認めている場合
- 家族等事件とは関係のない人が対象であること
- 起訴された後であること
上記に該当する場合は、比較的接見禁止を解除されやすい傾向です。たとえば、先ほども解説したとおり否認事件の場合は証拠隠滅の可能性が高いと判断されやすいため、接見禁止解除が難しくなります。
そのため、実際に罪を認めた事実があるのであれば、素直に罪を認めてしまったほうが接見禁止が解除されやすいです。
そして、事件とはまったく関係のない家族である場合は、接見が許可される可能性が高いです。ただし、家族を介して共犯者や組織等に事件に関する伝言を伝え、結果的に証拠隠滅を図ろうとした場合は、即時接見禁止となるため注意しなければいけません。
そして、勾留期間中に起訴された被疑者は、その後に接見禁止解除されやすくなります。そもそも起訴できるだけの証拠が集まっている前提があるためです。とはいえ、いずれの条件を満たしている場合であっても、やはりかならず接見解除されるわけではありません。
裁判官が検察官へ意見を求める
接見禁止一部解除の申立て書を提出した後に、裁判官が検察官に対して意見を求めます。そして、検察官が接見禁止の一部解除を認めるべきかどうか、認めない場合にはなぜ認めないのか、などについて意見をします。
一方で、検察官が有利な意見を出してくれれば、接見禁止解除の可能性が高まるでしょう。
裁判官が接見一部解除の判断
裁判官が申立書や検察官からの意見をもとに、接見を一部解除するか否かについて決定します。一部解除を認める場合には、その範囲を定めたうえで接見できるようになります。一部とは、たとえば「家族に限定」などの条件が付けられていることです。
接見一部解除の決定書が刑事施設へ送られる
接見一部解除の決定書を被疑者もしくは被告人が収容されている刑事施設へ送付されます。
被疑者・被告人へ呈示
接見禁止の決定書が刑事施設へ送られた後、被疑者もしくは被告人に呈示します。もし、決定書に記載されている内容に納得ができない場合は、何度でも申立てを行うことができます。
接見禁止の一部解除が認められた場合は、その後から許された範囲内での接見が許される流れです。
【注意】再逮捕された場合は再度接見禁止になる
注意事項として、再逮捕された場合は再度接見禁止となる可能性があるため注意してください。事件ごとに管理されているため、今回の事件で接見禁止の一部解除が認められたとしても、別の事件で再逮捕された場合は、再度接見禁止となる可能性があります。
この場合であっても、改めて接見禁止一部解除の申立てを行うことが可能です。接見禁止一部解除が認められれば、改めて接見が可能となります。
接見禁止の解除方法に関するよくある質問
接見禁止の解除方法に関するよくある質問を紹介します。
Q.接見禁止中は手紙も出せないのですか?
A.接見禁止中は、原則手紙のやり取りも禁止されます。
そもそも、接見禁止されている理由は「証拠隠滅の恐れがある場合」です。たとえば、接見を許可することによって、その人と証拠隠滅の打ち合わせがなされる可能性があります。これは、手紙でも同様です。手紙を出したり受け取ったりすることによって、証拠を隠滅できる可能性があるためです。
とはいえ、弁護人以外の人との接見中は、警察官がかならず立ち会います。手紙を出す際も手紙を出す前に内容を確認します。届いた手紙についてもかならず確認をしてから被疑者もしくは被告人に渡されるのです。
そのため、「証拠隠滅は不可能であり、そもそも禁止する理由がない」と考える人が多いかもしれません。しかし、その人たちにしかわからない隠語を使用される可能性も否定できません。
さまざまな可能性を考慮したうえで接見禁止中は、弁護人以外の人とのやりとりがすべて禁止されます。
なお、接見禁止中の差し入れについても生活必需品を除いて原則禁止されています。差し入れを検討している人は、事前に確認しておいたほうが良いでしょう。
Q.接見禁止の期限はいつまでですか?
A.期限に定めはありません。
刑事事件はいくつかの流れに大別できます。まずは逮捕〜勾留請求まで(最長72時間)、勾留期間(最長20日間)、判決確定までの期間(通常は1カ月〜2カ月程度)です。
まず、逮捕から勾留請求までの最長72時間はすべての被疑者が接見禁止となります。その後、勾留期間中に接見禁止となった場合、起訴された後に解除される可能性があるものの、引き続き解除されないケースもあります。
起訴された場合は、刑事裁判を待つ未決勾留者となりますが、この期間も接見禁止が継続するケースがあるのです。そのため、最終的に接見禁止が解除されるタイミングとして、もっとも遅いのは刑罰が確定した後となります。
数カ月後となることも多いため、家族等に会いたい場合は接見禁止一部解除を求めるなどの対応を検討しましょう。
Q.接見可能な人の範囲はどこまでですか?
A.基本的には、親族・恋人・友人・会社の同僚、その他更生に必要であると判断された人です。
接見可能な人の範囲は、基本的に上記のとおりです。ただし、接見禁止中に接見禁止一部解除の申立てを行い、許可された場合は接見できる人の範囲が限定されることがあります。
たとえば、「家族のみ」となることも多いです。この場合は、恋人や友人、その他の人との接見はできないため注意しましょう。
Q.接見禁止でも差し入れは可能ですか?
A.接見禁止中でも差し入れは可能ですが、限定的です。
接見禁止中に差し入れが許可されているものは、基本的には生活に必要なもののみです。たとえばお金や衣類、身の回り品が該当します。当然、手紙の差し入れはできません。
なお、差し入れが可能な範囲は収容されている場所や被疑者もしくは被告人によって異なる場合がありますので、事前に確認をしてください。
Q.被害者側から被疑者・被告人に接見禁止を求めることはできるのですか?
A.接見禁止を求めることはできません。
報復が怖いなどの理由から、被疑者・被告人の接見禁止を求めたいと考える被害者がいるかもしれません。接見が許可されることによって、人伝に報復に来られるのではないか?と考えている人もいるでしょう。
しかし、被害者側からの接見禁止を求めることはできません。警察や検察に処罰感情が強いことや報復が怖いことなどを伝えておくだけでも、何らかの対応をしてくれることがあるかもしれません。
まとめ
今回は、接見禁止の解除方法について解説しました。
とくに証拠隠滅の可能性が高いと判断された被疑者については、基本的に接見禁止となり得ます。接見禁止となった場合は、家族であっても接見することが許されません。
突然逮捕され、家族も不安な気持ちににあっているはずです。少しでも早く家族と接見し、不安を解消するためにも、まずは弁護士への相談を検討してみましょう。