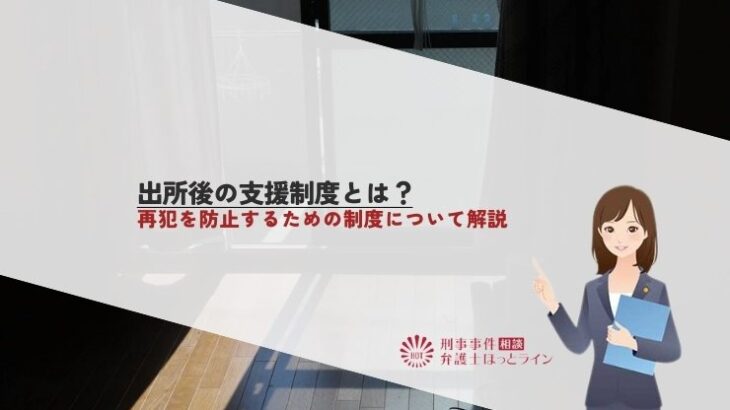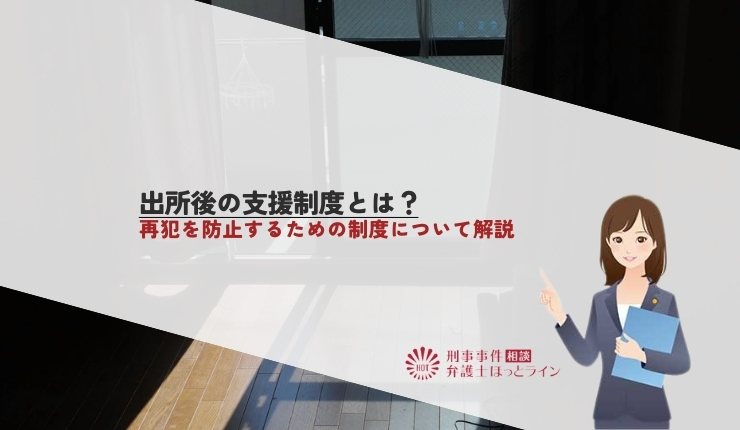
出所後は再犯を犯さないためにもさまざまな支援を受ける必要があります。大切なのは、生活の基盤を確実にすることです。主に「雇用の確保」と「住居の確保」でしょう。
可能であれば出所前に出所後の生活基盤を確保しておくことが好ましいものの、難しければ出所後の支援を利用する必要があります。この記事では、出所後の支援制度について詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
【雇用】出所後の支援
出所後の支援として大切なのは「雇用」と「住居」です。まずは、働くところを見つけなかれば、生活をしていくためのお金を得ることができません。しかし、就職をするためには住む場所(住所)がなければいけません。
そのため、出所後の生活を送るためにまずは、雇用と住居の確保が必要不可欠です。まずは、雇用面から見る出所のサポートについて詳しく解説します。
ハローワークとの連携
ハローワーク(公共職業安定所)では、一般の求人のみならず刑務所から出所された人のみを対象とした専用の求人があります。出所者専用求人の特徴は、以下のとおりです。
- 一般求職者には非公開
- 雇用を希望する矯正施設の特定が可能
ハローワークが行う出所者専用の求人では、一般求職者には非公開で求人が出されています。一般の人に公開されないメリットとして、一般の人が応募できないため、出所者の雇用枠を減らさない点が挙げられます。
もちろん、出所者の能力等に応じて採用・不採用が決定することは前提となっているものの、一般求職者による応募で枠が埋まらないように配慮されています。また、一般求職者の中には、出所者が雇用されることに抵抗のある人がいるかもしれません。
そのため、一般求職者には非公開としたうえで出所者専用の求人として公開しています。
もうひとつの特徴として、事業主は矯正施設の特定ができます。矯正施設ごとに特性があるため、事業主はその特性を理解したうえで出所者を入社させることが可能です。そのため、出所者も安心して入社できる点が大きなメリットです。
また、特定された矯正施設内では求人をあらかじめ確認できる場合もあります。事前に仕事内容等を確認し、入社を希望されてみてはいかがでしょうか。なお、ハローワークによる紹介を希望される出所者は、お近くのハローワークへ行ったうえで相談してみてください。
そして、更生を目指すうえで必要に応じて職業訓練も可能です。職業訓練もハローワークを通じて行います。職種に応じて職業訓練を行い、必要な資格を取得してから就職を目指していく方法もあるため、検討してみると良いでしょう。
いずれにせよ、まずはハローワークへの相談を検討してみてください。
更生保護就労支援事業の実施
国制度として、「更生保護就労支援事業」というものがあります。この事業は、国委託によって民間企業が行う事業であり、出所者の支援を行っています。
更生保護就労支援事業は、主に出所者のうち就労が困難な人が対象です。就職先を見つけるのが難しい出所者は、更生保護就労支援事業を検討してみると良いでしょう。
なお、本事業は入所中から支援を受けられます。通常は、入所している際に説明を受け、必要に応じて依頼する流れです。出所後でも相談は可能であるため、まずは保護司等へ相談をされてみてはいかがでしょうか。
【住居】出所後の支援
働くうえで「住む場所」の支援も必要不可欠です。就職先の中には量を完備しているところもありますが、自分で住居を構える場合やすぐに就職が難しい人は、以下の支援を検討してみましょう。
- 更生保護施設
- 生活困窮者自立支援制度
- 生活ほど制度
次に、出所後の住居支援について詳しく解説します。
更生保護施設
更生保護施設とは、出所者や出院者を対象に身寄りのいない人もしくは、帰るべき住居がない人、帰るべき住居はあるものの、更生の妨げになる場合に利用できる施設です。たとえば、身寄りがない人であれば、更生保護施設の担当者が身元引受人となってくれます。
更生に必要であると判断されれば、一時的に更生保護施設で生活を送ることができます。更生保護施設にいることで、確実に住居を確保できる点が大きなメリットです。出所後、まずは更生保護施設へ入って就職先を見つけ、働きながら改めて自立を目指していくと良いでしょう。
なお、更生保護施設は保護観察所からの委託のほか、保護を必要としている人からの申し出によって入ることができます。まずは、刑務所の中で確認しておくか、出所後に保護観察所へ相談をしてみましょう。
生活困窮者自立支援制度
生活困窮者自立支援制度とは、出所者に限らずすべての国民を対象にした制度です。さまざまな事情から生活が困窮している人を対象に行う制度であり、出所後の生活困窮を支援してもらえる可能性があります。
たとえば、「住む場所が見つからない」「仕事が見つからない」などの事情を抱えている人は、本制度を利用して一時的な支援を受けられます。具体的には、仕事の支援や家賃相当額の補助などの支援を受けられるため、相談を検討してみましょう。
なお、生活困窮者自立支援制度の相談先は、お住まいの地域の市区町村役場です。もし、お住まいの地域に相談先がない場合は、都道府県への相談でも良いです。
生活保護制度
生活保護制度は、出所者に限らず日本に住むすべての人が対象となる制度です。生活保護制度は、何らかの事情で最低限度の生活を送ることが難しい人を対象にした制度であり、主に金銭の補助と自立へ向けた支援を行っています。
受け取れる金額等は世帯人数や住まいの地域によって異なりますが、まずは生活保護による支援を受けられることを確約したうえで、生活の基盤を構築していく方法もあります。
ただし、刑務所から出所する際は、一般的には数十万円程度のお金を持っている人が多いです。数十万円程度のお金がある場合は、生活保護の受給申請に影響を与える可能性があるため注意しましょう。
なお、生活保護制度の相談窓口は、お住まいの地域の福祉事務所です。申請に不安がある場合や、申請自体を断られた場合は、弁護士に相談をしたうえで付き添ってもらうことも検討しましょう。ちなみに、生活保護の申請は住む場所がない人でも可能です。
出所後の相談窓口一覧
出所後の相談窓口は以下のとおりです。
- 保護観察所
- 地域生活定着支援センター
出所後はさまざまな不安を抱えていることでしょう。とくに身寄りがいない人であれば、誰に相談をすれば良いのか?といった不安を抱えている人も多いのではないでしょうか。また、長い間社会と離れていたことによって、何もわからずに不安を抱えている人もいるでしょう。
次に、出所後の相談窓口とどのような相談が可能なのか?について、詳しく解説します。
保護観察所
保護観察所では、指導のみならず出所後のさまざまな支援も行っています。現在の状況等を話し、具体的にどのような支援を受けられるのか、どのようなところへ相談に行けば良いのか、などの相談が可能です。
仮釈放の人や保護観察付きの執行猶予判決が下された人は、保護司と面談をする機会があります。そういった際に、今不安に思っていることなどを相談されてみてはいかがでしょうか。
地域生活定着支援センター
地域生活定着支援センターは、高齢や障害などを理由に福祉的な支援を必要とする人を対象に支援をするセンターです。関係各所と連携を取りながら、出所者の支援を行う窓口となるため、福祉的な支援を求める出所者は、相談を検討してみましょう。
なお、地域生活定着支援センターは各都道府県に設置されています。お近くの地域生活定着支援センターを探したうえで、相談をしてみましょう。
出所後の再犯を防止するためにできること
出所後、社会に馴染めずに再犯を犯してしまう人が多くいます。再犯者の中には、衣食住の確保ができずに「刑務所の中であれば衣食住を確保できる」と考えてしまう人も少なくありません。
そのため、出所後の再犯を防ぐために、以下3つのことを意識しておくと良いでしょう。
- 生活の基盤を築く
- 家族・知人との関係を構築する
- 出所兄応じて適切な支援を受ける
次に、出所者の再犯を防止するためにできることについて詳しく解説します。
生活の基盤を築く
もっとも大切なのは、衣食住を確保することです。衣類は、必要最小限で良いですが、食事と住む場所を確実に確保しておかなければいけません。いずれもお金が必要であるため、もっとも必要なのは就職先を見つけることでしょう。
可能であれば出所前に確実に住む場所と就職先を見つけ、出所後の生活基盤を確実にしておくことがとても大切です。必要に応じた支援を受けましょう。
家族・知人との関係を構築
家族や知人と関係を構築しておくことも大切です。これまで、長い間社会と離れていたため、さまざまな不安を抱えて出所してくることでしょう。家族や知人と関係を構築し、必要な支援を受けながら更生を目指していきます。
出所者に応じて適切な支援
出所者ごとに応じた適切な支援を受けることも大切です。相談先の確保、不安を解消するための支援先を知っておくことで、出所後も安心して生活を送れるようになるでしょう。先ほど解説した支援先、相談先などを活用しながら、更生を目指していきましょう。
出所後支援制度に関するよくある質問
出所後の支援制度としてよくある質問を紹介します。
Q.出所後に生活保護を受給できますか?
A.出所後の生活保護受給は可能です。
出所後であっても生活保護の受給は可能です。ただし、資産状況等に応じて生活保護の申請が通らない可能性もあるため注意しましょう。
出所者であることを理由に生活保護が断られることはありません。また、何人も生活保護の申請を拒否されることはありません。かならず申請は受理されたうえで、審理して最終的に決定します。
中には、「働ける」などのことを理由に申請自体を断る自治体があるかもしれませんが、申請を断ることは違法です。
Q.出所後に年金を受け取ることは可能ですか?
A.年金受給年齢に達していれば、受け取れる可能性があります。
年金を受給するためには、年金受給年齢に達していることに加え、年金を支払っていることが条件です。そのため、刑務所へ収監される前に年金を支払っていて、年金受給年齢に達している場合は、年金を受給できます。
ただし、若い頃から長期間にわたって刑務所に収監されていた場合、年金を受給できない可能性もあるため注意しなければいけません。
Q.出所前に居住地が決まっていない場合はどうなるのですか?
A.出所前に居住地が決まっていない場合は、さまざまな支援制度の利用を検討しましょう。
出所前に居住地が決まっていなければ、仮釈放等に影響を与える可能性があります。そのため、出所前に支援制度などを活用して居住地を確保しておくことが大切です。
居住地を確保する方法としては、身寄りを頼る方法や更生保護施設、自立準備ホーム、生活保護受給申請などを検討すると良いでしょう。
Q.身元引受人が居ない場合は出所できないのですか?
A.必ずしも必要であるとは限りません。
そもそも、刑務所の出所は大きく分けて2つあります。ひとつが「仮釈放」もうひとつが「刑期満了(満期出所)」です。仮釈放の場合は、身元引受人が必要ですが、刑期満了の場合は、身元引受人がいなくても良いです。
とはいえ、多くの人が仮釈放を目指すため、基本的には身元引受人が必要であると考えておいたほうが良いです。身寄りがいない場合は、各種支援制度を利用して身元引受人を確保しておくと良いでしょう。
Q.出所する際、おおよそいくらくらいのお金を持って出るのですか?
A.人によって異なります。
刑務所の中では働くことができ、作業報奨金を得られます。刑務所の中で得られた報奨金は、刑務所の中で日用品を購入する際に使用できます。
また、報奨金は各受刑者によって差があるため、一概にいくらくらいのお金を持って出所できるかはわかりません。お金を貯めている人で長期間刑務所にいた人であれば、100万円近いお金を貯めている人もいるでしょう。
短期の刑期であったりこまめにお金を使用している人であれば、数万円程度であることも多いです。人によって大きく異なるため、一概にはいえません。
まとめ
今回は、出所後の支援制度について解説しました。
出所後は、再犯を犯さないためにも社会でさまざまなサポートをしていく必要があります。必要に応じた支援を受け、更生を目指していく必要があるでしょう。
今回解説した内容を踏まえ、不安がある場合は関係相談先への相談を行い、確実な更生を目指していくと良いでしょう。