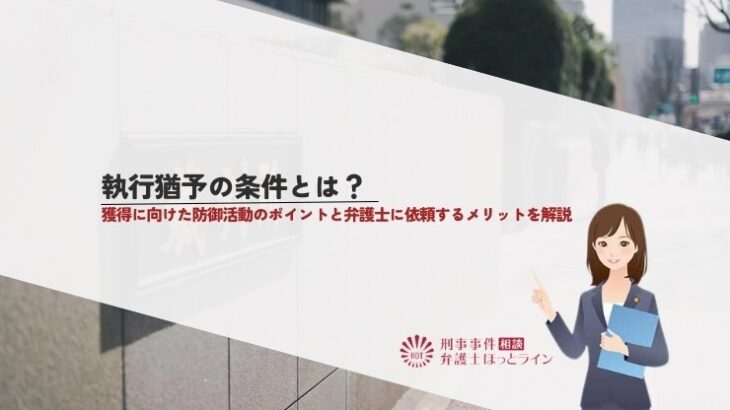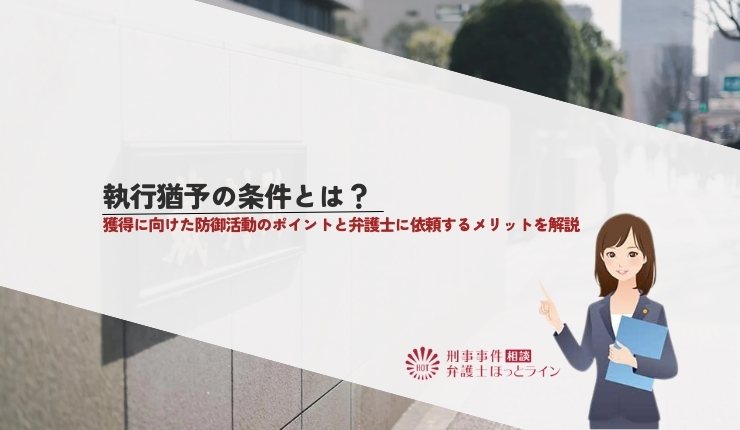
被告人の状況によって執行猶予の条件は異なります。
ただ、いずれにしても、刑事裁判において被告人に有利な情状証拠・情状証人を用意しなければいけないという点は共通しています。
適切な防御活動によって執行猶予付き判決を獲得できなければ、実刑判決が下されて刑務所に収監されます。一定期間社会生活から隔離されると、社会復帰が困難になりかねません。
そこで、この記事では、執行猶予を獲得できるか不安を抱えている人のために、以下の事項についてわかりやすく解説します。
- 執行猶予の条件・要件
- 執行猶予が取り消される場合
- 執行猶予獲得に失敗したときのデメリット
- 執行猶予獲得に必要な防御活動、弁護士に相談するメリット
刑事手続きは弁護士の力を借りるタイミングが早いほど有利な状況を作り出すことができます。現在依頼している弁護人に不信感が募ったり、今後の刑事裁判に不安を抱えていたりするなら、当サイトに掲載中の刑事裁判実績豊富な弁護士までお問い合わせください。
目次
刑の全部の執行猶予の条件
執行猶予は、「刑の全部の執行猶予」「刑の一部の執行猶予」に区分できます。
- 刑の全部の執行猶予:判決で言い渡された実刑判決部分の全ての執行を猶予すること
- 刑の一部の執行猶予:判決で言い渡された実刑判決の一部は執行されるものの、残りの部分の執行が猶予されること
まずは、刑の全部の執行猶予の条件やルールについて解説します。
刑の全部の執行が猶予される3パターン
まず、刑の全部の執行猶予の条件は、3つのパターンに分けることができます。
刑の全部の執行猶予パターン①
前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者が、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金刑の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、刑の全部の執行を猶予される可能性があります(刑法第25条第1項第1号)。
このパターンで刑の全部の執行が猶予される場合には、執行猶予期間中に保護観察が付される可能性があります(刑法第25条の2第1項前段)。
刑の全部の執行猶予パターン②
前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者が、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金刑の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、刑の全部の執行を猶予される可能性があります(刑法第25条第1項第2号)。
パターン①と同じように、この条件で刑の全部の執行が猶予される場合には、執行猶予期間中に保護観察が付される可能性があります(刑法第25条の2第1項前段)。
刑の全部の執行猶予パターン③
前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が1年以下の懲役または禁錮の言渡しを受けて、情状に特に酌量すべきものがあるときは、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、刑の全部の執行を猶予される可能性があります(刑法第25条第2項)
パターン①とパターン②では、所定の条件を満たす人物について「情状が認められる場合」に刑の執行が猶予されますが、パターン③では、「情状に特に斟酌すべきものがあるとき」に条件が引き上げられているのがポイントです。
また、パターン①とパターン②では、裁判所の判断で執行猶予期間中に保護観察が付くかどうかが決められますが、パターン③の場合には執行猶予期間中かならず保護観察が付されます(刑法第25条の2第1項後段)。
執行猶予が付くかどうかを左右する「情状」条件とは
執行猶予が付くかどうかを左右する大きなポイントが「情状」です。刑事裁判では、パターン①~③のどれであったとしても、被告人に対して執行猶予を付けるだけの情状要素があるかが判断されます。
情状として考慮されるのは犯罪に関連する全ての事項です。たとえば、以下の情状要素が執行猶予がつくかどうかに影響します。
- 容疑をかけられている犯罪の性質
- 犯行の手段や方法
- 犯行によってもたらされた結果の大きさ、深刻度、社会的影響
- 犯行に至った動機(計画的か衝動的かなど)
- 被告人の属性(年齢、性格、普段の生活の様子、境遇、前科や前歴の有無)
- 改悛の情の有無、程度
- 被害者との間で示談が成立しているか、示談交渉はどの程度進んでいるのか、被害弁償は済んでいるかなど
刑の全部の執行猶予が取り消される場合
刑事裁判で刑の全部の執行を猶予する判決が確定したとしても、執行猶予期間中の生活次第では、執行猶予が取り消される可能性があります。
刑の全部の執行猶予の必要的取消し
以下の事由が発生した場合、刑の全部の執行猶予が必ず取り消されます(刑法第26条)。これは「刑の全部の執行猶予の必要的取消し」と呼ばれます。
- 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき
- 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき
- 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき
刑の全部の執行猶予が取り消されると、直ちに刑務所に収監されて実刑判決で指定された期間服役をしなければいけません。たとえば、「懲役1年、執行猶予3年」の判決が確定したあと、執行猶予期間が満了する前に刑事事件を起こして「懲役2年」の判決を言い渡されると、執行猶予が取り消されて3年間(懲役1年 + 懲役2年)刑務所に収容されます。
刑の全部の執行猶予の裁量的取消し
以下に掲げる事由が発生すると、刑の全部の執行猶予が取り消される可能性があります(刑法第26条の2)。これは「刑の全部の執行猶予の裁量的取消し」と呼ばれます。
- 執行猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき
- 執行猶予期間中に保護観察が付された場合において、遵守すべき事項に違反し、その情状が重いとき
- 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられて、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき
刑の全部の執行猶予の裁量的取消しが問題になるケースは、必要的取消しの場面よりも比較的軽微な事象が発生したときです。
ですから、ここに挙げた項目に該当する事態が発生しても、執行猶予が常に取り消されるわけではなく、執行猶予がそのまま継続する可能性もあります。執行猶予の裁量的取消しを回避するためには一定の防御活動が必要になるので、可能な限り刑事実務に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
刑の一部の執行猶予の条件
次に、刑の一部の執行猶予の条件やルールについて解説します。平成28年6月施行の改正刑法から導入された比較的新しい制度です。
刑の一部の執行が猶予される3パターン
刑の一部の執行が猶予されるパターンも3種類に区分されます。
以下のいずれかに該当する者が、3年以下の懲役または禁錮の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときには、1年以上5年以下の期間、その刑の一部の執行が猶予される可能性があります(刑法第27条の2第1項)。
- 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
- 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
- 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
刑の一部の執行猶予は、執行を猶予されなかった部分の期間について実刑が執行されて、執行が終わった日またはその執行を受けることがなくなった日から猶予される期間を起算する、という流れで実施されます(刑法第27条の2第2項)。例えば、「被告人を懲役2年に処する。その刑の一部である懲役6ヵ月の執行を2年間猶予する」という判決が確定した場合、1年6ヵ月刑務所に服役をしたあと、6ヵ月分の懲役刑について執行猶予期間がスタートします。
また、刑の一部の執行猶予判決を下すときには、猶予期間中、保護観察が付されることもあります(刑法第27条の3第1項)。ただし、刑の一部の執行猶予判決が下されるのは薬物事犯などが多く、ほとんどのケースで保護観察処分が付されるのが実情です。
刑の一部の執行猶予の「必要性」「相当性」条件とは
刑の一部の執行猶予は、「犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり(必要性)、かつ、相当である(相当性)と認められるとき」に認められます。
必要性及び相当性の要件を満たすかを判断するときには、以下の事情が総合的に考慮されます。
- 再犯リスクの有無、程度
- 施設内処遇と社会内処遇の双方を活用することで更生を実現できるか
- 本人に社会内処遇での更生プログラムを受ける意欲があるか
- 社会内更生の環境は整っているか(家族のサポートの有無、交友関係の内容など) など
実務上、刑の一部の執行猶予制度の適用が想定されているのは、薬物犯罪、性犯罪、暴力事犯、アルコール依存症が原因で刑事事件を起こした場合、クレプトマニア(盗癖)などです。これらの犯罪や事情が存在する場合、刑務所で服役させるだけではなく、外部機関での更生プログラムを受けさせたほうが更生に資するといえるでしょう。
刑の一部の執行猶予が取り消される場合
刑の全部の執行猶予が取り消されるのと同じように、刑の一部の執行猶予が取り消される可能性もあります。
刑の一部の執行猶予の必要的取消し
まず、以下の場合には、刑の一部の執行猶予が必ず取り消されます(刑法第27条の4)。これは「刑の一部の執行猶予の必要的取消し」と呼ばれます。
- 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられたとき
- 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられたとき
- 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき
刑の一部の執行猶予の必要的取消し
次に、以下の場合には、刑の一部の執行猶予が取り消される可能性があります(刑法第27条の5)。これは「刑の一部の執行猶予の裁量的取消し」と呼ばれます。
- 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき
- 保護観察に付された者が遵守すべき事項に違反したとき
執行猶予を獲得できなかったときのデメリット3つ
執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予期間を経過したときには、刑の言渡しは効力を失います(刑法第27条)。
それでは、このような大きなメリットを有する執行猶予を獲得できなかったときには、どのようなデメリットが生じるのでしょうか。
実刑判決が執行される
執行猶予の条件を満たさなければ実刑判決が下されます。実刑判決が確定すると、判決で言い渡された刑期を満了するまで刑務所に服役をしなければいけません。
刑務所では共同生活が原則で、8畳程度の広さの部屋に5~6名が収容されます。そのため、プライベートは確保されず、トイレも簡単な仕切りがされたところで済まさなければいけません。一日のスケジュールは厳密に決められており、刑務作業をおこなったり、教育訓練を受けたりします。食事は1日3食提供されますが、質素な内容です。
最低限の人権は保障されてるとはいえ、刑期を満了するまで、もしくは、仮釈放が認められるまでは厳しい生活が続くので、心身に相当なストレスがかかるでしょう。
社会復帰の難易度が高くなる
実刑判決により一定期間刑務所への服役を強いられると、その期間は社会生活から完全に隔離されます。
たとえば、収容される前に勤務していた会社はクビになるでしょう。また、通学もできないので退学処分が下されたり、単位取得要件を満たせずに進学にも支障が出る可能性が高いです。さらに、出所後に転職活動をしようにも、履歴書に相当の空白期間が生じますし、前科もついた状態なので、なかなか内定を獲得できません。
このように、一度でも実刑判決が下されると、これまで築いたキャリアが崩れ切って再起するのが相当難しくなるでしょう。
家族や交友関係にも悪影響が生じる
執行猶予の条件を満たさずに実刑判決が下されると、これまでの人間関係が崩れてしまう可能性が高いです。
たとえば、親族や知人から縁を切られることも考えられます。また、実刑判決が確定して前科がつくことは「法定離婚事由」に該当するため、配偶者から離婚を申し入れられると拒絶できません。さらに、親が服役して前科者になると、いろいろな噂が広がって子どもも学校に通えなくなるリスクも生じます。
以上を踏まえると、執行猶予の条件を満たさず服役を強いられると、受刑者本人の社会生活にさまざまな支障が生じるだけではなく、受験者と関係がある身近な人たちや家族にも多大なる迷惑がかかるといえるでしょう。
執行猶予を獲得するためのポイント3つ
執行猶予がつくかどうかで被告人の今後の人生は大きく変わります。
ここでは、刑事裁判にかけられた被告人が執行猶予を獲得するためのポイントを3つ紹介します。
有利な情状証拠を収集する
執行猶予の条件でもっとも重要なものが「情状」です。被告人に有利な情状証拠を用意できるかが執行猶予がつくか否かを左右します。
たとえば、被害者がいるなら、できるだけ早いタイミングで示談交渉を開始して、刑事裁判が終了するまでに示談を成立させましょう。そして、可能であれば、被害弁償を含めて示談金を支払ってしまったほうが裁判所からの心証は良くなります。
また、犯行に至った動機や経緯にやむを得ない事情があるのなら、それを示す客観的証拠も用意しましょう。たとえば、以前から親の介護に苦労しているなかで、家計もひっ迫してしまい、やむを得ずに親を殺害するに至った事案なら、介護関係に要した費用の領収書、毎月の入出金が記帳されている預貯金通帳、親の状態を示す診断書などが情状証拠として役立ちます。他にも、普段から献身的に介護していた事情を知る友人や親族に証人として裁判所に出廷してもらうのも有効です。
入念に被告人質問への対策をする
刑事裁判では、「弁護人による主質問、検察官による反対質問、裁判官による補充質問」という流れで被告人に対する質問が実施されます。
裁判所からの心証が悪くならないように、被告人質問が実施される前に入念に準備をしておきましょう。特に、検察官による反対質問では、被告人の刑事責任を追及するために、厳しい質問が想定されます。検察官からの揺さぶりに負けると証言内容に矛盾や変遷が生じて、裁判官からのイメージが悪くなってしまいます。
刑事事件に強い私選弁護人に相談・依頼する
執行猶予獲得を本気で目指すなら、刑事事件に強い弁護士への依頼が不可欠です。
刑事裁判の実績豊富な弁護士の力を借りれば、以下のメリットを得られるでしょう。
- 被害者との間で早期に示談交渉を進めてくれる
- 被告人に有利な情状証拠を用意してくれる
- 検察官の誘導尋問には速やかに異議を申し立ててくれる
- 被告人質問で供述するべき内容について事前準備してくれる など
刑事裁判前に弁護士に相談すればさらにメリットを得られる
弁護士に依頼すれば執行猶予を獲得できる可能性が高まりますが、弁護士が活躍するのは刑事裁判だけではありません。
刑事裁判にかけられる前、たとえば、警察に逮捕された段階や、刑事訴追のリスクに晒されている段階で弁護士に相談・依頼すれば、さらに以下のようなメリットを得ることができるでしょう。
- 在宅事件化によって強制的な身柄拘束処分の回避を目指してくれる
- 勾留阻止活動に力を入れて身柄拘束期間の短縮化を目指してくれる
- 起訴猶予処分獲得を目指してさまざまな証拠を収集してくれる
- 取り調べ段階から一貫した供述ができるように早期に防御方針を明確化してくれる
- 被害者が警察に相談する前に示談交渉を開始して刑事事件化しないように試みてくれる
執行猶予付き判決を獲得すれば実刑判決を回避できます。
それ以上に、微罪処分や不起訴処分を獲得できれば、刑事裁判にかけられることもありませんし、有罪になったり前科がついたりする事態も防げるでしょう。
ですから、刑事訴追のリスクを抱えているのなら、できるだけ早いタイミングで刑事事件に強い弁護士に連絡をとって今後の防御方針などについてアドバイスをもらうべきだと考えられます。
執行猶予獲得を目指すなら私選弁護人の選任がおすすめ
刑事事件を起こした場合、当番弁護士や国選弁護人を利用できる場合があります。これらの制度を利用すれば、無料もしくは非常に安価で弁護士によるサポートを期待できます。
ただし、本格的に執行猶予付き判決などの有利な刑事処分獲得を目指すなら、被疑者・被告人自身の責任で私選弁護人と契約するのがおすすめです。なぜなら、弁護士の実績や人柄、熱意、年齢、性別などをチェックしたうえで、信頼できる専門家を選ぶことができるからです。当番弁護士や国選弁護人制度を利用すると、名簿に記載されている弁護士が順番に担当することになるので、どのような弁護士が担当につくかわかりません。
当サイトでは刑事事件の経験豊富な弁護士を多数掲載中なので、執行猶予付き判決獲得を目指している人はできるだけ早いタイミングで信頼できる専門家までお問い合わせください。
執行猶予の条件に関するFAQ
さいごに、執行猶予の条件などについてよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。
執行猶予は無罪みたいなものですか?
執行猶予期間中、被告人は一般の社会生活を送ることができるため、「執行猶予は無罪みたいなものなのでは?」「執行猶予は刑事処罰として意味がない」などの疑問が寄せられることがあります。しかし、これは間違いです。
というのも、執行猶予はあくまでも「実刑判決の執行を猶予する」という意味合いのものであり、有罪であることに変わりはないからです。
たとえば、執行猶予は前科扱いなので、前科によるさまざまなデメリットに晒されますし、執行猶予期間中に取消し事由が発生するとすぐに刑務所に収監されるリスクと隣り合わせです。
執行猶予中の生活はどのような様子ですか?やってはいけないことはある?
執行猶予中は、刑事訴追される前と同じような生活をおくることができます。基本的には生活に何かしらの制限が加えられることもないので、他の一般人と変わらずに支障なく日々を過ごせるでしょう。
ただし、執行猶予期間中に保護観察が付された場合には、以下の遵守事項を守らなければいけません。これらへの違反が発覚したときには、執行猶予が取り消されるリスクが生じます。
| 一般遵守事項 | ・再び犯罪に及ぶことがないように健全な生活態度を保持すること ・保護観察官や保護司の呼び出し・訪問には誠実に対応し、面接を受けること ・保護観察官や保護司から、労働・進学の状況、収入・支出の状況、家庭環境、交友関係などの実態について聴取されたときには、誠実にその事実を申告したり資料を提示したりすること ・保護観察官や保護司から、生活態度の保持や向上のために実行していること、犯罪的傾向を改善するために専門家から受けている援助のこと、被害者に対する謝罪の状況などについて問い合わせがあったときには、誠実にその事実を申告したり資料を提示したりすること ・速やかに住居を定めて、その地を管轄する保護観察所の長に届出をすること ・保護観察所の長に届出をした住居に居住すること ・転居や7日以上の旅行をするときには、事前に保護観察所の長の許可を受けること |
|---|---|
| 特別遵守事項 | 以下の事項について特別に遵守するべき内容を定められたときには遵守しなければいけない。 ・犯罪性のある者との交際、いかがわしい場所への出入り、遊興による浪費、過度の飲酒などの特定行為を禁止すること ・労働への従事など、健全な生活態度を保持するために必要と認められる特定の行動を実行・継続すること ・7日未満の旅行、離職、結婚や離婚などの身分関係の異動について、緊急の場合を除き、事前に保護観察官や保護司に申告すること ・特定の犯罪的傾向を改善するためのプログラムを受けること ・指定された更生施設に一定期間入所すること ・意識の涵養及び規範意識向上のために、地域社会の利益増進に寄与する社会的活動に一定期間従事すること など |
執行猶予が終わったらどうなりますか?
執行猶予期間が終わったら、刑の言渡しの効力がなくなります(刑法第27条)。これによって、法律上は前科がなくなります。
ただし、有罪判決を受けたという事実は残るため、前科によるさまざまなデメリットは残ってしまいます。たとえば、検察庁が保管している前科調書には前科履歴が残っているので、再犯に及ぶと厳しい追及が想定されるでしょう。また、前科を理由に資格制限を受けたり、履歴書での申告によって就職活動や転職活動へ悪影響が生じたりする可能性もあります。
執行猶予の条件に疑問があるときには弁護士へ相談しよう
執行猶予の条件を満たさなければ実刑判決が下されます。刑務所への服役を強いられると、社会復帰や更生が難しくなります。
そのため、刑事裁判にかけられたときには、可能な限り有利な情状証拠を用意するなどして、執行猶予獲得に向けて尽力する必要があるといえるでしょう。
当サイトでは、刑事裁判経験豊富な弁護士を多数紹介中なので、できるだけ早いタイミングで信頼できる弁護士までお問い合わせください。