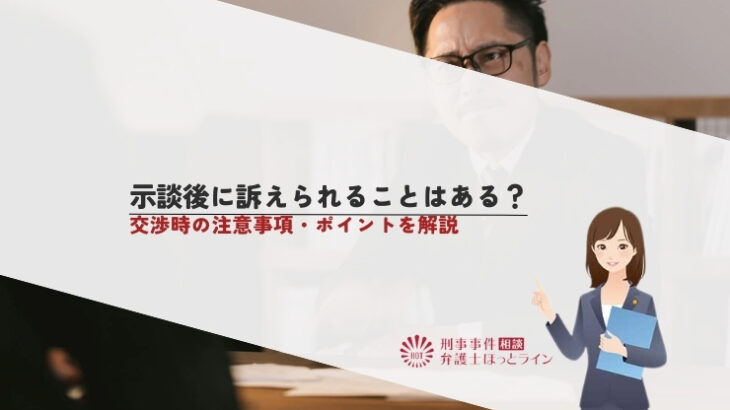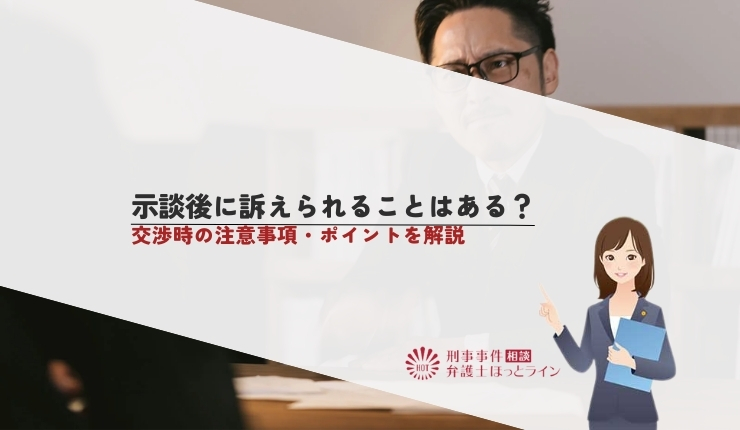
示談成立後に訴えられる可能性はゼロではありません。本来、示談は被害者加害者の双方が話し合い、和解していることを証明するためにあるものです。そのため、基本的に示談後に訴えられることはありません。
しかし、示談書に記載されている内容次第では、後に訴えられる可能性があるため注意しなければいけません。
この記事では、示談成立後に訴えられることはあるのか?訴えられないためにはどうすれば良いのか?について詳しく解説しています。示談を確実に行いたい人は、本記事をぜひ参考にしてください。
示談成立後に訴えられることがある
示談が成立した場合であっても、後に訴えられる可能性があります。
そもそも、示談とは加害者と被害者の当事者が話し合い、損害賠償や慰謝料を支払う代わりに被害届を取り下げる、もしくは刑事処罰を求めないなどの約束をすることです。「訴える」の定義が告訴・告発を指すのであれば、通常は示談を持って訴えられることはありません。
しかし、示談内容によっては示談成立後に訴えられる可能性もあるため注意しなければいけません。まずは、示談成立後に訴えられる可能性はあるのか?について詳しく解説します。
示談内容によっては訴えられる
示談内容によっては、示談が成立した後に訴えられる可能性があります。そもそも、前提として示談とは、「当事者間が話し合って金銭等で解決すること」であることは、先ほど解説したとおりです。
そのため、加害者であるあなたは被害者に対して慰謝料や損害賠償金を支払ったりする代わりに、被害者側は告訴や被害届の取り下げを検討します。そのため、本来であれば、示談成立後に訴えられることはありません。
ただし、示談成立後に訴えられないのは、あくまでも「示談成立後に訴えない」といった記載がある場合に限られます。万が一、このような記載がなければ、示談成立後に訴えられる可能性もあるため注意しなければいけません。
万が一、示談成立後に訴えられないようにするためにも、刑事弁護に強い弁護人を介して示談交渉を進めることが大切です。当事者間で示談交渉を行った場合は、示談による効力が低くなってしまう可能性が高いため要注意です。
告訴・告発後に示談が成立するケースもある
示談交渉がスムーズに進まなかった場合、被害者による告訴もしくは告発が行われてから示談が成立する可能性もあります。告訴や告発をすることによって、警察等の捜査機関は事件を認知し、捜査を開始します。
そのため、示談交渉成立後に告訴・告発が取り下げられたとしても、事件の内容次第では手遅れとなってしまう可能性があるため注意しなければいけません。少しでも早く示談交渉を完了させるためにも、被害者と話し合いができるうちに弁護士へ相談をし、示談を進めていきましょう。
なお、示談交渉は被害者対加害者の双方間で行うことができます。しかし、弁護士などの専門家に入ってもらわなければ、示談としての効力が低下する可能性があるため注意しなければいけません。
たとえば、必要事項(詳しくは後述)の記載漏れにより、示談が成立したものの、後から訴えられてしまう可能性があります。このような事態にならないためにも、かならず弁護士へ相談をしたうえで示談交渉を進めていきましょう。
示談後の注意事項
示談成立後に注意すべき点は、以下のとおりです。
- 示談が成立しても起訴される可能性はある
- 示談成立後は撤回や訂正ができない
- 示談金を期限内に履行する義務がある
次に、示談成立後に注意すべき点について詳しく解説します。
示談が成立しても起訴される可能性はある
示談が成立しても、起訴されて刑事罰を受ける可能性があります。そもそも、示談は被害者と加害者で行われる交渉であり、あくまでも「被害者側と金銭による解決ができています」といった証明にしかなりません。
たとえば、あなたが殺人事件を犯したとして、被害者遺族と和解交渉が成立していたとします。しかし、殺人を犯した事実は変わらないため、当然、起訴されて有罪判決が下されることになります。
示談が成立する大きなメリットとしては、被害者の処罰感情がない事実を証明できる点です。刑事事件においては、被害者の処罰感情が刑罰へ大きな影響を与えるため、「示談交渉が成立している=刑罰が軽くなる」ということになります。
上記のことから、たとえ示談交渉が成立して被害者の処罰感情がなくなっていたとしても、やってしまった事実に対する刑罰を避けることはできません。
ただし、親告罪の場合は被害者からの告訴・告発がなければ罪に問えません。そのため、示談交渉成立によって、告訴・告発が取り下げられた場合は、刑事罰に問われることはないでしょう。
親告罪は主に以下のような犯罪が該当します。
- 名誉毀損罪
- 侮辱罪
- 器物損壊罪
等々
上記のような犯罪の場合は、示談交渉が成立して被害者から告訴を取り下げられた場合は、刑事罰に問われません。
示談成立後は撤回や訂正ができない
一度示談が成立してしまった場合は、後から撤回したり訂正したりできません。たとえば、示談交渉の中に「告訴・告発を取り下げる」といった記載をせずに和解が成立した場合であっても、後から訂正できないため注意しなければいけません。
上記のようなミスを犯さないためにも、示談交渉を行う際は、かならず弁護士への相談を検討したほうが良いです。
示談金を期限内に履行する義務がある
一度示談が成立した場合は、後から訂正・撤回はできません。また、「◯月◯日までに示談金を支払います」といった旨の記載をした場合、その期日までに示談金を支払う義務があります。
もし、示談金を支払わなかったり遅れたりした場合は、示談の効力はなくなり、訴えられたり告訴・告発を取り下げてもらえなかったりするため注意しましょう。
示談書作成時の注意事項
示談書を作成する際は、かならず弁護士に作成を依頼したほうが良いです。なぜなら、示談書に記載すべき事項が漏れていると、和解成立後に訴えられてしまう可能性があるためです。
なお、示談作成時は以下のことを盛り込む必要があります。
- 清算条項
- 宥恕条項
- 被害回復の完了・見込み
- 被害届や告訴の取り消し
一個人が全てを網羅し、抜け目なく示談書を作成して相手方と交渉をするのは困難です。次に、示談書を作成する際の注意事項についても解説しますので、なぜ一個人が示談書を作成することが困難なのか?についての参考にしてください。
「清算条項」を盛り込む
示談書を作成する場合は、かならず清算条項を盛り込みましょう。清算条項とは、示談書に記載された内容以外の請求を行わないという内容です。
示談書は、金銭等を支払うことを約束する代わりに、告訴・告発、被害届の取り下げや嘆願書の提出を求める内容です。そのため、示談が成立した後は、何があっても成立時に約束した以上の金銭を求めないという内容を書く必要があります。
清算条項を盛り込まなければ、示談が成立した後でも、被害者側から「やっぱり示談金に納得できないから、追加で〇〇万円要求する」といった要求が通ってしまいます。このようなことが起こってしまうと、示談としての意味がありません。
そのため、かならず清算条項を盛り込んでおかなければいけません。
「宥恕条項(ゆうじょじょうこう)」を盛り込む
示談書を作成する場合は、かならず宥恕条項も盛り込みましょう。宥恕条項とは、刑事事件における示談書を作成する際に必要となる内容であり、被害者が加害者を「許す」といった意味合いで記載される部分です。
示談交渉が成立した場合は、問題が金銭で解決できたことを表わします。そもそも、示談交渉を行う目的は、被害者の処罰感情を低減することです。被害者自身が金銭を受け取って処罰感情が低減していたとしても、その事実を書面等で証明する必要があります。
刑事事件においては、被害者の処罰感情が刑事罰に大きな影響を与えるため、「被害者が許している」という事実が刑事処分を検討する際に良い影響を与える可能性があるのです。
宥恕条項がなければ、「示談交渉が成立した」という事実しか残りません。もしかすると、被害者が後から「示談には応じたけど許していない」という可能性もゼロではないでしょう。
そのため、示談交渉が成立した際は、示談書に「加害者を許す」といった内容を盛り込み、加害者側の刑罰軽減を目指すのです。
「被害回復の完了・見込み」を盛り込む
示談書には「被害回復の完了・見込み」についても記載しておきましょう。そもそも、示談交渉では犯罪等によって被害者に損害を与えた場合は、示談金の支払いによって賠償をしなければいけません。
そのため、示談書には以下の項目を盛り込む必要があります。
- 示談金額
- 支払い期日
- 支払い方法
示談金額は、賠償額や慰謝料等を合計した金額が相場です。犯罪の内容によっても異なるため、弁護士や被害者と相談をしたうえで決定します。
支払い期日は、示談成立後いつまでに支払いを完了させるのか?について、明記する必要があります。通常は、示談が成立してから1週間〜2週間以内に期日設定をします。
支払い方法は、基本的には振り込みです。振り込みで支払うことによって、示談金を振り込んだ証明ができるためです。また、基本的には一括での支払いが好ましいですが、一括支払いが難しい場合は、分割交渉を進めてみても良いでしょう。
そして、最後に支払いが完了している旨を示談書に記載する必要があります。これが、「被害回復の完了」と見なされるためです。
「被害届や告訴の取り消し」を盛り込む
示談書を作成するうえで最重要であると言っても過言ではない部分が「被害届や告訴の取り消し」です。この項目を書き込まなければ、示談成立後に訴えられる可能性があるため注意しなければいけません。
たとえば、告訴前であれば「示談が成立した場合は、告訴や被害届の提出を行わない」と記載します。告訴後であれば、「告訴を取り下げる」といった内容で記載する必要があります。
告訴後に示談が成立した場合であっても、被害届や告訴の取り下げによって、被害者の処罰感情が薄れていることが明らかとなります。そのため、刑罰が減刑されたり不起訴処分となったりする可能性が高いです。
なお、示談交渉を行う場合は、起訴される前や告訴される前に行っておくことがとても大切です。起訴されたあとに示談交渉が成立した場合、減刑される可能性は高いものの、何らかの刑罰が下される可能性が高く、前科が残る点に注意が必要です。
示談成立後に訴えられないためにできること
示談成立後に訴えられないためにできることは、以下のとおりです。
- かならず弁護士を介して示談交渉を行う
- 示談書の内容を把握・理解しておく
次に、示談が成立したあとに訴えられないためにできることについて詳しく解説します。
かならず弁護士を介して示談交渉を行う
かならず弁護士を介して示談交渉を行いましょう。弁護士へ相談をすべき理由は、以下のとおりです。
- トラブルなく進められる
- 和解後に訴えられる可能性をゼロにできる
まず、弁護士を介することによって、余計なトラブルを回避できます。たとえば、個人間同士でやり取りを行うことによって、相場とかけ離れた金額を要求される可能性があります。
事件ごとにある程度相場が決まっているため、弁護士であれば相場前後で和解が成立するよう、交渉を進めてくれるでしょう。また、加害者側から脅されて示談に応じてしまう可能性があるかもしれません。
事件の中には、被害者は加害者に対して「怖い」とイメージを持っていたり「会いたくない・話したくない」といったイメージを持っていたりするケースがあります。
上記の場合、被害者は、「早く交渉を済ませたい」と考えたり、「示談に応じなければ何をされるかわからない」と感じてしまうかもしれません。結果的に、トラブルに発展する可能性があるため弁護士を介したほうが良いです。
そして、示談書の作成に不慣れな一般の方が示談交渉を行い、示談書を作成しても、必要な事項が抜けている可能性があります。万が一、必要な情報が抜けていると、結果的に和解が成立しているにも関わらず訴えられてしまうかもしれません。
示談書の内容を把握・理解しておく
示談書にサインをする際は、内容をしっかりと把握・理解しておきましょう。小難しい言葉が出てくる部分も多いですが、不明な部分はかならず弁護士へ確認するなどして理解したうえでサインをして成立を目指します。
曖昧なままで示談を成立させてしまうと、後から思わぬトラブルに発展する可能性があるため注意してください。
示談後の訴訟についてよくある質問
示談後の訴訟についてよくある質問を紹介します。
Q.示談成立後に訴えることは許されるのですか?
A.原則できません。
前提として、示談内容に「示談成立後に告訴しない」や「告訴や被害届を取り下げる」といった内容を記載しておく必要があります。これらの記載がない場合は、示談が成立したあとに告訴や被害届を提出してもまったく問題ありません。
ただし、示談内容に「告訴や被害届を取り下げる」と記載されている場合は、告訴や被害届を提出したりすることはできません。もし、示談成立後に告訴等をした場合は、示談がなかったものとなるため、被害者は加害者に対して示談金を返還しなければいけません。
また、被害者側も一度示談に応じている以上、その内容を守る義務があります。そのため、原則、示談成立後に訴えることは許されないと思っておいたほうが良いでしょう。
Q.示談成立後に「訴えられたくなければ金銭を支払え」と言われた場合、どう対応すれば良いですか?
A.支払う必要はありません。
示談が成立した場合は、示談内容によって履行する義務があります。逆に言えば、示談書に書かれている以上の金銭等を支払う必要はありません。
たとえば、金銭を支払って示談が成立しているにも関わらず、後から「訴えられたくなければ金銭を支払え」と言われても、加害者側に金銭を支払う義務が発生しないのです。むしろ、被害者側が恐喝罪等の罪に問われる可能性があるため注意しなければいけません。
また、示談内容は原則撤回や訂正はできません。ただ、以下に該当する場合は、示談の撤回や追加請求が可能であるため注意しましょう。
- 示談後に後遺症が発覚した場合
- 不当な内容・方法で示談が成立した場合
- 示談を成立させる意思がなかった場合
- 示談内容を勘違いしていた場合
- 示談で詐欺・脅迫が行われていた場合
まず、示談が成立したあとに被害者の後遺症が発覚するケースがあります。この場合は、「示談成立時に気付けなかった」と認められる場合は、訂正や撤回が可能であるため、追加請求が可能となるケースもあります。
不当な内容や方法で示談が成立した場合とは、不十分な説明をしていたり、不当に相場より著しく低い示談金を支払っていた場合などが該当するため注意しましょう。これらの場合も、当然に示談内容の訂正・撤回が可能です。
被害者が示談成立させる意思がなく、示談成立に対する意思を加害者側も把握していた場合は、示談内容の訂正・撤回ができます。これを「心裡留保」と言います。ただし、加害者側が被害者の意思を把握していなかった場合は、訂正や撤回ができません。
示談内容を勘違いしていた場合も訂正・撤回できる可能性があります。たとえば、交通事故の被害者・加害者で「自動車保険の上限額である程度の保障を受けられると聞いていた」などのような場合は、訂正・撤回が可能です。
そして、示談交渉を行う際に詐欺や脅迫が行われていた場合は、当然、示談書の訂正・撤回が許されます。たとえば、加害者が被害者に対して「示談に応じなければ、〇〇(不法行為)を加える」などと伝えた場合が該当します。
上記に該当する場合は、示談内容の訂正・撤回が可能であるため、追加の示談金を要求される可能性があるでしょう。ただし、直ちに自分で判断するのではなく、かならず弁護士へ対応を依頼したほうが良いでしょう。
Q.示談成立後に気が変わって訴えたい場合はどうすれば良いですか?
A.示談書に「被害届や告訴の取り消し」が盛り込まれている場合は、訴えることはできません。
示談は、被害者および加害者の双方が納得をしたうえで和解が成立します。後から「気が変わった」という理由で訴えることが可能であれば、示談そのものの意味がありません。
よって、示談書に「被害届や告訴の取り消し」について盛り込まれている場合は、示談後に訴えることはできません。ただし、「被害届や告訴の取り消し」について盛り込まれていない場合は、訴えても良いです。とはいえ、示談が成立していることを考慮されるため、あまり意味がないでしょう。
Q.その場で口頭示談が成立した場合も有効ですか?
A.有効ですが、かならず弁護士を介して書面で行いましょう。
たとえば、痴漢を行ってしまった加害者が被害者に対して、その場で金銭を支払うことによって警察へ通報しないことを約束したとしましょう。この場合であっても、示談自体は成立します。
しかし、リスクしかないため絶対に行わないほうが良いです。そもそも、その場でお金を支払っている時点で、後から「支払われていない」と言われる可能性があります。また、「訴えないとは言っていない」など、さまざまなことを言われる可能性があるでしょう。
被害者・加害者目線で見てすぐにその場で解決を目指したい気持ちはわかりますが、絶対に行わないほうが良いです。効果として有効ですが、かならず後からトラブルに発展します。
まずは相手の連絡先を聞いたうえで、弁護士を介して適切な示談書を作成し、振り込み等履歴として残る形で示談金の支払いを行うべきです。
Q.示談成立後に新たな被害が発覚した場合は訴えられますか?
A.訴えたり、示談金の追加請求が可能です。
たとえば、友人Aが被害者であるあなたの自宅から高級腕時計1点を窃盗したとしましょう。この事件については示談が成立して解決したと仮定します。しかし後に、別の高級時計を窃盗されていたことが発覚したとします。
上記の場合は、初めの窃盗事件については解決しているものの、もうひとつの窃盗事件については解決していません。そのため、当然訴えたり、追加の示談金を請求したりしても良いです。
まとめ
今回は、示談成立後に訴えられることはあるのか?について解説しました。
基本的には、示談書に「被害届や告訴の取り消し」についての内容を盛り込んでいるため、示談成立後に訴えることはできません。もし、「被害届や告訴の取り消し」について盛り込まれていなければ、訴えることは可能ですが、非道徳的行為であると言えるでしょう。
そのため、基本的には示談が成立したあとに訴えを起こすことはできない、と考えておいたほうが良いでしょう。
示談成立後に訴えを起こされたり、トラブルを発生させたりしないためにも、かならず弁護士を介して示談書を作成してください。示談は、刑事事件において大きな効果を発揮するため、できるだけ早めに進めておくことを検討しましょう。