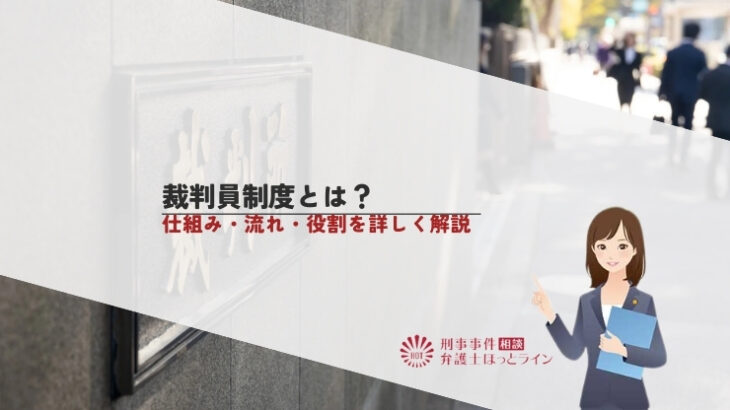2009年に導入された「裁判員制度」は、これまで専門家だけが担ってきた刑事裁判に一般の国民が参加できる制度です。テレビや新聞などで耳にしたことはあっても、実際にどのような仕組みなのか、具体的な役割はどのようなものか、深く理解している人は意外と少ないかもしれません。
この制度では、無作為に選ばれた国民が、殺人や強盗、放火などの重大な刑事事件において、裁判官とともに被告人の有罪・無罪や量刑を判断します。選ばれた裁判員には報酬や交通費が支給される一方、精神的・心理的な負担の大きさや、法律知識の乏しさからくる不安など、現場では多くの課題も見えてきます。
この記事では、「裁判員制度とは何か?」という基本的な仕組みから、実際に選ばれた場合の流れ、裁判員として行う役割、そして制度のメリット・課題、辞退できるケースやサポート体制まで、裁判員制度の全体像をわかりやすく丁寧に解説していきます。突然通知が届いても慌てないために、また制度そのものを正しく理解するために、ぜひ参考にしてください。
目次
裁判員制度とは?
裁判員裁判は、国民が刑事裁判に参加できるようにするためにできた制度です。2009年に開始した司法制度の一つで、刑事事件のうち重大事件に該当する事件にのみ、国民が参加できます。
国民の市民感覚を反映させることを目的とした制度ではあるものの、一般人を刑事裁判に参加させることでさまざまな問題や課題も発生しています。まずは、裁判員制度とは何か?について詳しく解説します。
国民が刑事裁判に参加する制度
裁判員裁判を一言で表すなら「国民が刑事裁判に参加する制度」です。刑事裁判等の裁判は、通常、裁判官と検察官、弁護人や被告人が立ち会って行われるものです。
刑事裁判では、犯罪を犯した者(被告人)が犯した罪について、検察官と弁護人がそれぞれ主張し、裁判官が中立的な立場から判決を言い渡します。検察官は「被告人が罪を犯した」という前提のもと、被告人が犯人である証拠等を主張していきます。
一方で、弁護人は被告人の味方であり、被告人が罪を犯していない証拠を提示したり、犯罪事実に争いがない場合は減刑を目指して弁護活動を行います。
検察官と弁護人それぞれがそれぞれの主張を行い、中立的立場にある裁判官がお互いの主張を聞いたうえで判決を言い渡します。これが刑事裁判です。
裁判員裁判は、国民が裁判官と同じ立場になって刑事裁判に参加をします。つまり、国民が検察官や弁護人の主張を聞いたうえで、本物の裁判官と一緒になって無罪・有罪を考え、有罪である場合はどの程度の刑罰に処するかを決定する制度です。
2009年にスタートした国民参加型の司法制度
裁判員制度は、2009年にスタートした制度です。刑事裁判に市民感覚を反映させることを目的として始まった制度ではあるものの、裁判員として選ばれた人の精神的負担等が問題となるケースも多いです。
対象は重大な刑事事件のみ
裁判員裁判の対象となる刑事事件は、たとえば殺人事件や放火事件などいわゆる「重大事件」と呼ばれる事件のみです。
重大事件の多くは死刑や無期拘禁刑など、非常に重い刑罰の規定がある犯罪が多いです。そのため、国民が死刑判決を判断して言い渡さなければいけないケースも多く、裁判員として選ばれた人たちの精神的負担も問題となっています。
裁判官と裁判員が一緒に評議し判決を決める
裁判員は、本物の裁判官と一緒になって評議して判決を言い渡します。先ほども解説したとおり、裁判員対象事件となった裁判に参加し、弁護人・検察官それぞれの主張や証拠を聞きます。
そのうえで、初めに被告人が有罪であるか無罪であるかを判断します。そのうえで、有罪である場合はどの程度の刑罰に処するべきかを判断しなければいけません。過去の類似事件や検察・弁護人の主張を聞き、裁判官と話し合って量刑を決定します。
流れとしてまずは、裁判官と裁判員で評議を行わなければいけません。評議を行いながら、有罪・無罪を判断します。もし、評議の結果全員で一致しなければ、多数決を取ります。
裁判員裁判では、3人の裁判官と6人の裁判員が参加します。そのため、たとえば5人が有罪、4人が無罪となった場合は被告人は有罪判決が言い渡されるでしょう。一方で、5人が無罪、4人が有罪と言った場合は、被告人に無罪判決が言い渡されます。
ただし、有罪判決が言い渡されるためには、裁判官1人以上+裁判員の過半数以上の賛成が必要です。一方で、無罪の場合は、9人のうち過半数以上であれば問題ありません。つまり、裁判官3人を含む合計4人が有罪、裁判員5人が無罪といった場合、被告人は無罪となります。
最終的に有罪であると判断された場合は、被告人に対してどの程度の刑罰を処するべきかを決定します。裁判員の意見は、裁判官と同等の重みを持つため、量刑に与える影響は大きいものとなる点に注意が必要です。
市民感覚を反映させることが目的
裁判員裁判は、市民感覚を反映させることを目的とした制度です。裁判官は、毎日裁判に触れ、単調に審理して判決を言い渡さなければいけません。市民感覚を取り入れることによって、裁判の公平性や透明性を高めたうえで、司法の理解や信頼を深めることを目的としています。
裁判員に選ばれるまでの流れ
裁判員の候補者は住民票を元に無作為に選ばれます。その後、裁判所から通知が届き、裁判所へいきます。そして、当日に裁判員が決定される流れです。
次に、裁判員が選ばれるまでの大まかな流れについても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
裁判員候補者は住民票を基に無作為に選ばれる
初めに、裁判員候補者名簿というものが毎年無作為に作成されます。裁判員候補者名簿は、その時点で衆議院選挙権を有している者の中からくじで選んで翌年の候補者として作成されます。
完全に無作為で選ばれるため、18歳以上の選挙権を持つ人であれば裁判員に選ばれる可能性があります。
なお、裁判員制度が始まった当初は、成人年齢が20歳でした。現在は、民法改正に伴い18歳以上が成人として扱われています。これに伴い、2023年以降は18歳以上の者も裁判員に選ばれる可能性があるため覚えておきましょう。
通知は裁判所から封書で届く
裁判員候補者に選ばれた者は、前年の11月頃に裁判員候補者に選ばれた旨の通知が届きます。この時点ではまだ、候補者の段階であるため裁判所に出向く必要はありません。また、担当する事件も決まっているわけではありません。あくまでも、候補者になったというだけです。
また、封書の中には「調査書」というものが含まれています。調査書は、裁判員になることができない場合は、その旨を記載して返送をします。たとえば、弁護士や検察官などの司法関係者や自衛官などは裁判員になれません。
事件ごとに候補者が選任される
候補者に選ばれた通知が届いて以降、事件ごとに候補者が選ばれます。もし、あなたが何らかの事件の候補者に選ばれた場合は、質問票を同封した選任手続期日のお知らせが届きます。
質問票は、裁判員になれるかどうか?体調はどうか?などの質問が記載されているため、正直に質問に答えれば良いです。
そして、お知らせの中には選任手続期日に関する内容が記載されている書類もあります。記載されている日時に裁判所へ行かなければいけません。
なお、この時点でもなお裁判員として選ばれたわけではありません。あくまでも最終的な候補者として選ばれたというだけであり、質問票を元に裁判員になれる人を集めて最終的に決定する流れです。
当日の選任手続きで裁判員が決定される
記載されている日時に裁判所へ行くと、最終的に裁判へ参加する6人へ絞るための手続きが行われます。辞退希望の有無や理由等を聞いたうえで最終的にはくじ引きで6人が決定します。
この時点で6人に選ばれなかった者は、今回は裁判員になれません。一方で、裁判員の6人に選ばれた場合は、裁判員として裁判に参加することとなります。
裁判員に選ばれたら何をするのか
裁判員に選ばれた場合、主に行うべきことは「被告人の有罪・無罪の決定、および量刑判断」です。しかし、法律知識のない一般人が被告人の有罪無罪を判断し、量刑を判断することは容易ではありません。
そのため、基本的には裁判官と一緒になって裁判官の話やアドバイスを聞きながら、自分の意思で決定していく流れとなります。
もちろん、被告人の人生を左右する決定をしなければいけないため、決して簡単な役割ではありません。しかし、裁判官がいるためわからないことや不安なことは裁判官に尋ね、自分の意思をもとに意見を主張していくことがとても大切です。
次に、裁判員に選ばれたらすべきことについて詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
裁判に出席し証拠や証言を見聞きする
裁判員に選ばれた場合、刑事裁判に参加します。参加する裁判は、あなたも裁判官の一員と同等です。検察官や裁判官、双方の意見や主張を聞いたうえで、自分自身の意思や意見をはっきりとさせなければいけません。
決して簡単なことではありませんが、裁判員というのはそういうものです。もちろん、裁判官が丁寧に説明をしてくれます。わからないことがあれば質問をすることで、わかりやすく丁寧に教えてくれるため、その内容を聞いたうえで自分の意思を決めましょう。
裁判官とともに事実認定と量刑判断を行う
裁判官とともに事実認定と量刑判断を行わなければいけません。検察官や弁護人の話を聞きながら、被告人が罪を犯したのかどうか?の事実認定を行います。
とくに否認事件(被告人が否認している事件)の場合は、有罪無罪を判断するのが難しいでしょう。それでも、自分の意思や意見を持ってどちらかを選ばなければいけません。また、結果的に有罪判決となった場合は、裁判員は裁判官と一緒に量刑判断も行わなければいけません。
評議と多数決で判決を決定する
判決は、評議と多数決で決定します。被告人にとって不利となる判決(有罪判決)の場合は、裁判官および裁判員それぞれ1人以上がいること、過半数以上であることが条件です。
裁判員裁判では裁判官3人、裁判員6人の合計9人で判断します。たとえば、裁判員5人が有罪判決であるといった場合でも、裁判官3人と裁判員の1人が無罪であると主張した場合は、無罪判決が言い渡されます。
一方で、裁判官が1人でも有罪に賛成し、裁判員を含めた人数が過半数を超えた場合は、有罪判決を言い渡すことができるのが裁判員制度です。基本的には、評議に従って全員一致を目指しますが、意見が割れた場合は多数決で決定することを覚えておきましょう。
多数決の際は、「被告人にとって不利な判決である場合は、裁判官・裁判員それぞれ1人以上、過半数」が条件であることも覚えておきましょう。一方で、無罪の場合は条件がなく、過半数を超えた場合に無罪判決となります。たとえば、裁判官全員が有罪、裁判員全員が無罪である場合、被告人には無罪が言い渡されます。
責任重大な役割であることを認識し、公平な目線を持ってしっかりと対応することが求められます。
【注意】守秘義務を守る必要がある
裁判員には守秘義務があります。裁判で知り得た情報は、一生涯口外してはいけません。万が一、守秘義務に違反した場合は、刑事罰の対象となるため注意しましょう。
たとえ家族であっても話をすることはできません。あくまでも評議できるのは、事件を担当する裁判官や同じ事件を担当している裁判員に限定されています。
ただし、事件に関する内容を話すことは守秘義務に該当しません。「どのような事件であった」「自分は何を思った」などのことを話すことはまったく問題ありません。むしろ、このような情報を発信していくことで、裁判員制度に関する誤解を払拭できる可能性が高まります。
守秘義務を負うのは、たとえば多数決の数や他の裁判員の情報、事件関係者のプライバシーに関する内容です。これらについても、裁判官等から説明があるため、とくに気負う必要はないでしょう。
裁判員制度のメリットと課題
裁判員制度は「国民感覚の反映」や「司法絵の理解・関心の高まり」など、多くのメリットがあります。一方で、裁判員への「精神的負担」や「専門知識の不足」「辞退者が多い」といった様々な課題があるのも事実です。
次に、裁判員制度のメリットや課題についても詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
【メリット】国民感覚を取り入れた公正な判断が期待できる
裁判員制度は、国民感覚を取り入れるために始まった制度です。裁判員制度が始まる前は、司法試験に合格して司法修習を経て裁判官採用試験に合格した裁判官のみで、構成され、裁判を審理して判決を言い渡していました。
いわゆる法律の専門家のみで構成されており、裁判官の主観のみで判決が言い渡される傾向にあり、主観的な判断が偏りやすいといったデメリットがありました。国民の感情や感覚と乖離する部分も多かったため、裁判員制度が導入されています。
裁判員制度の開始に伴い、国民感覚・国民の意識を取り入れられるようになった点が大きなメリットです。とくに、裁判員制度の対象となる事件は、重大事件のみであり、国民の関心が高い事件を取り扱うこととなり、国民の感情や感覚を取り入れやすいといったメリットがあります。
【メリット】司法への理解や関心が高まる
国民の司法に対する理解や関心が高まる点も大きなメリットです。裁判は犯罪を犯した者の有罪・無罪を決定し、有罪である場合は量刑を判断し、判決として言い渡さなければいけません。
刑事裁判は、一般に広く公開されているものの、裁判に関する興味関心を示す国民が少なく、裁判所に対する信頼低下に繋がる恐れがありました。
裁判員制度の導入に伴い、選挙権を有する国民はすべて裁判員に選ばれる可能性があります。このことにより、多く人が裁判に対する興味関心を持つきっかけとなり、裁判所に対する信頼性、不当な判決リスクの軽減等といったメリットが生まれています。
【課題】精神的負担や心理的ストレスが大きい
裁判員裁判は、裁判員の精神的な負担や心理的な負担が問題となっています。裁判員裁判は、とくに重大な事件のみを取り扱ううえに、公正な判断をするために現場写真等を裁判員が見なければいけません。
たとえば、ナイフで滅多刺しにされた殺人事件の裁判員に選ばれた場合、裁判員は被害者が滅多刺しにされた写真を見なければいけません。凶器のナイフを見たり、殺人に至るまでのリアルな経緯を聞いたりしなければいけません。
とくに重大な事件のみを取り扱う裁判員制度であるからこそ、精神的・心理的負担がとても重たくなる点が大きな課題です。
【課題】専門知識の不足による判断の難しさがある
裁判員は、国民の中から無作為に選ばれます。すべての人が法律知識に興味関心があるわけではありません。実際、裁判員に選ばれた人の多くが法律知識に乏しいです。
法律知識が乏しいながらも、刑事裁判に参加をして有罪・無罪を判断し、有罪である場合は量刑を判断しなければいけません。もちろん、裁判官等が丁寧に説明をしてくれるため、理解を深めたうえで裁判に参加できます。
とはいえ、知識が乏しいが故に「何も知らない自分が判断を下して良いのだろうか」といった葛藤が生まれるのも自然なことです。専門知識の不足による判断の難しさも、裁判員制度の課題の一つであると言えるでしょう。
【課題】辞退者が多く制度の持続可能性が問われている
裁判員制度は、本来は正当な理由がなければ辞退はできません。しかし、さまざまな理由で辞退をする人が多く、制度の持続可能性が問われています。
自分が人の人生に大きく関わる判断を下さなければいけないというのは、大きな負担になり得ます。このことから、「なんとかして辞退したい」と考える人が多いのも事実です。
裁判員制度を支える仕組みとサポート
裁判員制度に関する不安や疑問を抱えている国民は多いです。そのため、実際に行われている仕組みやサポートについても詳しく解説します。
裁判所からの説明・資料提供がある
初めて裁判に参加する人も多いため、さまざまな不安や疑問を抱えていることでしょう。しかし、初めての人でも安心できるよう、裁判所からしっかりと説明を受けられるため、安心して裁判員裁判に参加できます。
また、事件についての説明や必要書類も提供され、わからないことがあれば丁寧に教えてもらえます。このように、法律知識の乏しい一般の人でも安心して裁判員に参加できるような仕組みが整えられています。
わからないことはわからないとはっきり伝え、しっかりと理解したうえで判断を下すようにしましょう。
報酬や交通費が支給される
裁判員裁判に参加した人は、報酬や交通費が支給されます。また、宿泊が必要な場合は、宿泊費も支給されます。報酬は、裁判員候補者で裁判所に呼ばれた場合は8,000円以内、裁判員や補充裁判員に選ばれた場合は、10,000円以内で支払われます。
別途昼食代が支払われることはないものの、裁判所内にある食堂を利用したりお弁当を頼んだりできる裁判所があります。
勤務先は配慮が義務付けられている(労働基準法)
裁判員候補者や裁判員、あるいは補充裁判員に選ばれた場合、基本的には会社を休んで裁判所へ行かなければいけません。そのため、会社側には労働者が裁判員等に選ばれた場合は、配慮する義務が求められます。
具体的には、業務に著しい影響を与える場合を除いて休暇を与えたり、休暇を取得したことによる不当な解雇、不利益な取り扱いを禁止しています。これらは、労働基準法にて規定されており、違反した場合は会社側が処罰対象となるため注意しましょう。
精神的ケアや相談窓口が用意されている
裁判員裁判は残酷・残忍な事件を扱うケースも多く、話を聞いたり証拠を見たりすることによって、精神的ダメージを受けるケースがあります。そういった人たちのために、精神的ケアや相談窓口が設置されています。
もし、精神的・心理的なダメージを受けた場合も、ケアを受けられるという点で安心して裁判員裁判に参加できるのではないでしょうか。
守秘義務違反には罰則がある
裁判員に参加した場合、裁判上で知り得た情報について守秘義務を負います。守秘義務に違反した場合は、「6カ月以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金」が科されます。
ただし、裁判上で知り得た情報すべてにおいて守秘義務を負うわけではありません。むしろ、守秘義務を負う項目以外の内容は積極的に発信し、多くの国民の興味関心を集めることが良いと考えられています。
- 裁判員裁判で守秘義務を負う主な項目は以下のとおりです。
- 評議の秘密
- 職務上知った秘密
評議の秘密とは、話し合った内容を指します。結論に至った理由や裁判官、他の裁判員が話した内容を口外してはいけません。また、多数決の数も守秘義務を負います。
職務上知った秘密では、被害者のプライバシーに関する内容や裁判員の氏名等です。いずれも裁判員として参加する際に説明を受けるため、不明な点は確認をしたうえで守秘義務を守るようにしましょう。
裁判員を辞退できるケース
裁判員制度は、国民の意見等を司法に反映するためにある制度です。そのため、基本的には辞退できません。しかし、特別な事情がある場合は、辞退できる可能性があります。次に、裁判員を辞退できるケースについて詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
年齢・職業・資格などによる除外規定がある
裁判員は以下に該当する場合に辞退できる可能性があります。
- 70歳以上
- 学生
- 妊娠中
- 出産から8週間以内
- 妻・娘の出産の立ち会い・入退院の付き添い
- 同居人・家族の入退院の付き添い
- 重い病気やけが
- 親族の養育・介護
もちろん、上記に該当する人でも裁判員に参加することは可能です。あくまでも、上記に該当した場合は、辞退理由になり得る。ということです。
その他、以下に該当する場合は裁判員になれません。
- 欠格事由のある人
- 就職禁止事由のある人
- 不適格事由のある人
欠格事由とは心身故障が認められ、裁判員の職務が難しい人や禁錮刑以上の刑に処せられた人、国家公務員法38条の規定に該当する人、義務教育を終了していない人が該当します。
就職禁止事由のある人とは、国会議員や司法関係者、逮捕・勾留されている人、自衛官市町村長や都道府県知事等が該当します。
不適格事由がある人とは、たとえば裁判員裁判の対象となった事件の関係者(被害者遺族等)が該当します。
上記に該当した人は、裁判員になることができません。辞任できるケースとは異なり、そもそも裁判員になることができないことを覚えておいてください。
正当な理由があれば辞退できる
裁判員は、正当な理由がある場合は辞退できます。たとえば、健康・仕事・社会生活のうえで「正当である」と判断された場合です。おおむね裁判員を辞退できる事由について決められているものの、その他辞退したい理由がある場合は個別事案ごとに判断されます。
辞退申請は書面で提出する
辞退を希望する場合は、裁判員候補者に選ばれた際に調査票(質問票)が同封されていますので、その書面に辞退理由等を記載して返送します。
ただし、裁判員の自体は原則認められません。そのため、調査票に回答をしても裁判所のほうで辞退可否を判断し、認められなければ参加しなければいけません。
辞退が認められない場合もある
先ほども解説したとおり、正当な理由がなければ裁判員は原則辞退が認められません。辞退が認められなければ、裁判員へ強制的に参加する必要があります。
とはいえ、裁判員候補者に選ばれた人の7割弱が辞退している背景があります。このことから、正当な理由の範囲は広く判断されると思っておいて良いでしょう。なお、親族の葬儀など突発的に発生する事情がある場合は、裁判員として裁判に参加しなければいけないタイミングであっても辞退が可能です。
無断欠席は過料の可能性がある
裁判員に選ばれた人が正当な理由なく無断欠席をした場合、10万円以下の過料が科される可能性があるため注意しましょう。なお、「過料」と「科料」は異なり、裁判員の無断欠席による「過料」は刑事罰ではないため前科は付きません。
裁判員制度に関するよくある誤解
裁判員制度に関するよくある誤解を以下のとおり解説します。
- 裁判員は法律の知識が必要
- 一度なったら何度も呼ばれる
- 辞退すると罰則がある
- 判決に影響力はある
次に、裁判員制度に関するよくある誤解を解説しますので、ぜひ参考にしてください。
裁判員は法律の知識が必要
裁判員は法律的な知識がなくてもなれます。もちろん、有罪無罪を判断したり、量刑を判断したりするうえでは、必要最低限の法律知識が必要になる場面も多いです。
この点は、裁判官や裁判所職員から丁寧に教えてもらえます。過去の判例をもとにどの程度の刑罰が下されているか、どのようなことを基準に有罪・無罪を判断していたかなど、すべて丁寧に教えてもらえるため安心して参加してください。
一度なったら何度も呼ばれる
裁判員は完全無作為で選任れます。そのため、一度なったからといって、何度も呼ばれることはありません。むしろ、過去に裁判員に選ばれた人が2回目以降も裁判員候補者に選ばれた場合、辞退の申立てが可能です。
辞退できるのは裁判員(補充裁判員含む)の場合は5年以内、選任予定裁判員の場合は3年以内、裁判員候補者の場合は1年以内である場合のみです。
また、過去1年以内に裁判員等に選ばれた人は、その年に再度裁判員候補者に選ばれることはありません。
辞退すると罰則がある
裁判員を辞退しても罰則はありません。裁判員で罰則規定があるケースは、あくまでも「無断欠席した場合」です。無断欠席であっても、正当な理由がある場合は罰則はありません。
正当な理由がないにも関わらず、辞退をした場合は10万円以下の罰則となる可能性があるため注意しましょう。
判決に影響力はある
判決に影響力を与えるのは事実ですが、裁判官や他の裁判員と共に評議して判決を決定します。そのため、自分1人ですべてを悩み、結論を出す必要はないため安心してください。
裁判員制度に関するよくある質問
裁判員制度に関するよくある質問を紹介します。
Q.裁判員になると報酬はもらえますか?
A.裁判員になると報酬が支払われます。
裁判員候補者として裁判所に行った場合は、1日8,000円以下の報酬が支払われます。その他、交通費や宿泊が必要な場合は、宿泊費が支払われます。
裁判員に選ばれて、裁判に参加した場合は1日あたり10,000円以下の報酬が支払われ、交通費や宿泊費が必要な場合は別途支給されるため安心してください。なお、有給休暇等で会社から報酬を得たとしても二重取りになることはありません。
Q.守秘義務はいつまで続きますか?
A.一生涯続きます。
裁判員と知り得た情報のうち、守秘義務を負う内容の場合は一生涯守秘義務を負います。裁判が終了しても、被告人が出所してもなお、守秘義務が続くため注意してください。
Q.審理中にどうしても行けない日がある場合はどうすれば良いですか?
A.補充裁判員がその役割を担います。
事件によっては裁判の期間が長期化するケースがあります。この場合、裁判期間中になんらかの事情で参加できなくなるケースもあるでしょう。万が一、裁判員が参加できなくなった場合は、補充裁判員が変わって裁判に参加します。
Q.内容を家族に話しても良いですか?
A.守秘義務を負う内容以外は話しても問題ありません。
守秘義務を負っている内容については、たとえ家族であっても口外してはいません。ただし、守秘義務を負う内容以外のことについては、家族等に話をしても良いです。
Q.トラウマになったら賠償請求は可能ですか?
A.損害賠償請求は可能ですが、認められるかどうかは別問題です。
損害賠償請求は誰でも可能です。ただし、損害賠償が認められる可能性は低く、費用対効果が見込めません。
裁判員に選ばれて裁判に参加した人のうち、トラウマ等を受けた人は精神的なケアを受けられる制度等もあります。これらの制度の活用を検討されてみてはいかがでしょうか。
まとめ
裁判員制度は、司法制度の透明性を高め、国民の感覚を裁判に反映させるために導入された重要な仕組みです。選ばれた裁判員は、裁判官と同じ目線で重大な刑事事件に対する判断を下すという非常に責任の重い役割を担います。
証拠を見聞きし、被告人の有罪・無罪や量刑を決めるという過程には、相当な精神的負担やストレスが伴いますが、制度としては国民の司法参加を促す大きな一歩となっています。
一方で、制度が抱える課題も多くあります。法律知識を持たない一般人が判断することの難しさ、精神的負担の大きさ、そして辞退者の増加といった点は、制度の持続性にも影響を及ぼしかねません。これらの課題をカバーするために、裁判所からの説明や報酬制度、精神的ケア、勤務先への法的配慮など、さまざまなサポート体制が整備されています。
裁判員制度に選ばれるかどうかは運次第です。万が一通知が届いたときに慌てず対応するためにも、制度の仕組みや流れ、守るべきルールやサポート内容について、正しく理解しておくことが大切です。市民一人ひとりが司法に関心を持ち、制度の意義を理解することが、よりよい司法の実現につながる第一歩と言えるでしょう。