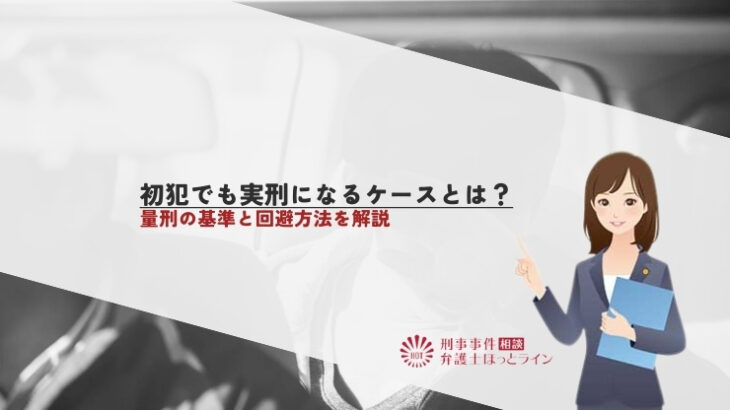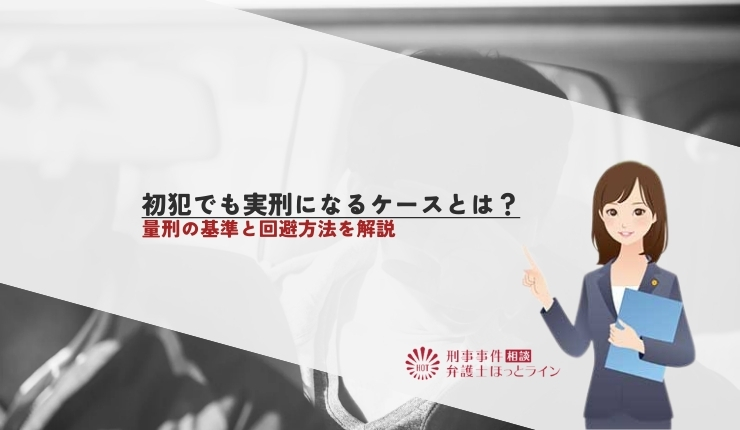
初犯であれば、刑事事件において必ず執行猶予が付くと考える人も少なくありません。しかし、現実には初犯であっても、犯罪の内容や悪質性、法定刑の範囲によっては実刑判決が言い渡されるケースがあります。
たとえば、殺人や強盗、薬物犯罪、性犯罪、危険運転致死傷罪、詐欺や横領などの経済犯罪は、初犯であっても実刑になる可能性が高い犯罪です。実刑判決とは、執行猶予が付かず刑罰が実際に執行される判決を指し、刑務所への収監だけでなく罰金刑も含まれる点に注意が必要です。
初犯でも実刑が科されるかどうかは、法定刑の範囲だけでなく、被害の程度や人数、計画性や悪質性の有無、反省や再犯防止の姿勢、被害者との示談状況など、さまざまな要素が量刑判断に影響します。
本記事では、「初犯で実刑になるケース」に焦点を当て、どのような犯罪や状況で実刑判決が下されやすいのか、逆に執行猶予付き判決が得られる可能性があるケースまで、具体例を交えてわかりやすく解説します。刑事事件のリスクを正しく理解し、初犯での実刑回避のポイントを押さえるために、ぜひ参考にしてください。
初犯と実刑の関係性
初犯とは、一般的に「有罪の確定判決を受けたことがない人」という意味で使用される言葉です。一方で、「実刑」とは「執行猶予とはならず、実際に刑罰が執行された場合」を指す言葉です。
初犯であっても実刑となる可能性はありますし、再犯者や前科がある人でも執行猶予付きの判決が言い渡される可能性もあります。まずは、初犯と実刑の関係性とは何か?について詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
「初犯」の定義
初犯とは、「これまでに有罪の確定判決を受けたことがない人」を指します。通常、刑事裁判では以下の流れで事件が進んでいきます。
- 逮捕・在宅捜査
- 起訴・不起訴の判断
- 刑事裁判
- 判決
初犯とは、「これまでに有罪の確定判決を受けたことがない人」を指すため、過去に逮捕や被疑者として捜査対象になったことがある人でも、有罪判決が確定していなければ「初犯」となります。
たとえば、「逮捕された経験はあるけど、不起訴になった」や「刑事裁判まで行ったけど、無罪判決を受けた」という人が新たな罪を犯してもそれは初犯です。
一方で、初犯を「初めてその犯罪を犯した人」という意味合いで使用されるケースもあります。たとえば、「過去に前科はあるけれども、覚せい剤取締法違反で逮捕されたのは初めて」という場合に「覚せい剤では初犯」といった言い方をするケースもあります。
ただ、一般的に初犯といった場合は「これまでに有罪の確定判決を受けたことがない人」という意味であることを覚えておきましょう。
実刑判決の定義
実刑判決とは、執行猶予が付かずに刑事罰が執行された場合に使用される言葉です。
まず、「執行猶予」とは刑罰の執行を猶予されることを指します。たとえば、「拘禁刑1年執行猶予3年」の判決が言い渡された場合、拘禁刑1年の刑罰は、直ちに執行されません。刑事罰を3年間猶予し、社会生活を送る中で更生を目指します。
ただし、執行猶予期間中に罰金刑以上の刑罰が確定した場合は、執行を猶予されていた拘禁刑1年が加算されて刑罰が執行されます。
たとえば、新たに犯した罪で「100万円の罰金刑」が確定した場合は、100万円の罰金刑に加えて、1年間の拘禁刑も執行されるということです。一方で、罰金刑以上の刑罰が確定することなく、執行猶予期間を過ごした場合は、1年の拘禁刑は執行されません。
拘禁刑とは、2025年6月1日に導入された新しい刑事罰です。これまでは、刑務作業が義務付けられている「懲役刑」と刑務作業が義務付けられていない「禁錮刑」という刑罰がありました。これらが一本化され、「拘禁刑」となりました。刑務作業が義務ではなくなり、受刑者の状況に応じて、刑務作業等が割り当てられます。
中には、「実刑判決=刑務所に収監されること」と勘違いをされている人もいます。しかし、実刑判決は「執行猶予がつかなかった判決」のことを指すため、たとえば、略式起訴されて「50万円の罰金」が言い渡された場合も実刑判決と呼びます。
執行猶予が適用されるケース
執行猶予が適用されるためには、以下の要件を満たしている必要があります。
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
2 前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。引用元:刑法|第25条
つまり、執行猶予が付くかどうかは、初犯かどうかは関係ありません。過去に前科がある場合であっても、状況によっては執行猶予が付きます。
一方で、初犯であっても重大な犯罪を犯し、3年を超える拘禁刑や50万円を超える罰金刑が相当であると判断された場合は、執行猶予が付かず実刑判決となります。
たとえば、殺人罪の法定刑は「死刑または無期懲役もしくは5年以上の拘禁刑」です。法定刑の下限が5年以上の拘禁刑であるため、原則、殺人罪で執行猶予は付きません。
初犯でも実刑が科される代表的な犯罪
初犯であっても実刑判決が科される代表的な犯罪は、以下のとおりです。
- 殺人・強盗などの重大犯罪
- 薬物犯罪
- 性犯罪
- 危険運転致死傷など交通犯罪
- 詐欺や横領などの経済犯罪
それぞれの法定刑と共に、実刑判決と執行猶予付き判決の違いについて詳しく解説します。
殺人・強盗などの重大犯罪
殺人罪や強盗罪など、いわゆる重大犯罪に分類される犯罪を犯した場合は、実刑判決となる可能性がとても高いです。
たとえば、殺人罪の法定刑は「死刑または無期懲役もしくは5年以上の拘禁刑」です。強盗罪の法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」です。
改めて、執行猶予を付けるための条件を確認すると「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたとき」です。つまり、法定刑から見ても執行猶予を付けることができず、実刑判決となる可能性が高いのです。
ただし、先ほども解説したとおり、過去には殺人罪で執行猶予付きの判決が言い渡された事例もあります。この事例を確認すると、情状酌量による減刑が認められたことが要因です。
殺人という重大犯罪を犯すに至った経緯などを考慮し、情状酌量による減刑が認められ、3年以下の懲役(当時は懲役刑)が言い渡されたため、執行猶予が可能でした。このように、事情次第では、重大犯罪であっても執行猶予付き判決が言い渡される可能性がゼロではありません。
しかし、強盗のように身勝手な犯行である場合は、情状酌量による減刑はほとんど認められません。「お金がなくて」「明日も食べるものがなくて」といった状況であっても、強盗を犯して良い理由にはならないためです。
薬物犯罪
薬物犯罪の場合、初犯であっても実刑判決が言い渡される可能性があります。たとえば、違法薬物の大量輸入や大量譲渡など、違法性が高い場合が該当します。
薬物犯罪の場合は、違法となる薬物の種類によって法定刑が異なるため、一概には言えません。たとえば、覚せい剤取締法違反を例に見ると、法定刑は以下のとおりです。
| 罪状 | 法定刑 |
|---|---|
| 輸入・輸出・製造 | 1年以上の有期拘禁刑 |
| 営利目的での輸入・輸出・製造 | 無期又は3年以上の拘禁刑、情状により1000万円以下の罰金併科 |
| 所持・譲渡し・譲受け | 10年以下の拘禁刑 |
| 営利目的での所持・譲渡し・譲受け | 1年以上の有期拘禁刑、情状により500万円以下の罰金併科 |
| 使用 | 10年以下の拘禁刑 |
| 覚せい剤原料の輸入・輸出・製造 | 10年以下の拘禁刑 |
| 営利目的での覚せい剤原料の輸入・輸出・製造 | 1年以上の有期拘禁刑、情状により500万円以下の罰金併科 |
| 覚醒剤原料の所持・譲渡し・譲受け・使用 | 7年以下の拘禁刑 |
上記のとおり、いずれの場合も執行猶予付き判決の条件は満たせる可能性があります。しかし、現実的に悪質性が高い場合は、3年を超える拘禁刑や50万円を超える罰金刑が言い渡される可能性が高く、初犯でも実刑判決となる可能性が高いです。
ただし、覚せい剤使用による検挙で所持量が少ない場合や、営利目的ではない場合などは初犯であれば執行猶予が付く可能性が高いでしょう。ただし、再犯の場合は実刑判決となる可能性が高いため注意しましょう。
性犯罪
性犯罪は法定刑が厳しく、執行猶予の条件を満たせていないため実刑判決となる可能性が高いです。主な性犯罪のの種類と法定刑は以下のとおりです。
| 罪状 | 法定刑 |
|---|---|
| 不同意性交等罪 | 5年以上の有期拘禁刑 |
| 不同意わいせつ罪 | 6カ月以上10年以下の拘禁刑 |
性犯罪は法定刑が上記のとおり厳しいため、執行猶予付き判決を得られる可能性は低いです。また、性犯罪は被害者の処罰感情が強いケースも多く、結果的に「3年以下の拘禁刑」といった条件を満たせずに実刑判決となることが多いです。
危険運転致死傷など交通犯罪
交通犯罪も法定刑が厳しく、執行猶予付き判決が下されにくい傾向にあります。よくある交通犯罪とそれぞれの法定刑は以下のとおりです。
| 罪状 | 法定刑 |
|---|---|
| 危険運転致死傷罪 | 人を死亡させた場合:1年以上の有期拘禁刑 人を怪我させた場合:15年以下の拘禁刑 |
| 過失運転致死傷罪 | 7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
上記のとおり、法定刑が3年を超える拘禁刑となる可能性が高いことから、執行猶予付きの判決が下される可能性が低いことがわかります。ただし、過失運転致死傷罪の場合、執行猶予付きの判決が下される可能性もあります。
過失の程度にもよりますが、被害者にも過失がある場合は執行猶予付き判決となるケースがもあるため覚えておきましょう。たとえば、歩行者が信号を無視して道路上に飛び出してきて、負傷で済んだ場合が該当します。
基本的には歩行者側の過失割合が高くなりますが、たとえば自動車の運転手の前方不注意が認められる場合は、過失運転致死傷罪が適用されるケースもあります。とはいえ、この場合は歩行者側の重過失が認められるため、基本的には不起訴や執行猶予付きの判決が下されるでしょう。
一方で、危険運転致死傷罪は執行猶予の可能性がとても低いです。危険運転致死傷罪が適用されるケースとは、たとえば飲酒運転によって人を死傷させた場合や、過度なスピード超過により人を死傷させた場合です。相当悪質であるため、基本的には実刑判決となる可能性が高いと思っておいたほうが良いでしょう。
詐欺や横領などの経済犯罪
詐欺罪や横領罪の場合も、初犯でも実刑判決となる可能性が高いです。とくに被害者が多くいる場合や被害額が大きい場合です。詐欺罪や横領罪のそれぞれの法定刑は以下のとおりです。
| 罪状 | 法定刑 |
|---|---|
| 詐欺罪 | 10年以下の拘禁刑 |
| ※業務上横領罪 | 10年以下の拘禁刑 |
※横領罪は、単純横領罪や占有離脱物横領罪、業務上横領罪等ありますが、ここでは業務上横領罪を前提に話を進めます。
詐欺罪および業務上横領罪は、いずれも法定刑が「10年以下の拘禁刑」です。そのため、現実として3年以下の拘禁刑が言い渡される可能性はゼロではありません。つまり、執行猶予付きの判決が言い渡される可能性はあります。
しかし、法定刑が10年以下の懲役であれば、情状酌量が認められたり、初犯であったりしても実刑判決を回避するのは非常に困難です。
量刑判断に影響する要素
量刑判断に影響を与える要素は以下のとおりです。
- 被害程度・被害人数
- 計画性や悪質性の有無
- 反省の有無と再犯の可能性
- 示談の成立と被害者の処罰感情
量刑を軽減できれば、実刑判決を回避し、執行猶予付き判決を得られる可能性もあるでしょう。次に、量刑判断に影響を与える要素についても詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
被害者への被害の程度や人数
被害者の被害程度や人数によって、量刑判断は大きく異なります。たとえば、詐欺罪を例に見ると、詐欺被害の人数や被害額が大きければ大きいほど、厳しい量刑が言い渡されます。
一方で、被害者が1人で被害額が少額で、被害弁済がなされている、などの事情がある場合は量刑が軽くなる可能性があります。結果的に実刑判決を回避できる可能性が高まるでしょう。
計画性・悪質性の有無
計画性や悪質性の有無も量刑判断に大きな影響を与えます。たとえば、殺人罪を例に見ると、「〇〇さんを殺害するために、あらかじめ包丁を用意しており、社内には山中へ埋めるようにスコップを用意していた」また、「〇〇さんの生活スタイルを事前に把握し、狙って犯行を行った」という場合は、計画性が認められるため量刑は厳しくなります。
一方で、「その場で口論になり、突発的に〇〇さんを殺害してしまった」という状況であれば、計画性は認められません。計画性が認められなかったからといって減刑されることはないものの、殺害に至った経緯や事情などを考慮して、計画性が認められた場合よりも量刑が軽くなる可能性はあります。
また、悪質性を殺人罪で例えるならば、「自己中心的な犯行かどうか」で判断できるでしょう。たとえば、「〇〇さんからお金を借りており、返済できなくなって殺害した」となれば、自分勝手で身勝手な犯行であると判断されます。
一方で、「長年暴力を振るわれており、そのうち自分が殺されてしまうのではないかと思った。殺される前に殺そうと思って、犯行に及んでしまった」という場合は、悪質性が低いと判断されます。他にも、残忍性や残虐性などを考慮したうえで量刑が判断されることとなるでしょう。
反省の有無と再犯の可能性
反省の有無と再犯の可能性も考慮したうえで、量刑が判断されます。反省している態度を示すことはもちろん、具体的にどのように再犯を防止するのか?といった点も非常に重要です。
たとえば、薬物乱用者が「今回初めて逮捕されたことで、薬物を辞めるきっかけになった」と反省の弁を述べてもあまり意味がありません。具体的に「〇〇(施設名)や〇〇の力を借りて、薬物を断ちます」のように具体的な再販防止策を述べられるかどうかがポイントです。
示談の成立と被害者の処罰感情
被害者がいる事件の場合は、被害者の処罰感情が量刑判断に大きな影響を与えます。被害者と示談が済んでいる場合は、不起訴処分となったり執行猶予付きの判決が言い渡されたりする可能性が高まります。
実際、重大な事件であっても被害者と示談交渉が完了しており、被害者の処罰感情がなくなっていることを理由に、執行猶予付き判決が言い渡されるケースは多くあります。
初犯でも実刑となるケースの具体例
初犯でも実刑となる主なケース、具体例について以下のとおり解説します。
- 覚せい剤の使用・所持事件
- 飲酒運転による死亡事故
- 詐欺グループに関与した初版の実刑例
次に、初犯でも実刑判決が言い渡された主な事例について詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
覚せい剤の使用・所持事件での実刑判決
覚せい剤の使用や所持は、基本的に初犯であれば執行猶予付きの判決が言い渡される可能性が高いです。しかし、所持量が多くて営利目的である可能性が高いと判断された場合は、実刑判決が下されるケースも多々あります。
飲酒運転による死亡事故の実例
飲酒運転によって人を死亡させた場合は、危険運転致死傷罪という犯罪が成立します。この犯罪の法定刑は「1年以上の有期拘禁刑」です。
「1年以上の有期拘禁刑」であるため、1年〜3年の判決が言い渡されれば、執行猶予が付く可能性もあります。しかし、上限は20年(加重で30年)です。つまり、現実的に考えて執行猶予付き判決が言い渡される可能性は限りなくゼロに近いと思っておいたほうが良いでしょう。
詐欺グループに関与した初犯の実刑例
詐欺罪は、初犯であっても実刑判決となる可能性が高い犯罪です。とくに、詐欺グループに関与していた場合、被害額や被害人数が多い傾向にあります。このことから、執行猶予の可能性は低いと思っておいたほうが良いでしょう。
また、受け子や出し子といった末端の人たちが逮捕されたとしても、執行猶予が付くケースは稀です。「とくに詐欺罪は実刑判決の可能性が高い」と思っておいた方が良いでしょう。
初犯で実刑を回避できる可能性
初犯で実刑を回避するためには、以下のポイントを押さえておく必要があります。
- 被害者との示談交渉を進めておく
- 反省・更生の態度を示しておく
- 弁護士による適切な弁護活動
初犯で実刑を回避できるかどうかは、まず第一に犯罪の内容です。たとえば、殺人罪のようや強盗殺人のように重大な犯罪の場合は、ほぼ100%執行猶予が付きません。
一方で、軽犯罪法違反のように比較的軽微な犯罪であっても、実刑判決となる可能性はあります。
一概に「〇〇をすれば執行猶予が付く、実刑になる」といったことは言えません。ただし、これから解説する内容をしっかりと対応することで実刑を回避できる可能性は高まるため、ぜひ参考にしてください。
被害者と示談することの効果
初犯で実刑を回避するためには、被害者との示談交渉成立有無が非常に重要です。示談交渉が成立することによって、被害者の処罰感情が弱くなっていることが明らかとなります。
示談の成立が法的根拠となることはないものの、量刑を判断するうえで被害者の処罰感情は非常に重要なものとなります。被害者があなたに対して「示談が済んでおり、処罰を求めません」と伝えることで、実刑を回避できる可能性が高まるでしょう。
一方で、被害者が「一切示談に応じない」という姿勢を示し、「厳罰を望みます」といった場合は、量刑が重くなる可能性があるため注意しましょう。
反省・更生の姿勢を示す方法
反省している態度、更生を目指す態度をしっかりと示すことが大切です。量刑判断をするにあたって、「再犯の可能性」も考慮されるためです。被告人本人が反省して更生を目指す態度を取っている場合、裁判官としては「社会生活の中で更生を目指してほしい」と考え、執行猶予を付ける可能性が高まります。
弁護士による適切な弁護活動の重要性
弁護士による適切な弁護活動が非常に重要です。弁護士は、被疑者や被告人にとって唯一の味方です。
たとえば、反省や更生を目指している態度の示し方、被害者との示談交渉を進めるなど、被疑者や被告人にとって有利となるように活動してくれます。裁判においては、「被告人は〇〇のとおり反省しており、再犯の可能性は低い」などと主張してくれます。
なお、弁護人は国選弁護人と私選弁護人のいずれかがかならず選任されます。国選弁護人であれば、費用は発生しないものの、選任されるタイミングが遅いです。一方で、私選弁護人は自分で費用を負担しなければいけないものの、自分の好きなタイミングで選任できます。
できるだけ早めに刑事弁護に強い弁護人を選任し、適切な弁護活動を開始してもらうようにしましょう。
よくある質問
初犯での実刑回避に関するよくある質問を紹介します。
Q.初犯なら必ず執行猶予がつきますか?
A.初犯でも実刑判決になる可能性があります。
犯罪の種類や内容、状況等によっても異なりますが、初犯であっても実刑判決となる可能性があります。初犯だから執行猶予が付く、再犯だから実刑判決が言い渡される、といったことはありません。
Q.実刑になった場合、刑期短縮は可能ですか?
A.初犯であることを理由に刑期が短縮されることはありません。
刑期が短縮される主な理由は、刑務所の中の生活態度や被害者への被害弁済等を考慮したうえで判断されます。そのため、初犯であることを理由に早期に釈放される、といったことはありません。
Q.示談すればかならず実刑を回避できますか?
A.かならず実刑が回避できるとは限りません。
示談が成立したとしても、実刑を回避できるとは限りません。あくまでも「被害者の処罰感情がなくなった」という事実を客観的に証明するためのものにすぎません。
反省の態度や再犯の可能性、事件の内容等を総合的に判断したうえで判断されるため、一概に「示談=実刑回避」とは言い切れません。とはいえ、実刑を回避できる可能性は高まるでしょう。
Q.弁護士に相談するのはいつがいいですか?
A.できるだけ早い段階で相談をしたほうが良いです。
弁護士へ早めに相談をすることで、実刑回避だけではなく、「不起訴」の可能性も出てきます。たとえば、犯罪の内容や程度によるものの、起訴前に示談交渉が成立すれば、不起訴処分を得られる可能性があるでしょう。
なお、私選弁護人であれば自分の好きなタイミングで弁護人を選任できるため、依頼を検討されてみてはいかがでしょうか。
Q.初犯で実刑になった場合、刑務所の生活はどのようなものですか?
A.初犯か再犯かによる違いはありません。また、刑務所や受刑者によって生活は異なります。
刑務所の中では、外から鍵を閉められる部屋に複数人で生活を送ります。規則正しい生活を送りながら、更生して再犯防止プログラムを実施したり、刑務作業を行ったりして刑期を過ごします。
模範囚となれば、早期に仮釈放が認められる可能性もあります。まずは、刑務所の生活に慣れ、早期の社会復帰を目指しましょう。
まとめ
初犯であっても、実刑判決が下される可能性は決してゼロではありません。とくに、殺人・強盗などの重大犯罪や、薬物の営利目的所持、性犯罪、危険運転致死傷罪、詐欺や横領など、法定刑の下限が高く悪質性の強い犯罪では、初犯でも執行猶予が付かずに実刑となるケースが多く見られます。
逆に、軽微な犯罪や被害者との示談が成立している場合、初犯で反省・更生の姿勢を示すことで、執行猶予付き判決を得られる可能性もあります。量刑判断では、被害の程度や人数、計画性や悪質性の有無、被告人の反省態度、再犯防止策、被害者の処罰感情などが総合的に考慮されます。
また、初犯での刑事手続きでは、弁護士による適切な弁護活動が実刑回避に大きく影響します。被害者との示談交渉や、反省の態度の示し方、法的主張の整理など、専門家の助言を得ることで、量刑を有利に進められる可能性があります。
初犯だからといって安心せず、犯罪の内容や状況に応じた対応が重要です。本記事では、初犯で実刑となるケースやその具体例、執行猶予を得るためのポイントを詳しく解説しており、刑事事件のリスクを理解し適切に対応するための参考資料として活用できます。