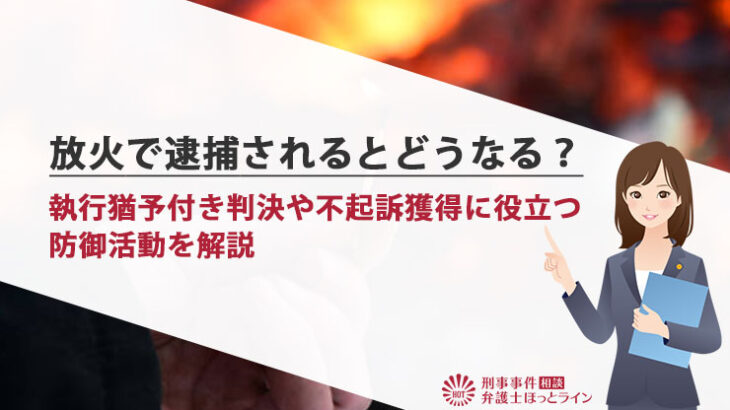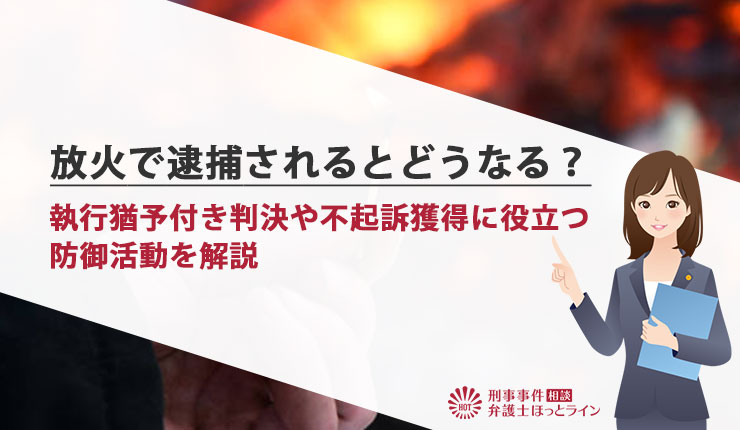
放火の容疑で逮捕されると極めて重い刑事処分が下されます。なぜなら、放火は「公共の危険」を発生させるだけではなく、特定個人の生命・身体や財産的利益を侵害することもある重大犯罪に位置付けられるからです。
特に、人が居住している住宅や人が所在する建造物を放火したときには、逮捕・勾留によって長期間身柄拘束されるだけではなく、初犯でも長期の実刑判決を下される危険性に晒されかねません。
そこで今回は、過去の放火事件を理由に後日逮捕されるのではないかと不安を抱えている方や、ご家族が放火の容疑で逮捕された方のために、以下4点について分かりやすく解説します。
- 放火事件を起こして逮捕されるときの犯罪類型(構成要件・法定刑)
- 放火事件を起こして逮捕されるときの刑事手続きの流れ
- 放火の容疑で逮捕されるときに生じるデメリット
- 放火の容疑で逮捕されたときに弁護士へ相談するメリット
放火をめぐる犯罪の法定刑は極めて重いので、不起訴処分や執行猶予付き判決獲得を目指すなら、刑事手続き初期段階からの効果的な防御活動が不可欠です。
かならず放火事件などの刑事事件を専門に扱っている私選弁護人までご依頼ください。
目次
放火犯が逮捕されるときの犯罪類型
以下のように、放火をした客体によって成立する犯罪類型は異なります。
- 現住建造物等放火罪
- 非現住建造物等放火罪
- 自己所有非現住建造物等放火罪
- 建造物等以外放火
- 自己所有建造物等以外放火罪
現住建造物等放火罪
現住建造物等放火罪とは、「放火をして、『現に人が住居に使用し、または、現に人がいる建造物・汽車・電車・艦船・鉱坑』を焼損したとき」に成立する犯罪類型のことです(刑法第108条)。
「公共の危険」だけではなく「建造物等の内部に所在する人に対する危険」も生じるため、現住建造物等放火罪は「死刑または無期懲役もしくは5年以上の懲役刑」という極めて重い法定刑が定められています。
現住建造物等放火罪は未遂犯も処罰対象です(同法第112条)。
また、現住建造物等放火罪を犯す目的でその予備をしたときには、「2年以下の懲役刑」の範囲で処断されます(同法第113条)。ただし、情状次第で刑が免除されます。
現住建造物等放火罪の客体
現住建造物等放火罪の客体は「現に人が住居に使用し、または、現に人がいる建造物・汽車・電車・艦船・鉱坑」です。
まず、住居とは、「人の起臥寝食の場所として日常使用されるもの」のことです(大判大正2年12月24日)。たとえば、学校の宿直室や待合の離れ座敷なども住居に含まれると考えられています。
次に、建造物とは、「家屋その他これに類似する建築物であり、屋根があって壁・柱で支持されて土地に定着し、少なくともその内部に人が出入りすることができるもの」を意味します(大判大正3年6月20日)。つまり、毀損せずに取り外し可能な建具・布団・畳・雨戸などは建造物の一部だとは言えません(最判昭和25年12月14日)。
さらに、汽車・電車とは、「一定の軌道上を運行する交通機関(汽車の動力は蒸気機関、電車の動力は電気)」のことです。ディーゼルカーやモノレールはこれらに含まれますが、その一方で、軌道上を走行しないバスや航空機は現住建造物等放火罪の客体ではありません(大判昭和15年8月22日)。また、艦船とは「軍艦及び船舶」のことを、鉱坑は「炭坑など地下の鉱物を採取するための設備」を意味します。
現住性・現在性
現住建造物等放火罪の客体は、「現に人が住居に使用するもの(現住建造物等)」「現に人が存在するもの(現在建造物等)」である必要があります。
まず、現住性・現在性を判定する際の「人」とは、「犯人及び共犯者以外の者」のことです(最判昭和32年6月21日)。たとえば、犯人の家族や同居人がいる建造物等に放火したときには現住建造物等放火罪が成立しますが、犯人のみが単独で居住する建造物等や居住者全員を殺害した後に放火をしたときには、非現住検討物等放火罪の成否が問題になるにとどまります。
次に、外観上複数の建造物が接合された「複合建造物」について、その一部に現住性が認められる場合、物理的一体性がある部分に限って全体として現住建造物等として扱うことが可能だと考えるのが判例です(最決平成元年7月14日)。たとえば、人が寝泊まりしている劇場の便所に放火しただけだとしても、劇場と便所には物理的一体性があると評価される以上、現像建造物等放火罪の容疑で逮捕されます。
さらに、集合住宅のような「不燃性・難燃性建造物」については、確かに構造上の一体性は認められるものの、耐火構造によって区画ごとの独立性が強いと考えられる以上、延焼可能性が排斥されている場合に限って区画ごとを独立した建造物と評価できます(延焼可能性がある場合には建物全体が1個の建造物として判断されます)。たとえば、3階建てマンションの空き家に放火したとき、マンションの耐火構造がしっかりしている場合には非現住建造物等放火罪が成立するにとどまりますが、延焼可能性を否定できない場合には現住建造物等放火罪の容疑で逮捕されるでしょう。
現住建造物等放火罪の実行行為
現住建造物等放火罪の実行行為は「放火すること」です。
放火行為には「現住建造物等に焼損を生じさせる行為」が幅広く含まれます。たとえば、目的物である現住建造物等に対して直接火を着ける行為だけではなく、媒介物を点火すること、ガソリンなどの引火性の強い物質を散布して点火することなどが挙げられます。
なお、ここに言う焼損は「火が媒介物を離れて、目的物が独立に燃焼を継続するに至った状態」を指すと考えるのが判例実務です(独立燃焼説、最判昭和23年11月2日)。
非現住建造物等放火罪
非現住建造物等放火罪とは、「放火をして、『現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない”他人所有”の建造物・艦船・鉱坑』を焼損したとき」に成立する犯罪類型のことです(刑法第109条第1項)。
非現住建造物等放火罪の法定刑は「2年以上の有期懲役」と定められています。これは、建物内部に所在する人に対する危険が存在しないため、現住建造物等放火罪と比較すると可罰的違法性が低いと考えられるからです。
非現住建造物等放火罪は未遂犯も処罰対象です(同法第112条)。
また、非現住建造物等放火罪を犯す目的でその予備をしたときには、「2年以下の懲役刑」の範囲で処断されます(同法第113条)。ただし、情状次第で刑が免除されます。
自己所有非現住建造物等放火罪
自己所有非現住建造物等放火罪とは、「放火をして、『現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない”自己所有”の建造物・艦船・鉱坑』を焼損したとき」に成立する犯罪類型のことです(刑法第109条第2項本文)。
非現住建造物等放火罪と違って「他人の所有権」を侵害することはないので、「6カ月以上7年以下の懲役刑」の範囲で処断されます。
なお、自己所有非現住建造物等放火罪は、「公共の危険(燃え広がり・延焼による不特定・多数人の生命・身体・財産に対する危険)」を生じなかったときには処罰されません(同法第109条第2項但書、最決平成15年4月14日)。
建造物等以外放火罪
建造物等以外放火罪とは、「放火をして、『現住建造物等、非現住建造物等、自己所有非現住建造物等以外の”他人所有”の物』を延焼して、公共の危険を生じさせたとき」に成立する犯罪類型のことです(刑法第110条第1項)。
たとえば、人の乗車していない自動車、バイク、家具などに放火をしたときには、建造物等以外放火罪の容疑で逮捕されます。
建造物等以外放火罪の法定刑は「1年以上10年以下の懲役刑」です。
自己所有建造物等以外放火罪
自己所有建造物等以外放火罪とは、「放火をして、『現住建造物等、非現住建造物等、自己所有非現住建造物等以外の”自己所有”の物』を延焼して、公共の危険を生じさせたとき」に成立する犯罪類型のことです(刑法第110条第1項)。
自己所有建造物等以外放火罪の法定刑は「1年以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑」です。
放火をめぐるその他の関係犯罪
放火の客体やその他の事情次第では、以下の罪状で逮捕される可能性も生じます。
- 延焼罪
- 消火妨害罪
- 失火罪
- 激発物破裂罪
- 業務上失火罪・重失火罪
- ガス漏出等罪、同致死傷罪
延焼罪
延焼罪が成立する場面として以下2つの場面が挙げられます。
第1に、延焼罪は、「刑法第109条第2項の罪(自己所有非現住建造物等放火罪)または同法第110条第2項の罪(自己所有建造物等以外放火罪)を犯し、よって、同法第108条の罪(現住建造物等放火罪)または同法第109条第1項(非現住建造物等放火罪)に規定する物に延焼させたとき」に成立します(同法第111条第1項)。このパターンの延焼罪の法定刑は「3カ月以上10年以下の懲役刑」です。
第2に、延焼罪は、「刑法第110条第2項の罪(自己所有建造物等以外放火罪)を犯し、よって、同法第110条第1項の罪(建造物等以外放火)に規定する物を延焼させたとき」にも成立します(同法第111条第2項)。このケースの延焼罪の法定刑は「3年以下の懲役刑」です。
消火妨害罪
消火妨害罪とは、「火災の際に、消火用の物を隠匿・損壊、または、その他の方法によって消火を妨害したとき」を処罰対象にする犯罪類型のことです(刑法第114条)。
まず、状況として、本罪が成立するのは火災発生現場に限られます。火災発生現場における妨害行為は「公共危険の発生・拡大を促進する行為」と評価されるので、別途犯罪として処断されます。
また、消防車や消火用ホース、消火器などを隠匿・損壊するだけではなく、消防車の出動を妨げる行為や、消防士の消防活動を妨げる幅広い行為が本罪の処罰対象に含まれます。
消火妨害罪の法定刑は「1年以上10年以下の懲役刑」です。
失火罪
失火とは、「過失によって出火させること」です。失火罪が成立する場面として以下2点が挙げられます。
第1に、失火罪は、「失火によって、刑法第108条の罪(現住建造物等放火罪)、または、他人の所有する刑法第109条の罪(非現住建造物等放火罪)に規定される物を焼損したとき」に成立します(同法第116条第1項)。このケースの法定刑は「50万円以下の罰金刑」です。
第2に、失火罪は、「失火によって、刑法第109条(非現住建造物等放火罪)に規定する物であって自己所有に係るもの、または、同法第110条(建造物等以外放火罪)に規定する物を焼損して、公共の危険を生じさせたとき」にも成立します(同法第116条第2項)。この場合の失火罪の法定刑も「50万円以下の罰金刑」です。
激発物破裂罪
激発物破裂罪とは、「火薬・ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、『刑法第108条(現住建造物等放火罪)に規定する物、または、他人の所有に係る同法第109条(非現住建造物等放火罪)に規定する物』を損壊したとき」「『刑法第109条(非現住建造物等放火罪)に規定する物であって自己の所有に係るもの、または、同法第110条(建造物等以外放火罪)に規定する物』を損壊して、これによって公共の危険を生じさせたとき」を「放火犯」として取扱う犯罪類型のことです(同法第117条第1項)。
また、これらの行為が故意ではなく過失によって引き起こされたときには、「失火犯」として処断されます(同法第117条第2項)。
業務上失火罪・重失火罪
業務上失火罪・重失火罪は、「刑法第116条(失火罪)または刑法第117条第1項(激発物破裂罪)の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるものであるとき、または、重大な過失によって引き起こされたとき」に成立します(刑法第117条の2)。
業務上失火等罪とは「3年以下の禁錮刑、または、150万円以下の罰金刑」です。
業務上失火罪における「業務」とは、「職務として火気の安全に配慮すべき社会生活上の地位」のことです(最決昭和60年10月21日)。
たとえば、公衆浴場経営者・ボイラーマン・溶接作業員・調理師などの「火気を直接扱う職務従事者」や、高圧ガス等販売業者・ディーゼルエンジン自動車の運転者・サウナ風呂製作者・給油作業員などの「火気の発生しやすい物質・器具・設備等を取り扱う職務従事者」、夜警・劇場・ホテル経営者・支配人などの「火災の発見・防止を任務とする職務従事者」が挙げられます。
これに対して、個人的に行われる喫煙・家庭内で行われる調理などは、反復継続されたとしても、業務上失火罪における「業務」には該当しません。
ガス漏出等罪、同致死傷罪
「ガス・電気・蒸気を漏出・流出・遮断することによって、人の生命・身体・財産に危険を生じさせたとき」にはガス漏出等罪が成立します(刑法第118条第1項)。ガス漏出等罪の法定刑は「3年以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑」です。
また、「ガス・電気・蒸気を漏出・流出・遮断することによって人を死傷させたとき」には、ガス漏出等致死傷罪に問われます(同法第118条第2項)。ガス漏出等罪と傷害の罪(傷害罪、傷害致死罪など)を比較して重い刑の範囲で処断されます。
放火で逮捕されるときの刑事手続きの流れ
放火事件を起こして逮捕されるときの刑事手続きの流れは以下の通りです。
- 放火の容疑で警察に逮捕される
- 放火事件について警察段階の取調べが実施される
- 放火事件について検察段階の取調べが実施される
- 検察官が放火事件を公訴提起するか否か判断する
- 放火事件が公開の刑事裁判にかけられる
放火を理由に警察に逮捕される
放火事件を起こしたことが発覚すると警察に逮捕されるのが一般的です。
逮捕処分は以下3種類に分類されます。
- 通常逮捕
- 現行犯逮捕
- 緊急逮捕
通常逮捕
通常逮捕とは、「裁判官の事前審査を経て発付される逮捕令状に基づいて実施される身柄拘束処分」のことです(刑事訴訟法第199条第1項)。
たとえば、過去の放火事件について捜査活動が展開されて、容疑が固まったときに逮捕状が発付されます。そして、平日早朝など、被疑者が在宅していることが明らかなタイミングを見計らって、捜査員が自宅にやってきて逮捕状が執行されます。
過去の放火事件が発覚するきっかけ
過去の放火事件はさまざまなシチュエーションで発覚します。
たとえば、集合マンションなどの人の出入りが激しい建造物に放火をしたケースでは、マンション各所や駐車場に設置された防犯カメラや住民の自動車に搭載されたドライブレコーダーなどに犯行の様子が写り込んでいることもあるでしょう。放火をしたときに犯人自身が重度の火傷を負って通院を余儀なくされたときには、捜査機関が各医療機関に問い合わせを実施することで犯人の身元が明らかになります。
また、放火犯は快楽的な理由から同じような手口で犯行を重ねることも多いため、余罪への関与がきっかけで検挙に繋がるパターンもあり得ます。さらに、放火事案では消火活動が行われている現場の野次馬それぞれに対する捜査活動も実施される点に注意が必要です。
このように、放火の犯行現場自体の目撃者が存在しなくても、過去の放火事件はかなりの確率で捜査機関にバレる可能性が高いです。現段階で捜査機関から接触がない状況なら、自首や示談交渉などの防御活動によって刑事手続きを有利に進めることができるので、できるだけ早いタイミングで刑事事件実績豊富な弁護士までご相談ください。
放火事件を起こして通常逮捕される具体例
過去の放火事件に対して逮捕状が発付されるのは、次の2つの要件を満たすときに限られます(犯罪捜査規範第118条、同規範第122条)。
- 逮捕の理由:被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること
- 逮捕の必要性:被疑者の身柄を強制的に拘束した状態で取調べを実施する必要性があること(留置の必要性)
たとえば、放火事件に以下の事情があるときには、放火罪などの容疑で通常逮捕手続きが進められるでしょう。
- 放火犯が住所不定・無職・職業不詳で「逃亡のおそれ」がある場合
- 複数の放火事件への関与が疑われる場合
- 放火罪や器物損壊罪などの同種前科・前歴がある場合
- 放火事件の「証拠物(犯行時の衣服、火をつけた道具など)を隠滅するおそれ」がある場合
- 放火事件の被害が大きい場合
- 放火事件の被害者の処罰感情が強い場合
- 放火事件に関する任意の出頭要請を拒絶した場合
- 放火事件に関する任意の事情聴取で黙秘・否認をした場合、供述内容に明らかな矛盾点が存在する場合
過去の放火事件について時効逃げ切りを狙うのは非現実的
放火に関する各犯罪類型には「公訴時効」が適用されます。
放火から一定期間が経過して公訴時効が完成すると、検察官の公訴提起権が消滅し、この付随的効果によって、捜査機関に逮捕されることもなくなります(刑事訴訟法第253条第1項)。たとえば、現住建造物等放火罪の公訴時効期間は「25年」、非現住建造物等放火罪の公訴時効期間は「10年」、建造物等以外放火罪の公訴時効期間は「7年」というように、一定期間の経過によって刑事責任を追及されるリスクが消滅するでしょう(同法第250条各項各号)。
ただし、放火事件について公訴時効完成による逃げ切りを目指すのは適切ではありません。なぜなら、放火罪は刑法の中でも重い犯罪類型に位置付けられるので、公訴時効期間が経過するまでに検挙される可能性が高いからです。事件から数年が経過してある日いきなり通常逮捕されると、数年をかけて築いた社会的地位や人間関係が無に帰してしまいます。
したがって、過去に放火をして現段階で捜査機関からアプローチがない状況でも、念のために現段階で刑事事件に強い弁護士へ相談することを強くおすすめします。自首や示談などの防御活動を先取りすることで軽い刑事処分獲得の可能性を高めることができるでしょう。
現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、「現行犯人(現に罪を行い、または、罪を行い終わった者)に対する身柄拘束処分」のことです(刑事訴訟法第212条第1項)。
通常逮捕と違って、現行犯逮捕には令状は必要とされません(令状主義の例外)。なぜなら、逮捕する者の目の前で放火行為に及んだ状況のため、冤罪・誤認逮捕のおそれが極めて少ないからです。
また、現行犯逮捕は、検察官や警察官だけではなく、一般私人でも行うことができます(同法第213条)。たとえば、民家にガソリンを撒いて火をつけようとしている放火犯を通行人が取り押さえたときにも、現行犯逮捕は適法なものとして扱われます。
放火犯は準現行犯逮捕される可能性もある
現行犯逮捕は「放火行為に及んだ現場」を対象とする無令状の強制処分ですが、放火事件の態様次第では「犯行現場以外」の場面に無令状逮捕の対象が拡大される場合があります。これは「準現行犯逮捕」と呼ばれます。
準現行犯逮捕とは、「以下4つの要件のいずれかを満たす者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときに実施される無令状の身柄拘束処分」のことです(刑事訴訟法第212条第2項)。
- 放火犯として追呼されているとき
- 放火事件に使用したと思われる証拠物・贓物などを所持しているとき
- 身体や被服に放火に及んだ顕著な証跡があるとき
- 「放火犯だ!」と誰何されて逃走しようとするとき
たとえば、犯行現場から数キロ・犯行から数時間経過後に、放火に及んだ際に火傷を負ってボロボロの姿で逃走中の姿を発見された場合、準現行犯逮捕の要件を満たすと考えられるので、逮捕状の発付手続きを省略してその場で身柄を拘束されるでしょう。
なお、準現行犯逮捕の適法性は事案の個別事情を総合的に考慮して決定されます。たとえば、準現行犯逮捕の違法性を主張できるケースでは、その後の取調べで得られた供述証拠の排除を目指すことも可能なので(違法収集証拠の排除)、刑事裁判の経験豊富な私選弁護人までご依頼ください。
緊急逮捕
緊急逮捕とは、「死刑、無期懲役、長期3年以上の懲役刑・禁錮刑に当たる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、逮捕状の発付手続きを履践している余裕がないときに実施される逮捕処分」のことです(刑事訴訟法第210条第1項本文)。緊急逮捕を行う際には被疑者に対して理由を告げて、身柄拘束処分実施後に逮捕状発付手続きを履践するだけで足ります(同法第210条第1項但書)。
たとえば、繁華街で職務質問を行ったときに放火犯として指名手配されている人物であることが判明したケースが緊急逮捕の具体例として挙げられます。
緊急逮捕の合憲性については疑義が呈されたこともありますが、現在では憲法33条の趣旨を満たした強制処分として合憲であると判断されています(最判昭和30年12月14日)。
【注意!】放火事件を起こしても逮捕を回避できる場合がある
放火事件は悪質な犯罪類型なので、警察が捜査活動を実施した場合には、逮捕処分によって強制的に身柄が拘束されるのが一般的です。
ただし、放火事件が以下のような事情を有するときには逮捕状発付要件の1つである「逮捕の必要性」を満たさないと考えられるので、任意捜査の一環として出頭要請・事情聴取が行われる(在宅事件処理)こともあります。
- 放火犯の氏名・住所・職業が明らかで逃亡のおそれがない場合
- 放火行為について自供し、真摯に反省の態度を示している場合
- 放火事件の被害者との間で示談が成立しており、被害者に処罰感情がない場合
- 放火事件の余罪に関与した疑いがない場合
- 放火による被害が小さい場合(焼損による被害額が数万円程度、誰も怪我をしていないなど)
- 放火事件に関する証拠物を隠滅するおそれがなく、自らの意思で捜査機関に提出している場合
- 前科・前歴がない完全初犯
- 警察からの任意の出頭要請・事情聴取に誠実に対応している場合
放火事件が任意捜査の対象になる場合、取調べに対応するとき以外は普段通りの生活を送ることができます。たとえば、会社や学校生活に悪影響が生じることはありませんし、学校バレ・会社バレ・家族バレのリスクも大幅に軽減可能でしょう。
ただし、在宅事件処理の対象になったからと言って、不起訴処分や執行猶予付き判決が確定するわけではありません。なぜなら、逮捕処分か在宅事件かは「身柄拘束処分があるか否か」という違いでしかないからです。
したがって、放火事件が在宅事件の対象になったとしても、不起訴処分や執行猶予付き判決獲得を目指した防御活動は不可欠だと考えられます。できるだけ早いタイミングで示談や刑事弁護のノウハウ豊富な弁護士までお問い合わせのうえ、今後の防御活動を検討してもらいましょう。
放火について警察段階の取調べが実施される
放火の容疑で逮捕された後は、強制的に警察署へ身柄が連行されて取調べが実施されます。
逮捕処分に基づいて実施される取調べを拒絶することはできません。また、取調べが実施されるとき以外は、留置場や拘置施設に身柄が留められます。そのため、逮捕期間中は帰宅したり出社したりすることは許されず、また、家族などに電話連絡を入れることも不可能です。
逮捕段階で実施される取調べの制限時間は「48時間以内」です(刑事訴訟法第203条第1項)。期限が到来するまでに、検察官に身柄・証拠物が送致されます。
放火について検察段階の取調べが実施される
放火事件について警察段階の取調べが終了すると、事件が検察官に送致されて、検察段階の取調べが実施されます(刑事訴訟法第246条本文)。警察段階の取調べと同じように、逮捕処分に基づく検察段階の取調べも拒絶することはできません。
検察段階で実施される取調べの制限時間は「24時間以内」が原則です(刑事訴訟法第205条第1項)。「警察段階48時間と検察段階24時間を合計した72時間以内」に得られた証拠を前提に、検察官が公訴提起するか否かを判断します。
ただし、放火事件の状況や逮捕後の捜査活動の進捗次第では、72時間以内に公訴提起判断のための充分な証拠を得られない可能性も否定できません。
そこで、「やむを得ない理由」によって72時間の時間制限を遵守できないときには、検察官による勾留請求が認められています(同法第206条第1項)。
勾留請求が認められて裁判官が勾留状を発付した場合、被疑者の身柄拘束期間は例外的に「10日間~20日間」の範囲で延長されます(同法第208条各項)。つまり、放火の容疑で逮捕・勾留された場合、「最長23日間」の身柄拘束期間が生じるということです。
なお、勾留請求が認められる「やむを得ない理由」として、以下のものが挙げられます。
- 複数の放火事件に関与した疑いがある場合
- 放火事件の関係者(被害者や目撃者)が多く、参考人聴取に相当の時間を要する場合
- 放火行為や逃走経路、道具の準備などを立証するために膨大な防犯カメラ映像等を確認する必要がある場合
- 放火事件について被疑者が黙秘・否認している場合
- 放火事件に関する供述内容に矛盾点や疑問が残る場合
- 実況見分や鑑定に時間を要する場合
放火について検察官が起訴・不起訴を決定する
放火事件に関する捜査活動が終了すると、検察官が事件を公開の刑事裁判にかけるか(公訴提起するか)を判断します。
起訴処分とは、「放火事件を公開の刑事裁判にかける旨の訴訟行為」のことです。日本の刑事裁判の有罪率は約99%とも言われているので、刑事裁判にかけられた時点=起訴処分を下された時点で有罪判決が事実上確定します。
これに対して、不起訴処分とは、「放火事件を公開の刑事裁判にかけることなく、検察限りの判断で刑事手続きを終結させる旨の意思表示」を意味します。不起訴処分が確定した時点で刑事手続きが終了するので、前科がつくことはありません。
以上を踏まえると、不起訴処分を獲得できるかが今後の社会復帰の可能性を左右すると言えます。刑事手続き初期段階から放火事件に強い私選弁護人に効果的な防御活動を展開してもらいましょう。
放火事件が公開の刑事裁判にかけられる
放火事件について検察官が起訴処分を下した場合、公開の刑事裁判にかけられます。
公開の刑事裁判が開廷されるのは「起訴処分から1カ月~2カ月後」頃が目安です。放火事件に係る公訴事実に争いがなければ第1回公判期日で結審し、後日判決が言い渡されます。これに対して、建築物等の現住性や「公共の危険」の有無や、事実関係を争う否認事件の場合には、複数の公判期日をかけて弁論手続き・証拠調べ手続きが行われます。
放火行為は悪質な犯罪類型に位置付けられるので、初犯でも実刑判決が下される危険性を否定できません。実刑判決が確定すると刑期を満了するまで社会生活から完全に隔離された状態が続きます。
したがって、社会復帰の難易度を下げて更生の可能性を高めたいなら「執行猶予付き判決」は不可欠です。刑事裁判の経験豊富な私選弁護人にご依頼のうえ、自首減軽や酌量減軽などの防御活動を尽くしてもらいましょう。
放火事件を起こしたときや逮捕されたときに生じるデメリット6つ
放火事件が警察にバレたときに生じるデメリットは以下6点です。
- 長期間の身柄拘束によってさまざまなデメリットに晒される
- 高額の損害賠償責任を追及される可能性がある
- 実名報道によって個人情報が晒される危険性が生じる
- 放火事件で逮捕されたことが学校にバレると何かしらの処分が下される
- 放火事件で逮捕されたことが会社にバレると何かしらの処分が下される
- 放火事件で逮捕・起訴されると前科がついてさまざまなデメリットが生じる
逮捕されると長期間身柄拘束される可能性が高い
放火事件を起こしたことが警察に発覚すると、長期間身柄拘束される可能性が高いです。
まず、逮捕された時点で、公訴提起に至るまで72時間に及ぶ取調べを覚悟しなければいけません。
次に、勾留阻止に失敗したときには、公訴提起判断まで最長23日間身柄拘束が続く危険性に晒されます。
さらに、起訴処分後の保釈請求が通らなかった場合には、刑事裁判に至るまで2カ月(その後1カ月ごとに更新)日常生活に復帰することができません。
そして、放火事件についてどのような刑事処分を下されるかとは別に、身柄拘束期間が生じるだけで以下のデメリットが生じます。
- 学校や会社に隠しにくくなる
- 接見禁止処分が下されると弁護士以外とは一切面会できない
- 厳しい取調べや過酷な拘置所生活で心身が疲弊する
高額の賠償責任を問われる可能性が高い
放火犯として特定されると不法行為に基づく損害賠償責任を追及される可能性が高いです。
たとえば、被害者宅が火災保険に加入していない場合、家屋などに生じた損害と慰謝料は全額放火犯の負担となります。また、仮に火災保険に加入していたとしても、保険会社から放火犯に対して賠償請求される可能性も否定できません。さらに、数百万円、数千万円の賠償責任に応じる経済的余力がない場合でも、放火によって生じた賠償責任は自己破産でも免責されないので、一生をかけて金銭賠償を続けることになります。
逮捕されると実名報道されるリスクに晒される
放火事件を起こして逮捕されると実名報道のリスクに晒されます。
そもそも、どのような刑事事件を報道番組やネットニュースで配信するかは報道機関側の裁量次第です。放火事件を起こしたとしても、実名報道されずに済むこともあり得ます。
ただし、放火事件は社会的影響が大きい悪質な犯罪類型であり、話題性も高いため、逮捕された段階で報道される可能性が高いです。特に、現住建造物等放火罪に該当する犯罪や、愉快犯的に駐輪場のバイクや自転車に火を着けたような犯罪の場合には、実名報道のリスクに晒されるでしょう。
実名報道されると、インターネット上に放火事件を起こした情報が氏名付きで残り続けます。また、SNSや匿名掲示板で放火犯の身元が特定されると、卒業アルバムの写真や勤務先、家族の情報がWebに掲載されることもあります。そして、これらの情報が残り続けると、今後の就職活動・転職活動に困難が生じるだけではなく、恋愛や結婚、子育てなどにも悪影響が生じかねないでしょう。
放火事件を起こしたことが学校にバレると何かしらの処分が出される可能性が高い
放火事件を起こして警察に逮捕されると、身柄拘束をきかっけに学校にバレる可能性が高いです。
そして、放火事件で逮捕されたことを学校に知られると、学則・校則の規定にしたがって厳しい処分が下されます。
たとえば、甚大な被害が生じた放火事件だと退学処分・停学処分の対象になることが多いでしょう。これに対して、軽いボヤ騒ぎや失火程度なら厳重注意や戒告などの軽い処分で済むこともあります。
いずれにしても、放火事件を起こしたことを理由に学校から処分を下されると、履歴書にキズがついて今後の就職活動や学歴に支障が出るので、できるだけ早いタイミングで弁護士へ相談をして、在宅事件処理を目指した防御活動を展開してもらうべきでしょう。
放火事件を起こしたことが会社にバレると懲戒処分を下される可能性が高い
放火事件を起こして警察に逮捕されると、身柄拘束期間が数日程度であったとしても勤務先にバレる可能性が高いです。
そして、放火事件で逮捕されたことが会社にバレると、就業規則の懲戒規定に基づいて何かしらの処分が下されます。
一般的に、懲戒処分の種類は「戒告・譴責・減給・出勤停止・降格(降職)・諭旨解雇・懲戒解雇」に分類されます。現住建造物等放火罪のような重い犯罪に及ぶと懲戒解雇処分の対象になりますし、これに対して、比較的軽微な放火事件で済めば減給や譴責などの軽い処分も期待できます。
学校対策と同じように、会社バレのリスクを回避するなら、在宅事件処理を目指すしか方法は残されていません。放火事件について警察からアクションが起こされていない状況なら、出来るだけ早い段階で弁護士へ相談をして自首や示談交渉などの先手を打つ防御活動を展開してもらいましょう。
放火事件が原因で逮捕・起訴されると前科によるデメリットに苦しめられる
放火事件を理由に逮捕・起訴されると有罪判決が下される可能性が高いです。
実刑判決や執行猶予付き判決のどちらであったとしても、「前科」がつきます。
そして、前科者になると、今後の人生に以下のデメリットが生じます。
- 前科情報は履歴書の賞罰欄に記載しなければいけないので、今後の就職活動・転職活動が困難になる
- 放火で前科があることを理由に制限される職業・資格がある(士業、金融業、警備員など)
- 放火で前科・逮捕歴があることを配偶者に知られると離婚を拒絶できない
- 放火の前科を理由にビザ・パスポートの発給制限を受けると自由に海外旅行・海外出張できなくなる
- 放火での前科があると、再犯時の刑事処分が重くなる可能性が高い
前科によるデメリットを回避したいなら、「不起訴処分獲得」が最終ラインです。
特に、放火の容疑で逮捕・勾留されたときには示談交渉などの防御活動に充分な時間を用意することができないので、出来るだけ早い段階で不起訴処分獲得実績豊富な私選弁護人までご依頼ください。
放火で逮捕されそうなときに弁護士へ相談するメリット4つ
放火事件を起こして警察に逮捕されそうなときや、ご家族が放火事件を起こして逮捕されたときには、すみやかに弁護士へ相談することを強くおすすめします。
なぜなら、刑事事件に強い弁護士へ相談することで以下4点のメリットを得られるからです。
- 放火事件の被害者との間で示談交渉を進めてくれる
- 少しでも軽い刑事処分獲得を目指した防御活動を展開してくれる
- 接見交通権をフル活用して身柄拘束中の被疑者に有益なアドバイスを提供してくれる
- 被疑者が抱える放火癖などのケアにも配慮してくれる
放火関連の被害者との間で示談交渉を進めてくれる
弁護士は放火事件の被害者との間で効率的に示談交渉を進めてくれます。
示談は当事者間の和解契約のこと
示談とは、「放火事件の加害者・被害者間で紛争の解決条件について直接話し合いを行い、和解契約を締結すること」です。
本来、示談は民事の賠償責任に関する処遇について話し合いものなので、理屈上は刑事責任に影響を与えるものではありません。
しかし、刑事手続きでは、「被害者との間で示談が成立しているか、被害弁償が済んでいるか」が公訴提起判断や量刑判断を左右するのが実務的運用です。
したがって、放火事件の被害者との間での示談交渉に成功すれば、不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得しやすくなるでしょう。
放火事件の示談条件
放火事件の一般的な示談条件は以下の通りです。
- 加害者が被害者に対して放火事件で生じた損害に対する修繕費・慰謝料・治療費などを「示談金」として支払う
- 被害者は告訴状・被害届を取り下げて、「処罰感情がないこと」を捜査機関・裁判所に伝える
- 被害申告前なら、示談成立によって紛争の終局的解決として、今後放火事件について一切口外しない
なお、どのような示談条件で和解契約を締結するかは当事者が自由に決定できます。
放火事件の示談交渉を弁護士に相談するメリット
放火事件の示談交渉は加害者本人や加害者家族が行うことも可能です。
ただし、円滑な示談成立を期待するなら、示談交渉は弁護士に依頼することを強くおすすめします。
なぜなら、示談交渉を弁護士へ依頼することで以下のメリットを得られるからです。
- 身柄拘束中の被害者に代わって示談交渉を進めてくれる
- 警察経由で放火事件の被害者の連絡先を入手しやすくなる
- 怒りや不安を抱えている被害者との間でも冷静な話し合いをできる
- 不当な示談金の釣り上げなどに対抗してくれる
- 放火事件の賠償額が高額な場合、現実的な支払い条件・支払い方法について相手方からの譲歩を引き出してくれる
- 契約書の作成や交渉など、すべての労力・時間を節約できる
少しでも軽い刑事処分獲得を目指して防御活動を展開してくれる
刑事事件に特化した弁護士は、手続きの段階に応じて少しでも有利な条件獲得を目指した防御活動を展開してくれます。
自首
警察が放火事件を把握していないときや、放火事件自体は認知しているものの犯人特定に至っていないときには、「自首」が有効な防御活動のひとつになります。
自首とは、「まだ捜査機関に発覚しない前に、犯人自ら進んで下着泥棒に及んだ事実を申告し、刑事処罰を求める意思表示」のことです(刑法第42条第1項)。
自首が有効に成立した場合、「刑の任意的減軽」というメリットを得られます。たとえば、現住建造物等放火罪の容疑で逮捕・起訴されたとしても、自首によって捜査活動がスタートしたときには、執行猶予付き判決獲得の余地を見出せます。
弁護士は自首に同行してくれるだけではなく、自首後に実施される取調べ対策にも力を入れてくれるでしょう。
不起訴処分
弁護士は、不起訴処分獲得に向けた防御活動を展開してくれます。
そもそも、「放火事件を起こした以上、公開の刑事裁判にかけられるのは仕方ない」と考える放火犯は少なくはありませんが、これは間違いです。
なぜなら、不起訴処分は以下3類型に分類されるので、放火事件を起こしたことに疑いがない状況でも不起訴処分獲得を目指す余地は残されているからです。
- 嫌疑なし:放火事件に関与した証拠が一切存在しない場合、誤認逮捕・冤罪の場合
- 嫌疑不十分:放火事件への関与を基礎付けるだけの充分な証拠が存在しない場合
- 起訴猶予:放火事件の証拠は明確に存在するが、諸般の事情を総合的に考慮すると刑事裁判にかける必要がない場合
起訴猶予処分に付するか否かを判断するときには、犯人の性格・年齢・境遇・犯罪の軽重・情状・犯罪後の情況などが総合的に考慮されます(刑事訴訟法第248条)。
刑事手続きに強い弁護士は不起訴処分獲得に役立つ証拠を用意してくれるでしょう。
保釈請求
放火事件を起こして逮捕・起訴されたとしても、弁護士はすみやかに保釈請求を実施して早期の身柄釈放を実現してくれます。
保釈請求は以下3種類に分類されます。放火事件の状況に応じて適切な保釈手続きを履践してもらいましょう。
- 権利保釈(保釈除外事由に該当しない限り認められる保釈)
- 裁量保釈(裁判官の裁量によって認められる保釈)
- 義務的保釈(身柄拘束期間が不当に長期化している場合に認められる保釈)
執行猶予付き判決
不起訴処分を獲得できなかったときには、実刑判決を回避するために「執行猶予付き判決獲得」が重要な防御活動になります。
執行猶予とは、「執行猶予期間を無事に満了した場合に刑の執行権を消滅させる制度」のことです。実刑判決が下されずに済むので、普段通りの社会生活を送りながら更生の道を歩むことができます。
ただし、執行猶予付き判決の対象になるには「3年以下の懲役刑・禁錮刑・50万円以下の罰金刑の言渡しを受けたとき」という要件を満たさなければいけません(刑法第25条第1項)。たとえば、現住建造物等放火罪の法定刑は「死刑または無期懲役もしくは5年以上の懲役刑」なので、執行猶予付き判決の要件を満たすには自首減軽・酌量減軽などの防御活動を展開する必要があります。
刑事裁判実績豊富な私選弁護人に依頼すれば、裁判官を納得させるだけの情状証拠などを丁寧に主張・立証してくれるでしょう。
【注意!】放火事件は微罪処分を期待できない
微罪処分とは、「警察が捜査活動をスタートした事件を送検せずに、警察限りの判断で刑事手続きを終結させる事件処理類型」のことです(刑事訴訟法第246条但書、犯罪捜査規範第198条)。微罪処分の対象になれば送検以降の手続きがすべて省略されるので、日常生活への支障を最大限軽減できます。
ただし、放火事件を起こしたときには微罪処分を期待できません。なぜなら、微罪処分の対象になるのは事前に指定された極めて軽微な犯罪類型に限られており、放火事件は微罪処分の対象外とされているからです。
したがって、放火事件の容疑で警察の捜査活動がスタートしたときには、「公訴提起判断の際に不起訴処分を獲得すること」を目標に防御活動を展開するべきでしょう。
【注意!】放火事件は略式手続きを期待できない
略式手続き(略式起訴・略式命令・略式裁判)とは、「簡易裁判所の管轄に属する刑事事件について100万円以下の罰金刑が想定される場合に、被疑者側の同意がある場合に限って、公開の刑事裁判を省略して簡易・簡便な形で罰金刑を確定させる裁判手続き」のことです(刑事訴訟法第461条)。公開の刑事裁判プロセスをすべて省略できるので、数カ月は社会復帰するタイミングを前倒しできます。
放火事件の大半は法定刑に罰金刑が定められていないので、略式手続きによる事件終了は不可能です。したがって、起訴処分を回避できないときには、弁護士のサポートを受けながら執行猶予付き判決や無罪判決獲得を目指しましょう。
接見機会を利用して身柄拘束中の被疑者を励ましてくれる
逮捕・勾留中の身柄拘束された被疑者と自由に面会できるのは弁護士だけです。
そもそも、接見禁止処分が下されることが多いので、家族などの第三者とは一切面会できません。自分の唯一の味方になってくれる弁護士と会話をするだけで励みになるでしょう。
また、弁護士と面会するときには捜査員の立会いもないので、取調べに対する供述方針などについてアドバイスをもらうこともできます。
放火癖などのケアにも配慮してくれる
放火事件を起こした被疑者の中には、放火癖(病的放火)などの衝動制御障害を抱えているケースも少なくありません。
このような精神疾患を克服しなければ本当の意味での社会復帰は目指せないので、弁護士はNPO法人や専門のカウンセリング機関を紹介してくれるでしょう。
放火をしたときにはすみやかに弁護士へ相談しよう
放火事件を起こしたときや、警察から過去の放火事件について何かしらのアプローチがあったときには、出来るだけ早いタイミングで弁護士にご相談ください。
弁護士への早期相談によって、身柄拘束処分回避に向けた防御活動や、不起訴処分・執行猶予付き判決獲得に向けたサポートを期待できるでしょう。
当サイトでは、放火事件などの刑事事件を専門に扱う弁護士を多数掲載しています。アクセスの良い信頼できそうな法律事務所までお問い合わせください。