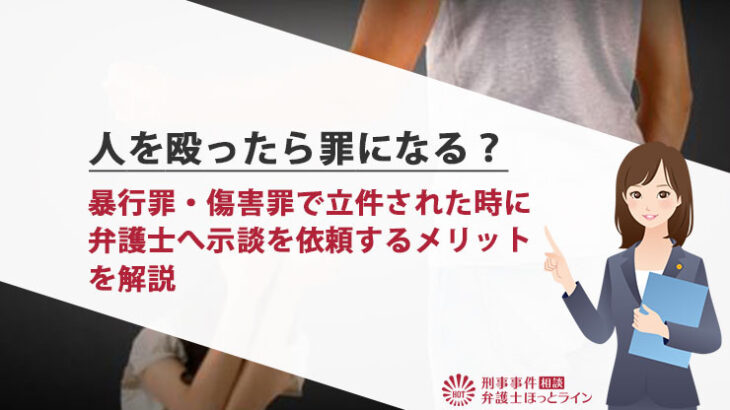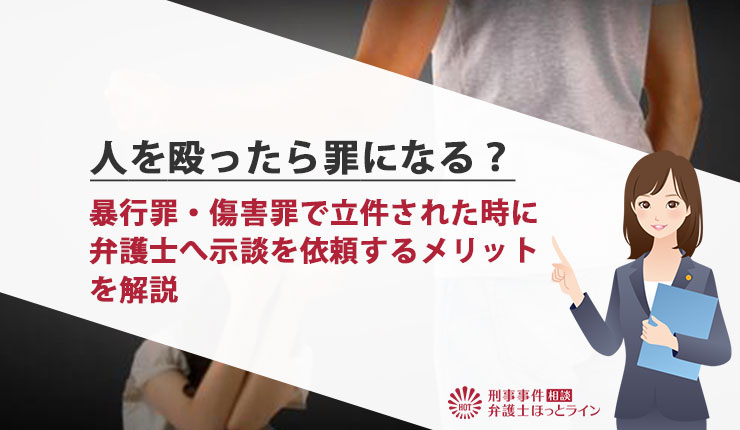
酔ったうえでの喧嘩や、衝動的にDVをしてしまったときなど、どのような事情があったとしても、人を殴ったら犯罪です。たとえば、暴行行為の態様や怪我の具合次第で、暴行罪・傷害罪・殺人未遂罪などの容疑をかけられます。
人を殴った後の対応を間違えると、警察に逮捕されて身柄拘束付きの取調べが実施される可能性があります。また、被害状況や示談交渉の進捗次第では、初犯でも実刑判決が下されかねません。
そこで今回は、人を殴ったことが原因で警察から出頭要請をかけられた方や、ご家族が暴行事件を起こして逮捕された方のために、以下4点について分かりやすく解説します。
- 人を殴ったときに問われる犯罪類型
- 人を殴ったらどのような刑事手続きが進められるのか
- 人を殴って逮捕されたときに生じるデメリット
- 人を殴ったときに弁護士へ相談するメリット
暴行罪や傷害罪の容疑をかけられたときには、示談交渉に着手するタイミングが重要です。たとえば、警察への被害申告前に示談交渉に成功すれば、事件が警察に発覚すること自体を回避できます。
暴行事件や示談実績豊富な弁護士に依頼をすれば、可能な限り軽い刑事処分獲得に向けた防御活動を期待できるので、当サイトに掲載中の法律事務所まで適宜お問い合わせください。
目次
人を殴ったときに問われる犯罪
人を殴ったら、以下の犯罪類型に問われる可能性があります。
- 暴行罪
- 傷害罪
- 殺人未遂罪
- その他の想定される犯罪類型
なお、人を殴ったシチュエーションがどのようなものであったとしても、「暴力をふるった以上は常に刑事責任を問われる可能性がある」とご理解ください。
たとえば、「DVは夫婦間・家族間の問題なので警察が介入することはないだろう」「学校での暴力沙汰は学校内で解決すべき問題」「酔ったうえで喧嘩をした程度なら大きな揉め事に発展することはないはず」などの理屈は一切通用せず、捜査機関が被害申告を受けたり目撃者が通報した段階で刑事手続きが開始します。
暴行罪
暴行罪は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に成立する犯罪類型のことです(刑法第208条)。
暴行罪の実行行為である「暴行」とは、「人に対する物理力の行使」のことです。
人の身体に対する不法な一切の攻撃方法が含まれて、性質上傷害の結果を惹起するべきものである必要はありません。また、物理力が人の身体に接触することも不要です。
たとえば、以下の行為はすべて暴行罪が適用される可能性があります。
- 相手を素手で殴りつける行為
- 着衣をつかんで引っ張る行為(大判昭和8年4月15日)
- 大太鼓などを連打して意識朦朧とした気分を与えて脳貧血を起こさせて、息を詰まる程度にさせる行為(最判昭和29年8月20日)
- 相手に塩を振りかける行為(福岡高判昭和46年10月11日)
- 相手を驚かせる目的で人の数歩手前を狙って石を投げる行為(東京高判昭和25年6月10日)
- 狭い室内で相手を怖がらせるために日本刀を振り回す行為(最決昭和28年2月19日)
暴行罪の法定刑は、「2年以下の懲役刑もしくは30万円以下の罰金刑、または、拘留もしくは科料」です。
傷害罪
傷害罪とは、「人の身体を傷害したとき」に成立する犯罪類型のことです(刑法第204条)。
傷害罪の実行行為である「傷害」とは、「生活機能の毀損、健康状態の不良変更」を意味すると解するのが判例です(大判明治45年6月20日)。また、傷害罪は「人を殴る」などの暴行行為によって傷害結果が発生するパターンが典型例ですが、いわゆる「暴力によらない傷害」も本罪の対象に含まれます。
たとえば、以下の行為が「傷害」に該当すると考えられます。
- 相手を殴って打撲・裂傷・骨折などの怪我をさせる行為
- 相手を殴って失神させる行為(大判昭和8年9月6日)
- 性病であることを隠して性病を感染させる行為(最判昭和27年6月6日)
傷害罪の法定刑は、「15年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑」です。
殺人未遂罪
殺人未遂罪とは、「殺人の故意をもって殺害行為の実行の着手に及んだものの、殺人結果が発生しなかったとき」に成立する犯罪類型のことです(刑法第199条、同法第203条)。殺人未遂罪の法定刑は、「死刑または無期懲役刑もしくは5年以上の懲役刑」と定められています。
たとえば、体格差のある被害者が既に抵抗を止めているのに胸部・腹部などを何度も繰り返し殴り続けたような事案では、暴行行為に相手の生命を脅かす危険性があると評価されるので、殺人未遂罪の容疑をかけられる可能性があります。
「殺すつもりはなかったから殺人未遂罪に問われるはずはない」と油断していると極めて厳しい刑事責任を問われかねないので、特に悪質な暴行事件に関与した経験があるなら、出来るだけ早いタイミングで弁護士にご相談のうえ、先手を打った防御活動を展開してもらいましょう。
【注意!】人を殴るとさまざまな罪状で容疑をかけられる可能性がある
人を殴った状況次第では暴行罪・傷害罪・殺人未遂罪以外の罪状で検挙される可能性もあります。
| 犯罪類型 | 具体例 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 器物損壊罪 | ・殴られた人の所持品や衣服を壊してしまったとき ・喧嘩のはずみで店の備品や第三者の財物を壊してしまったとき |
3年以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑、科料 |
| 決闘罪 | ・相手と事前に示し合わせて喧嘩をしたとき ・暴走族などの抗争で大規模な喧嘩に発展したとき |
決闘を挑んだ者、または、これに応じた者:6カ月以上2年以下の懲役刑 実際に決闘をおこなった者:2年以上5年以下の懲役刑 決闘の立会人となった者、または、立ち会いを約束した者:1カ月以上1年以下の懲役刑 決闘の場所を提供した者:1カ月以上1年以下の懲役刑 |
| 公務執行妨害罪 | ・喧嘩の現場にかけつけた警察官に暴力をふるったとき ・仲裁に入った警察官を威嚇したり暴言を吐いたとき |
3年以下の懲役刑・禁錮刑または50万円以下の罰金 |
| 傷害致死罪 | ・暴力を振るった結果、被害者が死亡してしまったとき | 3年以上の有期懲役刑 |
どのような容疑で検挙されたとしても、人を殴った行為が刑事事件化したときには「早期の示談交渉」が不可欠です。
出来るだけ早いタイミングで刑事事件に強い私選弁護人に相談をして、示談交渉や自首などの防御方法について検討してもらいましょう。
人を殴ったときの刑事手続きの流れ
人を殴ったときの刑事手続きの流れは以下の通りです。
- 人を殴った事件について警察から接触がある
- 人を殴った容疑について警察段階の取調べが実施される
- 人を殴った事件が警察から検察官に送致される
- 人を殴った容疑について検察段階の取調べが実施される
- 人を殴った事件について検察官が公訴提起するか否かを判断する
- 人を殴った事件が公開の刑事裁判にかけられる
人を殴った件について警察から接触がある
人を殴ったら警察から何かしらの形で接触があります。
人を殴ったときの状況によって、警察からのアプローチ方法は以下3つに大別されます。
- 通常逮捕
- 現行犯逮捕
- 任意の出頭要請
過去に人を殴ったことがバレたら通常逮捕される
喧嘩やDVなどで人を殴った過去が警察に発覚すると、「通常逮捕(後日逮捕)」によって身柄が拘束されることがあります。
通常逮捕とは、「裁判官の事前審査を経て発付される逮捕令状に基づいて実施される強制的な身柄拘束処分」のことです(刑事訴訟法第199条第1項)。被疑者の意思に関わらず身体・行動の自由を制約する強力な捜査手法なので、令状主義の原則が適用されます。
殴られた被害者が告訴状を提出すると、警察が暴行行為を把握します。その後実施された捜査活動によって被疑者の身元が特定されて犯行を裏付ける証拠が集まると、逮捕状が請求されます。そして、たとえば被疑者が在宅している可能性が高い平日早朝などのタイミングを見計らって捜査員が自宅にやってきて、逮捕状が執行されて身柄が押さえられます。
逮捕状を呈示された段階で、被疑者は一切の行動の自由を失います。たとえば、「会社に出社しなければいけないから別の日に出頭したい」「逮捕される前に会社に電話をしたい」などの希望は一切聞き入れられません。
人を殴って通常逮捕が実施される具体例
通常逮捕に必要な逮捕状は、「逮捕の理由」「逮捕の必要性」という2つの要件を満たしたときに発付されます。
逮捕の理由とは、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること」のことです。防犯カメラの映像や被害者・目撃者の証言などから犯行が裏付けられます。
また、逮捕の必要性とは、「留置の必要性(被疑者の身柄を強制的に拘束した状態での取調べを実施する必要性)」のことです。具体的には、逃亡や証拠隠滅のおそれがあることを意味します。
以上を踏まえると、人を殴って通常逮捕手続きが進められる場面として、以下のケースが挙げられます。
- 住所不定・無職・職業不詳で逃亡するおそれがある場合
- 暴行事件やDV事件などの前科・前歴がある場合
- 人を殴ったときの衣服などの証拠物を隠滅するおそれがある場合
- 殴られた被害者が重い怪我を負った場合
- 殴られた被疑者の処罰感情が強い場合
- 警察からの事前の出頭要請に応じない場合
- 警察からの出頭要請に応じたものの、任意の事情聴取で黙秘・否認・虚偽供述をした場合
人を殴ったら公訴時効完成までは後日逮捕リスクを抱えたまま
人を殴った行為について現段階で警察から何の接触がないとしても安心してはいけません。
なぜなら、公訴時効が完成するまではいつ後日逮捕されるか分からないからです。
公訴時効とは、「犯罪行為が終わったときから犯罪ごとに規定された公訴時効期間が満了することによって検察官の公訴提起権を消滅させる制度」のことです(刑事訴訟法第253条第1項)。検察官の公訴提起権が消滅することで刑事裁判にかけられずに済むので、刑事責任を追及される機会がなくなります。
人を殴ったときに問われる犯罪類型ごとの公訴時効期間は以下の通りです(同法第250条各項各号)。
| 犯罪類型 | 公訴時効期間 |
|---|---|
| 暴行罪 | 3年 |
| 傷害罪 | 10年 |
| 殺人未遂罪 | 25年 |
人を殴ったときに”時効逃げ切り”を狙うのは得策ではありません。
なぜなら、暴行事件は被害申告や第三者の通報によって捜査活動がスタートする可能性が高い犯罪類型であり、高確率で公訴時効完成前に被疑者の身元が特定されるからです。
たとえば、人を殴ってから数年が経過したタイミングである日いきなり逮捕状を持参した被疑者がやってくる事態になると、事件から数年間をかけて築き上げた社会的地位や人間関係が一瞬で崩れ去ってしまいます。特に、傷害罪や殺人未遂罪の容疑で立件されていると、10年・25年に及ぶ長期間を逃げ切らなければいけません。現実的にこれほどの長期間警察にバレることなく逃走し続けるのは不可能に近いでしょう。
したがって、過去に人を殴った経験があるのなら、念のために現段階で刑事実務に詳しい弁護士へ相談することを強くおすすめします。自首や早期の示談交渉によって少しでも有利な状況を作り出してくれるでしょう。
人を殴ったところを現行犯逮捕される
現行犯逮捕とは、「現行犯人(現に罪を行い、または、罪を行い終わった者)に対する身柄拘束処分」のことです(刑事訴訟法第212条第1項)。
現行犯逮捕は通常逮捕と異なり、逮捕状は必要とされません。これは、現行犯逮捕は犯人が犯罪行為に及んでいるのが明白な現場で実施されるものなので、冤罪・誤認逮捕のおそれが極めて少ないと考えられているからです(令状主義の例外)。
また、現行犯逮捕は警察官などの捜査機関だけではなく、一般私人も行うことが可能とされています(同法第213条)。私人逮捕が行われた場合には、すみやかに警察官に身柄が引き渡されます。
たとえば、以下のようなケースで、人を殴った行為について現行犯逮捕が実施されるでしょう。
- 繁華街で喧嘩をしているところ、目撃者が110番通報をしてかけつけた警察官に現行犯逮捕される
- 自宅で夫が妻を殴ったところ、悲鳴を聞いた近隣住民が110番通報をしてかけつけた警察官に現行犯逮捕される
- 公共交通機関で乗客同士のトラブルが殴り合いに発展したところを、同乗者に身柄を押さえられる
- 暴行犯として追呼されているとき
- 贓物や暴行事件に使用したと思われる兇器などの証拠物を所持しているとき
- 血痕や怪我など、身体や被服に人を殴った顕著な痕跡があるとき
- 「暴行犯だ!」と誰何されて逃走しようとするとき
運良く人を殴った現場から逃走することに成功しても状況次第では警察官に身柄を押さえられる可能性があるので、犯行から間もない状況なら、出来るだけ早いタイミングで弁護士に電話連絡を入れて、自首などの具体的な防御策について検討してもらいましょう。
人を殴ったことを理由に任意での出頭要請がかかる
人を殴って暴行事件として警察が捜査活動を開始したとしても、かならず通常逮捕手続きに移行するわけではありません。
なぜなら、人を殴った事件の態様次第では、「逮捕の必要性」という逮捕状の発付要件を満たさない場合があるからです。
ただし、逮捕状が発付されないからと言って、警察が何もしないというわけではありません。つまり、身柄拘束処分なしの任意ベースで出頭要請・事情聴取が行われるということです(在宅事件)。
暴行事件が在宅事件処理の対象になったとき、警察から出頭要請がかかったタイミングで警察署に訪問をして事情聴取を受けることになります。そして、任意の取調べが終了するとそのまま自宅に戻ることができます。出頭要請・事情聴取に応じる必要はありますが、日常生活に生じるデメリットを避けることができるので、会社バレ・学校バレのリスクを最大限回避可能です。
以下の事情がある場合、人を殴った事件が在宅事件処理の対象になるでしょう。
- 氏名・住所・職業が明らかで逃亡のおそれがない場合
- 人を殴った行為について素直に自供して真摯に反省の態度を示している場合
- 殴られた被疑者との間で順調に示談が成立しており、被害者の処罰感情が薄い場合
- 余罪に関与した疑いがない場合
- 殴られた人が怪我をしていない場合、軽症で済んでいる場合
- 暴行事件に関する証拠物を隠滅するおそれがなく、素直に警察に提出している場合
- 単独の暴行事件であり、共犯者と口裏を合わせるおそれがない場合
- 前科・前歴がない場合
- 任意の出頭要請に約束通り応じている
- 任意の事情聴取に嘘偽りなく供述している
なお、在宅事件処理は「身柄拘束処分がない」という意味合いのものでしかなく、不起訴処分や執行猶予付き判決が確約されるわけではありません。つまり、在宅事件として丁寧に任意の事情聴取が進められた後、在宅起訴によって有罪判決が下される可能性もあるということです。
また、任意の出頭要請や事情聴取に誠実に対応しない姿勢をもって「逃亡・証拠隠滅のおそれがある」と評価されるので、可能な限り捜査機関側の意向に沿った対応をする必要があります。
刑事実務に強い弁護士に相談をすれば、任意の事情聴取に対する供述方針などを明確化してくれるでしょう。
人を殴った件について警察で取調べが実施される
人を殴った事件が捜査機関に発覚すると、警察段階の取調べが実施されます。
逮捕された場合
まず、逮捕処分に基づいて実施される取調べは絶対に拒絶できません。
送検までに「48時間」という制限時間が設けられていますが(刑事訴訟法第203条第1項)、取調べ以外の時間は拘置所・留置場に身柄を留められるので、日常生活から完全に隔離された状態が続きます。
在宅事件の場合
次に、在宅事件として任意ベースの事情聴取が実施される場合、送検までの時間制限は存在しません。そのため、警察段階の取調べだけで数カ月の期間を要することもありますが、取調べが実施される日時以外は普段通りの生活を送ることができます。
なお、在宅事件の場合には必ずしも事情聴取に応じる必要はないので、帰宅したいときに取調べ室を後にすることも可能です。ただし、「逃亡・証拠隠滅のおそれがある」ことを理由に逮捕状の発付請求をされて、その場で通常逮捕手続きに移行する危険性もあるのでご注意ください。
人を殴った件について警察から検察官に送致される
人を殴った件について警察段階の取調べが終了すると、警察から検察官に事件・身柄・証拠物が送致されます(刑事訴訟法第246条本文)。
暴行事件は微罪処分の対象になる可能性がある
なお、人を殴った行為が暴行罪・傷害罪に問われるケースでは、「微罪処分」に付される可能性があります。
微罪処分とは、「警察が捜査活動をスタートした暴行事件を送検せずに、警察限りの判断で刑事手続きを終結させる事件処理類型」のことです(刑事訴訟法第246条但書、犯罪捜査規範第198条)。微罪処分対象になれば、起訴の不安に悩まされる心配もなくなりますし、有罪・前科が付くこともありません。つまり、人を殴って刑事事件化した場合には、微罪処分の獲得が被疑者にとって最もメリットが大きい状況だと言うことです。
微罪処分にするか否かは警察の判断次第ですが、一般的に、以下の要素を有する暴行事件は微罪処分の対象になる可能性が高いでしょう。
- 検察官があらかじめ指定した極めて軽微な犯罪類型に該当すること(暴行罪・傷害罪など)
- 犯情が軽微であること(計画性がない、衝動的な犯行、相手側から過度な挑発があった、人数で不利な喧嘩だったなど)
- 殴られた人の負った怪我が軽微であること(全治1週間程度の怪我が目安)
- 殴られた被害者との間で示談が成立していること、被害弁償が済んでいること
- 素行不良者でないこと
- 家族・親族・上司など、身元引受人がいること
なお、殺人未遂罪は刑法典の中でも重い罪状に分類されるため、微罪処分の対象になることはありません。
人を殴った件について検察官で取調べが実施される
人を殴った事件が微罪処分の対象にならずに送検された場合、検察段階の取調べが実施されます。
逮捕された場合
まず、検察段階で実施される取調べの制限時間は「24時間」が原則です(刑事訴訟法第205条第1項)。つまり、警察段階48時間と検察段階24時間の「合計72時間以内」の身柄拘束期間中に、起訴・不起訴の判断が行われるということです。
ただし、72時間の身柄拘束期間だけでは起訴・不起訴を判断するだけの充分な証拠が集まらない場合があります。
そこで、「やむを得ない理由」が存在するときには、検察官による勾留請求が認められています(同法第206条第1項)。検察官の勾留請求を裁判所が認めて勾留状が発付されると、身柄拘束期間が「10日間~20日間」の範囲で延長されます(同法第208条各項)。
勾留請求が認められる「やむを得ない理由」として、以下の事情が挙げられます。
- 暴行罪・傷害罪だけではなく、器物損壊罪や公務執行妨害罪などの余罪への関与が疑われる場合
- 人を殴った事件の被害者・目撃者が多数存在するため、参考人聴取に相当の時間を要する場合
- 防犯カメラ映像や犯行に至った経緯を示す物的証拠の解析などに時間を要する場合
- 被害者との示談交渉が難航している場合
- 人を殴った事件について被疑者が黙秘・否認している場合、供述内容に矛盾点がある場合
- その他、実況見分や鑑定に時間を要する場合
以上を踏まえると、人を殴った事件の刑事手続きが円滑に進まなかったとき、公訴提起の判断までに最大23日間の身柄拘束期間が生じるということです。
在宅事件の場合
逮捕されずに送検された場合、検察段階の取調べに制限時間は存在しません。
そのため、警察段階・検察段階の取調べ期間は数カ月以上に及ぶことも少なくないでしょう。
ただし、公訴提起判断までに長期間を要するということは、「示談交渉に使える時間も充分与えられている」ということを意味します。
示談成立は不起訴処分獲得の可能性を高めるものなので、示談実績豊富な弁護士までご依頼ください。
人を殴った件について検察官が公訴提起するか否かを判断する
取調べ期間中に得られたすべての証拠を前提として、検察官が起訴・不起訴を決定します。
起訴処分とは、「暴行事件を公開の刑事裁判にかける旨の訴訟行為」のことです。日本の刑事裁判の有罪率は約99%とも言われているので、検察官が起訴処分を下した時点で、有罪になることが事実上確定します。
不起訴処分とは、「暴行事件を公開の刑事裁判にかけず、検察限りの判断で刑事手続きを終結させる旨の意思表示」を意味します。不起訴処分の対象になった時点で刑事手続きが終了するので、有罪になることはありません(前歴は残ります)。
以上を踏まえると、「有罪になりたくない」「前科をつけたくない」と希望する場合、「不起訴処分を獲得すること」が最大の防御目標になると考えられます。
特に、逮捕処分によって身柄拘束されたときには公訴提起判断までの時間が限られているので、スピーディーな示談成立を達成するために、かならず示談実績豊富な私選弁護人のサポートを受けるべきでしょう。
- 嫌疑なし:人を殴った証拠が存在しない冤罪・誤認逮捕の場合
- 嫌疑不十分:人を殴ったことを立証する証拠が不十分な場合
- 起訴猶予:人を殴ったこと自体に間違いはないが、諸般の事情を総合的に考慮すると刑事裁判にかける必要がない場合
実際に暴行事件を起こしたときには、「起訴猶予処分を獲得できるか」がポイントになります。起訴猶予処分が相当かを判断するときには、「犯人の性格・年齢・境遇・犯罪の軽重・情状・犯罪後の情況」などの諸般の事情が総合的に考慮されます。検察官を納得させるだけの供述をする必要があるので、接見機会を通じて弁護士に供述方針を明確化してもらいましょう。
人を殴った件について公開の刑事裁判にかけられる
人を殴った事件について検察官が起訴処分を下した場合、暴行事件が公開の刑事裁判にかけられます。
刑事裁判が開廷されるタイミングは「起訴処分から1カ月~2カ月後」です。
公訴事実に争いがなければ第1回公判期日で結審するのが通例です。これに対して、正当防衛などを主張立証する否認事件では複数の公判期日を経て弁論手続き・証拠調べ手続きが実施されて判決に至ります。
初犯で暴行罪・傷害罪の容疑をかけられたケースでは執行猶予付き判決の公算が大きいです。他方で、殺人未遂罪のような重い容疑をかけられた場合には初犯でも実刑判決が下される可能性も否定できません。
「執行猶予付き判決を獲得できるか」「少しでも短い実刑で済むか」は今後の社会復帰の可能性を大きく左右するポイントになるので、刑事裁判経験豊富な弁護士までご依頼ください。
人を殴って逮捕されたときに生じるデメリット5つ
人を殴って逮捕されたときに生じるデメリットは以下5点です。
- 実名報道される
- 逮捕・勾留によって長期間身柄拘束される
- 会社にバレて懲戒処分を下される
- 学校にバレて何かしらの処分を下される
- 前科によるデメリットが今後の人生につきまとう
些細な喧嘩でも逮捕されると報道される危険性がある
どのような事情・経緯があったとしても、人を殴った以上は逮捕される可能性が生じます。
そして、暴行罪・傷害罪などの容疑で逮捕されると、実名報道リスクに晒されます。
たとえば、パートナーや子どもを殴ったDV事件は世間の注目を集める話題なので、軽微な怪我で済んだとしても報道番組やネットニュースで配信される可能性があります。また、繁華街での暴行事件がネットなどで拡散されると報道先行で身元が特定されたうえで捜査機関が動き出す可能性も否定できません。
一度でも実名報道されると、暴行事件を起こしたことが氏名・写真付きでインターネット上に残り続けてしまいます。社会復帰を目指すさまざまな局面で支障が生じかねないでしょう。
人を殴って大怪我をさせると長期間身柄拘束されるリスクに晒される
特に、人を殴って大怪我をさせると、長期間身柄拘束されるリスクに晒されます。
そもそも、刑事手続きの厳しさは被害状況にも左右されます。全治1週間程度の軽い怪我なら在宅事件処理や微罪処分・勾留回避を実現しやすいです。
これに対して、骨折など全治数週間以上の重症を負わせたり、後遺障害が生じる深刻な暴行を加えたりしたときには、逮捕・勾留によって数週間に及ぶ身柄拘束期間が生じるだけではなく、起訴後勾留によって刑事裁判までの数カ月間拘置所生活が続く可能性も否定できません。
身柄拘束期間が長期化するほど、会社や学校に暴行事件を起こしたことがバレる可能性が高まるので、身柄拘束処分の回避・軽減によって刑事手続きが社会生活に及ぼす悪影響の軽減を目指しましょう。
人を殴って逮捕されると会社から懲戒処分を下される可能性がある
人を殴った事件が勤務先にバレると懲戒処分を下される可能性が高いです。
懲戒処分は「戒告・譴責・減給・出勤停止・降格・諭旨解雇・懲戒解雇」に分類されます。
どのような懲戒処分が下されるかは各社の就業規則の懲戒規定次第ですが、人を殴った事件の理由・経緯次第では懲戒解雇処分が下されることもあり得ます。
刑事事件に強い弁護士は社会生活に生じるリスクにも配慮してくれるので、会社バレ回避や懲戒処分の軽減に向けた防御活動も期待できるでしょう。
人を殴って逮捕されると学校から何かしらの処分を下される可能性がある
人を殴った事件が学校にバレると何かしらの処分が下される可能性が高いです。
たとえば、学則・校則において厳しい処分基準を定めている学校では、暴行事件を起こしただけで退学処分が下されかねません。これに対して、学生の社会更生を重んじる校風なら、一時的な出席停止や厳重注意などの軽い処分で済むこともあります。
弁護士は、学校に連絡しないように捜査機関に働きかけたり、学校側との話し合いに同席するなどの方法によって、学歴や就職活動に影響がないように配慮してくれるでしょう。
人を殴って有罪になると前科によるデメリットに悩まされる
人を殴って逮捕・起訴されると、前科がつく可能性が高いです。
前科とは、「有罪判決を受けた経歴」を意味します。実刑判決だけではなく、執行猶予付き判決や罰金刑でも前科はつきます。
前科者になると、今後の人生に以下のデメリットが生じ続けます。
- 前科情報は履歴書の賞罰欄への記載義務が生じるので、就職活動・転職活動の難易度が高くなる
- 前科を理由に制限が生じる職業・資格がある(士業・警備員・金融関係など)
- 前科は「法定離婚事由」に該当するので、配偶者からの離婚申し出を拒絶できない
- 前科を理由にビザ・パスポートの発給制限を受けると、自由に海外旅行・海外出張できない
- 前科者が再犯に及ぶと刑事処分が重くなる可能性が高い
前科のデメリットを避けたいなら「不起訴処分獲得」が最大の防御目標になります。
刑事事件に強い私選弁護人にご依頼のうえ、公訴提起判断までに示談成立を実現してもらいましょう。
人を殴って逮捕されたときに弁護士へ相談するメリット5つ
人を殴って逮捕されたときや、過去の暴行事件について刑事訴追されるリスクを抱えているときには、出来るだけ早いタイミングで弁護士へ相談することをおすすめします。
なぜなら、弁護士のサポートを受けることで以下5つのメリットを得られるからです。
- 早期の示談交渉によって喧嘩相手との間での民事的解決を目指してくれる
- 殴られた被害者との間での示談成立が難しいなら自首を検討してくれる
- 人を殴った事件について少しでも軽い刑事処分獲得を目指してくれる
- 人を殴った経緯・事情を踏まえた防御活動を展開してくれる
- 接見交通権をフル活用して身柄拘束中の被疑者を励ましてくれる
なお、刑事弁護のサポートを受けるなら当番弁護士ではなく私選弁護人と契約することを強くおすすめします。
確かに、当番弁護士制度はすべての身柄拘束中の被疑者が利用できる制度で、初回無料で弁護士との接見機会を確保できます。
ただし、当番弁護士制度を利用できるのは逮捕・勾留中の被疑者だけです。在宅事件処理の対象になった被疑者は当番弁護士を頼ることはできません。また、当番弁護士制度を利用しても弁護士を自由に選べるわけではないので、年齢・性格・実績などに不満がある専門家がやってくる可能性も否定できないでしょう。
ご自身の責任で私選弁護人と委任契約を締結すれば、実績や性格・熱意などを踏まえて信頼に値する弁護士を選ぶことができます。当サイトでは暴行事件などの刑事事件に強い弁護士を多数掲載しているので、アクセスの良い法律事務所までお問い合わせください。
早期の示談交渉で喧嘩相手との民事的解決を目指してくれる
弁護士に相談すれば、殴られた被疑者との間で早期の示談成立を目指してくれます。
示談とは、「暴行事件の当事者同士で解決策・解決条件などについて直接話し合いを行い、和解契約を締結すること」です。
人を殴って示談成立を目指すべき理由
人を殴ったときに被害者との間で示談成立を目指すべき理由は以下の通りです。
- 被害申告前に示談交渉に成功すれば刑事事件化自体を回避できる(前科・前歴なし)
- 被害申告後に示談成立に成功すれば微罪処分・不起訴処分・執行猶予付き判決獲得の可能性が高まる
- 治療費や慰謝料など、民事的な賠償責任についても同時に解決できる
特に、被害者が警察に相談する前に示談交渉すれば民事的な話し合いだけで紛争の終局的解決を実現できるのが示談の最大のメリットと言えるでしょう。
弁護士に相談するタイミングが早いほど有利な状況を作り出すことができるでしょう。
人を殴ったときの一般的な示談条件
どのような示談条件で合意を形成するかは当事者の自由です。
ただし、一般的な暴行事件では、以下の内容で示談契約を締結することが多いです。
- 加害者が被害者に対して「示談金(治療費・慰謝料など)」を支払う
- 提出済みの被害届・告訴状を取り下げる
- 捜査機関や裁判所に対して「処罰感情がない旨」を伝える(宥恕条項)
- 暴行事件について今後口外しない(秘密保持条項)
- 被害申告前なら、示談契約締結によって紛争の終局的解決とする
人を殴ったときの示談交渉を弁護士へ依頼するメリット
人を殴ったときの示談交渉や加害者本人・加害者家族が行うことも可能です。
ただし、刑事事件の示談交渉を弁護士に依頼することで以下のメリットを得られる点は決して看過してはいけません。
- 弁護士が着任した方が警察経由で被害者の連絡先を入手しやすい
- 恐怖心や不安を抱いている被害者との間でも冷静に話し合いを進めてくれる
- 不当な示談条件の釣り上げにも粛々と対応してくれる
- 契約書の準備・実際の示談交渉など、すべての示談手続きを代理してくれる
- 送検・公訴提起判断など、刑事手続きの厳格な時間制限に間に合うように示談成立を目指してくれる
喧嘩相手との示談成立が難しいなら自首を検討してくれる
自首とは、「まだ捜査機関に発覚しない前に、犯人自ら進んで人を殴った事件について申告をし、刑事処罰を求める意思表示」のことです(刑法第42条第1項)。
自首が有効に成立すれば「刑の任意的減軽」というメリットを得られます。たとえば、暴行罪や傷害罪だけではなく、殺人未遂罪で立件されたときでも、執行猶予付き判決獲得を目指しやすくなります。
被害者との示談交渉が難航して和解契約締結による刑事処分の軽減を期待しにくい状況や、そもそも殴った相手の身元が分からないときには、先手を打って自首をすることで刑事手続きを有利に進めることができるでしょう。
少しでも軽い刑事処分獲得を目指してくれる
刑事事件を専門に扱う弁護士に依頼すれば、刑事手続きの各ステージに対応した目標を掲げて防御活動を展開してくれるでしょう。
| 被害申告前 | ・示談成立による刑事事件化の回避 ・自首 ・在宅事件化による逮捕の回避 |
|---|---|
| 逮捕後 | ・示談成立による微罪処分獲得 ・勾留阻止 |
| 送検後 | ・示談成立による不起訴処分獲得 ・略式手続きの適否判断 |
| 起訴後 | ・罰金刑、執行猶予付き判決の獲得 ・実刑の刑期短縮化を目指した防御活動 |
人を殴った経緯や事情を踏まえた防御活動を期待できる
刑事事件に強い弁護士は、人を殴った個別的事情を踏まえた防御活動を展開してくれます。
たとえば、相手が先に喧嘩を売ってきたために反撃をしたケースでは、「正当防衛・過剰防衛」を主張することで刑の回避・減軽を目指せる場合があります。
また、日々の執拗なモラハラに耐え兼ねてかっとして配偶者を殴ってしまったときには、暴行に至った経緯について同情の余地がある点を説得的に示して軽い刑事処分獲得を目指してくれるでしょう。
さらに、泥酔して繁華街で喧嘩をしてしまったときには、犯行時の飲酒量などの客観的データに基づき「心神喪失・心神耗弱」による責任の回避・軽減という戦術が考えられます。
情状の内容や反論方法は個別事件の詳細ごとにまったく異なります。刑事事件実績豊富な弁護士ほど事案への対応力があるので、依頼する私選弁護人を選ぶときには、「実績・取扱い分野」に注目することを強くおすすめします。
接見機会を通じて身柄拘束中の被疑者を励ましてくれる
刑事弁護に慣れた専門家に依頼をすれば、接見機会をフル活用してさまざまなメリットをもたらしてくれます。
そもそも、逮捕・勾留によって身柄拘束中の被疑者と自由に面会できるのは弁護士だけです。人を殴っただけでも逮捕された以上は接見禁止処分が下されることが多いので、家族や会社関係者・知人などと面会することはできません。
これに対して、身柄拘束中の被疑者には「接見交通権」が認められているので、捜査員の立会いなく自由に弁護士と面会し、書類や物品の授受をすることができます(刑事訴訟法第39条)。
そして、弁護士との接見機会は被疑者に対して以下のメリットをもたらしてくれるでしょう。
- 唯一の味方として被疑者を励ましてくれる
- 時々刻々と変化する捜査状況を踏まえて供述方針を明確化してくれる
- 家族への伝言などを承ってくれる
- 被疑者ノートの活用によって厳しい取調べを牽制してくれる
- 供述調書への署名・押印方法など、取調べ時の注意点を教えてくれる
人を殴ったらできるだけ早いタイミングで弁護士へ相談しよう
人を殴ったときに最初に着手するべきことは「示談」です。刑事事件化の回避や軽い刑事処分獲得など、刑事事件のあらゆる場面で被疑者にとってメリットをもたらします。
そして、早期の示談成立を実現するには、示談実績豊富な弁護士への依頼が不可欠です。
当サイトでは刑事事件の示談交渉に慣れた弁護士を多数掲載しているので、年齢・経験・性別・キャリア・事務所所在地などを総合的に考慮して信頼できそうな法律事務所までお問い合わせください。