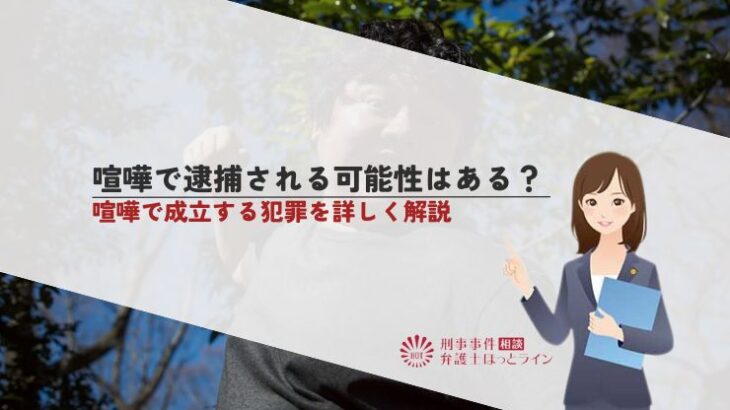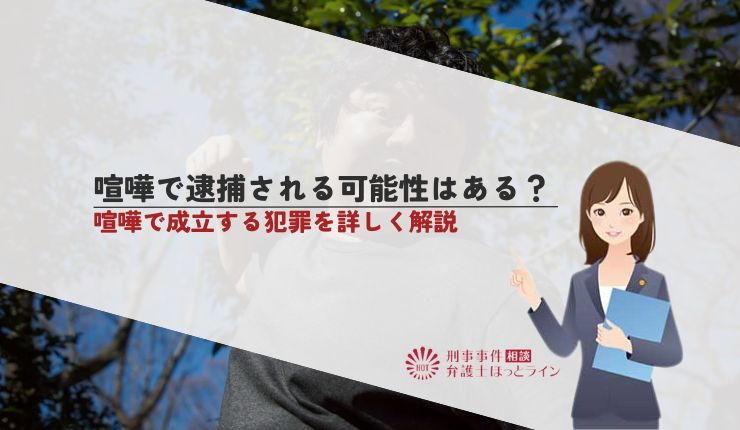
喧嘩は暴行罪や傷害罪といった犯罪が成立する可能性があります。もし、何らかの犯罪に抵触した場合は、当然ながら逮捕されてしまう可能性があるため注意しなければいけません。
この記事では、喧嘩によって成立する犯罪の種類や刑罰について詳しく解説しています。喧嘩をしてしまった人、普段から喧嘩を頻繁に行ってしまっている人は、今後自分がどのようなことになってしまうのか参考にしてください。
目次
喧嘩によって成立し得る犯罪とは
喧嘩によって成立し得る犯罪は以下のとおりです。
- 暴行罪
- 傷害罪・傷害致死罪
- 殺人未遂罪・殺人罪
- 決闘罪
上記犯罪は、いずれも身体への暴行が伴う喧嘩の場合に成立する犯罪です。喧嘩の種類はさまざまであり、たとえば口論(口喧嘩)をしたような場合で上記の犯罪が成立することはありません。
しかし、発する言葉次第では侮辱罪が成立する可能性があるため注意しなければいけません。たとえば口論している相手に対して「バカ」や「ブス」といった言葉を発すると侮辱罪になり得ます。
また、「殴るぞ」や「蹴るぞ」という発言は、その人の身体に危害を加えると脅していることになるため、脅迫罪が成立する可能性があるため注意しましょう。
今回は、相手の身体に対して暴行を加えた場合の「喧嘩」で成立し得る犯罪について詳しく解説します。
暴行罪
暴行罪とは、刑法に定められている犯罪であり以下のとおり明記されています。
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
引用:刑法|第208条
暴行罪とは、暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった場合に成立する犯罪です。傷害とは「人を傷つけること」や「ケガをさせること」を指します。
たとえば、「喧嘩をして相手に対して平手打ち(いわゆるビンタ)をしたが、相手は特にケガをすることはなかった」という状況であれば、暴行罪が成立します。しかし、「喧嘩をして相手に対して平手打ちをし、相手が口の中を切ってしまった」という場合は、ケガをしたと見なされてしまうため傷害罪が成立するため要注意です。
上記のように、暴行罪はあくまでも暴行を加えてケガを与えなかった場合に成立する犯罪です。
なお、暴行の定義は「人の身体に対する不法な有形力の行使をする行為のこと」と定義されています。典型的な例としては、殴る・蹴る・叩くといった行為が暴行に該当します。
また、上記のほか、喧嘩で「相手の胸ぐらを掴む」や「相手に飲み物をかける」といった行為もすべて暴行罪が成立します。
傷害罪・傷害致死罪
傷害罪とは、暴行の末に相手にケガをさせてしまった場合に成立する犯罪です。また、傷害の結果、相手を死亡させた場合は傷害致死罪が成立します。それぞれ刑法にて以下のとおり明記されています。
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(傷害致死)
第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
引用:刑法|第204条・205条
傷害罪は、暴行を加えた結果、人に傷害を負わせてしまった場合に成立する犯罪です。たとえば、「喧嘩をして相手を殴り、打撲をさせてしまった」というようなケースで傷害罪は成立します。
暴行罪と傷害罪の大きな違いは、相手に傷害を与えているかどうかです。傷害とは、「相手にケガをさせる行為」と認識してもらえれば良いです。暴行を加えた結果、ケガをすれば傷害罪、ケガがなければ暴行罪になるという認識で良いでしょう。
そのため、たとえば「喧嘩をして相手を突き飛ばし、転んで手に擦り傷を負った」というような場合でも傷害罪が成立し得ます。傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金であり、非常に重い処分が下される恐れもあるため注意しなければいけません。
また、傷害の結果人を死亡させてしまった場合は、傷害致死罪が成立します。法定刑は3年以上の有期懲役であるため、ほぼ100%の確率で刑務所へ収容されることになります。
傷害致死が成立するためには、前提として「殺意(相手を殺そうとする意思)がないこと」がなければいけません。殺意があって殺してしまった場合は、殺人罪が適用されるためです。
たとえば、「喧嘩をしていて相手を突き飛ばした際、相手が転んで頭を強く打ち、死亡してしまった」という場合は傷害致死罪です。また、「喧嘩相手の脇腹をナイフで刺した」という場合でも、殺意がなければ傷害致死罪が成立します。
殺人未遂罪・殺人罪が適用されることもある
喧嘩の結果、殺人未遂罪や殺人罪が成立する可能性もあるため注意しなければいけません。殺人罪もしくは殺人未遂罪の成立要件は、「殺意を持って人を殺した(殺そうとした)」場合に成立する犯罪であり、刑法に以下のとおり定められています。
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第二百三条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
殺人罪もしくは殺人未遂罪は「相手を殺してやろう」という意思(殺意)の有無によって判断されます。
たとえば、喧嘩をしている相手を「殺してやろう」と思い、交通量の多い道路に押し出したような場合が該当します。この場合、結果的に死亡した場合は殺人罪、死亡しなかった場合でも殺人未遂罪です。
他にも、「喧嘩相手をナイフで刺した」というケースでも、殺意があれば殺人罪もしくは殺人未遂罪になります。殺意がなければ、傷害罪や傷害致死罪といった軽い罪状によって処罰されることになるでしょう。
決闘罪
決闘罪は「決闘罪ニ関スル件」という法律によって定められている犯罪であり、以下のとおり明記されています。
第一条 決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス
第二条 決闘ヲ行ヒタル者ハ二年以上五年以下ノ重禁錮ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス
決闘罪とは、決闘を約束した場合に成立する犯罪です。たとえば「◯月◯日に〇〇(場所)で喧嘩をしよう」などと約束すると決闘罪が成立します。
決闘を約束したり実際に挑んだりした場合は、決闘罪によって処罰されます。法定刑は、6カ月以上2年以下の懲役です。
喧嘩によって逮捕される可能性
喧嘩をした場合、その内容次第では逮捕されてしまう可能性があります。たとえば、相手を殴ってケガをさせてしまった場合、傷害罪となるため注意しなければいけません。また、ケガをしなくても暴行罪が成立し、逮捕されて何らかの罰が下される可能性もあるでしょう。
喧嘩は、当事者となる全員が手を出し合っている状態であるため、基本的にはすべての人が処罰の対象となります。
しかし、喧嘩はお互いに悪いため、お互いに処罰感情がない状態であるケースが多いです。また、喧嘩をした当事者間でプライドがある、和解が成立しているなどさまざまな事情を考慮したうえで逮捕するかどうかが決定します。
同じ内容で前科・前歴がある場合は逮捕される可能性が高い
喧嘩は暴行罪や傷害罪といった犯罪が成立します。しかし、あまりにもひどい喧嘩ではない限り、警察官等は直ちに逮捕することなく、まずはお互いの言い分を聞いたうえで和解を促すでしょう。
とくに、逮捕という行為はその人の身柄を拘束するための手続きです。喧嘩は他の犯罪と比較しても「お互い様」という意識が強く、互いに被害者意識もあまりないでしょう。
また、逮捕という行為は逃亡の恐れもしくは証拠隠滅の恐れがある場合など、一定の条件を満たしている場合に限って行えます。
喧嘩はお互いに暴行しており、供述に大きな違いが発生するケースも少ないです。また、喧嘩といっても周辺にあるものを使用したり自分の体で殴ったり蹴ったりするため、証拠隠滅の恐れは低いです。
さらに、喧嘩の場合はその場で通報されるケースが多いため、逃亡の恐れも低いと判断sなれやすいです。上記のことから、余程の事情がない限りは逮捕されて取り調べを受ける可能性は低いと考えて良いでしょう。
ただし、逮捕されなかったとしても警察官や検察官から呼び出しされれば出頭しなければいけません。出頭しなければ、逮捕の可能性があるため要注意です。さらに、逮捕されなかったとしても後に起訴されて罰金刑や懲役刑といった刑罰が下される恐れもあるため注意しましょう。
一方で、逮捕される可能性が高い事例もあります。たとえば、傷害致死や殺人未遂、殺人罪など重大な事件に発展してしまった場合です。上記のような場合は、原則在宅事件(逮捕せずに取り調べを行うこと)にはなりません。
また、傷害罪であってもこれまでに何度も同じことを繰り返しているような場合、厳しい処分が言い渡される可能性が高いです。そのため、逮捕をして取り調べを行い、そのまま交流して裁判を受けるといった流れになることもあるでしょう。
喧嘩両成敗の原則によって双方が逮捕される
喧嘩をした場合、「喧嘩両成敗の原則」という原則により、喧嘩をした当事者全員が平等に処分されることになります。
喧嘩両成敗の原則とは「どちらに原因があったにせよ、喧嘩をした者は全員悪い」と判断されることです。喧嘩に勝った、負けたに関係なく、どちらも平等に処罰すべきという考え方があります。
ただし、一方が明らかに暴行をされ、ひどい傷害を負っている場合は傷害罪と暴行罪となるケースもあります。また、どちらか一方のみが一方的に手を出してしまった場合、手を出した者飲みが処罰されます。
たとえば、「飲食店で絡まれて人を殴ってしまった」というような場合です。ことの発端は絡んできた者であっても、手を出したのが自分だけであれば自分のみが悪くなってしまいます。
喧嘩で逮捕された場合の流れ
喧嘩をした場合、逮捕されてしまう可能性があります。実際に、逮捕されてしまった場合はどのような流れで事件は進んでいくのでしょうか。次に、喧嘩で逮捕されてしまった場合の流れについて詳しく解説します。
逮捕による身柄拘束
喧嘩をしているところに通報が入り、警察官が現れた場合は現行犯逮捕される可能性があります。また、後から呼び出しを受けて逮捕されたり、ある日突然自宅に警察官が来て逮捕されたりする「通常逮捕」の可能性があります。
いずれの場合も逮捕であることに変わりはないため、その後の手続きに大きな違いはありません。
まず、逮捕されると身柄の拘束が行われます。警察署内にある留置書に収容されて取り調べを受ける流れになります。逮捕後48時間以内に検察官へ事件を送致しなければいけないため、この時点で逮捕から最長48時間は身柄拘束が行われることになります。
勾留請求・勾留
警察官から事件を引き継いだ検察官は、さらに24時間以内に被疑者(逮捕されている人)を引き続き勾留(身柄拘束)するかどうかを判断しなければいけません。
勾留の必要があると判断された場合は、被疑者を連れて裁判所へ行き、勾留質問を経て最終的に裁判官が勾留の有無を決定します。
勾留が認められた場合、10日間の勾留が行われます。さらに、実務上はさらに10日間の勾留延長が認められるケースが多いため、合計20日間の勾留が行われることになるでしょう。
この時点で最長23日間の身柄拘束があり、社会的な影響もだんだん増していくため注意が必要です。
起訴・不起訴の判断
勾留されている場合、検察官は勾留期間中に起訴するか不起訴とするかを判断しなければいけません。。在宅事件の場合は期限に定めがなく、通常は書類送検から2カ月前後で起訴・不起訴が判断されます。
起訴された場合は、通常通り刑事裁判にかける「正式起訴」と略式命令で終了する「略式起訴」の2種類があります。
略式起訴された場合は、100万円以下の罰金もしくは科料の刑罰が科されることになるでしょう。略式命令によって判決が確定するため、すぐに社会復帰できる点がメリットです。
一方で、略式起訴の場合は裁判が開かれないため、弁解の機会を与えられません。たとえば「相手の方が悪かった」「相手に喧嘩を売られたから」などと情状を求めることもできません。
とはいえ、喧嘩の場合は暴行罪や傷害罪であり、前科があるなど特別な事情を除いて、罰金刑で済むケースが多いです。そのため、検察官から略式起訴に関する説明があった際は、改めて検討してみると良いでしょう。
刑事裁判を受ける
正式起訴された場合は、刑事裁判を受けることになります。刑事裁判では、犯行の態様を考慮したうえで有罪か無罪かを判断し、有罪であればどの程度の刑罰に処すかを決定します。
刑が確定・執行(もしくは執行猶予)
刑罰が確定した場合、その刑罰に従って服することになります。懲役刑であれば、刑期を全うするまでは、務所内で過ごさなければいけません。
なお、執行猶予付きの判決が下された場合は、直ちに刑の執行は行われません。しかし、執行猶予期間中に再度喧嘩をして暴行罪や傷害罪に問われた場合は、執行猶予が取り消されてしまうため注意してください。
喧嘩で逮捕された場合のリスク
喧嘩で逮捕されてしまった場合、以下のようなリスクが発生し得ます。
- 長期間の身柄拘束によるリスク
- 前科が付くことによるリスク
- 経済的損失によるリスク
次に、喧嘩で逮捕されてしまった場合のリスクについて詳しく解説します。
長期間身柄拘束によるリスク
逮捕されてしまった場合、初めに72時間の身柄拘束の可能性があります。その後、勾留が認められればプラス20日間で合計23日間もの間、身柄拘束されてしまう可能性があります。
身柄拘束されている間は、当然ながら社会へ戻ることはできません。自宅へ帰れない、会社へ出社できない、あるいは学校へ行けないといったことになり得ます。
働いている人であれば長期間休むことによるさまざまな影響が考えられるでしょう。学生であれば、退学処分の可能性もあります。
また、起訴されて保釈が認められなければさらに長期間の身柄拘束も行われます。長期間の身柄拘束はその後の社会生活にも多大な影響を与えるため注意しましょう。
前科が付く可能性
刑事事件において有罪判決が下された場合は、前科がついてしまいます。前科が付いても特に影響はないものの、就職をする際に「賞罰欄」がある場合は前科がある事実を記載しなければいけません。そのため、前科が原因で就職に影響を与える恐れもあるでしょう。
経済的損失のリスク
逮捕されてしまうと長期間の身柄拘束が行われます。身柄拘束されている間は、留置所や拘置所に収容されているため、懲役囚とは異なり、お金を稼げません。そのため、長期間になればなるほど経済的な損失リスクは大きくなるでしょう。
なお、冤罪(無罪)となった場合は、国に対して損害賠償請求を行うこともできます。しかし、喧嘩で逮捕されている以上、無罪判決となることはありません。よって、経済的な損失を受ける可能性が高いと思っておきましょう。
喧嘩で逮捕された場合の対処法
喧嘩で逮捕されてしまった場合、以下の対処法を検討しましょう。
- 反省している態度を示す
- 自分の過失次第では、治療費や示談金の支払いを検討する
- 相手と話し合い、和解しておく
次、喧嘩で逮捕されてしまった場合の対処法について詳しく解説します。
反省している態度を示す
逮捕されてしまった場合、客観的に見て「やりすぎ」と判断されています。そのため、しっかり反省している態度を示し、今後、繰り返さないことを約束しましょう。
そもそも、何らかのことが原因で喧嘩をしてしまうことは誰にでもあります。しかし、度を過ぎてやり過ぎてしまった場合や相手が怪我をしてしまった場合は、犯罪である以上逮捕したり処罰したりしなければいけません。
しかし、実際は喧嘩は誰にでもあることであるため、し、犯罪となるような行為について二度と繰り返さないよう反省し、態度を示せば厳しい処罰を免れる可能性は高いです。そのため、まずは自分がやってしまったことを俯瞰し、反省しておきましょう。
自分の過失が大きい場合は治療費や示談金の支払いも検討する
明らかに自分の過失が大きい場合や一方的にやり過ぎてしまった、と感じる部分があるのであれば、相手の治療費や示談金の支払いも検討しましょう。治療費や示談金の支払いによって、相手の処罰感情も薄れます。
結果的に厳しい処分を免れる可能性が高まるためです。たとえ、相手から売られた喧嘩であったとしても、やり過ぎてしまったほうが悪くなります。そのため、納得できない部分があっても、治療費や示談金お支払いは検討しておいたほうが良いです。
相手と話し合い、和解を成立させる
喧嘩の相手が知り合いなのであれば、和解しておきましょう。和解が成立し、お互いの処罰感情がなくなると、処分も軽くなります。逮捕されたあとでも不起訴処分となる可能性もあるため、和解を検討したほうが良いでしょう。
喧嘩に関するよくある質問
喧嘩に関するよくある質問を紹介します。
Q.相手から先に手を出してきた場合、正当防衛は成立しますか?
A.正当防衛の成立要件を満たしている場合は成立します。
正当防衛は刑法第36条にて「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」と定められています。この要件を満たしている場合は、正当防衛となり、罰せられません。
たとえば、「街を歩いているときに正面から歩いてきた人と肩がぶつかり、口論になって手を出されたため、こっちもやり返した」という場面であれば正当防衛は成立しません。なぜなら、急迫不正の侵害ではないうえ、自己防衛の目的も達成していないためです。
上記のケースの場合、肩がぶつかりそうになった時点で回避すれば済んだ話です。仮に、当たってしまったとしても、その場で謝罪をして離れる、その場から走って逃げるといった行動を取れたことでしょう。
一方で、「子供を連れて街を歩いていたら、突然正面から歩いてきた人に殴られた」というケースでは、自分1人で逃げるわけには行きません。そのため、自己防衛の範囲内で相手に攻撃を加える分には正当防衛が認められます。
Q.口喧嘩の場合は罪に問われますか?
A.口喧嘩の場合は、脅迫罪や名誉毀損罪が成立する可能性があります。
たとえば、喧嘩の中で「死ね」や「殺す」、「殴る・蹴る」などと発言すると脅迫罪に問われる恐れがあります。また、「バカ」や「ブス」などと発言した場合は、名誉毀損罪が成立するため注意しなければいけません。
ただ、実際に口喧嘩で逮捕されたり罪に問われたりするケースはありません。
Q.お互いに同意した上で喧嘩をした場合は罪に問われませんか?
A.決闘罪が成立する可能性があります。
決闘罪は、決闘を申し出たり参加したりした場合に成立する犯罪です。たとえば、「これから喧嘩しよう。お互い文句なしな」というように、双方で同意があった場合、決闘罪が成立して処罰される可能性があります。
Q.格闘技のようにルールの上で喧嘩をすれば罪に問われませんか?
A.格闘技として行う分には問題ありませんが、喧嘩であれば犯罪になり得ます。
格闘技は興行であり、細かなルール等が定められています。その範囲内でやる分には何らかの犯罪に触れることはありません。
しかし、ルールを定めた喧嘩の場合は格闘技ではないため、傷害罪や決闘罪といった罪に問われる可能性があります。どうしても喧嘩をしたいのであれば、格闘家として、またはスパーリングとしてルールの範囲内で行いましょう。
Q.兄弟喧嘩の場合は逮捕されないのでしょうか?
A.兄弟喧嘩でも逮捕される可能性はあります。
兄弟だからといって刑罰が軽くなることはありません。たとえ兄弟喧嘩であったとしても、暴行罪や傷害罪といった犯罪が成立する可能性があります。
ただ、兄弟喧嘩は自宅内で行われることが多く、警察が気づかないため、結果的に逮捕されないというのが現実です。
もし、大人が家庭内で喧嘩をして誰も手をつけられずに警察へ通報した場合は、たとえ兄弟であっても逮捕されます。兄弟や家族であっても特別扱いはありません。
まとめ
今回は、喧嘩で逮捕される可能性について解説しました。
喧嘩は、暴行罪や傷害罪、場合によっては傷害致死や殺人・殺人未遂罪といった重犯罪となる可能性もあります。とくに重犯罪の罪に問われた場合は、逮捕となる可能性はとても高いです。逮捕されてしまうと、長期間の身柄拘束が行われ、さまざまなリスクが発生します。
喧嘩は、ついカッとなって始まってしまうことが多いですが、喧嘩をしたところで何も良いことはありません。お互いに冷静になり、もし喧嘩をしてしまったら、最悪の場合はどのようなことが起こるのかを考え、正しい行動を取れるようになりましょう。