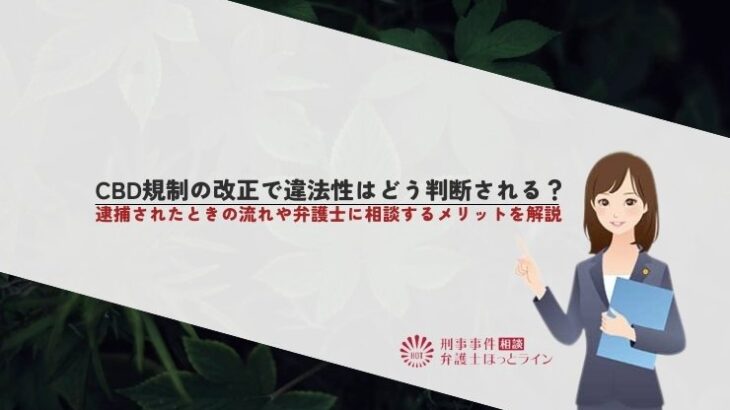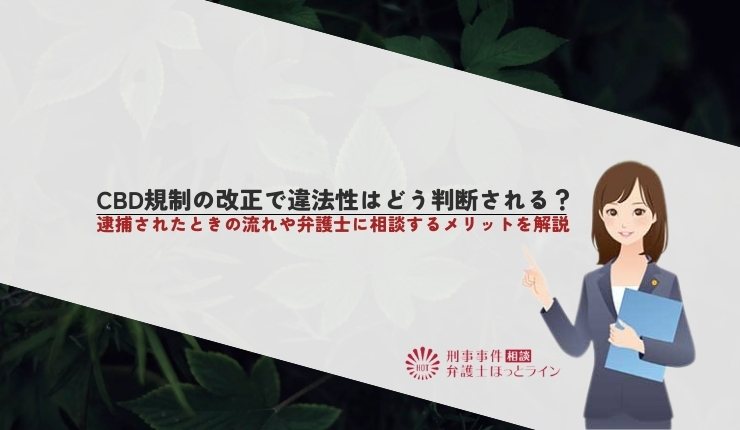
令和5年12月13日の法律改正により、大麻やCBD製品を取り締まる法律構造に大幅な変更が加えられました。これによって、従来は違法性に問題がないと判断されていたCBD関連製品が違法なものと扱われるようになり、CBD関連製品のユーザーが知らないうちに違法行為に手を染めてしまう状況が発生しています。
「CBD規制の改正なんて知らなかった」という言い訳は通用しません。麻薬取締法などの規制への違反が発覚すると、逮捕・勾留によって長期間身柄拘束を強いられたり、実刑判決などの重い刑事処分を下されたりしかねません。ですから、ご自身が所有・施用しているCBD関連製品が違法なものかを適切に判断したうえで、違法な製品ならば速やかに処分する必要があると考えられます。
そこで、この記事では、CBD製品を利用している人や近年の麻薬取締法関連の改正動向に関心がある人のために、以下の事項について分かりやすく解説します。
- CBD関連製品の違法性に対する法改正の動向
- CBD規制違反を理由に逮捕されたときの刑事手続きの流れ
- CBD規制違反を理由に刑事訴追されたときに生じるデメリット
- CBD規制違反に問われたときに弁護士へ相談・依頼するメリット
- 合法的にCBD関連商品を施用等するときに役立つポイント
刑事訴追のおそれがあるときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼することが推奨されます。早期の対策によって違法性を問われるリスクを大幅に軽減できるからです。
当サイトでは、薬物犯罪や刑事事件の実績豊富な弁護士を多数紹介しているので、少しでも不安がある人は、速やかに信頼できる法律事務所までお問い合わせください。
目次
CBDの違法性に関する法律改正のポイント
令和5年12月13日に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」が成立・公布され、令和6年12月12日にその一部が施行されました。これにより、大麻やCBD(カンナビジオール)に対する規制が大幅に変更されるに至っています。
まずは、CBDの違法性に関する法律改正のポイントについて解説します。
CBD・大麻をめぐる改正後の法律関係・構造について
まず、今般の法律改正によって、従来の「大麻取締法」から「大麻草の栽培の規制に関する法律」に名称が変更されました。
そして、従来は「麻薬及び向精神薬取締法」の適用を受けなかった大麻も本法の規制対象と扱われるに至っています。
つまり、CBD製品には「大麻草の栽培の規制に関する法律」「麻薬及び向精神薬取締法」の2つの法律が適用されて、厳しい規制が課されることになったということです。
CBD・大麻に関する法改正のポイント
今般の法改正の大きなポイントは以下のように整理できます。
- 一定要件を満たす大麻は「麻薬」に該当し、「麻薬及び向精神薬取締法」の適用を受ける
- 従来は合法と扱われていた「大麻の使用」が規制対象になる
- 大麻単純所持罪の法定刑が「5年以下の懲役」から「7年以下の懲役」に厳罰化 など
麻薬に該当する「大麻」
大麻とは、「大麻草(その種子及び成熟した茎を除く。)及びその製品(大麻草としての形状を有しないものを除く。)」のことです(大麻草の栽培の規制に関する法律第2条第2項、麻薬及び向精神薬取締法第2条第1項第1の2号)。
そして、法規制の対象になる大麻(麻薬)になるかどうかは、以下のように製品などの形状ごとに設定された残留するΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)の基準値を超えるか否かで判断されます。
| 形状 | 残留限度値 | 具体例 |
|---|---|---|
| 油脂(常温で液体であるものに限る。)及び粉末 | 百万分中十分の量(10ppm、10mg/kg、0.001%) | ・CBDオイル ・ヘンプシードオイル ・化粧オイル ・CBDパウダー ・プロテイン など |
| 水溶液 | 一億分中十分の量(0.1ppm、0.1mg/kg、0.00001%) | ・清涼飲料水 ・アルコール飲料 ・化粧水 ・牛乳 ・植物性の飲料 など |
| 油脂及び水溶液以外のもの | 百万分中一分の量(1ppm、1mg/kg、0.0001%) | ・菓子類 ・錠剤 ・バター ・電子タバコ ・シャンプー ・リンス ・乳液 ・クリーム ・マヨネーズ ・バーム ・ドレッシング ・ゼリー など |
2024年(令和6年)12月12日以降、CBD製品の規制がこれまでの「部位規制」から「成分規制」へと変更されました。これによって、Δ9-THCの含有量が残留限度値を超えて検出された場合には、当該製品が大麻由来であるか否かにかかわらず麻薬として取り扱われます。
つまり、CBD関連製品のΔ9-THC含有量が残留限度値未満であれば、違法な麻薬への該当性は否定されるということです。改正法に規定された数値基準を満たすCBD製品は合法であり、これらを所持・使用しても刑事責任を問われることはありません。ただし、改正法及び厚生労働省が定める数値基準は諸外国に比べて厳しい値が設定されているため、現在市場に出回っているCBD製品の多くが基準を満たさずに違法になるとの見込みです。
ですから、現在市場に出回っているCBD製品も改正法によって違法と扱われる可能性がある以上、安易にCBD製品を購入・利用するのはハイリスクだといえるでしょう。
大麻に関する罰則
今般の法改正によって、大麻に関する規制内容は以下のような変更が加えられました。
| 行為態様 | 罰則の内容 |
|---|---|
| 所持・譲渡・譲受 | 単純所持・譲渡・譲受:7年以下の懲役 営利目的:1年以上10年以下の懲役もしくは情状により300万円以下の罰金(併科あり) |
| 輸出入・製造 | 単純輸出入・製造:1年以上10年以下の懲役 営利目的:1年以上の有期懲役もしくは情状により500万円以下の罰金(併科あり) |
| 施用(使用) | 単純施用(使用):7年以下の懲役 営利目的:1年以上10年以下の懲役もしくは情状により300万円以下の罰金(併科あり) |
| 栽培 | 単純栽培:1年以上10年以下の懲役 営利目的:1年以上の有期懲役もしくは情状により500万円以下の罰金(併科あり) |
大きな改正点のひとつが、従来は合法と扱われていた「大麻施用(使用)」が違法化された点です。単純施用の場合には「7年以下の懲役刑」、営利目的施用(使用)なら「1年以上10年以下の懲役刑もしくは情状により300万円以下の罰金(併科あり)」の刑罰が科されます。
もうひとつの改正ポイントとして挙げられるのが、大麻の単純所持罪の法定刑が「5年以下の懲役刑」から「7年以下の懲役刑」に引き上げられた点です。執行猶予付き判決の対象になるのが「言い渡された刑が3年以下の懲役または禁錮、または50万円以下の罰金であること」という要件を満たす場合がであることを踏まえると、大麻所持罪で逮捕・起訴された場合に執行猶予付き判決を獲得するハードルが相当高くなったことがうかがえます。
CBD規制に違反して逮捕されたときの刑事手続きの流れ
違法なCBD製品を所持・使用などして逮捕されたときの刑事手続きの流れは以下のとおりです。
- 警察に逮捕される
- 警察段階の取り調べが実施される
- 検察官に送致される
- 検察段階の取り調べが実施される
- 事案によっては勾留請求される
- 検察官が公訴提起する
- 刑事裁判にかけられる
- 刑が執行される
麻薬取締法違反の容疑で逮捕される
麻薬取締法に規定されている基準に違反するCBD製品を所持・使用などしたことが発覚すると、警察に逮捕される可能性があります。
逮捕とは、被疑者の身体・行動の自由を制約する強制処分のことです。
たとえば、職務質問が実施されるタイミングで違法なCBD製品を所持していることが発覚したケースでは、「現行犯逮捕」が実施されます(刑事訴訟法第216条)。また、違法なCBD製品を取り扱う事業者を強制的に取り調べる必要が生じた場合には、「通常逮捕」がおこなわれます(刑事訴訟法第199条第1項)。
CBDの麻薬取締法違反について警察段階の取り調べが実施される
麻薬取締法違反の容疑で逮捕された後は、警察段階の取り調べが実施されます。
警察段階で実施される取り調べには「48時間以内」という制限時間が設けられています(刑事訴訟法第203条第1項)。48時間以内の取り調べが終了すると、被疑者の身柄と関係書類が検察官に送致されます。
逮捕処分に基づいて実施される取り調べは拒否することはできません(取り調べを受けたうえで黙秘をすることは可能です)。また、取り調べ以外の時間帯は拘置施設に身柄が留められるので、外出したり外部と連絡をとったりすることも不可能です。
CBDの麻薬取締法違反事件が検察官に送致される
違法なCBDの所持などを理由に麻薬取締法違反の容疑で逮捕されて警察段階の取り調べが終了すると、身柄・事件が検察官に送致されます(送検)。
CBDの麻薬取締法違反について検察段階の取り調べが実施される
CBDの施用などについて麻薬取締法違反の容疑で刑事訴追されると、検察段階の取り調べが実施されます。警察段階の取り調べと同じように、取り調べを拒絶することはできません。
検察段階の取り調べの制限時間は「24時間以内」です(刑事訴訟法第205条第1項)。
警察段階「48時間以内」と検察段階「24時間以内」の合計「72時間以内」の取り調べが終了した段階で、検察官が麻薬取締法違反事件について公訴提起するか否かを判断します。
CBDの麻薬取締法違反について勾留される
CBDの麻薬取締法違反事件について検察官が制限時間内に捜査活動を終了できないときには、勾留請求がおこなわれる可能性があります(刑事訴訟法第206条第1項)。
検察官の勾留請求が認められた場合、被疑者の身柄拘束期間は「10日間~20日間」の範囲で延長されます(刑事訴訟法第208条各項)。
そして、勾留期間中も逮捕段階と同じように被疑者の身体・行動の自由は大幅に制限された状態です。
以上を踏まえると、違法なCBD製品の施用などを理由に逮捕・勾留されると、「最短72時間以内~最長23日間」の範囲内で身柄拘束されるリスクが生じます。数週間に及ぶ身柄拘束期間が生じると、仮に不起訴処分を獲得できたとしても社会生活に甚大なデメリットが生じると考えられるので、違法なCBD製品の施用などが原因で刑事訴追されたときには、できるだけ早いタイミングで刑事事件を得意とする弁護士に相談・依頼をして、身柄拘束期間の回避・短縮化を目指した防御活動を展開してもらうべきでしょう。
CBDの麻薬取締法違反について検察官が起訴・不起訴を決定する
CBDの施用・所持などについて一定の捜査活動が終了した段階で、検察官が公訴提起するか否か(起訴するか不起訴にするか)を判断します。
起訴処分とは、麻薬取締法違反事件を公開の刑事裁判にかける旨の訴訟行為のことです。これに対して、不起訴処分は、麻薬取締法違反事件を刑事裁判にかけることなく検察官の判断で手続きを終了させる旨の意思表示を意味します。
日本の刑事裁判の有罪率は極めて高いため、刑事裁判にかけられることが確定した時点(検察官が起訴処分を下した時点)で有罪判決が事実上決まります。
以上を踏まえると、CBDの施用等で刑事訴追されたケースにおいて有罪や前科の回避を目指すなら、「不起訴処分を獲得できるか」がポイントになると考えられます。不起訴処分を獲得するには捜査活動の初期段階から適切な防御活動が必要になるので、警察からコンタクトがあった時点で速やかに信頼できる弁護士に相談・依頼をしてください。
CBDの麻薬取締法違反事件について刑事裁判が開かれる
CBDの施用・所持などについて麻薬取締法違反の容疑で起訴されると、公開の刑事裁判にかけられます。
公開の刑事裁判が開かれるタイミングは、「起訴処分から1か月~2カ月」です。逃亡や証拠隠滅のおそれが継続するなどの事情がある場合には、刑事裁判まで起訴後勾留が続く可能性もあります。
公訴事実を全面的に受け入れる場合には、第1回公判期日で結審し、判決が言い渡されます。これに対して、否認事件では、複数回の公判期日を経て証拠調べや証人尋問などが実施されて裁判官の判断を仰ぐ、という流れがとられることが多いです。
CBDの所持等に対する刑事罰が引き上げられた経緯を踏まえると、薬物犯罪は初犯でも実刑判決が下される可能性を否定できません。実刑判決が下されると今後の社会生活に甚大なデメリットが生じるので、起訴処分が下されたときには執行猶予付き判決や罰金刑獲得を目指した防御活動を展開してもらいましょう。
CBD規制違反を理由に逮捕されたときに生じる可能性があるデメリット4つ
CBD規制に違反して刑事訴追されたときに生じる可能性があるデメリットとして以下4つが挙げられます。
- 数日~数週間強制的に身柄拘束される
- 実刑判決が下される可能性がある
- 前科によるデメリットに晒され続ける
- 実名報道されるリスクが生じる
最終的に不起訴になったとしても一定期間身柄拘束されるリスクに晒される
CBD規制に違反して麻薬取締法違反の容疑で逮捕されると、一定期間強制的に身柄拘束されます。
まず、原則的な逮捕後の身柄拘束期間は、警察段階の取り調べで「48時間以内」、送検後の検察段階の取り調べについては「24時間以内」の、「合計72時間以内」です。
次に、検察官の勾留請求が認められた場合には、検察段階の取り調べが「10日間~20日間」の範囲で延長されます。つまり、逮捕時点からカウントすると「最長23日間」の身柄拘束期間が生じるということです。
そして、捜査段階でこれらの身柄拘束期間を強いられると、仮に不起訴処分や無罪判決を獲得できたとしても、以下のデメリットが生じる可能性があります。
- 外部と一切連絡がとれない状況が発生する
- 取り調べ以外の時間帯は留置施設に収容されるので外出できない
- 厳しい取り調べと環境が原因で肉体的・精神的にストレスがかかる
- 学校や会社に刑事事件を起こしたことがバレる可能性が高まる
以上を踏まえると、CBD規制違反を理由に捜査対象になったときには、「逮捕されないこと」「勾留阻止活動によって身柄拘束期間を短縮化すること」が重要だといえるでしょう。
有罪になると実刑判決が下される可能性がある
大麻の施用・所持などを理由に麻薬取締法違反の容疑で起訴されると、ほとんどのケースで有罪判決が下されます。
そして、CBD規制が厳罰化された昨今の動向を踏まえると、麻薬取締法違反を理由に有罪になる場面では、初犯でも実刑判決が下される可能性が高いです。
実刑判決が確定すると、判決で言い渡された刑期を満了するまで刑務所に収監されます。一定期間社会から隔離された状態が発生すると、就職先が見つかりにくいなどのデメリットを強いられかねません。
ですから、CBD規制違反を理由に起訴されたケースでは、執行猶予付き判決や罰金刑の獲得を目指した防御活動が重要だといえるでしょう。
前科によるデメリットに晒され続ける
CBD規制違反を理由に有罪判決が確定すると、刑罰が科されるだけではなく、前科によるデメリットを強いられます。
前科とは、有罪判決を下された経歴のことです。実刑判決だけではなく、執行猶予付き判決や罰金刑が下された場合にも前科がつきます。
前科者になると、今後の社会生活に以下のデメリットが生じます。
- 履歴書の賞罰欄への記載義務が生じるので就職活動・転職活動の難易度が高くなる
- 就業規則の懲戒事由に「前科・有罪判決」が掲げられている場合には何かしらの懲戒処分が下される
- 前科を理由に就業が制限される資格・仕事がある(士業、警備員、金融業など)
- 前科を理由に離婚を言い渡されたり結婚話がなくなったりしかねない
- ビザやパスポートの発給制限を受ける場合がある(海外旅行、海外出張に支障が生じる)
- 再犯に及んだときに刑事処分が重くなる可能性が高い など
これらのデメリットを避けるには、「前科がつかないようにする=有罪判決を受けないようにする=起訴されないようにする」ことが重要です。刑事手続きの初期段階からの防御活動が公訴提起判断時に大きく影響するので、CBD規制違反について心当たりがあるなら、警察から接触があった時点で弁護士に相談することを強くおすすめします。
実名報道されるリスクが生じる
CBD規制違反を理由に逮捕されると、実名報道のリスクに晒されます。
どの事件をニュースに載せるかは報道機関の裁量次第です。ただ、麻薬取締法などが改正された動向及びCBD製品の違法性が社会問題化している昨今の情勢を踏まえると、CBD規制違反を理由に逮捕された場合には実名報道のリスクが高いと考えられます。
一度でも実名報道されてしまうと、インターネット上に半永久的に事件を起こした情報が残り続けてしまいます。すると、就職活動や転職活動に悪影響が生じたり身近な人に発覚したりして、社会生活を送りにくくなります。
実名報道のリスクを軽減するには、「逮捕されないこと」「起訴されないこと」が重要です。警察から連絡があった時点で弁護士に相談すれば在宅事件化に役立つアドバイスを提供してくれるでしょう。
CBD製品を合法的に利用するために注意するべきポイント
麻薬取締法などの改正による大麻規制の抜本的な構造変化により、従来は合法だったCBD製品のなかにも違法と扱われるようになったものがあります。その一方で、麻薬取締法で規定される「麻薬」の基準に満たないCBD製品は、改正法のもとでも合法的に使用することができます(「合法だからやってもいい」というわけではありません)。
つまり、現在市場に流通している外国製のCBD製品などを合法的に利用するには、麻薬取締法のCBD規制基準値の条件を満たすかどうかを確認しなければいけないということです。
そのために役立つ方法として、以下のものが挙げられます。
- CBD製品中のΔ9-THCの含有量に関する検査が可能な機関に問い合わせをする(検査可能な機関は「製品等検査機関一覧」からご確認ください)
- フリマサイトや個人輸入業者などからCBD関連商品を購入しない
- 品質保証や検査内容を公表している正規事業者などから購入する
- 製品の成分表のTHC項目に「ND(Not Detected/「検出されない」の意味)」と記載されているものを購入する
なお、CBDオイルやCBDリキッドなどのCBD関連製品は常に麻薬取締法との関係が問題になる製品ですし、何かしらの有害性がある可能性は否定できません。「合法だから大丈夫」などと安易に考えるのではなく、基本的には施用等を控えるのが望ましいでしょう。
CBD製品の違法性が指摘されたときや逮捕されたときに弁護士へ相談・依頼をするメリット4つ
お手元にあるCBD関連製品が麻薬取締法に違反する違法なものか不安になったときや、麻薬取締法違反の容疑で警察からアプローチがあったときには、できるだけ早いタイミングで弁護士へ相談・依頼することを強くおすすめします。
というのも、刑事事件や薬物犯罪に詳しい弁護士の力を借りることで以下4つのメリットを得られるからです。
- 相談者が所持しているCBD関連製品の違法性を判断してくれる
- 身柄拘束期間の回避・短縮化を目指してくれる
- 少しでも軽い刑事処分獲得を目指してくれる
- 薬物依存の問題を抱える相談者を現実的にサポートしてくれる
麻薬取締法の改正内容を踏まえてCBD関連で刑事訴追されるか否かを判断してくれる
刑事事件や薬物犯罪に強い弁護士は、近年の麻薬取締法関係の改正事情に精通しています。
これらの弁護士に相談・依頼をすれば、相談者が所持しているCBD製品が麻薬取締法のCBD規制に違反する違法な製品かどうかを判断したうえで、麻薬取締部への相談などのサポートをしてくれるでしょう。
身柄拘束期間の回避・短縮化を目指してくれる
刑事事件や薬物犯罪に強い弁護士に依頼すれば、身柄拘束期間の回避・短縮化を目指した防御活動を展開してくれます。
まず、そもそも全ての刑事事件が「逮捕」によってスタートするわけではありません。事案の状況次第では、「逮捕」という強制処分ではなく、「任意の出頭要請・事情聴取」という形で刑事手続きが開始されることもあります。そして、任意捜査に対して真摯な姿勢で対応すれば、逮捕・勾留といった身柄拘束処分が下されることなく刑事手続きを進行させることができます(在宅事件)。全ての手続きを在宅事件として処理できれば、会社や学校などにバレずに刑事手続きが終了するでしょう。
次に、仮に逮捕されたとしても、強制的に実施される取り調べにおいて黙秘・否認をせずに丁寧に対応すれば、勾留されずに公訴提起判断の段階まで進んだり、途中で在宅事件に切り替わる可能性もあります。
刑事事件の実績豊富な弁護士の力を借りれば、事案の状況や捜査の進捗具合を総合的に判断したうえで、身柄拘束期間の回避・短縮化に役立つ供述方針を明確化してくれるでしょう。
少しでも軽い刑事処分獲得を目指して尽力してくれる
刑事事件を得意とする弁護士に相談・依頼をすれば、刑事手続きの段階に応じて少しでも軽い刑事処分獲得を目指してくれます。
- 逮捕前:逮捕処分を回避して在宅事件化を目指してくれる
- 逮捕後:勾留阻止活動によって早期の身柄釈放を目指してくれる
- 逮捕・勾留後:不起訴処分(起訴猶予処分)獲得を目指してくれる
- 公訴提起後:執行猶予付き判決や罰金刑獲得を目指してくれる
このなかでも特に重要なのが、「起訴猶予処分」です。公訴提起判断の段階で不起訴処分を獲得できれば刑事責任を問われることはありませんし、逆に、起訴処分が下されると事実上有罪が確定して前科者として扱われる未来が待っているからです。
起訴猶予処分は、実際に犯罪行為に及んだのは間違いないものの、事件に関する諸般の事情を総合的に考慮した結果、公訴提起する必要性がないときに下される不起訴処分の一種です。起訴猶予処分を下すか否かの判断の際には、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況が総合的に考慮されます(刑事訴訟法第248条)。たとえば、CBD規制に違反する違法な麻薬を所持していたとしても、所持するに至った経緯や反省の度合い、捜査活動に協力する姿勢などが評価に値するのなら、起訴猶予処分が下される可能性があります。
刑事事件を得意とする弁護士はさまざまなノウハウを有するので、起訴猶予処分獲得に役立つ証拠や証人を用意したり、取り調べでの供述方針などを提案してくれたりするでしょう。
薬物依存の治療をサポートしてくれる
CBD規制に違反する違法な製品を所持等している人のなかには、薬物依存トラブルを抱えている人も少なくはありません。
薬物犯罪の弁護経験が豊富な専門家はNPO法人や医療機関などとも提携しているので、更生プログラムへの誘導などをサポートしてくれるでしょう。
CBDの違法性に疑問があるときには少しでも早いタイミングで弁護士に相談しよう
麻薬取締法の改正により、”グレー”な状況で蔓延・普及していたCBD製品の多くが違法なものに区分された結果、従来からCBD関連商品を利用していた人が刑事責任を問われるリスクが急増しています。
麻薬取締法に規定されるCBD規制に違反すると、初犯でも重い刑事罰が科される可能性があります。「自分だけは大丈夫」という安易な考えでいると、ある日いきなり警察に逮捕されて長期間身柄拘束されたり有罪判決が下されたりしかねません。
当サイトでは、薬物犯罪や刑事事件を得意とする弁護士を多数掲載中です。私選弁護人に依頼することで一定の弁護士費用は発生しますが、相談者や依頼者の利益を最大化するために効果的な防御活動を展開してくれるでしょう。