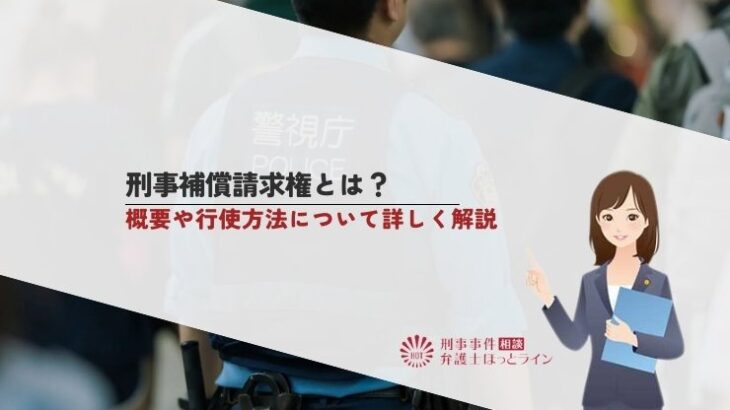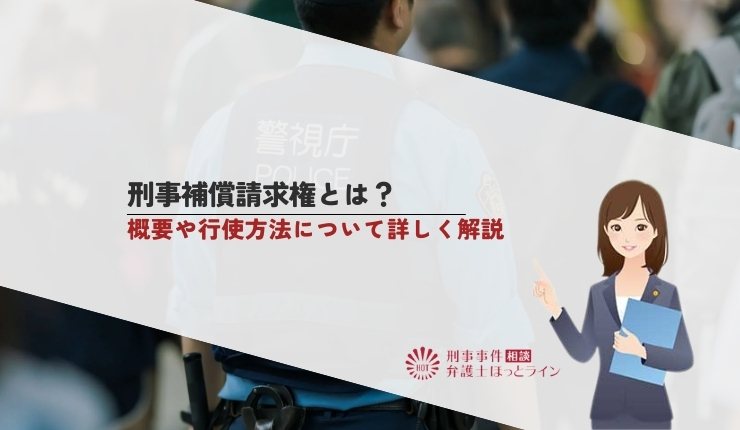
刑事補償請求権とは、身柄拘束を受けていた人が無罪判決が確定した場合に受けられる補償のことです。この記事では、刑事補償請求権について詳しく解説しています。刑事補償請求権に関することを知りたい人は、ぜひ本記事を参考にしてください。
刑事補償請求権とは
刑事補償請求権とは、刑事裁判の結果無罪判決を受けた人に対して行われる補償です。逮捕・勾留されていた日数分の保証が行われ、1日あたり1000円〜12,500円の範囲内で補償が行われる仕組みです。
まずは、刑事補償請求権とは何か?について詳しく解説します。
無罪判決を受けた人に対して行われる補償
刑事補償請求権とは、無罪判決を受けた人に対して行われる補償です。無罪判決を受けるということは、その犯罪については無実であることを刑事裁判で証明されたということです。
しかし、刑事裁判を受ける前には逮捕されたり勾留されたりなど、身柄を拘束されてしまいます。当然、身柄を拘束されている間は、働くことができないため収入を得ることができません。
また、無実であるにも関わらず身柄を拘束されていたという事実は、絶対に許されるべきではありません。許されない行為であるとはいえ、過去に戻って逮捕や勾留を回避することは不可能です。
そこで、無実であったにも関わらず身柄を拘束してしまったことに対する賠償金として、支払われるのが「刑事補償金」です。そして、刑事補償金を請求できる権利のことを「刑事補償請求権」と言います。
刑事補償請求権を行使するためには、無罪判決を受けた事実のほか逮捕・勾留されていることが条件です。次に、刑事補償請求権を行使するための条件についても解説しているので、ぜひ参考にしてください。
逮捕・勾留されていた日数分の補償が受けられる
刑事補償請求権を行使するためには、逮捕・勾留されていることが条件です。逮捕・勾留されていた日数分の補償を受けられます。
刑事裁判で無罪判決を受けるためには、一般的には逮捕→勾留→起訴→刑事裁判という流れがあります。逮捕〜勾留まで最長で23日間の身柄拘束が発生します。その後、起訴された場合は刑事裁判を受けるまでに数カ月単位で身柄拘束されます。
上記期間×金額で刑事補償金が支払われる仕組みです。つまり、そもそも逮捕勾留等の身柄拘束が発生していなければ、刑事補償金が支払われません。
通常、刑事裁判が確定するまでに最短でも半年(180日)程度の日数がかかります。仮に、すべての期間で身柄拘束が行われていた場合は、180日×刑事補償金=の金額が支払われる仕組みです。
1日あたり1,000円〜12,500円が支払われる
刑事補償金の金額は1日あたり1,000円〜12,500円の範囲で決定します。金額の決まり方は、本人の損失や精神的苦痛によって判断されます。
とはいえ、会社員が身柄拘束された場合は1日あたり最大の12,500円が支払われたとしても不足するケースが大半でしょう。それでも最大は12,500円となる点に注意しなければいけません。
たとえば、あなたが冤罪によって重大な商談に参加できず、億単位の損失が発生したとしても最大で12,500円です。ただし、これはあくまでも「刑事補償請求権」の話です。もし、実際に発生した損失を刑事補償請求金で賄えない場合は、国家賠償請求権の検討ができます。
国家賠償請求権は、公務員等の過失によって違法に他人に損失を与えた場合に認められる賠償金です。国家賠償請求権を行使することによって、不足分を補填できる可能性もあるでしょう。
しかし、実際に国家賠償請求が認められるケースは非常に稀です。なぜなら、前提として「公務員による過失」がなければいけないためです。
たとえば、警察や検察が正当な捜査を行ってあなたを犯人と特定していた場合、「過失あった」とは認められにくいです。結果的に、国家賠償請求権は認められません。
刑事補償請求権の条件
刑事補償請求権を行使するためには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 逮捕・勾留その他抑留されていること
- 無罪判決が下されていること
次に、刑事補償請求権を行使するための条件について詳しく解説します。
逮捕・勾留その他抑留されていること
刑事補償請求権を行使するためには、逮捕・勾留その他抑留されていることが条件です。
そもそも、罪を犯したからといってすべての人が逮捕・勾留されるわけではありません。逮捕・勾留するためには、犯罪を犯したと疑うに足りる十分な証拠があることを前提に、逃亡の恐れもしくは証拠隠滅の恐れがあること、その他身柄拘束をする必要があると判断された場合に限られています。
もし、罪を犯した疑いをかけられていても、逮捕されずに在宅事件として捜査が行われていた場合は、刑事補償請求権の行使はできません。
なお、逮捕・勾留された場合は最長で23日間の身柄拘束が行われます。その後、起訴された場合は刑事罰が確定するまで勾留されるのが一般的です。逮捕・勾留はそれぞれ期限が定められていますが、起訴後の身柄拘束は期限に定めはありません。
つまり、「その他抑留されていること」というのは、起訴されたあとの身柄拘束されている期間をさします。簡単に言えば、「刑事事件において身柄拘束されていた事実があること」というのが一つ目の条件となります。
無罪判決が下されていること
刑事補償請求権を行使するためには、最終的に無罪判決が下されて確定していることが条件です。刑事裁判においては、「無罪」もしくは「有罪」の2択しかありません。有罪である場合は、どの程度の刑罰に処するかを決定して判決として言い渡します。
無罪ということは、犯罪行為に該当しないもしくは、罪を犯したことが認定できないという事実です。
刑事補償請求権は、「無実であるにも関わらず不当に身柄拘束が行われていた事実に対する賠償金」という性質があります。つまり、無罪でなければそもそも刑事補償請求権は行使できません。
なお、一度有罪判決を受けた場合であっても、後から無罪であることが発覚して判決として言い渡された場合は、刑事補償請求権を行使することができます。
刑事補償請求権を行使できないケース
刑事補償請求権を行使するための条件は、「逮捕・勾留その他抑留されていたこと」と「無罪判決が確定していること」です。しかし、この2つの条件を満たしていたとしても、刑事補償請求権を行使できないケースがあります。そのケースは以下のとおりです。
- 虚偽の自白をした場合
- 他の犯罪で有罪判決を受けている場合
次に、刑事補償請求権行使の条件を満たしていても、行使できないケースについて詳しく解説します。
虚偽の自白をした場合
虚偽の自白をした場合は、刑事補償請求権を行使できません。たとえば、実際に罪を犯していないにも関わらず、誰かを庇うつもりで「私がやりました」と嘘の自白をした場合は、刑事補償請求権を行使できないため注意しましょう。
自白証拠は刑事事件において重大な証拠として扱われます。そのため、嘘の自白をした場合は、相手を欺いたことになるため、刑事補償請求権の行使は認められません。
他の犯罪で有罪判決を受けている場合
他の罪で有罪判決を受けている場合も刑事補償請求権を行使できません。たとえば、詐欺罪で逮捕されたとしましょう。Aという事件で立件されて有罪判決を受けた一方で、Bという詐欺事件では立件できずに無罪となったとします。上記の場合は、刑事補償請求権の行使はできないのです。
ただし、まったく別の罪で無罪判決となった場合は、この限りではありません。たとえば、道路交通法違反で有罪判決を受けたとしましょう。この被告人は、殺人罪でも起訴されていたとします。そして、殺人罪で無罪判決となったとします。
道路交通法違反と殺人罪の因果関係は認められないため、殺人罪における刑事補償請求権の行使は可能ということです。
無罪判決確定で行えるその他の請求
無罪判決が確定した場合、基本的には刑事補償請求権の行使を検討します。しかし、1日あたり1,000円〜12,500円しか支払われません。長期間にわたって身柄拘束をされている人からすると、「満額支払われても足りない」と思うのは当然でしょう。
そこで、無罪判決が確定した場合に行えるその他の請求権についても確認しておきましょう。
裁判費用補償請求
裁判費用補償請求権とは、裁判費用を補償してもらうための請求権です。本来、刑事裁判で有罪判決が下された場合、裁判費用は原則として被告人が負担しなければいけません。
しかし、無罪判決が下された被告人に対しては、裁判費用の補償を受けられる請求権が認められています。裁判費用補償請求権には、裁判費用のほか本人が出頭した旅費や宿泊費、弁護人の旅費や宿泊費等が含まれています。
「無罪=無実の罪で刑事裁判をかけられた人」となるため、裁判費用の補償を受けられるのは当然です。
国家賠償請求
無罪判決を受けた人は、国に対して「国家賠償請求」を行うことも可能です。国家賠償請求とは、公務員等が不当な行為によって不利益を被った場合に行使できる請求権です。
無罪判決を受けたということは、警察や検察による不法行為が行われていた可能性も否定はできません。この場合は、不法行為に対する賠償金の請求が可能です。
ただし、警察や検察もある程度の証拠を揃えたうえで「あなたが犯人である」と推定しています。そのため、現実的に国家賠償請求が認められるケースは非常に稀です。
国家賠償請求が認められるためには、たとえば自白の強要があった、証拠の捏造があったなどの事実がなければいけません。なお、これらの証明は原告側にあります。
刑事補償請求権に関するよくある質問
刑事補償請求権に関するよくある質問を紹介します。
Q.刑事補償請求権と国家賠償請求権の違いは何ですか?
A.目的や条件が異なります。
刑事補償請求権とは、無実の罪で身柄を拘束されていた場合に行使できる請求権です。一方で、国家賠償請求権は、公務員等の不法行為によって不利益を被った場合に国に対して行える請求権です。
刑事補償請求権は「身柄拘束されていたこと」と「無罪判決を受けたこと」の2つの条件を満たしている時点で認められる可能性があります。無実=警察や検察の不法行為ではありません。
刑事事件においては、1%でも無実の可能性がある場合は罪に問うことはできません。これは「疑わしきは罰せず」の原則に従っています。つまり、警察や検察が捜査を行い、「罪に問える」と判断した材料を揃えたとしても、弁護側の主張に合理性があり、可能性を否定しきれなければ無罪判決を下さなければいけないのです。
つまり、99%の確率で罪を犯していたと疑うに足りる証拠があったとしても、1%罪を犯していない事実がある場合は無罪となります。そのため、必ずしも警察や検察の不法行為によって起訴されたとは言い切れません。
裁判無罪判決が確定した時点で、その人を同じ罪で罪に問うことはできません。つまり、「無実の人」となるのです。真偽はどうであれ、無実の人の身柄を拘束していたことに対する賠償をしなければいけないのは当然です。そこで認められているのが刑事補償請求権です。
一方で、国家賠償請求権とは、公務員等の不法行為によって不利益を被った場合にのみ認められます。たとえば、警察や検察からの自白の強要や証拠の捏造等があった場合です。
警察や検察等が正当な捜査を行って起訴している場合は、国家賠償請求権を行使したとしても認められる可能性は限りなくゼロに近いです。
Q.冤罪だった場合、受けられるのは経済的な補償のみですか?
A.基本的には、経済的な補償のみです。
冤罪が認められた場合は、刑事補償請求権や国家賠償請求権の行使によって経済的な補償を受けられます。しかし、実際に無実の罪で逮捕されたり勾留されたりした人は、全国ニュースで報道されたり、ネットニュースになったりなどさまざまな影響を受けるでしょう。
そのため、中には「冤罪であった」という報道を行って名誉を回復してほしいと考える人もいるかもしれません。しかし、国等に対して行えるのは、経済的な補償を求める請求権のみです。
ただし、名誉回復措置という方法があり、この方法を行使することによって強制的に名誉回復できる可能性があります。名誉回復措置を利用するためには、報道等をしたメディアに対して、HP、新聞、WEBメディア等を介してお詫びや記事の訂正、冤罪であった事実の記事を記載するなどの要求ができます。
大きな事件であればあるほど、事件当初は大きく報道されてしまうため、名誉回復措置が不十分であると感じることがあるかもしれません。しかし、現状では上記のような方法しかないのが実情です。
Q.刑事補償請求権の行使に時効はありますか?
A.無罪判決が確定してから3年です。
刑事補償請求権を行使できる時効は、無罪判決が確定してから3年です。無罪判決からではなく、あくまでも「確定してから」です。刑事裁判において判決が言い渡されてから判決が確定するまでは、14日間かかります。
この間に検察やあなたが控訴した場合は、判決が確定せずに刑事裁判が継続するためです。つまり、判決が言い渡されて14日経過した時点で確定し、そこから3年で消滅時効が成立するのです。
Q.取り調べを行った警察官や検察官に対して賠償請求を行えますか?
A.国家賠償請求を行うことができます。
国家賠償請求は、警察官や検察官といった公務員に対して行える賠償請求権です。後から、無罪判決が確定した場合は、国家賠償請求として国を相手にして賠償請求ができます。
ただし、何度もお伝えしているとおり、国家賠償請求が認められるケースは稀です。警察官や検察官の不法行為が認められた場合に限って、賠償請求が認められることを覚えておきましょう。
あなたとしては「許せない」という気持ちがあるかもしれません。しかし、法律上の範囲内で判断をするしかなく、国家賠償請求は難しいものであることを覚えておきましょう。
Q.有罪判決が確定して収監された後に無罪が確定した場合はどうなりますか?
A.刑事補償請求権の行使が可能です。
有罪判決を受けて刑務所に収監されていた場合、刑務所に収監されていた日数分の補償を受けられます。
まとめ
今回は、刑事補償請求権とは?について解説しました。
刑事補償請求権とは、刑事裁判において身柄拘束を受けていた人が無罪判決を受けた場合に請求できる権利です。無実である人を拘束していたことに対する補償であり、1日あたり1,000円〜12,500円の範囲内でさまざまな事情を考慮して金額は決定します。
実際に身柄拘束されていた人からすると「足りない」と感じるかもしれませんが、上記以上の補償を受けることは難しいでしょう。まずは、弁護士へ相談をしたうえで、無罪判決を勝ち取るための対応・対策を検討していきましょう。