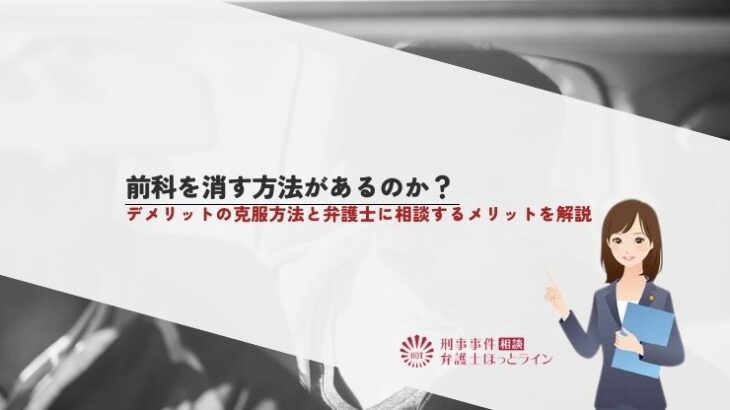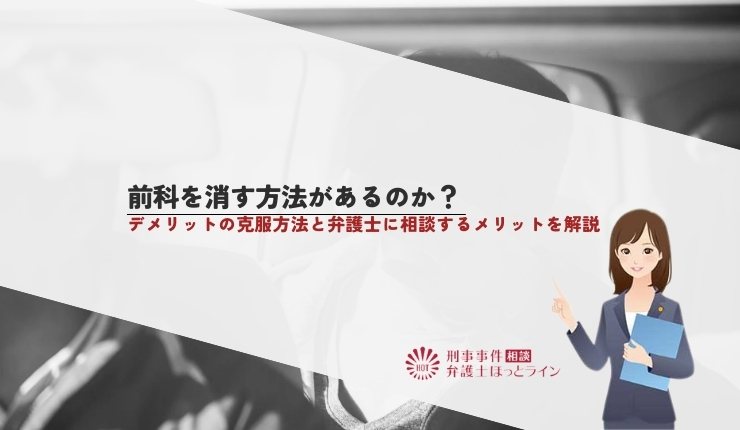
「前科があるせいで転職活動に不安を感じている」「しっかりと更生を果たしたいので前科を抹消して真っ白な状態からやり直したい」というように、刑事責任を果たしたあとの人生をリスタートするにあたって前科の存在を不安に感じる人は少なくありません。
前科があると、仕事や日常生活にさまざまな悪影響が生じる可能性があります。たとえば、現在の勤務先を解雇されたり、離婚を申し入れられて結婚生活が終わったりしかねません。
そこで、この記事では、「前科を消す方法があるのか」と疑問を抱いている人のために、以下の事項についてわかりやすく解説します。
- 前科を消す方法があるのか
- 前科の内容、前歴との違い
- 前科が原因で生じるデメリット
- 前科を回避するための方法、弁護士に相談・依頼するメリット
前科をつけないようにするには、刑事訴追された初期段階から適切な防御活動を展開して不起訴処分獲得を目指すのが合理的です。刑事事件に強い私選弁護人に依頼して、事案の状況に応じて適切な防御活動を展開してもらいましょう。
目次
前科を消す方法があるのか?
まずは、前科の定義や前科を消す方法の有無などについて解説します。
前科は有罪判決に処された経歴のこと
前科とは、有罪判決を下された経歴のことです。前科がある人は「前科者」と呼ばれます。
前科の根拠になる有罪判決には、実刑判決だけではなく、執行猶予付き判決、罰金刑、科料、拘留すべてが含まれます。ただし、交通違反の犯歴は前科には含まれません。
前科は有罪判決が確定するまでつかない
前科がつくのは有罪判決が確定したタイミングです。
逮捕されたとき、勾留されたとき、起訴処分が下されたとき、刑事裁判中などは、まだ前科はついていない状態です。
たとえば、逮捕・勾留されて長期間身柄拘束されたとしても、不起訴処分獲得に成功すれば、前科はつきません。
前科と前歴の違い
前科と似て非なる概念として「前歴」というものがあります。
前歴とは、警察や検察の捜査対象になった経歴のことです。逮捕されたかどうか、起訴されたかどうか、有罪になったかどうかなどとは関係なく、一度でも捜査機関の対象になると前歴が残ります。たとえば、ある刑事事件への関与が疑われて任意の事情聴取が複数回実施されたものの、起訴するだけの客観的証拠が得られなかったため、不起訴処分が下された場合には、前科はつきませんが前歴はつきます。
つまり、前科がついた場合には必ず前歴は残りますし、前歴があるからといって前科がついているわけではない、ということです。
前科を消す方法はない
前科は、検察庁が作成・保管する「前科調書」にデータとして記録されています。
前科調書にアクセスできるのは捜査機関だけで、世間一般には公開されていません。
そのため、前科情報が外部に漏れる事態は考えられないといえるでしょう。
ただし、その反面として、一般人側から前科情報の抹消を請求できないのが実情です。なぜなら、前科調書はあくまでも捜査機関の内部資料として活用されるものだからです。
ですから、一度でも前科調書に前科情報が登録されると当該情報は半永久的に残り続けると理解しておきましょう。
前科がつくとできないことや前科がつくと困ることは何ですか?
前科がつくと困ることがたくさんあります。
ここでは、前科がつくデメリットについて解説します。
前科があると行けない国がある
前科が原因で海外旅行や海外出張・海外赴任に支障が生じる可能性があります。
前科を理由にパスポートの発給や渡航先の追加が拒否される可能性がある
まず、日本を出入国するにはパスポートが必要です。
しかし、以下の事情がある場合には、外務大臣の判断で一般旅券の発給等が制限される可能性があります(旅券法第13条第1項)。有効なパスポートを取得できなければ、日本国から出国できず、海外旅行などにいくことができません。
- 渡航先に施行されている法規で入国を認められない者
- 死刑、無期もしくは長期二年以上の刑に当たる罪で刑事訴追されている者、または、これらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状、鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣へ通報されている者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、または、執行を受けることがなくなるまでの者
- 旅券法第23条の規定に違反して刑に処せられた者(パスポートの偽造、申請書類の虚偽記載、他人名義のパスポートの使用など)
- 旅券や渡航書の偽造、旅券・渡航書として偽造された文書の行使、これらの未遂罪を犯し、公文書偽造罪などの刑に処せられた者
- 自力で帰国費用を捻出できず公共負担で帰国させなければいけないおそれがある者
- 著しく、かつ、直接に日本国の利益や公安を害する行為をおこなうおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
たとえば、パスポートの偽造などの容疑で前科がついている場合には、海外旅行などを希望したとしても、一般旅券が発給されない可能性が高いです。また、パスポート関係以外の犯罪であったとしても、国際的な薬物犯罪・強盗事件・特殊詐欺事件などに関与した疑いで有罪判決が下された経歴がある場合も、パスポートを取得できない危険性があります。
前科がある場合はパスポート申請手続きが複雑になる
パスポートの発給申請をするときには、一般旅券発給申請書に必要事項を記入して各自治体の旅券事務所などに提出しなければいけません。
そして、一般旅券発給申請書の「刑罰等関係」欄に該当する場合(前科があるとき)には、パスポート申請をするときに、渡航事情説明書や起訴状の写し・判決謄本などの提出も求められます。そして、提出してすぐにパスポートが発給されるわけではなく、審査に1ヵ月程度の期間を要するのが一般的です。
ですから、前科がある人が海外旅行・海外出張・海外赴任を予定しているのなら、できるだけ早いタイミングで申請手続きを済ませる必要があるといえるでしょう。前科がある場合の必要書類や申請方法について疑問があるときには、お近くの旅券事務所などまでお問い合わせください。
渡航先から入国を拒否される可能性がある
まず、渡航予定先次第では、入国にビザが必要とされる場合があります。たとえば、ロシア、イラク、サウジアラビア、パキスタンなどに入国するには、渡航予定国のビザを発行してもらわなければいけません。ただ、入国審査の際には前科の有無が確認されるため、前科を理由にビザが発行されず、入国できないリスクがあります。
次に、入国要件にビザが課されていない場合でも、電子渡航認証システムで実施される入国審査に引っかかって入国を拒否される可能性があります。たとえば、ヨーロッパ各国ではETIAS(エティアス)、アメリカではESTA(エスタ)、カナダではeTA(イータ)、オーストラリアではETAS(イータス)という電子渡航認証システムによる審査が実施されており、重大犯罪や薬物犯罪、深刻な交通事故を起こして前科がついている場合には入国を許されないでしょう。
前科がつくとなれない職業がある
前科があると、仕事や資格、キャリア形成に一定の悪影響が生じる可能性があります。
前科が原因で就職活動・転職活動が不利になる
まず、就職活動や転職活動の際、履歴書・職務経歴書の提出を求められるのが一般的です。
そして、履歴書には賞罰欄が設けられており、前科の有無について申告をしなければいけません。採用段階で前科があることが会社に発覚すると、それだけで印象が悪くなり、内定に至らない可能性が高いでしょう。
また、前科を理由に不採用になることを嫌って、前科があることを隠して就職活動をおこない内定を獲得したとしても、就職後に前科があることがバレると、経歴詐称を理由に懲戒解雇されるリスクが生じます。
つまり、希望職種を問わず、前科がある人のキャリアチェンジ・キャリア形成は一般の人よりも困難になるといえるでしょう。
特に、金融関係の職業は従業員の身辺調査が厳しい傾向が見られるので、前科があると就職は難しいです。
前科があると制限される資格一覧
資格に対する社会的信頼性を保持する目的から、前科を理由に資格を制限する旨の規定が置かれている場合があります。
たとえば、医者については医師法にルールが定められており、「罰金以上の刑に処せられた者や、医事に関して犯罪や不正行為に及んだ者」の医師免許資格が剥奪されます。また、弁護士は「禁錮以上の刑に処せられた者」、司法書士は「禁錮以上の刑に処せられて、その執行を終わり、または、執行を受けることがなくなってから3年が経過しない者」が資格制限の対象です。さらに、警備員や教員、国家公務員・地方公務員などについても同様の定めが置かれています。
このように、各資格について規律する法律ではさまざまな制限事由が定められているので、現在資格を利用して仕事をしている人や今後資格取得を検討している人は、前科を理由に資格制限になるかを事前に確認しておきましょう。資格制限一覧については以下のリンク先をご確認ください。
参照:資格制限について|法務省
前科がつくと会社をクビになる危険性もある
会社は就業規則という社内ルールを定めなければいけません。就業規則のなかには、必ず「懲戒規程」が置かれます。懲戒規程には、懲戒処分の種類や程度、懲戒事由が詳細に定められています。
そして、前科がつく事態になると、現在の勤務先が定めている就業規則の懲戒規程に抵触し、会社をクビになるリスクに晒されます。
たとえば、「禁錮以上の実刑判決を下されたこと」が懲戒解雇事由として規定されている場合、強盗事件などを起こして有罪判決が確定すると、懲戒解雇処分が下されます。また、「企業の社会的信用を毀損したこと」のような包括的な条項が懲戒事由に掲げられている場合、刑事事件を起こしたことがニュースで報道されて企業名もバレたりしただけで懲戒処分の対象になりかねません。
前科が原因で家庭や身近な人間関係に悪影響が出かねない
前科がつくと、家族などの身近な人間関係に悪影響が生じる可能性があります。
前科は法定離婚事由に該当する
民法第770条第1項第5号では「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を法定離婚事由と定めています。法定離婚事由に該当する事実が発生すると、配偶者から離婚を申し出られたときに抗うことができないのが原則です。
そして、「前科があること」「前科がついたこと」「逮捕されたこと」などは、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当すると考えられています。
ですから、結婚生活を送っているなかで刑事事件を起こして前科がついてしまうと、配偶者に離婚されるリスクに晒されるといえるでしょう。この場合、離婚時の慰謝料や子どもの親権、面会交流権などの諸条件も不利になる可能性が高いです。
前科がバレると身近な人間関係が壊れる可能性がある
前科がついたことが身近な人にバレると、交友関係・人間関係が壊れる可能性があります。
たとえば、結婚を視野に入れて交際しているパートナーにバレると破談になることもあるでしょう。また、家族や親族に縁を切られたり、友達が離れていってしまうことにもなりかねません。
前科が原因で子どもにもデメリットが生じることがある
前科がつくと、子どもの生活にも実質的な悪影響が生じる可能性があります。
たとえば、親に前科がついたことが子どもが通う学校で噂になると、「犯罪者の子どもだ」などと偏見をもたれて、子どもが学校でイジメに合うリスクが生じます。場合によっては転校を余儀なくされるでしょう。また、前科がついたことで職を失って家計が厳しくなると、習いごとを辞めなければいけなくなったり、希望どおりに進学できなくなったりします(警察関係、金融関係など)。さらに、子どもが結婚するときに身辺調査を実施されると、親の前科がバレて結婚に反対される危険性に晒されます。
このように、「親は親、子どもは子ども」という理屈が通用しにくい場面では、親の前科を理由に子どもが何かしらの不利益を強いられてしまうでしょう。
インターネット上の情報が原因で社会生活に支障が生じる
刑事事件を起こすと、ニュース番組やネットニュースで報道される可能性があります。
どの事件がどのタイミングで報道されるかについて明確なルールは存在しません。ただ、世間的に関心が高い事件、悪質な凶悪犯罪などに関与したときには、逮捕や在宅起訴された段階で報道されるリスクがあると理解しておきましょう。
そして、一度でもテレビやネットで報道されると、インターネット上に事件を起こした事実が半永久的に残ってしまいます。
たとえば、就職希望先の企業や知人などに氏名をWeb検索されると簡単に前科があることがバレてさまざまな弊害を強いられかねないでしょう。
前科があると再犯時のペナルティが重くなる
前科がある状態で再犯に及ぶと、厳しい刑事処分を下される可能性が高いです。
まず、前科者が犯罪に及んぶと、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されて、逮捕・勾留されるリスクが高まります。初犯なら在宅事件ベースで刑事手続きが進行するような事案でも、強制的に身柄を拘束されかねません。捜査段階の身柄拘束期間は最長23日間にも及ぶので、会社や家族に隠しとおすのが難しくなってしまいます。
次に、前科の有無や内容、回数は情状要素として考慮されるので、前科者が再犯に及ぶと、起訴猶予処分や執行猶予付き判決などの有利な処分・判決を獲得しにくくなるのが実情です。
さらに、前科と再犯のタイミング次第では、刑法に規定されている狭義の「再犯」に該当し、再犯加重のペナルティを科されます。具体的には、「懲役刑に処せられた者がその執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内にさらに犯罪に及んだ場合、その者について有期懲役を処すときには、法定刑の『長期が2倍以下』まで拡張される」というものです(刑法第56条第1項、刑法第57条)。たとえば、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されていますが、再犯加重が適用される場面では、「20以下の懲役又は50万円以下の罰金」の範囲内で実刑判決が下されます。
【注意!】前科のデメリットには誤解もある
ここまで紹介したように、前科は消すことができませんし、前科があることでさまざまなデメリットが生じるのは紛れもない事実です。
その一方で、「前科のデメリット」として世間で語られているもののなかには、誤解に基づくものも少なくありません。
たとえば、以下の項目は全て間違いです。
- 前科がつくとブラックリストに登録される
- 前科がつくとローンを組めない
- 前科がつくとクレジットカードが使えなくなる
- 前科の情報は戸籍や住民票、運転免許証などに記載される
- 前科情報は一般人でも簡単に調べられる
- 前科がつくと生活保護費や年金を受け取ることができなくなる
第1に、前科は個人の経済的信用力とは全く関係がありませんし、CICやJICCなどの個人信用情報機関が前科情報を入手するのは不可能です。ですから、前科があるからといって信用情報にキズがつくことはありません。たとえば、収入などの要件を満たせば住宅ローンやカードローン契約を締結できますし、今までどおりにクレジットカードも使用しつづけられます。
第2に、戸籍や住民票、運転免許証には氏名や住所などの情報が記載されるだけで、前科の有無に関する項目は存在しません。ですから、戸籍や住民票、運転免許証がきっかけで第三者に前科の有無を知られることもないでしょう。
第3に、生活保護制度や年金保険制度はそれぞれ独立した目的の制度なので、前科がついても、要件を満たす限りで保護費などを受給できます。
前科持ちはバレるのか?前科がある人の特徴
前科がバレるきっかけや、前科をバレにくくする方法について解説します。
前科持ちがバレるきっかけ
前科持ちの前科がバレる代表的なきっかけとして以下のものが挙げられます。
- 実名報道されてインターネット上に事件の情報が残っている場合
- 自分で前科があると発信した場合
- 有罪になったことを知ってる知人や会社関係者から噂で広まった場合
- 探偵や興信所を使って前科の有無を調査された場合
特に、実名報道されると、氏名を検索しただけで簡単に前科がバレてしまいます。SNSが普及した情報化社会では、実名報道は致命的といえるでしょう。
前科をバレにくくする方法
前科をバレにくくする方法として以下のものが挙げられます。
- 専門業者に逆SEO対策を依頼して、名前を検索されて犯罪に関する記事が検索上位にあがってこないようにする
- 前科があることを誰にも口外しない
- 養子縁組をして氏名を変更する
- 家庭裁判所に、名の変更許可・氏の変更許可を申し立てる
ただし、これらの対策をしたとしても、一度でもどこかに前科情報が洩れてしまうと、一生「前科がバレるのではないか」という不安と隣り合わせで生きていかなければいけなくなります。
すでに前科がついている人はこれらの対策に力を入れるしかありませんが、現段階でまだ前科がついていない状態なら「前科を回避すること」を防御目標に掲げて適切な防御活動に専念するべきだといえるでしょう。
前科がつかないようにするにはどうすればよいのか?
一度でも前科がつくと消すことができません。
つまり、前科のデメリットを回避したいなら、「前科をつけないこと」が何より重要だということです。
さいごに、前科がつかないようにするための対処法について解説します。
早期に示談交渉を開始する
万引きや痴漢など、被害者がいるタイプの刑事事件を起こしたときには、できるだけ早いタイミングで示談交渉を開始するのがおすすめです。
示談交渉とは、刑事事件の加害者・被害者間で和解条件について交渉をおこなって民事的解決を目指すことです。加害者が被害者に対して示談金を支払う代わりに、提出済みの被害届・告訴状を取り下げてもらったり、そもそも捜査機関に被害申告せず民事的な解決で納得してもらったりします。
たとえば、警察に相談する前に被害者に接触して示談交渉をスタートすれば、刑事事件化する前に当事者間で紛争を解決できます。結果として、前科だけではなく前歴もつかずに済むでしょう。
また、仮に警察に相談されて捜査活動がスタートしたとしても、「被害者との間で示談が成立済み」という事実は情状要素として考慮されるので、微罪処分や起訴猶予処分を獲得できる可能性が高まります。微罪処分や不起訴処分の獲得に成功すれば刑事裁判にかけられず、前科がつくこともありません。
ただし、薬物犯罪や公然わいせつ罪のような被害者が存在しないタイプの犯罪行為で刑事訴追されたケースでは示談交渉をする余地はないので、軽い刑事処分獲得を目指すなら別の防御活動を模索する必要があります。
微罪処分や不起訴処分獲得を目指す
日本の刑事裁判の有罪率はほぼ100%です。つまり、刑事裁判にかけられた時点で実質的には有罪になって前科がつくことが確定します。
ですから、前科の回避を目指すなら、捜査段階で適切な防御活動を展開して、微罪処分や不起訴処分獲得を目指す必要があるといえるでしょう。
たとえば、罪を認めて真摯に反省の態度を示す、犯行に至った動機にやむにやまれぬ事情があったことを証明する、被疑者のために証言してくれる証人を用意するなどの対策が挙げられます。
刑事事件に強い弁護士に相談する
刑事事件を起こしたときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談することを強くおすすめします。
というのも、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することで、以下のメリットを得られるからです。
- 早期に被害者との間で示談交渉を進めてくれる
- 逮捕・勾留を阻止するために捜査機関に働きかけてくれる
- 微罪処分・不起訴処分獲得に向けて役立つ証拠を収集してくれたり、事情聴取での供述方針を明確化してくれる
- 逮捕・勾留中の被疑者と積極的に接見機会を作って励ましてくれる
- 起訴処分が下されたとしても、執行猶予付き判決や罰金刑などの有利な判決獲得を目指して防御活動を展開してくれる
- 前科によるデメリットを回避するための現実的なアドバイスを提供してくれる など
警察に逮捕されると当番弁護士や国選弁護人を選任できる場合がありますが、弁護士によるメリットを最大限享受したいなら、被疑者本人の責任で私選弁護人と契約するのがおすすめです。所定の弁護士費用は発生しますが、さまざまなノウハウを発揮して依頼者の利益を最大化してくれるでしょう。
前科を消す方法はない!軽い刑事処分獲得を目指して早期に弁護士へ相談・依頼しよう
前科を消す方法は存在しません。一度でも前科がついてしまうと、前科によるデメリットに悩まされ続けます。
ですから、すでに前科がついてしまっているのなら、前科がバレないように慎重に社会生活を営む必要があります。また、刑事事件を起こしたものの現段階ではまだ捜査活動がおこなわれている途中なら、前科回避を目指した防御活動を展開するのが重要だといえるでしょう。
当サイトでは、刑事事件の実績豊富な弁護士を多数紹介中です。弁護士の力を借りるタイミングが早いほど有利な状況を作り出しやすいので、刑事訴追のリスクに晒されているなら速やかに信頼できる弁護士までお問い合わせください。