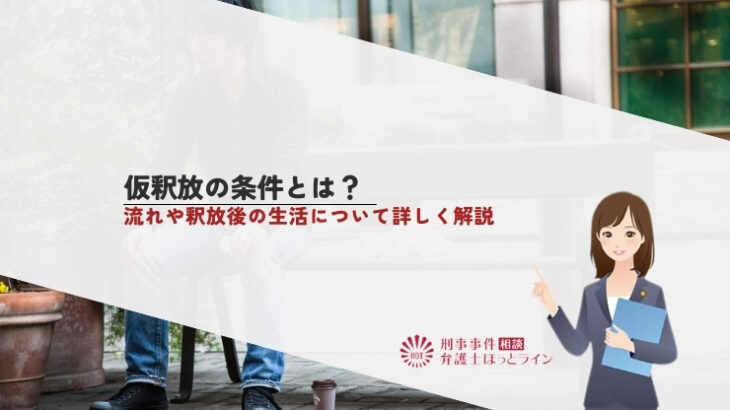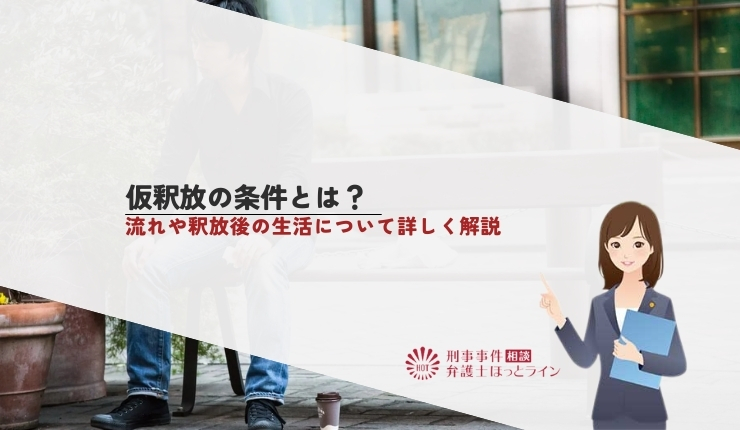
仮釈放とは、刑務所に収容されている受刑者が一定の条件を満たした場合に、刑期の満了前に社会復帰を許可される制度です。あくまで「仮の釈放」であり、釈放後も保護観察のもとで生活しなければならないなど、いくつかの条件があります。
仮釈放の目的は、受刑者の更生を促進し、円滑な社会復帰を支援することにありますが、すべての受刑者が対象となるわけではありません。仮釈放が認められるかどうかは、これまでの服役態度や反省の有無、再犯のおそれ、被害者への影響など、さまざまな要素を考慮したうえで判断されます。
本記事では、仮釈放の概要とあわせて、その具体的な条件や判断基準について、詳しく解説します。
仮釈放とは
仮釈放とは刑期が満了する前に釈放されることです。まずは、仮釈放とは何か、保釈との違いは何か?について詳しく解説します。
刑期満了前に釈放すること
仮釈放とは、刑期が満了する前に釈放されることを指します。刑期を全うした場合は「満期出所」と言いますが、仮釈放の場合は満期を迎える前に出所できます。
そもそも、刑事罰には「懲役刑」という刑罰があります。懲役刑は、一定期間刑務所に収監されて刑務作業が義務付けられている刑罰です。
たとえば、「懲役5年」の有罪判決が下された場合は、5年間(未決勾留日数を除外されることもある)刑務所に収監されて刑務作業を行わなければいけません。しかし、5年経過する前に釈放されることもあります。この場合、「仮釈放」と言います。
仮釈放が認められる受刑者は、いわゆる模範囚と呼ばれる者です。刑務所内での生活態度が良いなど、一定の条件を満たした場合に検討され、認められれば仮釈放が許される流れです。
なお、懲役刑を大きく分けると「有期」と「無期」があります。有期懲役は、その名の通り期間の定めがある懲役刑を指します。無期懲役は、その名の通り期限の定めがない懲役刑です。
無期懲役の場合は、期間の定めがないため、多くの人は仮釈放もないと思われるかもしれません。しかし、無期懲役囚であっても可能性は低いものの、仮釈放が認められるケースがあります。
仮釈放中は保護観察が付くため、定期的に保護観察官や保護司と呼ばれる人と面談を行わなければいけません。もちろん、さまざまな約束事も定められており、約束を破った場合は刑務所に戻らなければいけません。
とはいえ、社会に戻って生活を送ることができるため、受刑者にとってはメリットの多い制度であると言えます。そして、仮釈放を認める目的としては、社会生活の機会を与えて社会の中で更生を促そうとすることです。
社会に触れることで円滑な社会復帰を目指そうとするのが、仮釈放の主な目的であると考えておけば良いでしょう。
釈放・保釈との違いとは
釈放(しゃくほう)と保釈(ほしゃく)は似た言葉であり、どちらも身柄を解放することという意味で使用される言葉です。しかし、それぞれ明確な違いがあります。
釈放と保釈の明確な違いは、「身柄解放されるタイミング」です。保釈とは、起訴された被疑者が保釈金を支払って身柄解放されることを指します。
一方で、釈放とは逮捕された被疑者が起訴される前に身柄拘束から解放されることを指します。また、受刑者が満期出所前に身柄拘束から解放されることは、仮釈放と呼びます。
このように意味としては「身柄拘束からの解放」ですが、タイミングによって保釈と釈放を使い分けています。なお、保釈の場合は保釈金といって、保証金を預け入れなければいけません。
仮釈放の条件
仮釈放を受けるためには以下の条件を満たしている必要があります。
- 一定以上の刑が執行されている
- 反省・更生の意欲が認められている
- 再犯の恐れがない
- 保護観察が必要であること
- 社会が仮釈放を認めている
- 身元引受人・帰住予定地があること
次に、仮釈放が認められるための条件について詳しく解説します。
一定以上の刑が執行されている
仮釈放が認められるためには、一定以上の刑が執行されていることが条件です。具体的な条件は、以下のとおりです。
- 判決による刑期
- 仮釈放の条件
- 有期刑の場合
- 刑期の1/3以上服役
- 無期懲役の場合
- 10年以上服役
参考:刑法|第28条
刑法に定められている仮釈放の条件は上記のとおりです。しかし、実際には刑期の1/3以上もしくは無期懲役の場合は10年以上の刑期を過ごしても、仮釈放が認められることはありません。
実務上は、刑期の7割〜8割以上が執行されていなければ仮釈放は認められていないため、実際は「7割〜8割以上である」と思っておいたほうが良いです。
たとえば、懲役10年の刑罰が確定した場合、刑法に定められている仮釈放の条件で見れば、3年以上の服役で仮釈放が認められる可能性があります。しかし実際には、7年〜8年以上服役しなければ、仮釈放が認められることはありません。
また、期間の定めがない無期懲役の場合は、一般的には30年以上服役しなければ仮釈放の審査すら受けられないと言われています。30年以上である理由は、有期刑の最高刑が30年であるためです。
上記のことから、期間の定めがない無期懲役囚の場合は30年以上で審査が可能となります。実際には、30年以上経過しても仮釈放が認められるケースは稀であり、いわゆる終身刑化されているとも言われています。
反省・更生意欲が認められること
刑務所内での過ごし方等を考慮し、犯罪について反省し、しっかりと更生しようとしている姿勢が認められる場合は、仮釈放が検討されます。
いわゆる模範囚として生活している人は、仮釈放が検討される可能性が高まります。他にも、刑務所内では、生活態度等に応じて等級(区分)わけされているため、仮釈放を目指す人は生活態度を改め、良好な等級(区分)を目指していくことになるでしょう。
再犯の恐れがないこと
当然ですが、再犯の恐れがないことが条件です。仮釈放後に受刑者が再犯を起こした場合、「なぜ仮釈放を認めたのか?」と問題になります。
そのため、再犯の恐れがないかどうかを検討されたうえで可能性がないと判断されて初めて、仮釈放が検討されます。なお、刑務所の中でも再犯防止プログラム等を受講できるため、積極的に受講すると良いでしょう。
保護観察が必要であること
仮釈放が認められた場合は、残りの刑期の間は保護観察が付きます。保護観察とは、保護観察官や保護司と呼ばれる人と定期的に面談を行い、社会生活での状況等をお話しします。
もちろん、約束事(遵守事項)なども細かく定められており、約束を破った場合は仮釈放が取り消される可能性があるため注意しなければいけません。たとえば、飲酒による事件を起こした人は、「飲酒をしない」などの約束事が定められます。
社会が仮釈放を認めていること
社会の感情が受刑者の仮釈放を認めているかどうかも重要なポイントです。たとえば、被害者が仮釈放を認めているかどうか、地域住民が仮釈放を認めているかどうか、などで判断されます。
また、報道等によって社会の一般意見で「仮釈放すべきではない」と判断された場合は、仮釈放が認められません。
身元引受人・帰住予定地があること
仮釈放が認められるためには、身元引受人や帰住予定地があることが条件です。通常は、家族等の身内もしくは会社の社長等が身元引受人となります。帰住予定地は、家族が住む家や会社の寮など、監督者がいることが条件です。
仮釈放までの流れ
仮釈放の大まかな流れは以下のとおりです。
- 仮釈放前の調査
- 仮釈放前の面接
- 身元引受人への通知
- 仮釈放前の処遇
- 仮釈放
次に、仮釈放までの大まかな流れについて詳しく解説します。
仮釈放前の調査
まずは、仮釈放前の調査が行われます。仮釈放前の調査では、刑務所の中で行われる面接を通して、主に以下のことについて確認します。
- 身元引受人の調査
- 居住予定地の状況
- 就労などの生活環境
- 被害者の感情調査
- 社会復帰のための援助について
仮釈放は、満期を迎える前に釈放されることを指します。そのため、かならず身元引受人がいなければいけません。
身元引受人は誰でも良いわけではなく、受刑者が更生を目指すうえで相応しい人かどうかを判断すると思っておきましょう。たとえば、受刑者の家族で犯罪歴などもなく、一般的な人であり、受刑者の更生を目指すうえで邪魔にならない人であれば認められます。
一方で、たとえば反社会勢力に属している人が同じ組織に属している人を身元引受人に設定することはできません。そもそも、反社会勢力に属している場合は、仮釈放が認められません。
そして、次に居住予定地の調査が行われます。たとえば実家に帰る場合は、実家が受刑者の更生をサポートしていくうえで適切な環境かどうかを確認します。
次に、就労などの生活環境調査も行わなければいけません。仮釈放が認められれば、社会で生活を送っていくことになるため、当然就労してお金を稼がなければいけません。就労環境が整っていることも仮釈放の条件の一つであるため、調査されます。
そして、被害者の感情調査も行われます。被害者が受刑者の仮釈放を認めているかどうか?についても調査されるため、被害者が認めていなければ仮釈放は難しいでしょう。
その他、社会復帰のための援助を受けられるかどうかも確認します。家族や会社からのサポートはもちろんのこと、公的なサポートを積極的に利用しようとしているかどうか?なども確認されます。
上記のような内容をすべて調査したうえで仮釈放の検討をすべきかどうかが判断される流れです。
仮釈放前の面接
仮釈放の検討が進められた場合、受刑者に対して仮釈放前の面接を行います。面接は2回行われ、1回目は仮釈放が行われる3カ月〜9カ月前に行われ、仮面や準面とも呼ばれます。。
1回目の面接(予備面接)が終了してから1カ月〜6カ月経過後にもう1回面接が行われる流れです。なお、2回目の面接のことを「本面」と呼びます。地方更生委員会との面会であり、本面を通して最終的に仮釈放を認めるかどうかが決定される流れです。
身元引受人への通知
仮釈放が決定すると、その旨を身元引受人に通知されます。通知が届くまでは、本面からおおよそ1カ月程度です。さらに1カ月程度経過した時点で仮釈放となるケースが多いです。
なお、仮釈放後は初めに保護観察所へ行かなければいけません。また、基本的には身元引受人が出迎えることが好ましいです。
仮釈放前の処遇
受刑者の処遇として、仮釈放の2週間程度前になると仮釈放準備寮と呼ばれる場所に移されるケースが多いです。刑務所内にある施設ではあるものの、社会生活に近い環境で過ごし、徐々に社会に慣れることを目的としています。
仮釈放
すべての手続きが完了すると仮釈放となります。仮釈放中は、さまざまな制約の中で生活をしなければいけませんが、更生を目指して絶対に再犯等を行わないように注意しましょう。
仮釈放の種類とは
「仮釈放」と言っても、その種類はさまざまです。具体的には、以下のような種類があります。
- 仮出獄
- 仮出場
- 仮退院
次に、仮釈放の種類や対象者やその他の違いについて詳しく解説します。
仮出獄
仮出獄とは、懲役刑や禁錮刑によって刑務所に収監されている受刑者が仮釈放されることを指します。仮出獄が認められるためには、先ほど解説した以下の条件を満たしている必要があります。
- 一定以上の刑が執行されている
- 反省・更生の意欲が認められている
- 再犯の恐れがない
- 保護観察が必要であること
- 社会が仮釈放を認めている
- 身元引受人・帰住予定地があること
一般的に「仮釈放」と言うと仮出獄のことを指すと思っておけば良いでしょう。
仮出場
仮出場とは拘留や労役場留置を受けている者が、情状等によって刑期満了前に釈放されることを指します。
まず、拘留とは1日以上30日未満の間、刑事施設に収監する刑事罰のことです。読み方が同じ「勾留」というものもありますが、勾留は刑事罰ではなく、刑事手続きにおいて被疑者・被告人の身柄を拘束するためのものです。
労役場留置とは、罰金刑が確定した者のうち罰金を納められない人を1日5,000円程度で労役場へ収監することです。罰金刑は、通常身柄の拘束が発生しませんが、下された判決に従って金銭を納められない場合は、労役場留置となります。
仮退院(保護処分対象者)
仮退院とは、少年院などの施設から仮退院することを指します。刑務所に収監されている者の場合は、「出獄」や「出所」などと言いますが、少年院の場合は「退院」と言う言葉を使用します。
通常、少年院へ入院する者は期間が定められていますが、期間が満了する前に退院する場合は「仮退院」と呼びます。
仮退院(婦人補導院の在院者)
仮退院は、婦人補導院へ入院している者に対して使うケースもあります。婦人補導院とは売春防止法によって定められた補導処分を受けた者が入院する場所です。
なお、2024年4月1日に売春防止法の改正が行われ、婦人補導院がすべて廃止されました。そのため、現在は婦人補導院を対象とした仮退院はありません。
仮釈放後の生活
仮釈放後の生活は、基本的にはとくに制約はなく日常生活を送れます。ただし、仮釈放が認められた者ごとに定められた、遵守事項を守らなければいけません。また、保護観察が付されるため、保護司や保護観察官との面談を定期的に行う必要があります。
次に、仮釈放後の生活についても詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
遵守事項を守って日常生活を送れる
仮釈放が認められた場合、基本的には日常生活を送れます。ただし、それぞれに対応した遵守事項が定められています。遵守事項は、一般遵守事項と特別遵守事項の2つがあります。
一般遵守事項は、健全な生活態度を保持することや保護観察官、保護司と定期的に面談することなど、すべての人に対して定められた約束事です。
特別遵守事項は、保護観察を受ける人それぞれに定められている遵守事項を指します。たとえば、共犯者との交際を禁止したり、飲酒による犯罪である場合は、飲酒を控えるなどの遵守事項が定められます。
再犯を防止し、更生を目指すために必要となることを特別遵守事項として定められると思っておけば良いでしょう。なお、遵守事項を守らなかった場合は、仮釈放が取り消されて再度、刑務所に収監される可能性があるため注意してください。
保護観察が付される
仮釈放中は、保護観察が付されます。保護観察とは、保護観察官や保護司と呼ばれる人たちが、仮釈放者の監督や指導、支援を行います。
保護観察中は、保護観察官や保護司と定期的に面談を行なったうえで、適切なサポートを受けられます。もし、保護観察期間中に特別な事情がないにも関わらず、保護観察官や保護司との面談に参加しなかった場合は、仮釈放が取り消される可能性があるため注意しましょう。
保護観察の期間は残刑期
保護観察の期間は、残りの刑期分です。たとえば、懲役10年の判決を受けた者が7年で仮釈放された場合、保護観察に付される期間は3年間です。
無期懲役囚の場合は、生涯にわたって保護観察が付されることとなります。ただ、保護観察がついているからといって、何らかの制限を受けることはほぼありません。日常生活を送りながら、定期的に面談が行われるものであると考えておけば良いでしょう。
仮釈放が取り消されるケース
仮釈放は、満期を迎える前に社会へ戻ってこられる制度です。しかし、以下に該当した場合は、仮釈放が取り消されて再度、刑務所へ収監されることになるため注意しなければいけません。
- 保釈後に罪を犯して罰金刑以上の刑罰が科された場合
- 保釈前に犯した罪で罰金刑以上の刑罰が科された場合
- 遵守事項を守らなかった場合
次に、仮釈放が取り消されてしまうケースについて詳しく解説します。
保釈後に罪を犯して罰金刑以上の刑罰が科された場合
仮釈放中に何らかの罪を犯し、罰金刑以上の刑罰が確定した場合は、仮釈放が取り消されてしまいます。たとえば、仮釈放中に暴行事件を起こし、暴行罪に問われて罰金刑が確定したとしましょう。
この場合、暴行罪に対する罰金刑に加え、仮釈放によって保護観察に付されていた期間と刑期の残期間は刑務所に戻らなければいけません。また、基本的にその後に改めて仮釈放が認められる可能性はゼロに近いでしょう。
たとえば、懲役10年の刑罰が確定した受刑者が7年服役した後に仮釈放が認められたとします。この場合、残期間は3年間です。仮に、2年間何事もなく過ごし、その後に罰金刑が確定したとしましょう。
上記例の場合は、仮釈放中であった2年間は刑期に参入されないため、改めて3年間刑務所に収監されることになります。
保釈前に犯した罪で罰金刑以上の刑罰が科された場合
保釈前に犯した罪で罰金刑以上の刑罰が科された場合も、保釈が取り消されてしまいます。たとえば、仮釈放となった犯罪を犯す前に何らかの犯罪を犯し、バレることなくやり過ごしていたとしましょう。
その後、仮釈放が確定してからこれまで発覚していなかった事件が発覚するケースもあります。この場合、この事件についても裁判が開かれることとなります。そして、最終的に罰金刑が下された場合は、仮釈放が取り消されてしまうのです。
遵守事項を守らなかったとき
仮釈放中は保護観察に付されます。保護観察中は、一般遵守事項と特別遵守事項を守らなければいけません。もし、それぞれの遵守事項を破った場合は、仮釈放が取り消されてしまうため注意しましょう。
一般遵守事項はすべての仮釈放者を対象に定められています。特別遵守事項は、各仮釈放者を対象に定められています。いずれの遵守事項もかならず守らなければいけません。
仮釈放の条件でよくある質問
仮釈放の条件でよくある質問を紹介します。
Q.無期懲役刑でも仮釈放になることはありますか?
A.無期懲役刑で仮釈放となる可能性があります。
無期懲役は、期間の定めがない懲役刑です。捉え方によっては、「数年で出所できる」とも考えられますし、「一生刑務所から出られない」といった考え方もできます。
刑法では、無期懲役囚は10年以上服役した場合に仮釈放を認めることが可能であると定められています。しかし、期間の定めがない無期懲役という刑罰は、本来は有期懲役よりも重い刑罰です。
このことを考慮すると、有期懲役以上の刑罰を科した後に仮釈放するべきであると考えられています。有期懲役の上限が30年であるため、実務上は30年以上服役しなければ、仮釈放は認められないケースがほとんどです。
また、無期懲役は日本の刑罰では死刑に次いで重い刑罰です。このことを考慮すると、簡単に仮釈放を認めるべきではありません。そのため、無期懲役囚が実際に仮釈放が認められるのは、相当厳しいのが現実です。
無期懲役として服役している人の多くは生命犯(人の命を奪っている)であることも考慮され、現実的に仮釈放が認められるのは相当厳しいでしょう。
Q.仮釈放と満期釈放の違いは何ですか?
A.刑期を満了しているかどうかです。
仮釈放は刑期が満了する前に釈放することを指します。一方で、満期釈放は刑期を満了してから保釈することを指します。
たとえば、懲役10年の刑罰を受けた人が7年〜8年で釈放される場合は、仮釈放と言います。一方で10年経過して出所する場合は、満期釈放と言います。
Q.日本で仮釈放なしの終身刑のような刑罰はないのですか?
A.日本で仮釈放なしの終身刑はありません。
そもそも、海外に目を向けると「終身刑」という刑罰がありますが、日本における刑罰「無期懲役」と同じです。つまり、海外における終身刑でも仮釈放が認められるケースがあります。
「終身刑=仮釈放は認められない」と考えている人も多いですが、実際には仮釈放が認められるケースがあります。しかし中には、「仮釈放なしの終身刑」が言い渡される国もあります。
日本では「仮釈放なしの無期懲役」というものはありません。しかし、死刑相当の罪を犯していながら無期懲役に減刑された人が仮釈放を認められるケースはほとんどありません。そのため、実務的に「仮釈放なしの無期懲役」となるケースもあります。
なお、無期懲役でも仮釈放を認めているのは、受刑者に希望を持たせることによって更生意欲を向上させることを目的としています。たとえば、無期懲役で仮釈放が絶対に認められないことがわかっていれば、「どうせ出られない」と考え、刑務所内での素行等にも影響を与える可能性があるためです。
Q.仮釈放は保釈金等のような金銭を支払う必要があるのですか?
A.金銭を支払う必要はありません。
仮釈放と保釈はまったく異なります。仮釈放が認められる人は、刑務所内でしっかりと反省し、再犯を犯さないことなどが条件です。また、「逃げる」という概念がないため、そもそも金銭等を預かる必要がありません。
刑務所に収監されている人の多くは「2度と戻ってきたくない」と考えています。残刑期を何事もなく過ごせれば、自由の身となれるため、犯罪を犯したり保護観察官等との面談に参加しなかったりする可能性は低いです。
Q.どのような犯罪でも仮釈放は認められるのですか?
A.基本的には認められます。
仮釈放は、犯罪の種類に関わらず一定以上の刑期が経過した場合やその他条件を満たした場合に検討されます。死刑ではない限り、仮釈放の可能性があります。
まとめ
今回は、仮釈放の条件について解説しました。
仮釈放は、有期懲役であれば刑期の1/3以上経過した時点、無期懲役であれば10年以上経過した時点で認められる可能性があります。しかし実務上は、有期懲役で刑期の7割〜8割以上、無期懲役で30年以上経過しなければ認められません。
また、仮釈放が認められるための条件も非常に厳しく、とくに無期懲役で服役している人は仮釈放が叶わずに獄中死する人が大半です。仮に仮釈放が認められたとしても、老人となっていて1人で生活できない人も多いです。
仮釈放は、受刑者に対して希望を持たせ更生意欲を向上させるためにある制度です。しかし、現実的には厳しい条件をクリアする必要があり、相当厳しいものであることを覚えておきましょう。