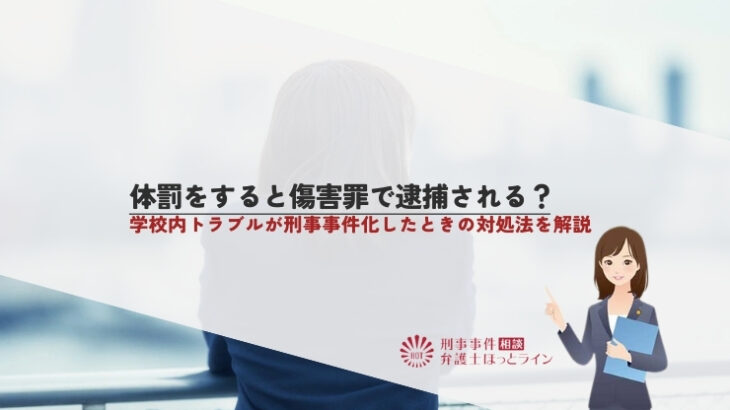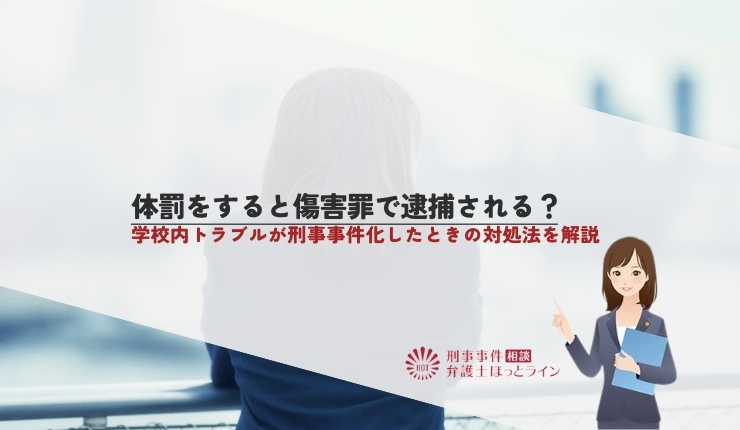
「昔の学校現場では多少の暴力は許されていた」「教育のためにある程度の体罰はおこなうべき」などと主張されることもありますが、体罰は学校教育法で禁止されている違法行為です。
そして、生徒や児童に対して有形力を行使した場合、傷害罪などの容疑で刑事事件化する可能性もゼロではありません。
たとえば、生徒が負った怪我や後遺症が重篤なケースや、教職員側が犯行を否認するケースなどでは、逮捕・勾留によって長期間身柄拘束される危険性があります。また、事案の内容次第では、初犯でも有罪判決が下されかねません。「学校内で起きたことだから話し合いをすれば穏便に解決するだろう」と油断をしていると、重い刑事責任を強いられて、今後の社会復帰が困難になってしまうでしょう。
そこで、この記事では、体罰が原因でトラブルになった教職員の方や、学校での体罰問題が原因でご家族が逮捕されてしまった方のために、以下の事項についてわかりやすく解説します。
- 体罰の定義
- 体罰に対して適用される罪状
- 体罰が原因で逮捕されたときの刑事手続きの流れ
- 体罰が刑事事件化したときに生じるデメリット
- 体罰トラブルが大きくなったときに弁護士に相談するメリット
目次
体罰は傷害罪に該当するのか?
まずは、体罰の定義や傷害罪への該当性などの基本事項について解説します。
そもそも体罰とは
体罰に関する文部科学省の考え方を整理しましょう。
学校教育法では体罰を全面的に禁止している
まず、学校教育法では、体罰について以下の規定を置いています。
引用:学校教育法|e-Gov法令検索
ここでは、「懲戒」と「体罰」が区分されており、教育上の必要性が認められるケースでは懲戒を加えることが可能とされる一方で、体罰を加えることについては明確に禁止されています。
ただし、懲罰と体罰の違い、体罰の定義については明示されていない点に注意が必要です。
また、体罰は学校教育法で禁止されている行為ではあるものの、体罰を理由に刑事罰が科されることはありません。体罰に及んで刑事罰を課されるのは、体罰が刑法が規定する傷害罪などに該当すると判断されたときだけです。
文部科学省が考える体罰への該当性と具体例
そこで、文部科学省は、教員などが児童生徒に対しておこなった行為が体罰に該当するかどうかは、児童生徒の年齢、健康、心身の発達状況、当該行為がおこなわれた場所的環境・時間的環境、行為態様の諸条件を総合的に考慮したうえで、客観的に判断するべきだという指針を出しています(体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知)|文部科学省)。
たとえば、個別具体的な状況次第ですが、以下のような行為が懲戒・体罰に該当すると考えられます。
| 体罰に該当する可能性が高い | ・体育の授業中、危険な行為をした児童の背中を足で踏みつける ・帰りの会で足をぶらぶらさせて座り、前の席の児童に足を当てた児童を、突き飛ばして転倒させる ・授業態度について指導したが反抗的な言動をした複数の生徒らの頬を平手打ちする ・立ち歩きの多い生徒を叱ったが聞かず、席につかないため、頬をつねって席につかせる ・生徒指導に応じず、下校しようとしている生徒の腕を引いたところ、生徒が腕を振り払ったため、当該生徒の頭を平手で叩く ・給食の時間、ふざけていた生徒に対し、口頭で注意したが聞かなかったため、持っていたボールペンを投げつけ、生徒に当てる ・部活動顧問の指示に従わず、ユニフォームの片づけが不十分であったため、当該生徒の頬を殴打する ・放課後に児童を教室に残留させ、児童がトイレに行きたいと訴えたが、一切、室外に出ることを許さない ・別室指導のため、給食の時間を含めて生徒を長く別室に留め置き、一切室外に出ることを許さない ・宿題を忘れた児童に対して、教室の後方で正座で授業を受けるよう言い、児童が苦痛を訴えたが、そのままの姿勢を保持させた など |
|---|---|
| 懲戒に該当する可能性が高い行為 | ・放課後等に教室に残留させる ・授業中、教室内に起立させる ・学習課題や清掃活動を課す ・学校当番を多く割り当てる ・立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる ・練習に遅刻した生徒を試合に出さずに見学させる など |
正当防衛や正当業務行為に該当すれば体罰による法的責任を問われない
教職員が暴力などをふるったとしても、正当防衛や正当業務行為を理由に違法性が阻却されるケースが存在します。
というのも、児童や生徒が暴力行為などに及んだケースでは、ほかの児童や生徒が安全に学習できる環境を確保するため、また、教職員自身の安全を守るために、一定の対抗行為をする必要があるからです。
そのため、児童や生徒から教員などに対して暴力行為がおこなわれたケースにおいて、教員等がやむを得ず有形力を行使した結果、身体への侵害や肉体的苦痛を与えたとしても、体罰には該当しないと判断されます。また、他の児童や生徒に対して被害を及ぼすような暴力行為を制止するなどのためにやむを得ず有形力を行使した場合にも、体罰への該当性は否定されます。
正当防衛や正当業務行為への該当性が肯定されるケースとして、以下のものが挙げられます。
- 児童が教員の指導に反抗して教員の足を蹴ったため、児童の背後に回り、体をきつく押さえる
- 休み時間に廊下で、他の児童を押さえつけて殴るという行為に及んだ児童がいたため、この児童の両肩をつかんで引き離す
- 全校集会中に、大声を出して集会を妨げる行為があった生徒を冷静にさせ、別の場所で指導するため、別の場所に移るよう指導したが、なおも大声を出し続けて抵抗したため、生徒の腕を手で引っ張って移動させる
- 他の生徒をからかっていた生徒を指導しようとしたところ、当該生徒が教員に暴言を吐きつばを吐いて逃げ出そうとしたため、生徒が落ち着くまでの数分間、肩を両手でつかんで壁へ押しつけ、制止させる
- 試合中に相手チームの選手とトラブルになり、殴りかかろうとする生徒を、押さえつけて制止させる など
傷害罪とは
傷害罪とは、人の身体を傷害したときに成立する犯罪類型のことです。
傷害の定義
傷害罪における「傷害」とは、生活機能の毀損、健康状態の不良変更を意味すると理解するのが判例です。傷害の程度は問題にされず、極めて軽微な障害であったとしても、傷害結果が発生した以上、傷害罪が成立すると判断されます。
たとえば、教職員が生徒を突き飛ばしてすり傷を負わせてしまったような事案でも、傷害罪は成立します。
傷害罪の故意
教職員が体罰をおこなう場合、児童や生徒を怪我をさせることを想定していないケースも少なくはないでしょう。
しかし、傷害罪は、傷害の故意がある場合だけではなく、暴行の故意はあるものの傷害する故意まではない場合(暴行の結果的加重犯)も含むと理解するのが一般的です。
ですから、児童や生徒に対して暴行する故意があり、その結果、児童・生徒に傷害結果が生じた場合には、傷害の故意がなかったとしても、傷害罪が成立します。
傷害罪の法定刑
傷害罪の法定刑は、15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑と定められています。幅広い法定刑が定められているのは、傷害行為の悪質性や傷害結果の程度などの個別事情を刑罰に反映させるためです。
執行猶予付き判決を獲得するには、「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の言渡しを受けたとき」という要件を満たさなければいけません。つまり、傷害罪の容疑で起訴されたときには、初犯でも実刑判決が下されるリスクがあるということです。
ですから、体罰について傷害罪の容疑で立件されて起訴されたときには、できるだけ早いタイミングで刑事事件が得意な弁護士に相談・依頼をして、罰金刑や執行猶予付き判決獲得を目指した防御活動を展開してもらうべきだと考えられます。
体罰は傷害罪に該当するのが原則だが立件されるかは事案による
ほとんどの体罰が刑法に規定される傷害罪などの構成要件を満たすため、刑事責任を問われかねない状況に追い込まれます。
ところが、教師が生徒に対して体罰をおこなった事案の多くが立件されずに済まされるのが実情です。
というのも、体罰が問題になるシチュエーションでは、教師が体罰に及ばざるを得なかった経緯や教育的理由などの個別事情が深く考慮されるからです。いきなり警察が介入するのではなく、学校や保護者、生徒などの当事者間で体罰事件に対する意見などが交わされて、内部的な解決を目指すという方針がとられる傾向にあります。
とはいえ、体罰は学校教育法で禁止される違法行為であることを踏まえると、児童や生徒側に深刻な被害が生じたようなケースや、教育的理由が見受けられない単なる暴行行為としか評価されないようなケースでは、傷害罪などの容疑で立件されるリスクがあると理解しておきましょう。
体罰で問われる可能性がある傷害罪以外の犯罪類型
教師が生徒や児童に対して体罰をしたケースでは、傷害罪以外にも、以下の罪状に問われる可能性があります。
| 犯罪類型 | 法定刑 | 具体例 |
|---|---|---|
| 暴行罪 | 2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料 | 生徒の頬を叩いたが、生徒に怪我はなかった |
| 傷害致死罪 | 3年以上の有期拘禁刑 | 生徒を投げ飛ばすなどして怪我を負わせた結果、当たりどころが悪くて死亡してしまった |
| 殺人未遂罪 | 死刑または無期もしくは五年以上の拘禁刑 | 無抵抗な生徒の腹や頭を何度も殴りつけた |
| 強要罪 | 3年以下の拘禁刑 | 不必要なまで長時間土下座・起立をさせた |
| 監禁罪 | 3ヵ月以上7年以下の拘禁刑 | 倉庫や使われていない教室などに長時間生徒を閉じ込めた |
体罰をして傷害罪の容疑をかけられたときの刑事手続きの流れ
体罰が原因で傷害罪の容疑をかけられたときの刑事手続きの流れについて解説します。
- 警察から任意の事情聴取を受ける
- 警察に逮捕される
- 身柄拘束付きの取調べを受ける
- 検察官が起訴・不起訴を決定する
- 公開の刑事裁判にかけられる
警察から任意の事情聴取を受ける
体罰が傷害事件として立件された場合、最初は警察から任意の事情聴取を受けることが多いです。
警察から出頭要請を受けた日時に警察署に出頭をして、体罰事件について数時間程度の取り調べを受けたらそのまま帰宅できます。事情聴取の日時を調整したり、取り調べを途中で切り上げたりすることも可能です。強制的に身柄拘束されることはありませんし、家族や勤務先との連絡が禁止されることもないです。
警察が体罰を立件するきっかけ
近年、体罰に対する社会的関心が高まっています。体罰の被害を受けた生徒やその関係者がSNSや匿名掲示板などで被害を告発し、炎上した結果、警察が捜査活動をスタートするというケースが少なくありません。
また、体罰被害を受けた生徒が直接警察に相談して捜査機関が体罰事件を認知するというケースも多いです。さらに、体罰事件が学校内や教育委員会などで問題になった結果、警察に相談されるというケースも想定されます。
任意の事情聴取を拒否すると逮捕される可能性がある
体罰について警察から任意の出頭要請を受けたにもかかわらず、警察からの連絡を無視したり、事情聴取で供述を拒否したりすると、逮捕される危険性があります。
というのも、任意の事情聴取へ誠実に対応する姿勢を見せなければ、逃亡または証拠隠滅のおそれがあると判断されかねないからです。
ですから、体罰について警察から事情聴取の要請があったときには、できるだけ誠実に対応するべきだと考えられます。もちろん、体罰事件の内容次第なので、認否や供述内容については、事前に弁護士に相談するのがおすすめです。
警察に逮捕される
以下の要件を満たすケースでは、体罰事件を起こした教職員は警察に逮捕されます。
- 逮捕の理由:被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること
- 逮捕の必要性:逃亡または証拠隠滅のおそれがあること
学校内で起きた出来事であったとしても、客観的証拠があるにもかかわらず教職員が体罰に及んだ事実自体を否認したり、事情聴取で黙秘を貫いたりしつづけると、逮捕される可能性があると理解しておきましょう。
捜査機関から取り調べを受ける
体罰事件について傷害罪などの容疑をかけられたときには、捜査機関から取り調べを受けます。
傷害罪などの容疑で逮捕された場合、まずは、警察段階の取り調べが実施されます。警察段階の取り調べには48時間以内の制限時間が設けられています。
次に、警察段階の取り調べが終了すると、体罰事件が検察官に送致されて、検察官が取り調べをおこないます。
検察段階の取り調べの制限時間は原則として24時間以内です。警察段階の48時間以内と検察段階の24時間以内、合計72時間以内に得られた証拠などを前提として、検察官が体罰事件を起訴するかどうかを判断します。
ただし、以下のような事情がある場合には、検察官が勾留請求をおこなう可能性があります。
- 体罰の被害を受けた生徒が入院や精神的な疾患を患っており、参考人聴取に時間を要する場合
- 体罰に至った経緯などを目撃した関係者の数が多く、参考人聴取に時間を要する場合
- ほかにも体罰被害を訴えている生徒が複数存在し、事情や経緯を確認するのに時間を要する場合
- 体罰に及んだ教職員が犯行を否認しているなど、入念に取り調べを進める必要がある場合 など
検察官の勾留請求が認められた場合、原則として10日以内の範囲で、再勾留が認められるとさらに10日間以内の範囲で、被疑者の身柄拘束期間は延長されます。
ですから、体罰に対して傷害罪などの容疑がかけられて、逮捕・勾留された場合には、検察官が公訴提起の判断を下すまでに最長23日間の身柄拘束期間が生じると考えられます。
検察官が起訴・不起訴を決定する
逮捕・勾留期限が到来するまでに、検察官が体罰事件を起こした被疑者を公訴提起するかどうか(起訴か不起訴か)を決定します。
起訴処分とは、体罰事件を公開の刑事裁判にかける旨の判断のことです。これに対して、不起訴処分とは、体罰事件を刑事裁判にかけずに検察段階で刑事手続きを終了させる旨の判断を意味します。
日本の刑事裁判の有罪率は極めて高いので、刑事裁判にかけられた時点で実質的に有罪になることがほぼ確定します。
ですから、「有罪になりたくない」「前科がつくと困る」という人は、刑事裁判で無罪判決獲得を目指すのではなく、検察官から不起訴処分の判断を引き出すための防御活動を展開するべきでしょう。
公開の刑事裁判にかけられる
体罰事件を起こして起訴された場合、公開の刑事裁判の審理を受けなければいけません。
刑事裁判が開廷されるタイミングは、検察官の起訴処分から1ヶ月〜2ヶ月後が目安です。公訴事実を争わなければ第1回公判期日で結審しますが、公訴事実を争う場合には複数の公判期日をかけて証拠調べなどがおこなわれます。
傷害罪の法定刑は「15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑」なので、生徒や児童に生じた傷害・後遺症の程度や行為態様の悪質性などの個別事情次第では、初犯でも実刑判決が下されかねません。
刑務所への服役を強いられると出所後の社会復帰が難しくなるので、実刑回避を目指した防御活動に専念してください。
体罰事件を起こして傷害罪で立件されたときのデメリット4つ
体罰事件を起こして傷害罪で立件されたときに生じる4つのデメリットについて解説します。
- 実名報道のリスクに晒される
- 免職などの処分を下される可能性が高い
- 逮捕・勾留によって一定期間身柄拘束される可能性がある
- 前科によるデメリットに晒されつづける
実名報道される危険性がある
体罰に対して傷害罪などの容疑で立件されると、実名報道される危険性があります。
報道機関がどの刑事事件を実名報道するかについて明確な基準は公表されていません。
しかし、体罰事件は世間の関心が高いトピックである実情を踏まえると、体罰が原因で逮捕・起訴されたケースでは、実名報道のリスクを覚悟しなければいけません。
そして、一度でもテレビの報道番組やネットニュースで実名報道されると、半永久的に体罰事件を起こした事実がインターネットなどで検索可能な状況に追い込まれてしまいます。転職や結婚などに支障が生じるだけではなく、家族などにも迷惑がかかる可能性が高いです。
教師を免職されるなどの処分を下されかねない
教職員が体罰に及ぶと、職務上の非行を理由に懲戒処分が下される可能性が高いです。
懲戒処分は、免職・停職・減給・戒告に分類されます。非違行為の態様・被害の大きさ・職責の重さ・過失の大きさ・職務への影響・常習性などの諸般の事情を総合的に考慮したうえで、処分の内容が決定されます。
たとえば、東京都教育委員会は、教職員が体罰に及んだときの処分内容について以下の目安を公表しています。
| 具体的なケース | 処分の内容 |
|---|---|
| ・体罰により児童・生徒を死亡させた場合 ・体罰により児童・生徒に重篤な後遺症を負わせた場合 ・極めて悪質または危険な体罰を繰り返したケースで、欠席や不登校など、児童・生徒の苦痛の程度が重い場合 |
免職 |
| ・常習的に体罰をおこなった場合 ・ 悪質または危険な体罰をおこなった場合 ・ 体罰により傷害を負わせた場合 ・ 体罰の隠ぺい行為をした場合 |
停職・減給 |
| ・体罰をおこなった場合 | 戒告 |
| ・暴言または威嚇をおこなったケースで、欠席や不登校など、児童や生徒の苦痛の程度が重い場合 ・常習的に暴言または威嚇を繰り返した場合 ・暴言または威嚇の内容が悪質である場合 ・暴言または威嚇の隠蔽行為をおこなった場合 |
停職・減給・戒告 |
逮捕・勾留によって一定期間身柄拘束される
体罰事件を起こして逮捕・勾留される事態におちいると、一定期間捜査機関に強制的に身柄を拘束されます。逮捕されただけなら72時間以内、万期まで勾留されると23日間の身柄拘束期間が生じます。
身柄拘束をされている期間中は、厳しい留置場生活を強いられます。帰宅や出勤は一切許されませんし、スマートフォンなどの所持品が取り上げられるので外部と連絡をとるのも不可能です。
前科がつく可能性がある
体罰事件を起こして傷害罪で有罪になると、刑事罰を科されるだけではなく、前科のデメリットも強いられます。
前科とは、有罪判決を下された経歴のことです。拘禁刑だけではなく、執行猶予付き判決や罰金刑を下された場合にも、前科と扱われます。
前科がつくと、今後の社会生活に以下のデメリットが生じます。
- 履歴書の賞罰欄への記載義務、採用面接で質問されたときの回答義務が課されるので、転職活動の難易度が高くなる
- 前科の事実を隠して内定を獲得しても、前科があることがバレると、経歴詐称を理由に内定取り消しや懲戒解雇処分を下される
- 前科を理由に就業が制限される職業・資格がある
- 前科が原因でビザ・パスポートの発給が制限されると、海外旅行や海外出張に支障が生じる
- 前科がある状態で再犯に及ぶと、刑事処分が重くなる可能性が高い など
体罰事件を起こしたときに弁護士に相談・依頼するメリット3つ
体罰が問題になったときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼をしてください。
刑事事件への対応が得意な弁護士の力を借りることで、以下3つのメリットを得られるでしょう。
- 被害者との間で示談交渉を進めてくれる
- 勤務先とのやり取りへのアドバイスを期待できる
- 刑事手続きを有利に進めてくれる
被害者生徒とすぐに示談交渉を進めてくれる
体罰が問題になったケースでは、できるだけ早いタイミングで被害者との間で示談交渉を進める必要があります。
示談とは、刑事事件の被害者と加害者との間で直接民事的な解決方法について話し合いを進めることです。当事者双方が示談条件に合意をした場合には、和解契約(示談契約)が締結されます。
被害生徒との間で示談が成立すれば、刑事手続きにおいて、以下のメリットを得られます。
- 刑事告訴される前に示談が成立すれば、刑事事件化することなく体罰事件を民事的に解決できる
- 体罰事件について警察の捜査活動が開始されたとしても、示談成立によって被害届や告訴状を取り下げてもらえる
- 検察官の公訴提起判断までに示談が成立すれば、不起訴処分獲得の可能性が高まる
- 検察官の公訴定期判断までに示談が間に合わなかったとしても、判決が下されるまでに示談を成立させることで、実刑判決を回避しやすくなる
ここで注意を要するのが、示談交渉は加害者本人や加害者家族がおこなうことも可能ですが、弁護士に代理してもらったほうがスムーズに進む可能性が高いという点です。
というのも、被害生徒やその家族は体罰に及んだ教職員や学校側に対して怒りや不安、疑念を抱いており、冷静に建設的な話し合いを進めるのが難しいことが多いからです。
ですから、スピーディーに被害生徒側と話し合いをおこなって刑事手続きを少しでも有利に進めたいのなら、できるだけ早いタイミングで刑事事件への対応が得意な弁護士に依頼することを強くおすすめします。
勤務先への対応方法についてアドバイスを期待できる
体罰事件が起きると、学校側も事情を把握するためにさまざまな調査活動をおこないます。
その際には、体罰に及んだ教職員に対する聞き取り調査も実施されて、調査内容を踏まえたうえで、懲戒処分を下すかどうかや、どのような懲戒処分を下すかなどが決定されます。
弁護士に相談すれば学校側に対する説明内容などのポイントを整理してくれたり、状況次第では、学校側が実施する聞き取り調査に立ち会ってくれたりするでしょう。
体罰事件の刑事手続きを有利に進めてくれる
体罰がきっかけで捜査機関からの追及を受ける事態に追い込まれた場合、弁護士に相談・依頼をすれば、以下の防御目標を掲げて、刑事手続きの状況に応じて適切な防御活動を展開してくれるでしょう。
- 逮捕による身柄拘束を阻止して在宅事件として処理されるように、捜査活動への対応方法についてアドバイスをくれる
- 逮捕されたとしても、勾留阻止活動に力を入れて、身柄拘束期間の短縮化を目指してくれる
- 早期に示談を成立させたり酌量するべき証拠を収集したりすることで、検察官から起訴猶予処分の判断を引き出してくれる
- 執行猶予付き判決に役立つ証拠を刑事裁判に提出して、実刑回避に向けた防御活動を展開してくれる
体罰事件を起こして傷害事件に発展したときはすぐに弁護士へ相談しよう
生徒や児童に対して体罰に及んでしまった場合には、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼するのがポイントです。
弁護士に相談・依頼をすれば、被害者との示談交渉だけではなく、刑事手続きや学校側への対応も期待できるでしょう。
刑事事件相談弁護士ほっとラインでは、体罰事件などの刑事事件への対応が得意な弁護士を多数紹介中です。弁護士に相談するタイミングが早いほど有利な状況を作り出しやすいので、体罰が問題になりそうなときには速やかに信頼できる弁護士までお問い合わせください。