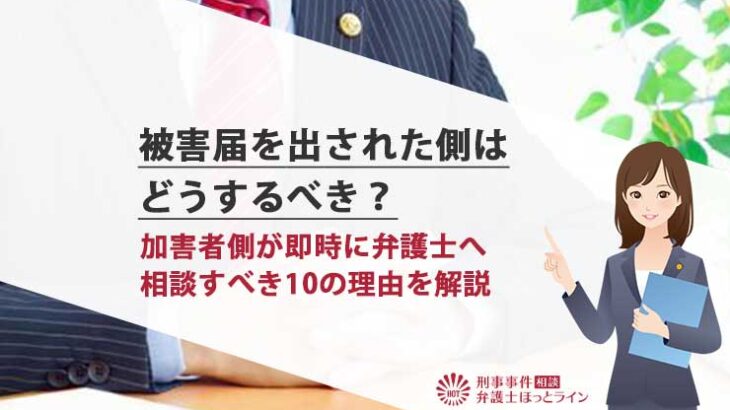被害届を出されたときには可能な限りすみやかに弁護士まで相談することをおすすめします。
なぜなら、被害届の受理によって警察が本格的な捜査活動へと着手する可能性が高いからです。捜査活動によって犯罪行為の証拠が明らかになれば、逮捕・勾留によって長期間身柄拘束されるだけではなく、実刑判決が言い渡されるなどの刑事責任が確定することになりかねません。
そこで今回は、被害届が受理されて警察から出頭要請がかかった方や、「過去の犯罪行為について被害届が提出されるのではないか」と不安を抱えている方のために、以下5点について分かりやすく解説します。
- 被害届の法的性質や告訴・告発との違い
- 被害届が出された後の刑事手続きの流れ
- 被害届が出されたまま放置すると生じるデメリット
- 被害届が出されたときに弁護士へ相談するメリット
- 被害届を提出させずに刑事事件化自体を回避するコツ
被害届の提出・受理は加害者にとって秘密裡に行われるので、気付いたときには捜査活動が相当進んでいるケースも少なくありません。
ただ、警察から連絡がくる前に加害者側が率先して弁護士を選任し、示談交渉等の適切な防御活動をスタートするだけで、刑事処分を軽減したり、刑事事件化自体を回避できたりする可能性が高まります。
「被害届が出されたか分からないのに弁護士に相談するメリットを感じられない」「警察から連絡がくる前に犯罪の相談なんてしたくない」という考えは捨てて、刑事事件や示談交渉を専門に取り扱っている弁護士までご相談ください。
目次
被害届とは
警察等の捜査機関が犯罪行為を認知してはじめて捜査活動は開始されます。
そして、「被害届」は捜査機関が犯罪行為を知る重要なきっかけになるものです。
まずは、告訴・告発との違いなどに注目しつつ、被害届がどのような役割を担うのかについて解説します。
被害届の内容や提出時の手続きの流れ
被害届とは、「犯罪行為によって被害が生じた旨を警察に申告するための届出」のことです。
たとえば、財布をスられたのに気付いて犯人を追いかけたが逃げられた場合、「いつ、どこで、どのような状況で、何を盗まれたのか」など、被害届には「窃盗被害にあったときの状況」を克明に記載します。そして、警察に被害届を提出し、被害届が受理された場合、当該窃盗事件に関する捜査活動がスタートするという流れです。
なお、後述するように、告訴・告発は、「犯罪事実の申告」という報告行為と「訴追を求める」という請求行為との複合的な訴訟行為である点で特徴的です。被害届は「犯罪事実の申告」しか行わなわず「訴追を求める」という請求行為は存在しないため、被害届と告訴状はまったく別物と言えるでしょう。
被害届の提出方法とは?
捜査機関に犯罪被害を申告する方法は以下4種類に大別されます(犯罪捜査規範第61条第1項、第2項)。
- 被害者本人が被害届を自筆して警察署に持参する方法
- 警察署に出頭して、警察官の面前で被害者本人が被害届を自分で記入する方法
- 警察署に出頭して、被害申告の内容を聞き取った警察官が被害者本人の面前で代筆する方法
- 警察署に出頭して、被害申告の内容を聞き取った警察官が被害届の代わりに参考人供述調書を作成する方法
被害届のテンプレートは公開されているので「別記様式第6号(犯罪捜査規範第61条)」からプリントアウトして必要事項を記入できます。
ただし、犯罪被害に遭って冷静さを失っている状況で、被害者本人自身が雛形を用意し、事件について反駁しながら書類に諸々記載する(①)のは簡単な作業ではありません。
そのため、犯罪行為の被害が発生した場合には、「『被害者が警察署を訪問』→『犯罪事実について口頭で相談』→『被害者の話を聞きながら捜査員が”被害届”を代筆するか(③)、明らかに深刻な犯罪被害を受けていると認められる場合には”参考人供述調書”を作成(④)』」という経過をたどるのが一般的です。
被害届の記載内容とは?
被害届の記載事項は以下の通りです(犯罪捜査規範第61条、別記様式第6号)。
- 被害届の提出日
- 被害届の届出人の住所・氏名・電話番号
- 被害者の住居・職業・氏名・年齢
- 被害の年月日時
- 被害の場所
- 被害の模様
- 被害金品(品名・数量・時価・特徴・所有者)
- 犯人の住居・氏名・通称・人相・着衣・特徴など
- 遺留品その他参考となるべき事項
被害届は誰でも提出できる?
被害届の提出権者は「犯罪の被害を受けた本人」が原則です。
ただし、被害届の提出権者に関して明確な法的根拠があるわけではないので、事件の態様・被害状況次第では、警察側の判断で「被害者以外の第三者」による被害届の提出でも受理される場合があります。
実際、被害届のテンプレートには「届出人と被害者が異なるときは、『届出人と被害者との関係性』、及び、『本人届出の理由』を被害届の備考欄にする」旨の注意書きが記載されており、被害者本人以外でも被害届を提出できることが前提とされているでしょう。
なお、犯罪被害者が未成年者の場合には法定代理人である親権者等、犯罪被害者が成年後見人の場合には後見人の付き添いや代筆が求められることもあります。
被害届はどこに提出する?
被害届は、最寄りの派出所や交番、警察署などに提出します。
また、管轄区域の事件であるか否かにかかわらず、どこの警察に提出しても受理対応等をしてもらえるでしょう。
被害届が受理されない可能性はある?
警察は被害届を絶対に受理するわけではありません。なぜなら、捜査機関に対して「被害届の受理義務」が課されているわけではないからです。
つまり、犯罪被害者が自宅で被害届を入念に作成したとしても、被害者から事件の詳細を聞き取って「刑事手続きを進めるほどの事件ではない」「被害者が困っているのは間違いないが犯罪を構成するわけではない」と判断したケースでは、担当捜査員の判断限りで被害届が受理されない場合もあり得るということです。
被害届が受理されるとかならず捜査活動が実施される?
被害届が受理されたからといってかならず入念な捜査活動が実施されるわけではありません。なぜなら、捜査機関に対して「被害届を端緒とする捜査義務」が課されているわけではないからです。
たとえば、万引き事件に関して被害店舗が被害届を提出して受理されたとしても、被害額が少額だったり、防犯カメラ映像がないなどの理由で犯人の身元特定が相当困難だったりすると、警察が捜査員を動員せずに捜査活動が自然消滅する可能性もゼロではありません。
さらに、仮に捜査活動がある程度展開されたとしても、当該捜査活動がどのような経過を辿り、どのような結論に至ったのかが通知されない場合も多いです。なぜなら、被害届が提出されたとしても、捜査機関には「処分結果を通知する義務」が課されていないからです。
被害届が出されたか確認できる?
犯罪加害者にとって最大の関心事のひとつは、「自分が起こした犯罪行為について被害届が提出された場合にその事実を確認できる手段はあるのか」という点でしょう。被害届が提出されることは警察に犯罪がバレることを意味するため、気になるのは当然です。
しかし、「被害届が受理されました」と加害者に対して連絡が来ることはありません。警察から接触があるときは、任意の事情聴取の要請がかけられるか、通常逮捕手続きに移行して逮捕状の発付を受けた捜査員が自宅にやってくるかの二択です。もちろん、任意の出頭要請や逮捕手続きが開始してから防御活動をスタートするのも間違いではありませんが、逮捕リスクが生じると社会生活に甚大な悪影響が生じる点を看過するべきではありません。
したがって、被害届が提出されたか否かを確認するには、「加害者自ら弁護士を選任して、警察から連絡がくるか否かにかかわらずできるだけ早いタイミングに犯罪被害者側と接触機会をもち、示談交渉をスタートする」ことしか方法は残されていないと考えられます。運よく被害届提出前に被害者と接触できれば刑事事件化自体を回避できますし、被害届受理済みでも示談成立によって被害届の取り下げを期待できるでしょう。
被害届に提出期限はある?
被害届には提出期限が設けられていません。
つまり、被害届は、犯罪被害者が「警察に相談したい」と思ったタイミングで提出されるものなので、犯罪行為からかなりの時間が経過した後でも、犯罪加害者は刑事訴追されるリスクを抱えるということです。
ただし、検察官の公訴権には「公訴時効」という期間制限が設けられている点に注意が必要です。つまり、犯罪ごと(法定刑ごと)に規定されている公訴時効期間が経過すれば刑事責任を問われることがなくなるので、犯罪行為から一定期間が経過することによって被害届が受理されなくなる(被害届が受理されても捜査手続きが進められない)ということです。
とはいえ、犯罪行為に及んでから公訴時効期間が経過するまで常に「被害届を出されるのではないか」と不安を抱え続けるのはストレスが溜まるものでしょう。また、いきなり数年前の犯罪行為を理由に逮捕されるとなると、犯罪行為の後で築いた社会的なキャリアや人生プランが簡単に崩れ去ってしまいかねません。
したがって、「公訴時効完成による逃げ切り」を目指すのが適切ではない状況なら、刑事事件に強い弁護士に相談をしたうえで、警察に被害届を提出する前に被害者と直接接触をして、民事的解決を目指すのが適切だと考えられます。
被害届と告訴・告発との違い
被害届と似たものに「告訴」「告発」と呼ばれるものがあります。
いずれも、捜査機関に対して犯罪事実を申告してその刑事訴追を求める意思表示であり「捜査の端緒」になるものですが、刑事手続き上、役割や効力に明確な違いが設けられている点に注意が必要です。
告訴とは
告訴とは、「犯罪の被害者等の告訴権者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その訴追を求める意思表示」のことです(刑事訴訟法第230条)。
告訴の流れ
告訴は、書面または口頭で、検察官または司法警察員に対して行われます(刑事訴訟法第241条第1項)。書面による場合には「告訴状」と呼ばれる書類が利用されます。また、告訴が口頭の方法で行われた場合には、警察官または検察官がかならず参考人供述調書を作成します(同法第241条第2項)。
司法警察員が告訴を受けたときには、すみやかに犯罪事実に関係する書類・証拠物が検察官に送付されます(同法第242条)。
そして、検察官は、告訴の事件について起訴・不起訴の処分をしたときには、遅滞なくその旨を告訴人に通知しなければいけません(同法第260条)。検察官が告訴のあった事件について不起訴処分を下した場合、告訴人から請求があったときには、不起訴処分を下した理由を告げる必要があります(同法第261条)。
なお、被害者等が告訴状を提出した場合でも、検察官が公訴提起する前までなら、「告訴の取消し」が可能です(同法第237条第1項)。したがって、犯罪行為に及んで告訴状が提出されてしまった場合には、検察官の公訴提起判断までに示談をまとめて告訴の取消しを引き出すことができれば、不起訴処分獲得の可能性が高まると言えるでしょう。
告訴権者
告訴は誰でもできるわけではなく、以下のように、法律上「告訴権」が与えられた人物だけに許された訴訟行為です。
- 被害者本人(刑事訴訟法第230条)
- 被害者の法定代理人(同法第231条第1項)
- 被害者が死亡したときは「配偶者・直系親族・兄弟姉妹」(同法第231条第2項。ただし被害者の明示した意思に反しない限り)
- 被害者の法定代理人が被疑者・被疑者の配偶者・被疑者と一定範囲の親族である場合は「被害者の親族」(同法第232条)
- 名誉毀損罪や死者の名誉を毀損した事件では「死者の親族または子孫」(同法第233条)
なお、告訴は代理人によって行うことも可能です(同法第240条)。
親告罪に関する告訴
親告罪については告訴が訴訟条件です。つまり、被害者等による告訴がなければ犯罪加害者が刑事処罰されることはありません。
たとえば、器物損壊罪(刑法第261条)・名誉毀損罪(同法第230条)・過失傷害罪(同法第209条)などの親告罪については、「犯人を知った日から6カ月を経過するまで」に告訴権者による告訴がなければ刑事訴追の可能性はゼロです(刑事訴訟法第235条)。
なお、告訴期限の起算点である「犯人を知った日」とは、犯人について他人と識別できる程度の認識があれば足り、犯人の氏名まで知る必要はありません(最決昭和39年11月10日)。
告発とは
告発とは、「告訴権者及び犯人以外の者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その訴追を求める意思表示」のことです。
告訴とは異なって「告発権者」に関する制限はなく、誰でも犯罪があると思ったときは告発をすることができます(刑事訴訟法第239条第1項)。ただし、官吏・公吏については、その職務を行うことによって犯罪があると思ったときは、告発をしなければいけません(同法第239条第2項)。
告発の方式・手続きの流れは告訴と同じです。口頭または書面にて検察官または司法警察員に対して行い、警察は告発があった事件について検察に送付しなければいけません。また、告発事件に関する処分結果通知義務・不起訴処分理由の通知義務が課されているのも同様です。
ただし、告訴とは異なり、告発には一切の期間制限がなく、また、特別な規定がない限り、告発の取消し後でもふたたび再告発できます(東京高判昭和28年6月26日)。
被害届・告訴・告発の相違点
被害届・告訴・告発の類似点・相違点のまとめは以下の通りです。
| 被害届 | 告訴 | 告発 | |
|---|---|---|---|
| 提出権者 | 原則被害者本人(運用次第) | 法定の告訴権者のみ | 告訴権者と犯人以外すべて |
| 犯罪事実の申告 | あり | あり | あり |
| 訴追を求める意思の申告 | なし | あり | あり |
| 捜査義務 | なし | あり | あり |
| 処分結果の通知義務 | なし | あり | あり |
| 不起訴処分時の理由通知義務 | なし | あり | あり |
| 届出に関する期間制限 | なし | あり(親告罪のみ) | なし |
被害届を出されたらどうなる?刑事手続きの流れを解説
被害届を出された後、警察が犯罪捜査の必要性があると判断した場合には、以下の流れで刑事手続きが進められるのが一般的です。
- 被害届が出された犯罪行為について警察から加害者に対して接触がある
- 被害届が出された犯罪行為について逮捕された場合には警察で48時間以内の取調べが実施される
- 被害届が出された犯罪行為について逮捕された後は、送検されて24時間~20日間の取調べが実施される
- 被害届が出された犯罪行為について検察官が公訴提起するか否かを判断する
- 被害届が出された犯罪行為がついて公開の刑事裁判にかけられる
犯罪加害者が押さえておくべきポイントは、「『被害届が出された=逮捕』『被害届が出された=有罪』ではない」ということです。刑事手続きの各ステージに対応した防御活動を適切に展開すれば、重い刑事処分や有罪判決を回避・軽減できる可能性は高まります。
現在の社会生活や今後の更生可能性への悪影響を避けたいのなら、できるだけ早いタイミングで刑事事件に強い弁護士へご相談ください。
被害届の内容について警察から加害者側に問い合わせがある
被害届が出された後、警察が本格的な捜査活動に踏み出した場合、以下4つの方法のいずれかで加害者に対するアプローチがかけられるのが一般的です。
- 任意の出頭要請・事情聴取
- 逮捕状に基づく通常逮捕
- 逮捕状なしでの現行犯逮捕・緊急逮捕
- 捜索差押え
緊急性が低ければ被害届の内容について任意の事情聴取を求められる
警察からのアプローチ方法のひとつに「任意の出頭要請」「任意の事情聴取」があります。
任意の出頭要請及び事情聴取とは、「捜査機関が犯罪捜査の必要性があると感じたときに自由に実施できる捜査手法」のことです(刑事訴訟法第197条第1項、同法第198条第1項)。たとえば、「被害届の内容に記載された犯罪行為について加害者とされる人物に直接話を聞く必要がある」と捜査機関が判断したときに、携帯電話への問い合わせや自宅訪問などの方法によって、警察に出頭するように求められます。
なお、「”任意”の出頭要請・事情聴取」という言葉にある通り、出頭要請や事情聴取に応じるかどうかは捜査対象者が自由に決めて良いというのが建前です。たとえば、「仕事が忙しいから出頭要請に応じることはできない」「気分が乗らないから事情聴取を受けたくない」などの理由で出頭要請・事情聴取を拒んでも問題はありません。
被害届受理後に捜査機関が任意の事情聴取を選択するケース
被害届の提出によって犯罪事実を把握した警察がどのような捜査手法を選択するかは自由です。たとえば、いきなり通常逮捕手続きに移行する可能性もありますし、加害者の身元を特定したうえで直接接触はせずに尾行等の方法で捜査活動を進めるケースもあり得ます。
そのなかで、警察が「任意の出頭要請・事情聴取」という捜査方法を選択するケースは以下の通りです。
- 加害者の住居・職業が明らかで、逃亡のおそれがない
- 犯罪行為の立証に関する証拠を隠滅されるおそれがない
- 加害者に前科・前歴がない
- 被害届が出された犯罪行為が重大犯罪ではない
- 加害者が更なる犯罪行為に及ぶ見込みが少ない
被害届受理後の任意の出頭要請・事情聴取に応じるべき理由
警察から任意の出頭要請や事情聴取を求められたときは、できるだけ警察側の要望に応じた方が良いでしょう。
なぜなら、任意の出頭要請等に応じない加害者は「逃亡・証拠隠滅のおそれがある=留置の必要性が高い」という判断に基づき逮捕状が請求されて、身柄拘束付きの取調べを強制されるだけだからです。
任意の取調べならスケジュール調整や帰宅のタイミングなどについてある程度融通を効かせてもらえますが、逮捕処分に基づく取調べは自宅に帰ることも第三者と電話連絡をとることも許されず、数日~数週間は留置場や拘置所に居なければいけません。
このような強制的な身柄拘束処分のリスクを少しでも回避するべきなので、任意ベースで刑事手続きが進められている段階で誠実に対応した方が賢明でしょう。
被害状況が深刻ならいきなり後日逮捕される可能性もある
被害届が出された場合、犯罪事実を認知した警察がいきなり逮捕状を請求して、「後日逮捕手続き(通常逮捕手続き)」に移行する可能性もあります。
通常逮捕とは、「逮捕状に基づいて執行される強制的な身柄拘束処分」のことです(刑事訴訟法第199条第1項)。裁判所の事前審査によって逮捕状を発付するか否かが決定されます。
逮捕状が執行されると、被疑者の身柄はその時点で拘束されて警察署に連行されます。逮捕後の取調べに対して黙秘を貫くのは自由ですが、任意の事情聴取・出頭要請とは異なり、連行や取調べ自体を拒絶することはできません。
被害届を受理した後、警察が任意捜査ではなく強制捜査である逮捕手続きを選択するケースは以下の通りです。
- 被疑者が住所不定・無職など逃亡のおそれがある
- 被害者が犯罪に関する証拠を所持している可能性が高く罪証隠滅のおそれがある
- 被疑者に前科・前歴がある
- 被害届が提出された犯罪行為が極めて悪質
被害届によって捜査活動が展開されている場合には現行犯逮捕されるパターンも想定される
被害届が受理された後の流れ次第では、犯罪行為に及んでいる場面を「現行犯逮捕」される可能性も否定できません。たとえば、過去の下着泥棒に関して被害届が受理された後、犯行現場周辺を警察が定期的に巡回している際に、再度下着泥棒に及んでいる現場を取り押さえられるようなケースが挙げられます。
現行犯逮捕とは、「現行犯人に対する逮捕処分」のことです(刑事訴訟法第212条第1項)。現行犯人とは、「現に罪を行い、または、現に罪を行い終わった者」を意味します。たとえば、下着泥棒をするために被害者宅のベランダに侵入したところや、ショッピングモール等で置き引きをしたところを捜査員等によって現認されると、逮捕状なしでその場で逮捕されることになります。
なお、「現に罪を行い、または、現に罪を行い終わった者」だけではなく、「犯人として追呼されている者、犯罪に関する証拠物等を所持している者、誰何されて逃走しようとする者などが、犯罪行為を終えてから時間が経っていないと明らかに認められる場合」にも、逮捕状なしで身柄拘束されます(「準現行犯逮捕」同法第212条第2項)。
加害者宅等に対して捜索差押えが行われる
被害届が出された場合、加害者宅や犯罪に関連した施設等に対して捜索・差押えが実施される場合があります。
捜索・差押えとは、「裁判官の発する令状に基づいて、一定の場所に対して犯罪の証拠物等を探し、対象物を押収する強制処分」のことです(刑事訴訟法第218条第1項)。
たとえば、下着等を盗撮されて盗撮画像がインターネット上にアップロードされた事件について被害届が出された場合、ログなどの情報を頼りに犯人の身元が特定されて、加害者宅に捜索差押え令状を所持した捜査員がやってくるケースが挙げられます。捜索によって自宅にあるPCから違法画像等が発見されると、そのまま逮捕手続きに移行します。
被害届をきっかけに逮捕されると警察段階で48時間以内の取調べが実施される
被害届を出された犯罪行為を理由に逮捕された場合、被疑者の身柄は警察の管理下に置かれて、警察署で取調べが実施されます。
取調べに対してどのような供述をするのか、黙秘をするのかは被疑者側が自由に決定できますが、取調べ自体を拒絶することはできません。また、警察段階の取調べが実施されている間は、弁護士以外の第三者との面会や、外部との電話連絡なども不可能です。さらに、取調べが行われないタイミングは留置場・拘置所に拘束されるので、自宅に帰ることも許されません。
逮捕後実施される警察段階の取調べには「48時間以内」という制限時間が設けられています(刑事訴訟法第203条第1項)。48時間以内に得られた証拠物と供述内容を勘案して、事件を送検するか微罪処分に付するかが決められます。
警察から検察官に送致される
被害届が出されて逮捕された場合、警察段階での取調べを受けた後は、事件・身柄が検察官に送致されます。
検察段階では、「24時間以内」という時間制限のもと、身柄拘束付きの取調べが実施されるのが原則です(刑事訴訟法第205条第1項)。「警察段階48時間+検察段階24時間の合計72時間」の身柄拘束付き取調べで得られた証拠等を総合的に考慮して、検察官が被害届が出された事件について公訴提起するか否かを決定します。
ただし、被害届が出された事件の種類や取調べの進捗次第では、これらの制限時間内だけでは充分な捜査活動を展開できないケースも少なくありません。
そこで、やむを得ない理由によって制限時間を遵守できない場合には、検察官による勾留請求が例外的に認められています(同法第206条第1項)。勾留請求が認められた場合には、「10日間~20日間」の範囲で被疑者の身柄拘束期間が延長されます(同法第208条各項)。
つまり、被害届が出された事件について逮捕された場合には、検察官が公訴提起判断を下すまでに「72時間~23日間」の範囲で社会生活から断絶される期間が生じるということです。会社生活などへの影響を考えると、「逮捕・勾留による身柄拘束を避けること」「逮捕・勾留後の身柄拘束期間をできるだけ短縮化すること」の重要性をご理解頂けるでしょう。
検察が公訴提起するか否か判断する
被害届が出された事件について逮捕・勾留された場合、身柄拘束期限が到来する前に、検察官が起訴処分・不起訴処分を決定します。
起訴処分とは、「被害届が出された犯罪を刑事裁判にかける旨の訴訟行為」のことです。日本の刑事裁判の有罪率は約99%とも言われているので、検察官が起訴処分を下した時点でほぼ有罪が確定することになります。つまり、どうしても有罪や前科を避けたいなら、起訴処分の回避(不起訴処分の獲得)は必須だということです。
これに対して、不起訴処分とは、「被害届が出された事件を公訴提起せず、検察官限りの判断で刑事手続きを終結させる旨の意思表示」のことを意味します。不起訴処分は以下3類型に分類される点に注意が必要です。
- 嫌疑なし:被害届が出された事件について被疑者が罪を犯した証拠がないケース
- 嫌疑不十分:被害届が出された事件について公判を維持できるほど被疑者が罪を犯したという証拠が得られていないケース
- 起訴猶予:被害届が出された事件について被疑者が罪を犯したことは間違いないが、示談や反省の態度等を総合的に考慮すると、刑事裁判にかける必要性が低いと判断できるケース
したがって、被害届を出された事件への関与自体が間違いない状況でも不起訴処分を獲得できる余地は残されているので、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士に相談のうえ、適切な防御活動を展開してもらうべきでしょう。
刑事裁判が開かれる
被害届を出された事件について起訴処分が下された場合、公開の刑事裁判で刑事責任について最終的な判断が下されます。
刑事裁判が開廷されるのは起訴処分の判断が下されてから1カ月~2カ月頃のタイミングが一般的です。逮捕・起訴後の保釈請求が認められた場合には刑事裁判までは自宅に戻ることが許されますが、被害届を出された事件が重大事件に該当する場合などでは、起訴後も勾留生活が続きます。
刑事裁判は、公訴事実に争いがなければ第1回の口頭弁論期日で結審に至りますが、否認事件などの場合には複数の口頭弁論期日を経て弁論手続き・証拠調べ手続きが進められます。
最終的な判決内容は検察官の求刑及び法定刑を勘案して裁判官に決定されます。刑罰は「死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料・没収」の7種類です。なお、懲役刑・禁錮刑の実刑判決に対しては執行猶予付き判決が付されることもあります。
犯罪行為に及んだ以上、それ相応の刑罰を科されるのは仕方ありません。ただ、防御活動への力の入れ具合で科刑量はかなり変動するものですし、できるだけ軽い判決を獲得した方が今後の社会生活への影響を軽減できるのは間違いないです。かならず刑事裁判実績豊富な弁護士に相談のうえ、個別事案に応じて適切な防御活動を展開してもらいましょう。
被害届を出されたまま放置したときに生じるデメリット5つ
被害届の受理によって捜査活動がスタートしたにもかかわらず放置し続けると、以下5つのデメリットが生じます。
- 長期間の身柄拘束によって心身が疲弊する
- 会社にバレて懲戒処分を下される
- 学校にバレて退学処分等を下される
- 報道されるとWeb上に事件・実名の情報が残り続ける
- 有罪が確定すると今後の社会生活にさまざまな支障が生じる
裏を返せば、被害届を出されたことを早期に察知して適切な防御活動を展開すれば、これらのデメリットも回避・軽減できるということです。
したがって、刑事手続きによってもたらされるデメリットを避けたいのなら、被害届が出されたか否かにかかわらず、まずは刑事事件を専門に取り扱っている弁護士に相談のうえ、今後採るべき防御活動の方針についてアドバイスを貰いましょう。
刑事手続き中に長期間身柄拘束されるリスクが高まる
被害届を出されるほどの状況で防御活動を疎かにすると、逮捕・勾留によって「数日~数週間」身柄拘束されるリスクに晒されます。また、起訴処分後の保釈請求が却下された場合には、刑事裁判が終了するまで「数カ月」に及んで社会生活との断絶を強いられかねません。
身柄拘束期間中は拘置所・留置場での生活が続くので、心身共に疲労が蓄積します。また、実生活から隔離されるので、会社や学校生活への支障も避けられません。仮に不起訴処分・無罪を獲得できて刑事責任に問われることがないとしても、身柄拘束生活が続くだけで今までの生活が失われるリスクさえ生じかねないでしょう。
事件を起こしたことが会社にバレて懲戒処分を下される
被害届が受理されて厳しい捜査活動が展開されると、いずれ会社に事件を起こしたことがバレるでしょう。
起こした犯罪の種類や勤務先の就業規則次第ですが、会社にバレると懲戒処分を下される可能性が高いです。
一般的に、懲戒処分の内容は以下のように分類されます。
- 戒告
- 譴責
- 減給
- 出勤停止
- 降格
- 諭旨解雇
- 懲戒解雇
なお、仮に懲戒処分が下されずに済んだり、戒告等の軽い処分内容で済んだとしても、昇格・昇給のチャンスを棒に振ることになりかねませんし、上司同僚などからの信頼を失うので日々の仕事自体がやりにくくなってしまうでしょう。
事件を起こしたことが学校にバレて退学処分等を下される
学生が事件を起こして被害届を出された場合、逮捕・勾留などの身柄拘束処分の対象になると、事件を起こしたことや犯人として捜査対象になっていることが学校にバレる可能性が高いです。
嫌疑をかけられている犯罪の種類や学則・校則の規定次第ですが、犯罪行為に及んで逮捕された場合や、報道等によって学校の信用を毀損した場合には、更生可能性や生徒の心身の発達への影響を加味したうえで、以下のような処分が下されるリスクに晒されます(学校教育法施行規則第26条第2項)。
- 訓告
- 停学
- 退学
事件が実名報道されると半永久的に社会的制裁を受け続ける
被害届を出された犯罪の種類・内容次第では、報道番組やネットニュース等で事件のことが実名報道される可能性もあります。
たとえば、強盗事件などの重大犯罪や、性犯罪などの話題性の高い犯罪類型などは、大々的に配信されるリスクを伴うでしょう。
特に近年では、ネットニュースやSNS等で事件情報が拡散される傾向にあるので、一度でも実名報道されると半永久的にインターネット上に過去の犯罪歴が残る状態に陥ってしまいます。
有罪判決が下されると今後の社会生活にさまざまな悪影響が生じる
被害届を出された後、捜査機関主導で刑事手続きを進行させられてしまうと、公訴提起された後、有罪判決が下される可能性が高いです。
まず、実刑判決(懲役刑・禁錮刑)を内容とする有罪判決が確定すると、刑期を満了するまで刑務所に収監されます。これでは社会人生活や学生生活を継続するのは難しく、また、刑期満了後にやり直すのも簡単ではないでしょう。
次に、有罪判決が確定した段階で「前科」がつく点に注意しなければいけません。
前科とは、「過去に有罪判決を受けた経歴」のことです。実刑判決だけではなく、執行猶予付き判決・罰金刑など、刑罰の種類を問わず有罪になった時点で「前科者」として扱われます。
前科情報は一般公開されておらず、また、ローン審査等にも影響しない反面、以下のような場面で悪影響を及ぼす可能性が高いです。
- 前科情報は履歴書の賞罰欄への記載義務があるので、就職活動・転職活動の難易度が高くなる
- 前科の内容次第では制限される職種・資格がある(士業・警備員・金融業など多数)
- 逮捕歴や前科歴は「法定離婚事由」に該当するので、配偶者からの離婚申し出を最終的には拒絶できない
- 前科の内容次第ではパスポート・ビザ発給が制限されるので海外渡航できなくなる
- 前科があると再犯時の刑事処分・判決内容が重くなる可能性が極めて高い
被害届を出されたときに弁護士へ相談するメリット10つ
「被害届を出されたのではないか」と不安を抱いているのなら、できるだけ早い段階で弁護士に相談することを強くおすすめします。
なぜなら、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士の力を借りれば、以下10点のメリットが得られるからです。
- 弁護士への依頼によって被害届が出されたか分かる確率が高まる
- 弁護士は迅速な示談交渉の末に被害届の取り下げを目指してくれる
- 弁護士は微罪処分獲得による刑事手続きの早期終結を目指してくれる
- 弁護士は在宅事件扱いによる身柄拘束処分回避を目指してくれる
- 弁護士は逮捕・勾留処分の妥当性を争って早期の身柄釈放を目指してくれる
- 弁護士は不起訴処分獲得によって有罪・前科回避を目指してくれる
- 弁護士は少しでも軽い判決内容獲得を目指してくれる
- 弁護士は略式手続きを利用する是非について冷静に判断してくれる
- 弁護士は逮捕・勾留によって厳しい取調べを強いられる被疑者を接見機会に励ましてくれる
- 弁護士は刑事手続き以外に発生する法律問題やトラブルにも丁寧に対応してくれる
上述のように、被害届が受理されて捜査活動がスタートすると、厳格な時間制限の下、着実に刑事手続きが進行します。
悠長に構えていると知らないうちに防御活動の機会が失われかねないので、犯罪行為への関与に思い当たる節があるのなら、今すぐに刑事事件に強い弁護士までご相談ください。
弁護士は被害届を出したか否かを確認してくれる
被害届に関する取扱いは捜査機関に確認しても教えてもらえません。したがって、被害届を出されたか否かを知るには、被害者本人に確認するしか方法は残されていないと考えられます。
しかし、加害者自身が被害者に連絡をしたところで、その場で警察に通報されるか、連絡を無視されるのが目に見えています。
これに対して、弁護士が代理人として被害者本人にコンタクトを取れば、加害者自身が交渉を行うときよりもスムーズに事が進むはずです。被害者側にとっても、犯罪行為に及んだ加害者と連絡を取り合うのは恐怖・不安が募るものですが、専門家である弁護士が窓口となれば安心感が得られるので、被害届を出したか否かを教えてくれやすくなるでしょう。
弁護士は被害届を出した本人と示談交渉を進めてくれる
被害者がどこの誰か判明している事件類型の場合、弁護士は即座に被害者と連絡をとって示談交渉をスタートしてくれます。
示談とは、「加害者と被害者との間の話し合いによって事件解決に関する和解案に合意をすること」です。刑事事件に関する示談交渉では、「被害弁償と慰謝料を合わせた示談金を支払う代わりに、『被害届を出さない旨』『既に提出した被害届を取り下げる旨』の確約を得ること」が和解条件に掲げられるのが一般的です。
たとえば、被害届を出される前に示談交渉をスタートすれば、被害届の提出自体を予防し、犯罪行為が刑事事件化する前に決着させることができます。また、既に被害届を出されて受理された後でも、示談成立によって被害届が取り下げられるので、微罪処分・不起訴処分・執行猶予付き判決など、軽い刑事処分獲得の可能性が高まるでしょう。
弁護士は微罪処分獲得に向けて尽力してくれる
被害届を出された犯罪行為の種類次第では、「微罪処分」獲得も不可能ではありません。
微罪処分とは、「警察が捜査活動を実施した事件を検察官に送致せず、警察限りの判断で刑事手続きを終結させる事件処理類型」のことです。
原則として、警察が捜査を実施した事件は送検する必要があります(刑事訴訟法第246条本文)。ただし、すべての事件について検察官の意思決定を仰ぐ必要があるとなると、検察実務の事務処理の効率性が阻害されかねません。そのため、以下の要素を満たす一定の事件類型(犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたもの)については、例外的に警察限りの判断で送致せずに刑事手続きを終結できるとされています(同法第246条但書、犯罪捜査規範第198条)。
- 被害届を出された犯罪行為が極めて軽微な犯罪類型に該当すること(窃盗罪、占有離脱物横領罪など)
- 被害額が少額であること(窃盗罪なら2万円程度までが目安)
- 犯情に斟酌の余地があること(計画性がない衝動的な犯行など)
- 素行不良者ではないこと(前科・前歴がないこと)
- 身元引受人など、犯人の社会更生をサポートする体制が整っていること
- 被害者との間で示談交渉が進んでいること、被害弁済が済んでいること
微罪処分に付された場合、送検後に待ち受けている勾留による長期の身柄拘束や、起訴処分のリスク、ひいては有罪判決を下される可能性をすべて回避できます。
被害届が受理されて間もない段階で弁護士に相談すれば早期の示談成立を期待できるので、微罪処分獲得の可能性が高まるでしょう。
弁護士は在宅事件処理を目指して尽力してくれる
被害届を出された犯罪行為に対する加害者側の向き合い方次第で、「在宅事件」扱いを期待できます。
在宅事件とは、「逮捕・勾留などの身柄拘束処分なしで捜査段階の取調べや裁判手続きが進められる事件処理類型」のことです。逮捕・勾留が実施されると拘置所と取調室の往復しかできませんが、在宅事件処理なら日常生活を送りながら要請があったタイミングで刑事手続きに参加すれば良いだけなので、会社や学校に隠し通しやすいでしょう。
ただし、被害届を出された場合に在宅事件扱いを受けるには以下の要素を満たす必要があります。
- 住所や職業が明らかで逃亡のおそれがないこと
- 犯罪に関連する証拠物を隠滅するおそれがないこと
- 捜査機関や裁判所からの出頭要請に応じていること
- 取調べに否認せずに素直に反省の態度を示していること
- 被害者との示談交渉が進んでいること、被害弁償が済んでいること
被害届を出されて間もないタイミングで弁護士に依頼をすれば、早期に示談交渉を進めるだけではなく、在宅事件処理獲得に資するような取調べへの対応方法などについてアドバイスを貰えるでしょう。
弁護士は身柄拘束期間短縮化に向けて尽力してくれる
被害届を出されて逮捕・勾留されたとしても、刑事事件の実績豊富な弁護士に相談すれば、逮捕処分・勾留処分の妥当性を争って早期の身柄解放に向けて尽力してくれます。また、起訴後すみやかに保釈手続きに踏み出して実生活への悪影響を最大限軽減してくれるでしょう。
たとえば、勾留理由開示請求・勾留決定に対する準抗告・勾留取消請求・勾留執行停止の申立てなどの法的措置を採ったり、明らかに留置の必要がないのに身柄拘束処分が継続している場合には釈放に向けて働きかけたりします。
弁護士は不起訴処分獲得に向けて尽力してくれる
被害届を出された事件について逮捕・送検されたとしても、弁護士に相談すれば不起訴処分獲得に向けて防御活動を展開してくれるでしょう。不起訴処分を獲得できれば「無罪」で刑事手続きを終わらせられるので、前科によるデメリットを回避できます。
まず、嫌疑をかけられている事件についてまったく身に覚えがないケースであれば、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」を目指すのも選択肢のひとつです。
これに対して、容疑をかけられている犯罪行為について心当たりがある場合には、「起訴猶予処分」を目指すのが合理的な戦術でしょう。なぜなら、むやみに否認しても客観的証拠に基づいて犯罪が立証されるわけですし、「否認=反省の態度がない」と受け取られて起訴処分のリスクが高まるからです。
起訴猶予処分獲得には以下のポイントが重要になります。弁護士のアドバイスを参考にしながら、取調べには誠実に対応してください。
- 罪を認めて真摯に反省の態度を示すこと
- 客観的な証拠と反する供述をしないこと
- 不必要に罪が重くなるような供述調書にはサインをしないこと
- 被害者との間で示談交渉が進んでいること、示談金の支払いが済んでいること
弁護士は軽い判決獲得に向けて尽力してくれる
検察官が公訴提起判断を下した場合でも、刑事弁護に強い専門家に依頼すれば、できるだけ軽い判決内容獲得を目指してくれるでしょう。
たとえば、実刑判決よりも執行猶予付き判決・罰金刑の方が大きなメリットを得られるのは言うまでもありません。また、執行猶予付き判決ではなく罰金刑を獲得できれば、執行猶予期間の生活に何の制限もなくなる点で社会復帰を目指しやすいと考えられます。
刑事裁判で少しでも軽い判決を獲得するには以下のポイントが重要です。刑事事件の経験豊富な弁護士に相談のうえ、必要な情状証拠を主張立証してもらいましょう。
- 罪を認めて真摯に反省していること
- 被害者との間で示談が成立していること
- 身元引受人や監督者など、更生のために必要な環境の準備が整っていること
弁護士は略式手続きを利用する是非を判断してくれる
被害届を出された事件の種類次第では、略式手続きによって簡易・簡便に刑事手続きを終結させられる場合があります。
略式手続きとは、「公開の刑事裁判によらずに刑事手続きを終結させる事件処理類型」のことです(刑事訴訟法第461条)。ただし、すべての刑事事件について略式手続きを利用できるわけではありません。略式手続きの対象事件の要件は以下の通りです。
- 簡易裁判所の管轄に属する事件であること
- 100万円以下の罰金または科料を科す事件であること
- 被疑者が略式手続による審判に書面で同意していること
たとえば、比較的軽微な窃盗事件について被害届が提出されて、同種累犯があることなどを理由に起訴処分が相当と判断されるようなケースであり、かつ、検察官が罰金刑を求刑する予定である場合、略式手続きを利用すればその時点で罰金刑が確定するので、公判手続きを遂行する負担から解放されて、社会復帰を目指すタイミングを前倒しできるでしょう。
ただし、略式手続きを利用した場合、公開の刑事裁判で反論をする機会を失うというデメリットが生じる点に注意が必要です。たとえば、「窃盗罪ではなく遺失物横領罪が成立する」「不法領得の意思が存在しないから窃盗罪は無罪だ」など、検察官の公訴事実を真正面から争いたいのなら、略式手続きの利用に賛成してはいけません(もちろん、公判で被告人側の主張が通るとは限りません)。
刑事裁判の実績豊富な弁護士なら、略式裁判に基づく罰金刑で手打ちとするべきか、公開の刑事裁判で争うべきかを冷静に判断してくれるでしょう。
弁護士は接見交通権を活用して被疑者をサポートしてくれる
弁護士は接見交通権を有しているので、逮捕・勾留処分によって厳しい身柄拘束付きの取調べを強いられている被疑者と面会して励ましてくれます。
また、接見機会を利用して時々刻々と推移する取調べ状況をチェックして、次の取調べでどのような供述をするべきかについてアドバイスを提供してくれます。
逮捕・勾留中は、弁護人以外との面会は原則禁止です。心身が疲弊するなか孤独に取調べに向き合っている被疑者の力強い味方になってくれるでしょう。
弁護士は刑事事件から派生した法律トラブルにも対応してくれる
被害届を出されて過去の犯罪行為が明るみに出た場合、刑事責任を追及される以外にもさまざまなリスクに晒される可能性が高いです。
たとえば、刑事事件に関連して発生が危惧される問題として、以下のものが挙げられます。
- 配偶者との離婚問題(離婚の成否・慰謝料額・親権など)
- 学校や会社から下された処分内容の妥当性
- インターネット上に拡散された個人情報や誹謗中傷記事等への削除要請、損害賠償請求
- 性犯罪や盗症などの根本的な治療
刑事事件を専門に取り扱っている弁護士は、「依頼人が本当の意味で社会復帰を目指せる環境を整えること」を目標にさまざまなケアを施してくれるでしょう。
被害届を出されたときは弁護士へ相談を!早期の対応で刑事事件化自体を回避できる
被害届を出されたときや、被害届を出されたか不安なときには、すみやかに弁護士まで相談することをおすすめします。
なぜなら、被害届提出前に示談交渉に成功すれば刑事事件化自体を回避できますし、すでに被害届受理後でも、示談条件次第では被害届の取り下げも期待できるからです。
被害届を出された犯罪の種類にもよりますが、早期に示談交渉をスタートすることにはメリットしかありません。少しでも軽い刑事処分を獲得するためにも、刑事弁護や示談交渉のノウハウ有する専門家をご活用ください。