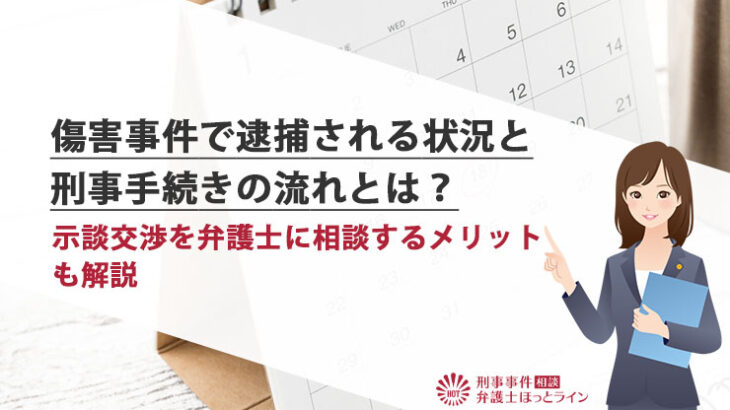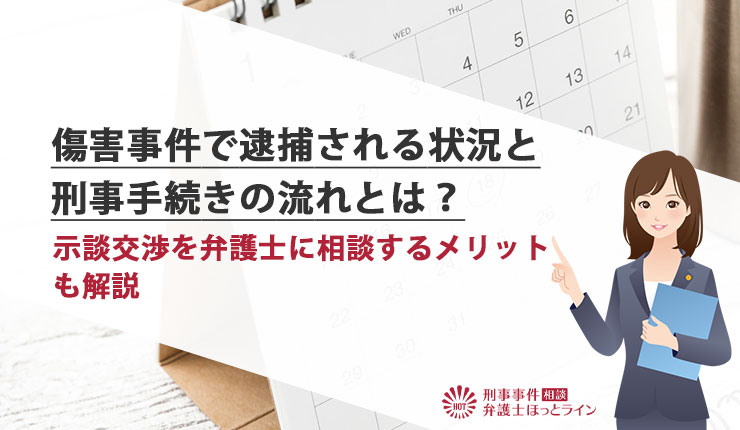
傷害事件を起こしたときは、傷害罪・暴行罪・殺人未遂罪などの容疑で逮捕されるのが一般的です。たとえば、居酒屋の客同士で喧嘩をした場合や、家庭内暴力(DV)で配偶者や恋人に怪我をさせた場合などが挙げられます。
傷害事件が警察にバレた場合、逮捕・勾留による長期間に及ぶ身柄拘束、実刑判決の確定による服役、前科によるデメリットなどのリスクに晒されます。これらのリスクを回避するには、捜査活動のステージに応じた適切な防御活動が不可欠です。
そこで今回は、過去の傷害事件が原因で後日逮捕されるか不安を抱えている方や、ご家族が傷害事件を起こして現行犯逮捕された方のために、以下4点について分かりやすく解説します。
- 傷害事件を起こして逮捕されるときの犯罪類型
- 傷害事件が警察にバレた後の刑事手続きの流れ
- 傷害事件を起こして逮捕されたときに生じるデメリット
- 傷害事件を起こしたときに弁護士へ相談するメリット
傷害事件が捜査機関に発覚したときは、被害者との間で示談交渉を進めるのが重要な防御活動になります。刑事事件や示談実績豊富な弁護士に相談をして、できるだけ軽い刑事処分獲得を目指して尽力してもらいましょう。
目次
- 1 傷害事件を起こして逮捕されるときの犯罪類型と法定刑
- 2 傷害事件で逮捕されるときの刑事手続きの流れ
- 3 傷害事件を起こして逮捕リスクに晒されたときに弁護士へ相談するメリット5つ
- 4 傷害事件で逮捕されるか不安なときは刑事事件に強い弁護士へ相談しよう
傷害事件を起こして逮捕されるときの犯罪類型と法定刑
傷害事件を起こして逮捕される場合、以下の犯罪類型の容疑をかけられるのが一般的です。
- 傷害罪
- 暴行罪
- 殺人未遂罪
なお、傷害事件を起こした際に被害者の財布や所持品を奪った場合には、窃盗罪・強盗罪・事後強盗罪・強盗致傷罪・占有離脱物横領罪などの財産犯で逮捕されるリスクに晒されます。また、傷害事件の態様によっては、器物損壊罪・決闘罪・公務執行妨害罪・現場助勢罪などの容疑をかけられることもあるでしょう。
このように、傷害事件の経過・事情次第でどのような容疑をかけられてどう防御活動を展開するかが変わってくるので、過去の傷害事件について後日逮捕されるのではないかを不安を抱えている場合には、かならず刑事事件の実績豊富な弁護士までご相談ください。
傷害罪
傷害事件を起こして逮捕される場合、「傷害罪」の容疑をかけられるのが典型的です。
傷害罪の構成要件
傷害罪とは、「人の身体を傷害したとき」に成立する犯罪類型のことです(刑法第204条)。
傷害罪の構成要件として以下4点が挙げられます。
- 傷害行為(傷害罪の実行行為)
- 人の身体に傷害結果が生じたこと(傷害罪の結果)
- 実行行為と結果との間の因果関係
- 故意
第1に、傷害罪の実行行為は「傷害行為」です。平手打ち・拳で殴りつける・道具を使って殴打するなどの物理的な有形力の行使が典型例ですが、いわゆる「暴行によらない傷害」も傷害罪の対象に含まれます。たとえば、執拗な嫌がらせの電話、性病であることを隠して性器を押し当てる行為、怒号なども、傷害罪の結果を生じるものであれば傷害罪の実行行為性が認定されるでしょう。
第2に、傷害罪の結果は「人の身体に傷害結果が生じたこと」です。ここに言う「傷害結果」とは、「生活機能の毀損、健康状態の不良変更(=生理機能の侵害)」を意味すると解するのが判例です(大判明治45年6月20日)。たとえば、病毒への感染(最判昭和27年6月6日)、失神(大判昭和8年9月6日)、胸部疼痛(最決昭和32年4月23日)、不安・抑うつ症(名古屋地判平成6年1月18日)、PTSD(心的外傷後ストレス症候群)などは、すべて傷害結果に該当します。これに対して、剃刀で女性の頭髪を切断するだけでは生理機能を侵害したとは言えないので、傷害罪は成立しません。
第3に、傷害罪が成立するには、「傷害行為と傷害結果との間に因果関係が存在すること」が必要です。ここに言う「因果関係」とは、「単純な条件関係」ではなく、「実行行為から結果が発生することが相当かどうか」という観点から判断されます。たとえば、傷害事件の最中に殴られた被害者が地面に転んだが、立ち上がるときに足を滑らせて手首を骨折してしまったようなケースでは因果関係の相当性は認められます。これに対して、傷害事件で軽い怪我をした被害者が念のために救急車で搬送されている途中で自動車の衝突事故に巻き込まれて重篤な後遺障害を抱えるに至った場合には、「重篤な後遺障害」という結果に対して傷害罪が成立するとは考えにくいでしょう。
第4に、傷害罪で逮捕されるには、主観的構成要件である「故意」が必要です。ただし、傷害罪が成立するには、「傷害の故意」だけではなく「暴行の故意」で足りるとするのが実務的運用です。たとえば、「殴ってやろう」という認識だけで怪我をさせるつもりがなかったとしても、傷害事件の被害者が怪我をしてしまった場合には、「殴る」という行為に対する認識・認容があるだけで傷害罪で逮捕されます。
傷害罪の法定刑
傷害罪の法定刑は、「15年以下の懲役刑また50万円以下の罰金刑」です(刑法第204条)。
懲役刑の幅が広く設定されているのは、傷害事件の被害者が負った怪我の程度に応じて量刑を定めるためです。たとえば、全治1週間程度の軽い打撲程度なら、刑期はかなり短期間で済むでしょう(実際には、不起訴処分が下されるか、罰金刑・執行猶予になる可能性が高いです)。
これに対して、傷害事件の被害者に深刻な後遺症が残るようなケースでは、どうしても刑期はある程度長くなってしまいます。執行猶予付き判決を獲得するには「3年以下の懲役刑・禁錮刑または50万円以下の罰金刑の言渡しを受けたとき(刑法第25条第1項)」という要件を満たす必要があるので、刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼をして、早期に示談交渉を進めてもらうべきでしょう。
暴行罪
傷害事件の態様次第では、「暴行罪」の容疑で逮捕される可能性も生じます。
暴行罪の構成要件
暴行罪とは、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に成立する犯罪類型のことです(刑法第208条)。
暴行罪の実行行為である「暴行」とは、「人に対する物理力の行使」を意味します。たとえば、喧嘩相手の頬を平手打ちしたり、頭を拳骨で殴ったりした場合が典型例です。
ただし、刑事実務では暴行概念はかなり緩やかに捉えられており、人の身体に対する不法な一切の攻撃方法が含まれ、性質上傷害の結果を惹起するようなものである必要はありません。たとえば、着衣をつかんで引っ張る行為(大判昭和8年4月15日)、大声や騒音などを鳴らす行為(最判昭和29年8月20日)、塩をふりかける行為(福岡高判昭和46年10月11日)、相手を威嚇する目的で数歩手前を狙って石を投げる行為(東京高判昭和25年6月10日)などが該当します。
なお、傷害罪の項目で説明したように、「傷害の結果を生じる故意がなく、暴行行為をする故意しか存在しない場合」でも、結果として傷害結果が生じた場合には、暴行罪ではなく傷害罪で逮捕されます。
暴行罪の法定刑
暴行罪の法定刑は、「2年以下の懲役刑もしくは30万円以下の罰金刑、拘留もしくは科料」です(刑法第208条)。拘留とは「1日以上30日未満刑事施設への拘置」、科料とは「1,000円以上10,000円未満の金銭付加刑」を意味します(刑法第16条、第17条)。
傷害罪と異なり、暴行罪の懲役刑は最長でも「2年」なので、任意的減軽や情状酌量などの防御活動に専念しなくても執行猶予付き判決の対象です。
ただし、被害者との示談が成立していなかったり、明らかに反省の態度が見られないとき、再犯の可能性があると判断された場合には、躊躇なく実刑判決が下されるので、傷害事件を起こして暴行罪で逮捕されたとしても、かならず刑事事件を専門にしている弁護士へ相談をして防御活動に尽力してもらいましょう。
殺人未遂罪
悪質な傷害事件を起こした場合、「殺人未遂罪」の容疑で逮捕される可能性も否定できません。
殺人未遂罪の構成要件
殺人未遂罪は、「殺人行為の『実行の着手』があるとき」に成立する犯罪類型のことです(刑法第43条本文)。
実行の着手とは、「既遂の具体的・客観的危険性が生じたこと」を意味します。
たとえば、傷害事件において刃渡り数十センチのナイフを使って被害者の胸部を狙って切りかかった場合、数キログラムある鈍器で被害者の頭部を殴打した場合、体格の劣る被害者一人に対して柔道経験のある屈強な男性数名で何度も暴行を加えた場合には、傷害罪の範囲に収まらない「被害者の死亡」の具体的・客観的危険性が生じていると言えるでしょう。
殺人未遂罪の法定刑
殺人未遂罪の法定刑は、「死刑または無期もしくは5年以上の懲役刑」です(刑法第199条、同法第203条)。殺人既遂罪と同じ法定刑の範囲内で量刑が定められます。
ただし、傷害事件を起こして殺人未遂罪で逮捕された場合は、「既遂結果が発生していない」という点が評価されて、刑の任意的減免を期待できます(同法第43条本文)。
したがって、殺人未遂罪で逮捕されたとしても、未遂減免や被害者との示談交渉、反省の態度を示すなどの防御活動を効果的に展開すれば、情状酌量によって執行猶予付き判決獲得も視野に入ってくるでしょう。
【注意!】DVも傷害事件として逮捕リスクに晒される
「DVは家庭内や恋人同士の問題だから警察は動かない」というのは間違いです。
確かに、ドメスティックバイオレンスは家庭内などの閉鎖的な環境で行われることが多いので、「捜査機関に発覚しにくい」という性質があります。
しかし、近年ではDV被害者救済の動きが強まっていますし、暴力行為を受けた配偶者やパートナーがその場で110番通報したり後日被害届を提出したりするケースも少なくありません。また、DV中の悲鳴を聞いた近隣住民に通報される場合も多いです。
このような経緯でDVによる傷害事件が警察に発覚した場合には、暴行罪や傷害罪、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」違反などの容疑で逮捕されます。「DVは民事不介入だから逮捕されない」というのは間違いで、警察がDV加害者の身柄を確保するべきだと考えたときには躊躇なく逮捕手続きに着手するでしょう。
特に、DVが傷害事件として立件された場合には、逮捕後の刑事責任に関する対応だけではなく、離婚や慰謝料、親権、養育費をめぐる民事紛争への対策も考えなければいけません。かならず、刑事事件のなかでもDV事案の経験豊富な弁護士までご相談ください。
傷害事件で逮捕されるときの刑事手続きの流れ
傷害事件を起こして逮捕されるときの一般的な刑事手続きの流れは以下の通りです。
- 警察が傷害事件について捜査をスタートする
- 傷害事件を理由に逮捕されると警察段階の取調べが実施される
- 傷害事件が警察から検察官に送致される
- 傷害事件について検察段階の取調べが実施される
- 検察官が傷害事件を公訴提起するか否か判断する
- 傷害事件が刑事裁判にかけられる
傷害事件について警察が捜査活動をスタートする
傷害事件が警察に発覚した場合、以下3つのパターンで犯人に対する接触が行われます。
- 現行犯逮捕
- 通常逮捕
- 任意の出頭要請・事情聴取
傷害事件の現場で現行犯逮捕される
傷害事件の現場で110番通報されたようなケースでは、「現行犯逮捕」によって被疑者の身柄が押さえられます。
現行犯逮捕とは、「現行犯人(現に罪を行い、または、罪を行い終わった者)に対する逮捕処分」のことです(刑事訴訟法第212条第1項)。
傷害事件の現行犯逮捕は無令状で行われる
現行犯逮捕は「令状主義」の例外に位置付けられる強制処分です(刑事訴訟法第213条)。
令状主義とは、「逮捕・差押えなどの重大な人権侵害の危険性を有する強制処分については、捜査機関だけの判断でこれを行うことを禁止し、原則として裁判官の事前判断を要する」という制度を意味します。
たとえば、逮捕処分には「被疑者の身体・行動の自由」を侵害するという性質があるため、原則として裁判官が事前に逮捕状を発付した場合にしか認められません(日本国憲法第33条)。裁判官が逮捕状を発付する際に「逮捕の必要性」「逮捕の相当性」を判断することによって、逮捕権の濫用や冤罪リスクが回避されます。
ただし、現行犯逮捕のシチュエーションには令状主義を及ぼす必要はありません。なぜなら、傷害事件の渦中で違法行為に着手している現場で行われる逮捕権の行使には濫用や誤認逮捕のリスクは存在しないからです。
したがって、現行犯逮捕が行われるときには「逮捕状の発付手続き」は省略されるので、現場にかけつけた警察官に身柄を押さえられるとそのまま警察署に連行されることになります。
傷害事件の現行犯逮捕は警察官以外の人物にも行うことができる
現行犯逮捕は、検察官・検察事務官・司法警察職員・司法巡査だけではなく、一般私人でも行うことができます(刑事訴訟法第213条)。
たとえば、傷害事件の現場を通りがかった第三者や目撃者、被害者本人による現行犯逮捕(私人逮捕)も可能です。
なお、検察官・検察事務官・司法警察職員以外の人物が犯人を現行犯逮捕した場合、直ちに被疑者の身柄を地方検察庁・区検察庁の検察官か司法警察職員に引き渡さなければいけないとされています(同法第214条)。
傷害事件の現場から逃走しても準現行犯人として無令状逮捕される可能性がある
傷害事件を起こしている最中や、傷害事件を起こして被害者を殴り終わったタイミングで身柄が取り押さえられるのが現行犯逮捕の典型例です。
ただし、「傷害事件の現場から離れてしまえば現行犯逮捕されることはない」というわけでもありません。なぜなら、以下4つのいずれかに該当する人物が罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときには現行犯人とみなされる(準現行犯人)からです(刑事訴訟法第212条第2項)。
- 傷害事件の犯人として追呼されているとき
- 贓物や明らかに傷害事件に供したと思われる兇器その他の証拠物を所持しているとき
- 身体や被服に傷害事件の顕著な証跡があるとき
- 誰何されて逃走しようとするとき
たとえば、繁華街で傷害事件を起こしたがパトカーのサイレン音に気付いて逃走を図った場合、目撃者や被害者に追呼され続けていたり、衣服に血痕が付いていたりすると、犯行現場から数百メートル~数キロ離れて、また、犯行から数時間が経過していたとしても、準現行犯人として逮捕状なしで身柄拘束される可能性があります。
なお、傷害事件を起こしてから準現行犯逮捕されるまでの経緯次第では、準現行犯逮捕自体の適法性を争う余地も残されています。刑事事件に強い弁護士に相談すれば、準現行犯逮捕の違法性を主張すると同時に、「違法な逮捕処分から得られた供述証拠等を排除するべき」などの法律論を展開して有利な刑事処分・判決内容獲得に向けて尽力してくれるでしょう。
傷害事件について後日逮捕される
過去の傷害事件が後日警察に発覚した場合、「通常逮捕」によって被疑者の身柄が拘束されます。
通常逮捕とは、「裁判所が事前に発付する逮捕状に基づいて被疑者の身柄を押さえる強制処分」のことです(刑事訴訟法第199条第1項)。現行犯逮捕とは異なり、令状主義が素直に適用される強制処分と位置付けられるでしょう。
過去の傷害事件が警察にバレる理由
「過去の傷害事件が今さらバレるはずがない」とお考えの人も少なくはないでしょう。
しかし、「傷害事件は現行犯以外逮捕されない」というのは間違いです。なぜなら、以下のような端緒で過去の傷害事件は警察に発覚するからです。
- 被害者や目撃者の証言から犯人像が明らかになる
- 傷害事件の犯行現場や逃走中の様子が防犯カメラやドライブレコーダーに録画されている
- 被害者が通院して診断書をとれば傷害結果の証拠になる
- 被害者が後日被害届や告訴状を提出する
- 傷害事件の様子を撮影した動画・画像がSNSや動画サイトに投稿されて拡散される
したがって、数年前に起こした傷害事件が今になって掘り起こされる可能性も否定できないので、後日逮捕されるのではないかと不安を抱えているのなら、警察から連絡があるか否かにかかわらず弁護士へ相談をして、今後の防御活動についてアドバイスをもらうべきでしょう。
過去の傷害事件は公訴時効が完成するまで常に通常逮捕リスクを抱えたまま
過去の傷害事件がいつまで後日逮捕リスクを抱えているかは捜査活動の進捗次第です。
犯人の身元特定が簡単に済めば傷害事件から数日~数週間で通常逮捕される可能性もありますし、身元特定や犯罪立証に慎重な捜査を要するケースでは数カ月~数年が経過したタイミングである日いきなり逮捕状をもった警察官が自宅にやってくることもあり得ます。
ただし、過去の傷害事件は未来永劫いつまでも後日逮捕リスクを抱えているわけではありません。なぜなら、刑事手続きには「公訴時効」という制度が用意されており、公訴時効が完成すれば検察官の公訴提起権が消滅する(=逮捕されることもなくなる)からです。
なお、以下のように、公訴時効が完成するまでの期間はどのような容疑をかけられるかによって異なります(刑事訴訟法第250条)。
| 犯罪類型 | 公訴時効期間 |
|---|---|
| 暴行罪 | 3年 |
| 傷害罪 | 10年 |
| 殺人未遂罪 | 25年 |
たとえば、傷害事件について傷害罪の容疑をかけられている場合、傷害事件が終わったときから10年が経過しなければ公訴時効は完成しません。通常逮捕手続きは被疑者に予告なく行われるので、傷害事件後に手に入れた社会的地位や結婚生活などが突如として失われてしまいます。
過去の傷害事件について被疑者側が主導して防御活動に動き出せば、在宅事件として取り扱ってもらえたり、刑事事件化自体を回避できる可能性も見出せます。したがって、警察から連絡があるか否かにかかわらず、過去に傷害事件を起こした経験があるのなら、すみやかに弁護士へ相談をして現段階で採り得る防御活動について検討してもらいましょう。
過去の傷害事件で通常逮捕されるのは身柄拘束要件を満たすときだけ
過去の傷害事件が警察に発覚したとしても、かならず通常逮捕手続きに移行するわけではありません。
なぜなら、逮捕状が発付されるのは以下2点の要件を満たすときに限られるからです(刑事訴訟規則第143条)。
- 被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
- 逮捕の必要性
第1に、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」とは、「傷害事件が存在すること・被疑者が傷害事件の犯人であること」を根拠付ける客観的な証拠を意味します。たとえば、被疑者が傷害事件の犯人である物証や目撃者等の証言、診断書などによって「逮捕の理由」があることが証明されます。
第2に、逮捕状が発付されるのは「逮捕の必要性」があるときだけです。「逮捕の必要性」とは、「被疑者の身体・行動の自由を侵害してまで強制的に身柄を拘束する必要があるのか」という観点から判断されるものです。具体的には、「逃亡や証拠隠滅のおそれにより留置する必要性があるのか」という視点を意味します。たとえば、以下のような事情があると、逮捕状が請求される可能性が高まるでしょう。
- 住所不定・無職・職業不詳
- 共犯同士で口裏を合わせる可能性がある
- 傷害事件などでの前科前歴がある
- 別件で複数の傷害事件を起こした疑いがある
- 警察からの任意の出頭要請を拒否している
逮捕の必要性がないときは任意の出頭要請がかけられる
傷害事件を起こしたこと自体は間違いないものの「逮捕の必要性(逃亡・証拠隠滅のおそれ)」がないケースでは、逮捕状が発付されることはありません。
ただし、通常逮捕されない場合でも、任意の出頭要請・任意の事情聴取によって傷害事件について捜査活動が進められます。
任意捜査には強制力がない
任意の出頭要請・事情聴取とは、「犯罪捜査の必要性がある場合に警察の自由裁量に基づいて実施される捜査活動」のことです(刑事訴訟法第197条第1項本文、第198条第1項本文)。
たとえば、警察から被疑者の携帯電話に電話がかかってきたり、捜査員が自宅にやってきたりして、警察署への出頭・動向を求められます。また、任意で出頭した後は、取調べ室で傷害事件についてさまざまなことが尋ねられて、供述調書が作成されます。
ただし、任意の出頭要請・事情聴取は令状に基づく強制処分ではないので、被疑者には出頭義務や取調べの受忍義務は課されません。「仕事が忙しいから」という理由で出頭を拒絶しても良いですし、「今さら傷害事件のことは話したくないから」という理由で事情聴取を勝手に切り上げることも可能です。
任意の出頭要請・事情聴取には素直に応じた方が大きなメリットを得られる
確かに、任意の捜査活動に応じる義務は課されていませんが、任意の出頭要請・事情聴取には素直に応じることを強くおすすめします。
なぜなら、任意の出頭要請・事情聴取を拒否すると、「逃亡・証拠隠滅のおそれがある」と判断されて通常逮捕手続きに移行する可能性が高まるからです。
後述するように、逮捕処分によって強制的に身柄が拘束されると取調べ等を拒絶することはできません。これに対して、任意捜査に応じた場合には、出頭日時や取調べの時間を自由に設定できて、取調べ以外は自宅に戻って普段通りの社会生活を営むことができます。通常逮捕処分に基づく取調べでも、任意に基づく事情聴取でも、過去の傷害事件について細かく聴き取りが行われることには変わりません。
したがって、警察から任意の出頭要請をかけられた場合には、弁護士に相談をして供述方針を明確化したうえで取調べ等に対応した方がメリットは大きいと言えるでしょう。
任意の出頭要請・事情聴取に応じれば在宅事件処理の期待が高まる
過去の傷害事件に対する捜査活動として捜査機関が任意処分を選択したとき、上手く対応すれば、在宅事件のまま刑事手続きの終結を目指せます。
在宅事件とは、「逮捕・勾留という身柄拘束処分なしで捜査手続き・裁判手続きを進めることができる事件処理類型」のことです。捜査機関や裁判所の呼び出しがあったタイミングで手続きに関与する必要がありますが、誠実に対応している限りは日常生活から切り離されることはありません。また、身柄拘束期間が発生しないので、学校や会社にバレる心配も軽減できるでしょう。
ただし、在宅事件として扱われても無罪が確定するわけではない点に注意が必要です。たとえば、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを理由に逮捕・勾留を免れられたとしても、在宅起訴によって刑事裁判にかけられて有罪判決が下されることは充分にあり得ることだからです。
したがって、在宅事件処理によって身柄拘束処分を回避できたとしても、微罪処分・不起訴処分・執行猶予付き判決等の有利な処分獲得に向けた防御活動は不可欠だと考えられます。警察から任意の出頭要請等がかかった場合には、できるだけ早いタイミングで弁護士へ相談したうえで、被害者との示談交渉等の防御活動を進めてもらいましょう。
傷害事件で逮捕された後は警察で取調べが実施される
傷害事件を起こして現行犯逮捕・通常逮捕された後は、警察段階の取調べを受けなければいけません。
警察段階で実施される取調べには「48時間以内」という制限時間が設けられています(刑事訴訟法第203条第1項)。これは、逮捕処分は被疑者の人権制約の側面が強いため、無制限な身柄拘束処分を禁止する趣旨です。
逮捕処分に基づく身柄拘束期間中は、以下のような制約を受けます。
- 取調べ室と留置場・拘置所の往復だけで帰宅できない
- 家族や会社に電話連絡できない
- 当番弁護士や私選弁護人以外とは面会できない
傷害事件が送検される
警察段階の取調べが終了した後は、警察から検察官に傷害事件が送致されます。
なぜなら、原則として、刑事手続きを終結させるか公訴提起するかの判断権を握っているのは検察官だからです(刑事訴訟法第246条本文)。
ただし、警察が捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続きをとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送検せずに警察官限りの判断で刑事手続きを終結させることができます(犯罪捜査規範第198条)。これを「微罪処分」と呼びます。
傷害事件が微罪処分の対象になるには、以下の要素を満たす必要があります。
- 傷害事件が暴行罪・傷害罪で立件されていること(殺人未遂罪は対象外)
- 傷害事件の被害が軽微であること(全治1週間程度の怪我までが目安)
- 犯情が軽微であること(計画性がない、酔っ払って衝動的など)
- 被害弁償が済んで被害者との示談が成立していること(治療費や慰謝料など)
- 素行不良者ではないこと(前科・前歴がないこと)
- 被害者側が処罰を望んでいないこと
- 身元引受人が存在して再犯対策が出来ていること
微罪処分を獲得できれば、前科なしで刑事手続きを短期に切り上げることができます。
そのためには、被害者との示談成立は不可欠なので、逮捕後送検までの48時間以内に和解契約締結に向けて弁護士に尽力してもらいましょう(在宅事件の場合には時間の猶予はもう少し与えられます)。
傷害事件について検察段階の取調べが実施される
傷害事件について警察段階で微罪処分を獲得できなかった場合には、送検され、検察段階の取調べを受ける必要があります。
検察段階で実施される取調べは「原則24時間以内」です(刑事訴訟法第205条第1項)。警察段階の48時間と検察段階の24時間を合わせた「合計72時間以内」に、傷害事件を刑事裁判にかけるか否かが判断されます。
もっとも、否認事件や余罪の疑いがある事件などでは、72時間の身柄拘束期間だけでは起訴・不起訴の判断をするのに充分な証拠を収集できないことも少なくありません。
このように、72時間を超えて被疑者を取り調べる必要があるケースでは、検察官による勾留請求によって身柄拘束期間を延長することが認められています。検察官が勾留請求をした場合、被疑者の身柄拘束期間は10日間~20日間の範囲で延長されます(刑事訴訟法第206条第1項、同法第208条)。
以上を踏まえると、傷害事件を起こして逮捕・勾留された場合には、最長で23日間身柄拘束付きの取調べを強いられる危険性があるということです。心身が疲弊するだけではなく、勤務先や学校に傷害事件で刑事訴追されたことがバレてしまうので、懲戒処分等のリスクにも晒されかねません。
したがって、傷害事件について微罪処分を獲得できなかった場合には、「勾留請求されないこと」を目的に防御活動を展開するのが重要だと考えられます。取調べでの供述方針を工夫したり身元引受人を用意するなどの方法で勾留を回避できる可能性が高まるので、適宜弁護士までご相談ください。
検察官が傷害事件について公訴提起するか否かを決定する
逮捕・勾留による身柄拘束期限が到来するまでに、検察官が傷害事件について起訴・不起訴を決定します。
起訴処分とは、「傷害事件を刑事裁判にかける旨の訴訟行為」のことです。これに対して、不起訴処分とは、「傷害事件を刑事裁判にかけずに検察限りの判断で刑事手続きを終結させる旨の意思表示」を意味します。
さらに、不起訴処分は、不起訴に付する理由によって以下3種類に大別されます。
- 嫌疑なし:被疑者が傷害事件を起こしていないケース
- 嫌疑不十分:被疑者が傷害事件を起こしたことに疑問が残るケース
- 起訴猶予:被疑者が傷害事件を起こしたことは間違いないが、諸般の事情を総合的に考慮して刑事裁判を見送るのが相当なケース
ここで重要なのが、「日本の刑事裁判の有罪率は99%を超える」という点です。つまり、検察官が起訴処分を下した時点(刑事裁判にかけられることが決まった時点)で有罪になることがほぼ確定するということです。
したがって、傷害事件を起こして逮捕・勾留された場合には、起訴猶予を理由とする不起訴処分獲得を目指した防御活動が重要になると言えるでしょう。
- 前科情報は履歴書の賞罰欄に記載しなければいけない(就職活動・転職活動が困難になる)
- 前科の内容次第では就業制限が生じる職種や停止・取消しになる資格がある
- 前科は「法定離婚事由」に該当するので、配偶者からの離婚申し出を最終的には拒絶できない
- 前科の内容次第ではビザ・パスポートが発給されないので海外渡航・旅行に制限がかかる
- 再犯時に厳しい刑事処分が科される可能性が高い
これらのデメリットを抱えたまま社会復帰を目指すことを避けたいのなら、できる限りの防御活動を尽くして不起訴処分獲得を目指すべきでしょう。
一定条件が整えば略式起訴で早期の刑事手続き終結を目指せる
検察官が起訴処分を選択した場合には公開の刑事裁判にかけられるのが原則ですが、以下の要件を満たすときには略式手続きを利用して刑事手続きの早期終結を実現できます(刑事訴訟法第461条、同法第461条の2)。
- 簡易裁判所の管轄に属する事件であること
- 100万円以下の罰金刑・科料が予定される事件であること
- 被疑者が略式手続きを利用することについて書面で同意をしていること
略式手続き(略式命令・略式裁判)を選択すれば、公開の刑事裁判に要する時間・労力を節約して、早期に罰金刑が確定されます。たとえば、傷害事件が傷害罪・暴行罪の容疑で立件された場合には罰金刑が求刑されることが多いので、略式手続きの利用によって社会復帰を目指すタイミングを前倒しできるでしょう。
ただし、略式手続きを利用すると公開の刑事裁判で反論を展開する機会が失われる点に注意が必要です。たとえば、傷害事件で正当防衛や過剰防衛を主張したい場合、傷害行為自体を否認した場合には、略式手続きについて同意をするべきではないでしょう(なお、刑事裁判を選択したからと言って反論が認められるとは限りません)。
傷害事件について刑事裁判がひらかれる
傷害事件について検察官が起訴処分を下すと、起訴処分から1カ月~2カ月後のタイミングで公開の刑事裁判が開廷されます。
検察官が主張する公訴事実を全面的に認めるなら、第1回公判手続きで結審します。これに対して、正当防衛による無罪や違法収集証拠排除を主張するような否認事件では、複数回の公判期日を経て弁論手続き・証拠調べ手続きが行われます。
傷害事件が刑事裁判にかけられた場合、最終的には「実刑判決・執行猶予付き判決・罰金刑」のなかから判決内容が選択されるのが一般的です。
執行猶予付き判決・罰金刑を獲得できれば刑務所への収監を回避できますが、いずれも有罪であることには変わらないので前科は回避できません。
したがって、検察段階で不起訴処分を獲得できなかった場合には、「実刑判決を回避すること」を防御活動の方針として丁寧に情状を主張・立証するべきでしょう。
傷害事件を起こして逮捕リスクに晒されたときに弁護士へ相談するメリット5つ
過去の傷害事件を理由に後日逮捕の不安を抱えている方や、ご家族が傷害事件を起こして現行犯逮捕された方は、すみやかに弁護士へ相談することをおすすめします。
なぜなら、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士の力を借りれば、以下5点のメリットを得られるからです。
- 弁護士は傷害事件の被害者と早期に示談交渉を進めてくれる
- 弁護士は身柄拘束期間短縮化を目指して防御活動を展開してくれる
- 弁護士は刑事手続きのステージに応じて少しでも有利な刑事処分獲得を目指してくれる
- 弁護士は過去の傷害事件について自首するべきかを冷静に判断してくれる
- 弁護士は刑事責任以外に発生する法的トラブルにも配慮してくれる
弁護士は傷害事件の被害者との間で示談交渉を進めてくれる
刑事事件に強い弁護士は、傷害事件の被害者と早期に示談交渉をスタートしてくれます。
示談(和解契約)とは、「傷害事件の当事者間での話し合いによってトラブルの解決策について合意を形成すること」です。
一般的な示談では、加害者が被害者に対して一定の示談金(治療費、被害弁償、慰謝料等)を支払う代わりに、「被害届・告訴状を取り下げること」「捜査機関や裁判所に対して処罰感情がないと伝えること」が約束されます。
刑事処分や判決内容を決定する際には、「示談が成立しているか」「被害者の処罰感情の強さ」が考慮されるので、示談成立によって軽い刑事処分を獲得しやすくなるでしょう。
弁護士が着任しなければ被害者の連絡先を入手しにくい
繁華街などで見ず知らずの人と喧嘩をしてしまった場合のように、傷害事件の被害者がどこの誰か分からないというケースは多いです。被害者の氏名や連絡先が分からなければ示談交渉も進めようがありません。
このようなケースでは、「示談交渉のために連絡先を加害者に教えて良いか」と警察が被害者に打診をし、被害者がこれに了承した場合に限って連絡先を入手できますが、弁護士が示談交渉を代理する状況の方が被害者側の了承を得やすいのが実情です。
なぜなら、傷害事件の被害者は加害者に対して怒りや恐怖心を抱いているため、加害者本人と直接話し合いの場を設けることに抵抗を感じることが多いからです。
また、そもそも傷害罪等の容疑で逮捕・勾留されてしまった場合、身柄拘束中の加害者本人が被害者と連絡を取り合うことはできません。
したがって、傷害事件を起こして被害者とすみやかにコンタクトを取るには、弁護人を選任するのが最適な方法だと考えられます。
弁護士を選任しなければ示談条件について折り合いがつきにくい
示談条件は当事者同士の合意によって自由に決定できますが、これを逆手にとって、加害者側から示談相場を大幅に超過した示談条件が提示される場合があります。
たとえば、「早期に示談をまとめて不起訴処分を獲得したい」「話し合いだけで穏便に済ませて警察への通報をやめて欲しい」という加害者側の心理を見通して、治療費に加えて数百万円以上の慰謝料を請求されるケースは少なくありません。
示談交渉の実績豊富な弁護士は、犯罪被害者との話し合いを円滑に進めるノウハウや駆け引きを熟知しているので、相場通りの示談条件での合意を取り付けることができるでしょう。
弁護士は傷害罪等で逮捕・勾留後の身柄拘束期間短縮化を目指してくれる
傷害事件を起こした場合、「どのような刑事責任を問われるのか」という点だけでなく、「どれだけの期間、身柄拘束されるのか」という点にも配慮しなければいけません。
なぜなら、身柄拘束期間に比例して社会生活から隔離される時間も長くなり、社会生活への悪影響が大きくなってしまうからです。たとえば、長期間会社を無断欠勤すると傷害事件を起こしたことがバレる確率が高まります。
弁護士に依頼すれば、以下のような目標を立てて身柄拘束期間短縮化に向けて尽力してくれるでしょう。
- 逮捕される前なら、任意の事情聴取への対応方法を提案して「在宅事件処理」を目指してくれる
- 現行犯逮捕・通常逮捕後なら、「留置の必要性がないことを示して早期釈放」「微罪処分」「勾留回避」を目指してくれる
- 勾留後なら、「留置の必要性がないことを示して早期釈放」「不起訴処分」を目指してくれる
- 起訴処分後すみやかに「保釈請求」を履践してくれる
弁護士は傷害事件についてできるだけ軽い刑事処分獲得を目指してくれる
弁護士に相談すれば、刑事手続きのステージに応じてできるだけ有利な処分獲得を目指してくれます。
刑事手続きの段階に応じて目指すべき防御活動の目標は以下の通りです。
- 捜査機関に傷害事件がバレる前:早期の示談成立で刑事事件化自体を回避する
- 捜査機関に傷害事件がバレた後:在宅事件処理
- 警察に逮捕された後:微罪処分
- 検察官に送致された後:不起訴処分
- 公訴提起された後:執行猶予付き判決、罰金刑(傷害事件の詳細次第では「無罪」)
弁護士は傷害事件で逮捕される前に自首するべきか否かを判断してくれる
傷害事件について警察から連絡がない状況なら、「自首」という選択肢も有効な防御方法です。
自首とは、「罪を犯し、まだ捜査機関に発覚しない前に、犯人自ら進んで犯罪事実を申告し、処罰を求める意思表示」のことです(刑法第42条第1項)。
自首をした場合には、自ら出頭した真摯性が重視されて、「刑の任意的減軽」という効果を期待できます。たとえば、自首をせずに逃げ回っていれば「逃亡のおそれ」があることを理由に逮捕処分が下される可能性が高いですが、自首をした時点で「逃亡のおそれはない」と判断されるので、在宅事件処理を獲得しやすくなるでしょう。
ただし、すべての傷害事件について自首が適切な選択肢になるわけではありません。たとえば、傷害事件を起こしたのが9年前の場合、公訴時効完成までは残り1年です。9年間警察から連絡がないということは捜査活動が進んでいないと理解するのが素直ですし、そもそも、被害届が出されているかどうかも疑問が残ります。犯人自身が更生を果たしているのなら、今さら過去の犯罪行為を警察に告白するのではなく、このまま公訴時効完成を待つ方が合理的と考えられます。
刑事実務に詳しい弁護士なら、傷害事件の詳細を聞き取ったうえで、現段階で自首をするべきか否かを冷静に判断してくれます。また、自首をする道を選択する場合には、警察に出頭した際にどのような供述をするべきかについてもアドバイスを提供してくれるでしょう。
なお、弁護士には守秘義務が課されているので、「弁護士に通報されるか不安なので過去の傷害事件について相談しにくい」という心配をする必要はありません。
刑事責任以外の法律問題にも配慮してくれる
傷害事件を起こして逮捕された場合、刑事責任以外にもさまざまな法律問題・トラブルを抱えるリスクが生じます。
刑事弁護の実績豊富な専門家は「刑事事件が実生活に与える影響」をしっかり理解しているので、加害者の置かれた立場・環境を踏まえてさまざまな配慮を尽くしてくれるでしょう。
傷害事件を起こしたときに発生する可能性があるリスクの一例として、以下のものが挙げられます。刑事弁護を任せた専門家にそのまま処理を依頼すればスムーズです。
- 配偶者との離婚問題(離婚の成否、慰謝料、財産分与、親権など)
- 学校から下された処分内容を争いたい
- 会社から下された懲戒処分の内容を争いたい
- 個人情報や誹謗中傷・名誉棄損投稿がネット上に拡散された場合の削除請求
傷害事件で逮捕されるか不安なときは刑事事件に強い弁護士へ相談しよう
傷害事件を起こした場合、逮捕されるか否かにかかわらず、できるだけ早いタイミングで被害者と示談交渉をスタートするのが何より重要です。
なぜなら、示談成立によって軽い刑事処分を獲得できるからです。また、捜査機関が傷害事件を認知する前に示談が成立すれば、刑事事件化自体の回避も期待できます。
これらのメリットを享受するには、犯罪被害者との間で冷静かつ穏便に話し合いを進めることができるかが鍵になります。刑事事件や示談交渉の実績豊富な専門家に相談をして、示談交渉等の防御活動を展開してもらいましょう。