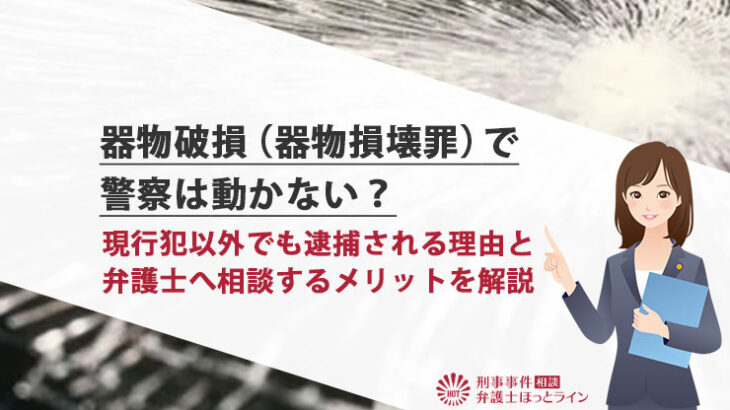「器物損壊罪程度で警察は動かない」「器物損壊罪は現行犯以外逮捕されない」というのは間違いです。なぜなら、器物損壊罪は刑法典に規定される犯罪のひとつであり、器物損壊を証拠付ける物証や目撃者の証言が揃っていれば、後日逮捕状に基づく通常逮捕手続きが実施されるからです。
つまり、一般的に軽微な犯罪類型に分類される器物損壊罪であったとしても、逮捕・勾留によって長期間身柄拘束されたり、場合によっては実刑判決が下されたりする可能性があるということです。
そこで今回は、以下5点についてわかりやすく解説します。
- 器物損壊罪の構成要件と法定刑
- 器物損壊罪で警察は動かないと言われる理由
- 器物損壊罪で逮捕されるときの刑事手続きの流れ
- 器物損壊罪で立件されたときに生じるデメリット
- 器物損壊罪の容疑をかけられたときに弁護士へ相談するメリット
器物損壊事件を起こしてしまったときや、警察から器物損壊について問い合わせがあったときには、示談経験や刑事弁護実績豊富な弁護士への相談が不可欠です。
刑事手続き初期段階から状況に応じた防御活動を展開することによって、身柄拘束処分や刑事事件化自体を回避できるでしょう。
目次
器物損壊罪とは
器物損壊罪とは、「公用文書等、私用文書等、建造物等以外の他人の物を損壊または傷害したとき」に成立する犯罪類型のことです(刑法第261条)。
まずは、器物損壊罪の構成要件や法定刑について解説します。
器物損壊罪の構成要件
器物損壊罪の構成要件は以下3点です。
- 他人の物(公用文書等、私用文書等、建造物等以外)
- 損壊または傷害
- 故意
器物損壊罪の客体
第1に、器物損壊罪の客体は「公用文書等、私用文書等、建造物等以外の『他人の物』」に限定されています。なぜなら、器物損壊罪は公用文書等毀棄罪(刑法第258条)、私用文書等毀棄罪(同法第259条)、建造物等損壊罪(同法第260条)の補充規定として位置付けられるからです。
たとえば、動産、不動産、電磁的記録媒体だけではなく、法令上違法なもの(法令違反の電話施設や公職選挙法違反のポスターなど)や法禁物などが幅広く含まれます。
したがって、「自分の物」は器物損壊罪の客体に含まれないのが原則です。ただし、自己の物であったとしても、差し押さえを受け、物件を負担し、賃貸し、または、配偶者居住権が設定されたものを損壊または傷害したときには、器物損壊罪などの容疑で逮捕される点に注意が必要です(同法第262条)。
器物損壊罪の実行行為
第2に、器物損壊罪の実行行為は「損壊または傷害」です。「損壊」には、物の物理的な損壊だけではなく、物の効用を害する一切の行為が含まれます。
たとえば、過去の判例及び裁判例では、以下のような行為も「損壊」に該当すると判断されています。
- 食器に放尿する行為(大判明治42年2月16日)
- 掛け軸に「不吉」という文字を墨書する行為(大判大正10年3月7日)
- 家屋を建設するために地ならしした敷地を掘り起こして畑地とする行為(大判昭和4年10月14日)
- 学校の校庭に杭を打ち込んで授業などの学校活動に支障を生じさせる行為(最決昭和35年12月27日)
- 盗難及び火災予防のために埋設貯蔵されているガソリン入りドラム缶を発掘する行為(最判昭和25年4月21日)
- 施設の塀に赤色スプレーで落書きをする行為(福岡高判昭和56年3月26日)
なお、器物損壊罪の実行行為のひとつである「傷害」とは、客体が動物の場合に用いられる法律用語であり、「損壊」と意味する内容は同じです。たとえば、他人が飼育しているペットを殺傷したり、養魚池から鯉を流出させて逃がしたりする行為は、「傷害」に該当することを理由に器物損壊罪で処罰されます。
器物損壊罪の主観的構成要件
第3に、器物損壊罪は故意犯なので、「他人の物を損壊または傷害すること」に対する認識・認容が必要です。
たとえば、うっかり他人の物を損壊してしまった場合(故意ではない場合)、器物損壊罪は過失犯に対する規定が存在しないため、故意を欠くことを理由に無罪と扱われます。
また、本当は他人の物なのに自分の物だと勘違いをして壊してしまった場合、器物損壊罪の客体に対する認識を欠くため、刑事処罰が科されることはありません。
器物損壊罪の法定刑
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑、科料」です(刑法第261条)。
器物損壊罪は比較的軽微な犯罪類型に位置付けられること、執行猶予付き判決の対象は「3年以下の懲役刑または禁錮刑、10万円以下の罰金刑」であることを踏まえると、器物損壊罪の容疑で逮捕・起訴された場合に初犯でいきなり実刑判決が言い渡される可能性はそう高くはないでしょう。
ただし、損壊によって高額被害が発生したケースや、被害者との間で示談が成立しないケースでは、法定刑に実刑判決が掲げられている以上、懲役刑が言い渡されて刑務所への収監を強いられることも否定できません。決して「器物損壊罪程度だから大丈夫だろう」と油断をせずに、警察から連絡があった時点ですみやかに弁護士へ相談をして、効果的な防御活動に専念してもらうべきです。
【注意!】器物損壊と器物破損の違い
「器物破損」と表現されることがありますが、これは正式な法律用語ではありません。
刑法上は、器物損壊罪(器物傷害罪)が正式な呼び方であり、「器物破損罪」は間違いです。
【注意!】器物損壊罪で逮捕されるときは別の容疑をかけられることもある
器物損壊罪の容疑で警察が動き出すと、事件態様や捜査活動の進捗次第では、器物損壊罪以外の容疑で逮捕されることもあります。
たとえば、口論中に相手方の近くにある物を壊したようなケースでは、「物を壊した」という点で器物損壊罪の容疑をかけられると同時に、相手方に向かって有形力を行使したことを理由に「暴行罪」の容疑をかけられ得るでしょう(刑法第208条)。また、実際に相手に怪我を負わせてしまうと、「傷害罪」で逮捕されます(同法第204条)。
また、ショッピングモールの備品をいたずら目的で壊して回ったような事案では、「備品を壊した」という点が器物損壊罪に該当するだけではなく、「いたずら目的でショッピングモールに侵入した」という点に対して「建造物侵入罪」が適用される可能性もあります(同法第130条)。
さらに、道路上を歩いている女性の背後から近付いて体液をかけたような事案では、器物損壊罪や暴行罪で立件されることもありますが、事案の状況次第では「不同意わいせつ罪」に問われ得るでしょう(同法第176条)。
つまり、犯人本人は「器物損壊罪の容疑をかけられる程度だから、仮に警察に発覚したとしても厳しい捜査はおこなわれないだろう」と安易に考えていたとしても、犯人の知らないところで器物損壊罪以外の容疑で本格的な捜査活動が実施される可能性もあるということです。
過去の犯罪行為に対してどのような容疑がかかっているか判然としない以上、念のために弁護士に相談をして、今後予想される捜査活動や問われる刑事責任の内容についてご確認ください。
器物損壊罪は警察は動かないと言われる4つの理由
「器物損壊罪程度なら警察はわざわざ動かない」「器物損壊罪は現行犯以外逮捕されない」と言われることがありますが、これは間違いです。
このような誤解が広がる理由として、以下4点が挙げられます。
- 器物損壊罪は比較的軽微な犯罪類型に位置付けられるから
- 器物損壊罪は親告罪だから
- 器物損壊罪は故意犯だから
- 器物損壊罪を立証する証拠を収集するのは簡単ではないから
器物損壊罪は比較的軽微な犯罪類型だから
「器物損壊罪で警察は動かない」と言われるのは、刑法典のなかで器物損壊罪が比較的軽微な犯罪類型に位置付けられることが多いからです。
- 法定刑の観点
- 被害内容の観点
- 行為の悪質性の観点
まず、器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑、科料」です(刑法第261条)。これは、殺人罪や強盗罪などのいわゆる「重大犯罪」の法定刑と比べると、相当軽微な犯罪類型に位置付けられます。
また、器物損壊によって「物」は壊れますが、裏を返せば、器物損壊によって被害が生じるのは「物」だけとも表現できます。たとえば、殺人罪や傷害罪のように「人の生命や身体、健康」が侵害されるわけではありませんし、不同意性交等罪などの性犯罪のように「人の性的自由」を脅かすものでもありません。薬物事犯のように公共の利益を阻害するわけでもないでしょう。
さらに、同じように人の財産を侵害する窃盗罪や強盗罪が「物を領得して犯人自身のものとして扱う」ことと比較すると、「壊すだけ」という意味において帰責性は小さいと考えられます。
以上の理由から、「軽微な犯罪類型に過ぎない器物損壊罪について警察が捜査活動を展開するはずがない」という誤解が広がっているのが実情です。
しかし、器物損壊罪も刑法典で規定される犯罪であることに間違いはないので、事案の状況次第では警察が本格的な捜査活動を展開する可能性は否定できません。器物損壊に及んだ記憶があるのなら、早期の示談交渉や自首を検討するために、すみやかに刑事事件に強い弁護士までご相談ください。
器物損壊罪は親告罪だから
器物損壊罪は親告罪です(刑法第264条)。被害者などの告訴権者による告訴がなければ逮捕・起訴される心配はありません。
たとえば、自宅の窓ガラス1枚程度が壊された程度なら、わざわざ警察に通報して刑事手続きに対応することを面倒だと感じる被害者は多いです。被害額も少なく警察の熱心な捜査活動も期待できない以上、泣き寝入りになったとしても自腹で窓ガラスを買い替えることになるため、器物損壊事件について立件されることはないでしょう。
ただし、器物損壊罪が親告罪であるということは、被害者などの告訴権者から提出された告訴状が受理された場合、警察はかならず本格的な捜査活動を実施するということを意味します。いたずら目的で投石をして民家の窓ガラス1枚を割っただけでも、被害者側が告訴に踏み切った場合には、周辺の防犯カメラ映像などが入念にチェックされて犯行・身元の特定に至りかねません。
したがって、器物損壊事件を起こしたときには、早期に被害者との間で示談交渉を開始して、告訴状の提出を回避したり、既に提出された告訴状を取り下げさせたりすることが有効な防御活動になると考えられます。告訴状が存在しない以上、器物損壊を裏付ける証拠がどれだけそろっていても警察は捜査活動を展開できなくなるので、すみやかに示談実績豊富な弁護士までご相談ください。
器物損壊罪は故意犯だから
器物損壊罪は故意犯であり、過失犯は処罰対象外です。
つまり、器物損壊罪の容疑について立件をするには、警察側は器物損壊行為を裏付ける証拠だけではなく、「犯人が器物損壊当時、器物損壊行為に対する認識・認容を有していたこと」を基礎付ける証拠も集めなければいけないということです。
たとえば、被害額が高額だったり、周辺エリアで同種手口の器物損壊事件について複数の被害申告がなされていたりするような悪質なケースなら、警察も本腰を入れて捜査活動を展開してくれますし、客観的状況から犯人の故意を認定する作業は難しいことではありません。これに対して、うっかり物を壊してしまったときや、泥酔中に記憶がない状態で物を壊してしまったときのように、犯人の故意を認定しにくい微妙な事案では、警察は労力を割いて捜査活動を展開することに抵抗感を示す可能性が高いです(軽微な事案では刑事事件化よりも民事的解決を優先する傾向にあります)。
ただし、故意の認定は客観的証拠に基づいておこなわれるものである以上、「加害者側には明確な故意はなかったのに状況証拠から刑事事件化されてしまう」という事態におちいりかねません。捜査機関側の収集した証拠に対して明確な反論をしなければ不利な刑事処分が下される危険性が高まるので、器物損壊事件について警察から出頭要請がかけられたときにはかならず弁護士に相談をして、取調べでの供述方針などについてアドバイスをもらうべきでしょう。
器物損壊罪は証拠を収集するのが難しいから
「器物損壊罪は証拠を収集するのが難しいため現行犯以外では逮捕されにくい」という特徴があります。
ただし、現行犯逮捕以外の方法では一切逮捕されないというわけではない点に注意が必要です。特に、近年ではドライブレコーダーを搭載した車両が増えていますし、自宅や店舗など街中に防犯カメラ映像が設置されているため、器物損壊行為に及んだ瞬間や逃走中の様子を記録した映像がどこかに残っている可能性が高いです。そして、過去の器物損壊行為を立証するだけの証拠が揃った場合、警察から任意の出頭要請がかかったり、通常逮捕手続きに移行したりします。
したがって、器物損壊行為について現行犯逮捕を免れることができたとしても「警察は動かないだろう」と油断をしきるのは非常に危険だと考えられます。現段階で警察から連絡があるか否かにかかわらず、かならず弁護士へ相談をして自首や示談交渉について検討してもらいましょう。
器物損壊罪で逮捕されるときの刑事手続きの流れ
器物損壊罪が立件されるときの刑事手続きの流れは以下の通りです。
- 器物損壊事件について警察から接触がある
- 器物損壊罪の容疑について警察段階の取調べが実施される
- 器物損壊事件が検察官に送致される
- 器物損壊罪の容疑について検察段階の取調べが実施される
- 検察官が器物損壊事件を公訴提起するか否か判断する
- 器物損壊事件が刑事裁判にかけられる
器物損壊について警察から接触がある
器物損壊事件に関する刑事手続きは「警察との接触」によってスタートします。
警察からの接触方法は状況に応じて以下3パターンに分類されます。
- 器物損壊の現場で「現行犯逮捕」される
- 過去の器物損壊行為について「通常逮捕(後日逮捕)」される
- 過去の器物損壊行為について「任意の出頭要請・事情聴取」がおこなわれる
器物損壊罪で現行犯逮捕されるケース
現行犯逮捕とは、「現行犯人(現に罪を行い、または、罪を行い終わった者)に対する身柄拘束処分」のことです刑事訴訟法第212条第1項。
現行犯逮捕は、捜査機関だけではなく一般私人がおこなうことも可能です。また、逮捕状なしで実施される点(令状主義の例外)も特徴として挙げられます(同法第213条)。
たとえば、器物損壊罪の容疑で現行犯逮捕される場合として、器物損壊行為の現場を目撃した第三者や被害者が110番通報してかけつけた警察官に取り押さえられるケースや、器物損壊行為の現場を目的した被害者・第三者に身柄を取り押さえられるケースが挙げられます。
現行犯逮捕によって身柄を押さえられた場合には、そのまま警察署に連行されて取調べを受ける必要があります。少なくとも、身柄拘束をされてから警察で実施される取調べが終了するまでは家族や会社に連絡を入れることはできません。
器物損壊行為の犯行現場から逃走しても準現行犯逮捕される場合がある
器物損壊行為に及んだ現場から逃走すれば現行犯逮捕を回避できるわけではない点に注意が必要です。
なぜなら、逮捕状不要の現行犯逮捕は「準現行犯逮捕」という形で犯行現場以外の場面にも拡張されているからです。
準現行犯逮捕とは、「以下4つの要件のいずれかを満たす者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときに実施される無令状の身柄拘束処分」を意味します(刑事訴訟法第212条第2項)。
- 器物損壊犯人として追呼されているとき
- 贓物や明らかに器物損壊の用に供したと思われる兇器などの証拠物を所持しているとき
- 身体は被服に器物損壊行為に及んだ顕著な証跡があるとき
- 「器物損壊犯人だ!」と誰何されて逃走しようとするとき
ただし、準現行犯逮捕は現行犯逮捕の拡張類型であることから、犯行現場から相当遠く離れていたり、また、犯行時から何日も経過した後に捜査機関に見つかったときには、通常逮捕や緊急逮捕によって身柄が押さえられることになります。
器物損壊罪で通常逮捕(後日逮捕)されるケース
通常逮捕とは、「裁判官の事前審査を経て発付される逮捕状に基づき実施される身柄拘束処分」のことです(刑事訴訟法第199条第1項)。現行犯逮捕とは異なって強制処分に関する「令状主義」が適用されるため、過去の器物損壊事件に対する通常逮捕手続きではかならず逮捕状が必要とされます。
逮捕状の発付審査では、「逮捕の理由(被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること)」「逮捕の必要性(留置の必要性=被疑者の身柄を強制的に拘束した状態で取調べを実施する必要性があること)」の2つの要件がチェックされます(犯罪捜査規範第118条、同規範第122条)。
たとえば、器物損壊事件が以下のような事情を有する場合、器物損壊罪の容疑で通常逮捕される可能性が高いでしょう。
- 被疑者が住所不定・無職・職業不詳など身元が不確かで「逃亡するおそれ」がある場合
- 被疑者の前科・前歴がある場合
- 器物損壊事件などの余罪への関与が疑われる場合
- 犯行時に着用していた衣服、物を壊したときに使用した道具など、器物損壊事件に関する「証拠を隠滅するおそれ」がある場合
- 器物損壊によって生じた被害額が高額な場合
- 器物損壊事件の被害者との間で示談が成立していない場合、被害者の処罰感情が強い場合
- 警察からの任意の出頭要請を拒否した場合
- 任意の事情聴取中に黙秘・否認した場合、客観的証拠と供述内容に明らかに矛盾がある場合
過去の器物損壊事件は3年経過で逮捕リスクが消滅する
過去の器物損壊事件を裏付ける証拠・証言が存在する場合でも、器物損壊行為が終わったときから3年が経過することによって警察に逮捕されるリスクは完全に消滅します。なぜなら、器物損壊罪は3年で公訴時効が完成するからです(刑事訴訟法第250条第2項)。
公訴時効とは、「犯罪行為が終わったときから一定期間(器物損壊罪の場合は3年)が経過することによって検察官の公訴提起権を消滅させる制度」のことです。検察官の公訴提起権が消滅するということは、当該事件について刑事裁判を経て有罪判決が下される可能性がゼロになることを意味するため、その付随的効果として、警察に逮捕されることもなくなります。
ただし、器物損壊事件を起こしたにもかかわらず、最初から「時効逃げ切り」を狙うのはおすすめできません。なぜなら、先ほど紹介したように、過去の器物損壊事件は防犯カメラ映像などに映像が記録されている可能性が高いからです。たとえば、器物損壊事件を起こして数カ月後、1~2年後にいきなり警察が自宅にやってくるというケースも少なくありません。
したがって、数カ月以上前に起こした器物損壊事件について警察から一切問い合わせがない状況だとしても、念のために現段階で弁護士に相談をしておくことが望ましいと考えられます。今後立件される可能性や、現段階で自首するべきか否かについてアドバイスをしてくれるでしょう。
器物損壊罪で任意捜査が実施されるケース
過去の器物損壊事件が警察に発覚したとしても、通常逮捕手続きではなく、任意捜査という手法で捜査活動が展開される場合が少なくありません。また、器物損壊事件については、最初は現行犯逮捕・通常逮捕によって身柄が拘束されたとしても、途中から身柄拘束処分が解かれる可能性も高いです。「身柄拘束がない状態での捜査活動」という意味で、これらの状況・刑事手続き処理は「在宅事件」と呼ばれます。
任意捜査とは、「捜査対象者の同意があることを前提に実施される捜査活動」のことです。たとえば、警察から出頭要請がかけられて、警察署やその他指定された場所などで事情聴取がおこなわれます。
器物損壊事件について任意捜査が選択されるのは以下のようなケースです。
- 器物損壊事件の被害額が少額の場合
- 器物損壊事件について他の余罪に関与した疑いがない場合
- 器物損壊事件の被害者との間で示談が成立している場合
- 警察からの出頭要請に素直に応じている場合
- 任意の事情聴取で器物損壊行為について自供して真摯に反省の態度を示している場合
- 前科前歴のない初犯の場合
- 氏名・住居・職業が明らかで、逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合
現行犯逮捕・通常逮捕とは違って、器物損壊罪について警察から任意での捜査協力を求められたとしても、これに応じる義務はありません。たとえば、「仕事が忙しいから」「警察に行くのは怖いから」などの理由で出頭自体を拒絶しても良いです。また、警察署の事情聴取で黙秘をしてもその行為自体に対してペナルティが科されることはありません。さらに、「捜査員の態度が気に食わないから」という理由で事情聴取を切り上げて帰宅することも可能です。
ただし、任意の出頭要請や事情聴取に応じないと、その不誠実な態度が「逃亡や証拠隠滅のおそれがあること」の証明に利用されるので、通常逮捕手続きに移行するリスクに晒される点に注意が必要です。つまり、器物損壊事件に関する任意捜査に応じる義務は存在しないものの、応じなければ身柄拘束処分という大きなデメリットを強いられるということです。
なお、器物損壊事件が在宅事件として扱われたとしても、「身柄拘束されない」というだけで、不起訴処分や無罪が確定するわけではありません。たとえば、任意の事情聴取を重ねた結果、器物損壊罪の容疑が固まった場合には、起訴処分(在宅起訴)により刑事裁判にかけられて有罪判決が下されるでしょう。
したがって、器物損壊事件について警察から出頭要請がかかった場合には、出頭前に弁護士へ相談をして、供述方針を固めてもらったり、被害者との間での示談成立を急いでもらったりするべきだと考えられます。
器物損壊について警察で取調べを受ける
器物損壊事件が警察に発覚すると、「警察段階の取調べ」が実施されます。
逮捕された場合
まず、器物損壊罪の容疑で現行犯逮捕・通常逮捕された場合、警察段階で実施される取調べの制限時間は「48時間以内」です(刑事訴訟法第203条第1項)。
身柄拘束期間中に実施される取調べには受忍義務があるので、被疑者はかならず取調べを受ける必要があります。
また、身柄拘束期間中は取調室と拘置所・留置場の往復だけで、自宅に戻ることや外部に電話で連絡することも認められません(逮捕期間中に被疑者と自由に面会できるのは弁護士だけです)。
逮捕されていない場合
次に、器物損壊罪の容疑で任意の事情聴取がおこなわれる場合、警察段階の取調べには制限時間が設けられていません。
そのため、送検されるまでに数週間~数カ月を要することもありますが、事情聴取以外は普段通りの生活を送ることができますし、また、事情聴取の日程を捜査機関側とスケジューリングすることも可能です。
ただし、捜査機関の出頭要請にまったく応じない状況が続くと逮捕状が請求されて強制的な身柄拘束処分に移行してしまうので、捜査協力要請にはできるだけ誠実に対応しましょう。
器物損壊事件が送検される
器物損壊事件について警察段階の取調べが終了すると、身柄・事件・証拠物がすべて「検察官に送致」されます(刑事訴訟法第246条本文)。
なお、器物損壊罪は「微罪処分」の対象ではないので、警察段階の取調べ段階で刑事手続きが終了することはありません。
器物損壊について検察官から取調べを受ける
器物損壊事件について警察段階の取調べが終了すると、送検後、「検察段階の取調べ」が実施されます。
逮捕された場合
器物損壊事件を起こして警察に逮捕された後、送検されると、検察段階で「原則24時間以内」の取調べが実施されます(刑事訴訟法第205条第1項)。身柄拘束期間中に実施される取調べである以上、被疑者は取調べを拒絶することはできませんし、自宅に帰宅することも許されません。また、逮捕期間中は接見禁止処分が下されることが多いため、弁護士以外の第三者と面会できないのも警察段階の取調べと同様です。
検察段階の取調べで注意が必要なのは、捜査の進捗状況次第では検察段階の取調べ期間が延長される可能性があるということです。具体的には、やむを得ない理由によって「警察段階48時間以内と検察段階24時間以内の合計72時間以内」の制限時間を遵守できないときには、検察官の勾留請求によって身柄拘束期間が10日間~20日間の範囲で例外的に延長されることがあります(同法第206条第1項、同法第208条各項)。
器物損壊事件で逮捕された後、勾留請求される可能性が高いのは、以下のようなケースです。
- 器物損壊事件について被疑者が黙秘をしている場合
- 器物損壊事件に関する客観的証拠や目撃者証言と明らかに矛盾する供述をしている場合
- 防犯カメラ映像などの解析、各種鑑定や実況見分に時間を要する場合
- 被害者や目撃者が多数存在しているために参考人聴取に時間を要する場合
- 同種の器物損壊事件について複数の被害届が出されており余罪への関与が疑われる場合
- 氏名・住所不定で逃亡のおそれがある場合
逮捕されていない場合
器物損壊事件が在宅事件として扱われている場合、警察段階と同じように、検察段階の取調べにも制限時間は設けられていません。担当検察官から要請がかかったタイミングで検察庁に出頭し、あくまでも任意を前提に取調べが実施されます。
ただし、器物損壊事件が在宅扱いになっている場合には警察段階でじっくりと時間をかけて捜査活動が実施されることが多いので、検察段階の取調べが数カ月にわたって長期化する可能性は低いでしょう。
器物損壊について検察官が起訴・不起訴を決定する
逮捕・勾留期限が到来するまで、また、検察官の公訴提起判断に必要な証拠が充分に揃ったとき、検察官が起訴・不起訴を決定します。
まず、起訴処分とは「器物損壊事件を公開の刑事裁判にかける旨の訴訟行為」のことです。日本の刑事裁判の有罪率は約99%以上なので、検察官が起訴処分を下した時点で有罪・前科が事実上確定します。
これに対して、不起訴処分とは「器物損壊事件を公開の刑事裁判にかけず、検察限りの判断で刑事手続きを終結させる旨の意思表示」を意味します。不起訴処分が下された時点で刑事手続きが終了するので、その時点で身柄が釈放されて、有罪や前科のリスクを回避できます。
つまり、「有罪になりたくない」「前科をつけたくない」と希望する場合には、「刑事裁判で無罪判決を獲得すること」ではなく「検察官の不起訴処分を獲得すること」が現実的な防御目標になるということです。特に、器物損壊罪の容疑で逮捕された場合には公訴提起判断までの期間が限られているので、できるだけ早いタイミングで刑事事件に強い弁護士へ相談をすることをおすすめします。
器物損壊について公開の刑事裁判にかけられる
器物損壊罪の容疑で起訴された場合、起訴処分が下されてから1カ月~2カ月後を目安に刑事裁判が開廷されます。
まず、公訴事実について争いがない場合には、第1回公判期日で結審し、後日判決が言い渡されるのが通例です。これに対して、公訴事実に争いがある場合(器物損壊の故意認定を争いたいときなど)には、複数回の公判期日をかけて弁論手続き・証拠調べ手続きが実施されます。
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑、科料」と定められている以上、器物損壊罪が比較的軽微な犯罪類型に位置付けられるとしても、実刑判決が下される可能性も否定できません。
そのため、器物損壊罪の容疑で起訴されたときには、罰金刑や執行猶予付き判決獲得を目指した防御活動に専念することになります。実刑判決が確定すると刑期を満了するまで刑務所への服役を強いられるので、かならず刑事裁判経験豊富な私選弁護人までご依頼ください。
器物損壊罪で警察に逮捕されたときに生じるデメリット4つ
器物損壊罪の容疑で警察に逮捕されたときに生じるデメリットは以下4点です。
- 器物損壊罪の容疑で逮捕されると長期間の身柄拘束リスクに晒される
- 器物損壊罪で逮捕されたことが勤務先にバレると懲戒処分が下されかねない
- 器物損壊罪で逮捕されたことが学校にバレると退学処分などのリスクに晒される
- 器物損壊罪の容疑で逮捕・起訴されると前科がつく
器物損壊罪でも長期間身柄拘束される可能性はゼロではない
器物損壊罪は一般的には軽微な犯罪類型に位置付けられるものの、逮捕された以上は、長期間身柄拘束されるリスクに晒されます。
そもそも、器物損壊罪は親告罪なので、警察段階で微罪処分に付されることはありません。そのため、逮捕されるとかならず送検されるため、かならず検察官の公訴提起判断まで身柄拘束期間が継続します。つまり、逮捕段階だけ最長72時間、勾留されると最長23日間の身柄拘束期間が生じるということです。
たとえば、捜査機関に身柄を押さえられている間は、弁護士以外の第三者(家族、友人、会社関係の人)と面会や連絡を取ることができません。また、自宅に戻ることも許されないため、逮捕されたことを学校や会社に隠し通すのは難しいでしょう。さらに、身柄拘束期間中は厳しい取調べと拘置所生活が続くので、心身に過度なストレスを強いられます。
このように、仮に不起訴処分を獲得できたとしても、身柄拘束状態が生じただけで数々のデメリットが生じかねません。早期の防御活動次第で身柄拘束処分の回避・軽減を目指せるので、警察から器物損壊事件について問い合わせがある前に弁護士へ相談するのが理想でしょう。
器物損壊罪で逮捕されたことが会社に知られると懲戒処分が下される
器物損壊罪の容疑で逮捕されると、身柄拘束期間が原因で会社に逮捕されたことがバレる可能性が高いです。
そして、警察に逮捕されたことやその後有罪になったことが会社にバレると、就業規則のルールにしたがって懲戒処分が下されます。懲戒処分は「戒告、譴責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇」に分類されますが、厳しい懲戒ルールを定めている企業の場合には、器物損壊罪で逮捕・有罪になっただけでクビになることもあり得るでしょう。
会社にバレずに器物損壊事件を終わらせるには、「逮捕されずに在宅事件処理を目指すこと」「不起訴処分獲得を目指すこと」が何より重要です。早期の防御活動が大切なので、逮捕手続きに移行したり警察から出頭要請がかかる前に、今すぐ弁護士までご相談ください。
器物損壊罪で逮捕されたことが学校に知られると何かしらの処分が下される
学生が器物損壊事件を起こして逮捕されると、学校バレのリスクに晒されます。ただし、社会人の場合とは違って、数日程度の欠席期間であれば別の言い訳で誤魔化すことも不可能ではありません。
逮捕・勾留によって長期間身柄拘束されたり、実名報道によって器物損壊事件のことがバレてしまった場合には、学則・校則の規定にしたがって処分内容が決定されるのが一般的です。たとえば、犯罪に及んだ学生に対して厳しい考え方を有する学校なら一発で退学処分が下されかねませんし、他方で、学生の更生・教育を重んじる校風であれば一時的な出席停止や戒告などの軽い処分で済むこともあるでしょう。
学校にバレて何かしらの処分が下されると学歴にキズがつくため、その後の進学や就職活動が阻害されます。早期の示談交渉や自首によって学校にバレないうちに刑事手続きを終結できるので、すみやかに弁護士まで今後の防御方針についてご相談ください。
器物損壊罪で逮捕・起訴されても前科がつく
器物損壊罪の容疑で起訴されると、有罪判決が下された結果、前科がつく可能性が高いです(実刑判決だけではなく、罰金刑や執行猶予付き判決でも前科は残ります)。
前科がつくと、今後の社会生活に以下の悪影響が生じます。
- 前科情報は履歴書の賞罰欄への記載義務が生じるので、就職活動・転職活動が不利になる(隠すと「経歴詐称」)
- 職業や資格次第では前科を理由に就業制限がかかるので、経済的にひっ迫するリスクがある(士業、金融業、警備員など)
- 前科や逮捕歴を理由に離婚を言い渡されると最終的には拒絶できない(法定離婚事由に該当するため)
- 前科が原因でビザやパスポートが発給されないと、海外旅行や海外出張に制限が生じる
- 前科者が再犯に及ぶと刑事処分や判決内容が重くなる可能性が高い
「前科がつくのは避けたい」と希望するなら「不起訴処分の獲得」が絶対です。
検察官の公訴提起判断までの時間は限られているので、早期の示談成立や自首などの防御活動によって不起訴処分獲得や刑事事件化の回避を目指しましょう。
器物損壊罪で立件されるか不安なときに弁護士へ相談するメリット6つ
ご家族が器物損壊罪の容疑で逮捕された場合や、過去の器物損壊事件について警察から出頭要請がかかった場合には、できるだけ早いタイミングで弁護士へ相談することをおすすめします。
なぜなら、刑事事件に強い弁護士への相談によって以下6点のメリットを得られるからです。
- 弁護士は被害者との間で早期の示談成立を実現してくれる
- 器物損壊事件が警察にバレる前なら弁護士は自首の是非を検討してくれる
- 身柄拘束処分の回避・短縮化に向けた弁護活動を期待できる
- 弁護士は不起訴処分獲得に向けて尽力してくれる
- 弁護士は略式手続きに同意するべきか判断してくれる
- 弁護士は執行猶予付き判決獲得に向けて尽力してくれる
被害者との間で早期の示談成立を実現してくれる
刑事事件に強い弁護士へ相談すれば、器物損壊事件の被害者との間ですみやかに示談交渉を開始してくれます。
示談とは、「器物損壊事件の当事者同士で解決策について直接話し合いを行い、和解契約を締結すること」です。たとえば、加害者が被害者に示談金を支払う代わりに、告訴状の取り下げなどが約束されます。
本来、示談は民事的な問題(損害賠償責任の問題)に関することなので刑事責任とは無関係ですが、刑事実務では「被害者との間で示談が成立していること」が軽い刑事処分の要素のひとつとして考慮されるのが実情です。
そして、器物損壊事件に関する示談交渉を弁護士に依頼することで以下6点のメリットを得られます。
- 器物損壊事件の被害者の連絡先を警察経由で入手しやすい
- 加害者本人が直接交渉を求めるよりも弁護士が代理した方が被害者側の冷静な対応を期待できる
- 相場と乖離した高額の示談金をふっかけられるリスクを予防できる
- 早期の示談成立によって告訴状の取り下げを期待できる
- 警察への被害申告前なら、示談成立によって刑事事件化自体を回避できる(前歴も残らない)
- 示談交渉に要する労力・契約書の準備などの手間をすべて弁護士に任せることができる
特に、器物損壊罪が親告罪であることを踏まえると、示談成立による告訴状の取り下げが非常に重要な意味をもちます。
検察官の公訴提起判断までに示談が成立しなければ起訴リスクが高まるので、早期の示談交渉で不起訴処分獲得を目指してもらいましょう。
器物損壊事件が警察にバレる前なら自首の是非を検討してくれる
器物損壊事件が警察にバレる前なら、自首をするのも選択肢のひとつです。
自首とは、「まだ捜査機関に発覚しない前に、犯人自ら進んで器物損壊事件を起こした事実を申告し、刑事処罰を求める意思表示」のことです(刑法第42条第1項)。警察に器物損壊事件を知られる前、または、警察に器物損壊犯人であると特定される前に自首をすれば、「刑の任意的減軽」というメリットを得られます。
たとえば、器物損壊事件の被害者との示談交渉が難航して告訴状を提出されそうな状況に追い込まれたとき、先手を打って自首をしておくことによって、後々告訴状が提出されたとしても軽い刑事処分の可能性が高まるでしょう。
ただし、器物損壊事件を起こしてからすでに2年が経過しており、公訴時効完成による逃げ切りを期待できそうな状況なら、わざわざ自首をする実益は少ないと言えるでしょう。
現段階で自首をするべきか否かについて弁護士は冷静に状況分析してくれるので、器物損壊事件について警察から連絡がくる前にご相談ください。
身柄拘束処分の回避・短縮化に向けた弁護活動を期待できる
刑事事件に強い弁護士に依頼すれば、身柄拘束処分の回避・短縮化に向けた防御活動を期待できます。
ここまで紹介したように、器物損壊罪の容疑で逮捕されると、最長23日間身柄拘束されるリスクに晒されます。また、複数の器物損壊事件で立件された場合には事件ごとに身柄拘束期間がカウントされるので、最悪の場合には社会生活から数カ月以上断絶されかねません。
逮捕・勾留中の被疑者と自由に面会できるのは弁護士だけなので、時々刻々と推移する取調べ状況に対する適切な供述方針を明確化してくれます。また、逮捕される前に自首や示談交渉を検討することによって、身柄拘束自体の回避も目指してくれるでしょう。
不起訴処分獲得に向けて尽力してくれる
刑事事件に強い私選弁護人に依頼すれば、不起訴処分獲得に向けた防御活動を期待できます。
そもそも、刑事事件を起こしたとき、かならず刑事裁判にかけられるわけではありません。なぜなら、不起訴処分が下されるシチュエーションは以下3つに分類されるので、器物損壊事件を起こしたことが原因で逮捕されたとしても、不起訴処分を獲得することは可能だからです。
- 嫌疑なし:器物損壊事件を起こした疑いがない場合
- 嫌疑不十分:器物損壊事件を立証する証拠が充分ではない場合
- 起訴猶予:器物損壊事件を起こした証拠はそろっているものの、諸般の事情を総合的に考慮すると刑事裁判にかける必要がない場合
器物損壊事件の容疑で逮捕される大半のケースでは「起訴猶予処分」を目指すことになります(刑事訴訟法第248条)。
起訴猶予処分に付するか否かを判断するときには、犯人の性格・年齢・境遇・犯罪の軽重・情状・犯罪後の情況などの諸般の事情が総合的に考慮されるので、不起訴処分獲得実績豊富な弁護士に武器になる証拠を用意してもらいましょう。
略式手続きに同意するべきか判断してくれる
器物損壊罪の容疑で起訴される場合には、略式手続きに同意するか否かが重要なポイントになります。
略式手続き(略式起訴・略式命令・略式裁判)とは、「簡易裁判所の管轄に属する刑事事件について100万円以下の罰金刑が想定される場合に、被疑者側の同意がある場合に限って、公開の刑事裁判を省略して簡易・簡便な形で罰金刑を確定させる裁判手続き」のことです(刑事訴訟法第461条)。
たとえば、器物損壊罪の容疑で起訴される段階で、検察官が公判で罰金刑を求刑する公算が大きい場合、略式手続きに同意をすれば、公開の刑事裁判手続きを省略して、起訴段階で罰金刑が確定します。これにより、刑事裁判に要する期間を節約されるので、社会復帰を目指すタイミングを大幅に前倒しできるでしょう。
ただし、器物損壊事件の事実関係を争いたい場合などでは、略式手続きの利用によって刑事裁判で反論を主張する機会が失われる点に注意が必要です。無罪を獲得できる可能性は高くないものの、どうしても刑事裁判でしっかりと反論をしたいと希望するのなら、略式手続きには同意してはいけません。
刑事裁判実務に詳しい弁護士に相談すれば、公開の刑事裁判で展開する主張が受け入れられる可能性や、現段階で略式手続きに同意をして罰金刑を妥協点とするメリットなどについて丁寧に解説・分析してくれるでしょう。
執行猶予付き判決獲得に向けて尽力してくれる
器物損壊罪の容疑で起訴されると、弁護士は執行猶予付き判決獲得に向けて刑事裁判でさまざまな防御活動を展開してくれます。
執行猶予とは、「被告人の犯情や事件の諸般の事情を考慮して刑の執行を一定期間猶予できる制度」のことです。「3年以下の懲役刑・禁錮刑・50万円以下の罰金刑の言渡しを受けたとき」という要件を満たす刑事事件が対象です(刑法第25条第1項)。
器物損壊事件のような軽い刑事事件でも、前科・前歴の有無や反省状況、今後の更生可能性や立件された事件の数次第では、実刑犯判決が下される可能性もゼロではありません。服役する期間が長いほど社会復帰が難しくなります。
刑事裁判に強い私選弁護人へ依頼すれば、被告人に有利な情状証拠・証人を集めて執行猶予付き判決獲得に向けて尽力してくれるでしょう。
器物損壊罪で逃げ得を狙うのはハイリスク!弁護士に示談交渉を任せよう
器物損壊罪で警察の捜査対象になると、逮捕や有罪のリスクに晒されます。刑法犯罪のなかでは「軽い犯罪」に位置付けられるものの、起訴されて有罪判決が下されると前科によるデメリットから逃れることができません。
そのため、過去に器物損壊事件を起こした場合や、器物損壊罪の容疑で逮捕された場合には、できるだけ早いタイミングで弁護士へ相談することが不可欠です。早期の示談交渉によって告訴状の取り下げに成功すれば逮捕・起訴を回避できますし、示談成立のタイミング次第では刑事事件化自体も防ぐことができるでしょう。