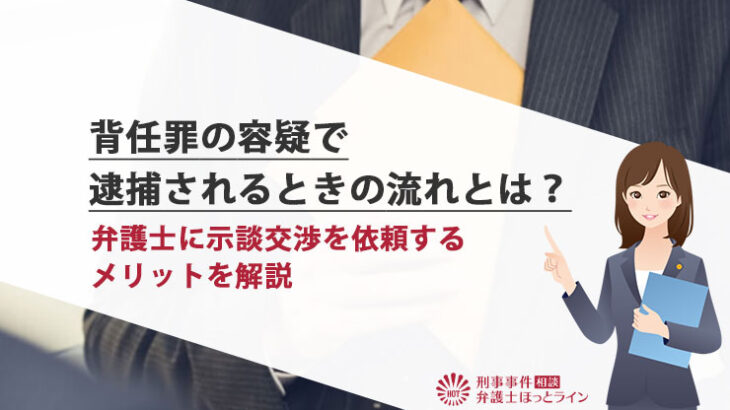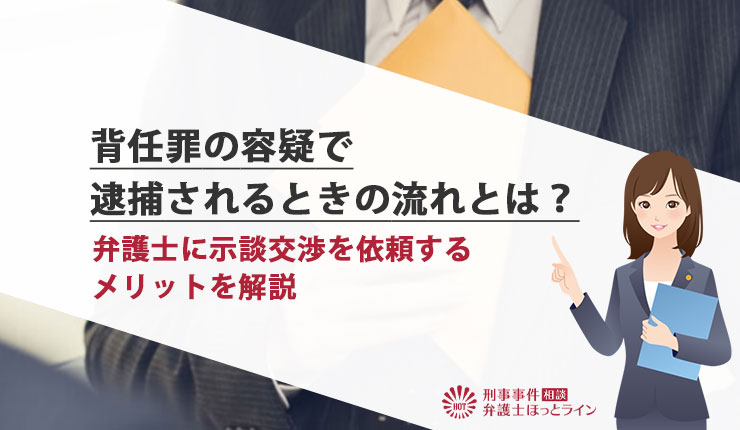
背任罪とは、本来の任務に背く行為によって任務を与えてくれた人の財産を減らしてしまったときに成立する犯罪類型のことです。たとえば、銀行の融資係が経済的信用性の低い企業に融資をして結果的に不渡りを出したような場面で背任罪の成否が問題になります。
背任罪の容疑で逮捕されると、長期間身柄拘束されたり、初犯でも実刑判決が下される可能性があります。また、刑事責任以外にも高額の賠償責任を問われかねません。さらに、会社との委任契約に違反して背任行為を働いたことを理由とする懲戒処分も避けがたいでしょう。
したがって、背任罪の容疑をかけられたときに大切なことは、出来るだけ早いタイミングで弁護士に相談をして、勤務先などの被害者との間で示談交渉を開始して支払い条件などについて話し合いを進めることだと考えられます。
そこで今回は、背任事件を起こして会社などの被害者から刑事訴追の可能性をちらつかせられた方や、背任罪の容疑で警察から連絡があった方のために、以下5点について分かりやすく解説します。
- 背任罪の成立要件・法定刑
- 背任罪と横領罪・詐欺罪の違い
- 背任罪の容疑で逮捕されたときの刑事手続きの流れ
- 背任罪の容疑で逮捕されたときに生じるデメリット
- 背任罪で逮捕されたとき、逮捕されるか不安なときに弁護士へ相談するメリット
当サイトでは、背任罪などの刑事弁護に強い法律事務所を多数掲載しています。「少しでも背任事件の責任を軽減したい」「信頼できる弁護士のサポートを受けたい」とご希望なら、各弁護士の実績などをご参考のうえ、信頼できそうな専門家まですみやかにお問い合わせください。
目次
背任罪の構成要件と法定刑
まずは、背任罪の構成要件と法定刑について解説します。
あわせて、背任罪と類似する特別背任罪・横領罪・詐欺罪との違いなどについても参考にしてください。
背任罪の構成要件
背任罪は、「他人のためにその事務を処理する者が、自己もしくは第三者の利益を図り、または、本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたとき」に成立する犯罪類型のことです(刑法第247条)。
ここから、背任罪の構成要件として以下5点が導かれます。
- 事務処理者
- 任務違背行為
- 財産上の損害
- 背任の故意
- 図利・加害目的
事務処理者
背任罪は、主体が「他人のためにその事務を処理する者(事務処理者)」に限定されている身分犯です(刑法第65条第1項)。傷害罪や窃盗罪とは異なり、誰でも犯せる犯罪ではありません。
事務処理者であるためには、「本人(事務処理の委託者)から事務処理について委託された者」であることが必要です。
まず、委託された事務処理の範囲は、自己が直接担当するものに限られます。たとえば、会社の従業員が偶然知り得た会社の秘密情報を第三者に漏洩したとしても、当該人物が会社の営業秘密の保管・管理の任務を有する役職員でない限り、背任罪は成立しません(神戸地判昭和56年3月27日)。
次に、委託された事務の内容は「財産上の事務」に限定されるとするのが通説的見解です。たとえば、治療を委託された医師が財産上の損害を加える目的で不適切な治療を行い、現に患者に財産上の損害を生じさせた場合でも、そもそも医師の事務が「財産上の事務」に該当しないため、背任罪の容疑で逮捕されることはありません。
さらに、背任罪の主体である事務処理者であるためには、「他人の事務」、つまり、「他人固有の事務」を本人に代わって行う必要があります。たとえば、売買契約における売主の目的物引渡義務・買主の代金支払義務、消費貸借契約における借主の返還義務などは、他人に対して行う事務ではあるものの「自己の事務」を処理しているに過ぎないので、これらの義務に違反したところで背任罪の容疑をかけられることはありません(ただし、別途債務不履行の問題を生じます)。
任務違背行為
背任罪の実行行為は「任務に背く行為(任務違背行為)」です。
そもそも、背任罪の本質は「『信任関係に違背した財産侵害』を処罰すること」とするのが判例通説です(背信説)。そのため、任務違背行為は、委託された事務の性質・内容、義務の実情などの客観的事情を総合的に考慮して、「誠実な事務処理の法的期待に違反したか否か」という観点から判断されます。そのため、背任罪の主体が純粋な代理人に限定されることはありませんし、また、単純な事実行為も任務違背行為に含まれ得ることになります。
たとえば、不良貸し付け(銀行の支店長が、全く回収の見込みがないのに無担保や充分な担保条件を課さずに貸し付けを行う行為)、蛸配当・粉飾決算(実際の赤字を隠蔽する目的から、空の利益を計上して株主にその利益を配当する行為)、自己取引(取締役が取締役会の承認を受けずに会社から金銭の貸し付けを受けるなどの行為)、債務負担行為(会社の役職員がその権限を濫用して会社名義で約束手形の振り出しや手形保証などに及ぶ行為)、冒険的取引(財産上の損害を生じさせる一定リスクのある行為)などは、すべて任務違背行為に該当し得るため、背任罪で逮捕される可能性が生じるでしょう。
財産上の損害
背任罪が成立するためには、「任務違背行為の結果、本人に財産上の損害が発生すること」が必要です。財産上の損害が生じた時点で背任罪は既遂に達します(これに対して、任務違背行為が行われても財産上の損害が発生しなかったときには、背任未遂罪の容疑で逮捕されるにとどまります)。
背任罪における「財産上の損害」とは、「全体財産の減少」のことです。たとえば、任務違背行為によって財産状態の減少がもたらされたとしても、反対給付が存在するなど、減少に見合った財産状態の増加が認められる場合には「財産全体として減少は存在しない」と判断されるので、背任既遂罪の容疑で逮捕されることはありません。
ただし、背任罪における「財産上の損害」は、単純な額面上のプラスマイナスだけで評価されるわけではありません。たとえば、担保を徴することなく金銭を貸し付けた場合、貸し付けた金銭に見合った債権を取得している以上、額面上は「財産上の損害」は生じていないようにも思えますが、貸し付け段階で当該債権の回収が不能・困難と経済的見地から判断できる状況なら、すでに「財産上の損害」が生じていると言っても過言ではないでしょう。
刑事実務でも、「経済的見地における本人の財産状態を評価し、任務違背行為によって本人の財産の価値が減少したとき、または、増加するべき価値が増加しなかったとき」に、「財産上の損害が生じた」と判断しています(最決昭和58年5月24日)。
背任の故意
背任罪は故意犯です。そのため、背任罪の容疑で逮捕されるのは、構成要件該当事実に対する認識・認容がある場合に限られます。
具体的には、「自分が事務処理者であること」「任務違背行為をすること」「任務違背行為によって本人に財産上の損害が生じること」の3点に対する認識・認容がなければ、背任罪で処罰されることはありません。
なお、故意は行為者の主観に関する要件ですが、「背任をするつもりはなかった」と主張するだけでは故意を否定するのは難しいです。というのも、実際の刑事実務では、「背任の故意があったことを基礎付ける客観的証拠」を前提に主観的な故意の有無が判断されるからです。
したがって、会社の業務において予期せず背任罪の容疑をかけられたときには、出来るだけ早いタイミングで弁護士に相談をして、故意を否定する材料を丁寧に主張立証してもらいましょう。
図利・加害目的
背任罪は、故意とは別に、「自己もしくは第三者の利益を図る目的(図利目的)、または、本人に損害を加える目的(加害目的)」という主観的要件が必要とされます。
故意とは別に図利・加害目的という主観的要件が必要なのは、「『本人の利益を図る目的(本人図利目的)』が存在しないこと」を背任罪の成立要件とする趣旨だと理解するのが通説的見解です、たとえば、図利加害目的と本人図利目的が併存するケースでは、2つの目的の主従関係によって背任罪の成否が判断されます(最決平成10年11月25日)。
なお、図利・加害目的における「利益」「損害」の内容は、財産上の利益・損害だけではなく、地位保全・信用面目の維持などの身分上の利益・損害も含まれると解するのが判例です(最決昭和63年11月21日)。
融資を受ける側も背任罪の共同正犯になる場合がある
背任罪が成立する典型的な場面は、銀行の支店長が回収見込みのない企業・個人に充分な担保を提供させることなく金銭を融資するケースです。
このとき、銀行支店長が背任罪で逮捕されるのは当然として、融資を受けた側も「背任罪の共同正犯」の容疑で刑事訴追されることがあります。
たとえば、「任務違背者に影響力を行使し得るような関係を利用したり、社会通念上許容されないような方法を用いるなどして積極的に働きかけて背任行為を強いるなど、背任行為を殊更に利用して借り手側の犯罪としても実行させたと認められるような加功をしたとき」(東京地判平成13年10月22日)だけではなく、「融資担当者の任務違背、本人の財産上の損害について高度な認識を有していたことに加えて、融資担当者が図利・加害目的を有していることを認識し、融資担当者が本件融資に応じざるを得ない状況を利用しつつ本件融資の実現に加担しているとき」(最決平成15年2月18日)、「利害の共通性が存在しない状況でも、融資の実現に積極的に加担したとき」(最決平成20年5月19日)など、個別具体的な事情を前提に、融資を受けた側にも背任罪の成立を認めるのが裁判実務です。
したがって、金融機関の担当者が背任事件を起こしたことを理由に逮捕されたとき、融資を受けた側が強度の働きかけをしていたり、利害関係が一体であると評価される事情が存在する場合には、融資を受けた側にも捜査のメスが入る可能性が高いとご理解ください。結果的に刑事責任を追及されるか否かは別問題として、捜査機関から追及を受けるだけでさまざまなリスクを強いられかねないので、融資担当者が背任事件を起こした情報を入手したときには、念のために弁護士へ相談しておくことを強くおすすめします。
背任罪の法定刑
背任罪の法定刑は、「5年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑」です。
つまり、執行猶予付き判決の対象が「3年以下の懲役刑・禁錮刑・50万円以下の罰金刑の言渡しを受けたとき」であることを踏まえると(刑法第25条第1項)、背任事件を起こした逮捕されると、初犯でも実刑判決が下される可能性があるということです。
したがって、背任罪の容疑で逮捕・起訴されたときには、執行猶予付き判決の対象まで減軽されるような方策を尽くす必要があります。背任事件の経験豊富な弁護士なら、自首減軽・酌量減軽などの方策によって執行猶予付き判決獲得を実現してくれるでしょう。
【注意!】特別背任罪が成立する場面
組織において一定の重要な役割を担っている人物が背任行為に及んだ場合、「特別背任罪」の容疑で逮捕される場合があります。
たとえば、「発起人・取締役・・会計参与・監査役・事業に関する特定事項の委任を受けた使用人などが、自己もしくは第三者の利益を図る目的や株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたとき」には、会社法上の特別背任罪が成立します(会社法第960条第1項)。これらの者が組織経営において重要な役割を担う点に鑑みて、会社法上の特別背任罪の罪に問われるときには、「10年以下の懲役刑もしくは1,000万円以下の罰金刑(併科あり)」の範囲で処断されます。
その他、清算株式会社、保険会社、社会医療法人、一般社団法人などにおける一定範囲の役職従事者についても、各法律において特別背任罪が定められています。
特別背任罪の容疑で刑事訴追される場合、刑法の背任罪よりもはるかに重い刑罰が科される可能性が高いです。早急な示談交渉などの防御活動を欠かせないので、できるだけ早いタイミングで企業法務や刑事事件に強い弁護士までご相談ください。
【注意!】背任罪と横領罪の違い
事件の態様次第では、背任罪と横領罪が同時に成立し得る場面が存在します。
たとえば、銀行の支店長が経済的信用力のない友人に無担保で融資をした場面では、背任罪の構成要件を満たすだけではなく、「支店長が、自己の占有する他人の財物(銀行の金銭)を不法に処分している」とも評価できるので、横領罪も成立するようにも思えます。
もっとも、このケースにおいて法益侵害は1つしか存在しないため、横領罪・背任罪の両罪の成立を認めるのは適当ではありません。
そこで、横領罪・背任罪の両罪が成立する場面では、両罪は法条競合の関係に立ち、重い方の犯罪のみの成立を認めるのが判例・通説です。具体的には、委託物横領罪・業務上横領罪と背任罪の成立範囲が重なる場面では、背任罪ではなく委託物横領罪・業務上横領罪だけの容疑で逮捕されると考えられます(大判昭和10年7月3日)。
背任事件として立件されるのか、横領事件として立件されるのかで、判決内容の重さはまったく異なります。会社から背任の嫌疑をかけられたとしても、その後の捜査活動において横領罪の容疑で刑事訴追されるケースも少なくないので、刑事弁護に強い専門家にスピーディーな示談交渉を依頼するべきでしょう。
【注意!】背任罪と詐欺罪の違い
「他人の事務処理者が、本人に対して欺罔行為を行い、物・利益を交付させたとき」には、背任罪と詐欺罪の両罪の成否が問題になることがあります。
たとえば、「生命保険会社の勧誘員が、被保険者が健康人であると偽って自らを保険契約者保険金受取人として生命保険会社との間に保険契約を締結し、保険証券を交付させたとき」(大判昭和7年6月29日)、「山林立木の売買において、買主である会社の係員と売主とが共謀して、立木の数を会社に過大に報告し、過大な価格で会社に購入させたうえで損害を与えたとき」(最判昭和28年5月8日)などが挙げられます。
このようなケースでは、法定刑の重い詐欺罪の構成要件を満たす以上、背任罪ではなく詐欺罪の容疑で逮捕されるとするのが判例通説です。背任罪の成否が問題になるのは、「詐欺罪の成否を検討したものの、欺罔行為が本人の交付行為に向けられたとは言えずに詐欺罪の成立が認められないような例外的場面」に限られると考えられます。
そして、詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役刑」と定められており、背任罪の「5年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑」よりも相当重い刑罰が想定されます。適切な防御活動を展開しなければ一発実刑もあり得るので、刑事手続き初期段階から実績豊富な私選弁護人に相談することを強くおすすめします。
背任罪で逮捕されるときの刑事手続きの流れ
背任罪の容疑で逮捕されるときの刑事手続きの流れは以下の通りです。
- 背任罪の容疑で警察に逮捕される
- 背任罪の容疑について警察段階の取調べが実施される
- 背任罪の容疑について検察段階の取調べが実施される
- 検察官が背任事件について公訴提起するか否かを判断する
- 背任事件が公開の刑事裁判にかけられる
背任罪の容疑で警察に逮捕される
背任事件が警察に発覚すると、「通常逮捕」によって身柄拘束されるのが一般的です。
通常逮捕とは、「裁判官の事前審査を経て発付される逮捕令状に基づく身柄拘束処分」を指します(刑事訴訟法第199条第1項)。
たとえば、被疑者が所在するのが明らかな平日早朝、逮捕状を持参した捜査員が自宅にやってきて身柄を拘束します。捜査員に逮捕状を呈示された時点で身体・行動の自由が制限されます。そのため、「別の日にスケジュール変更して欲しい」「連行される前に会社に電話連絡させて欲しい」などの要望は一切聞き入れられません。
背任罪の容疑で通常逮捕される具体例
逮捕状が発付されるのは、「逮捕の理由(被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること)」「逮捕の必要性(留置の必要性、被疑者の身柄を強制的に拘束した状態での取調べを実施する必要性)」という2つの要件を満たすときです(犯罪捜査規範第118条、同規範第122条)。
ここから、背任罪の容疑で通常逮捕される場面として、以下のケースが挙げられます。
- 住所不定・無職・職業不詳で逃亡するおそれがある場合
- 前科・前歴がある場合
- 背任行為について余罪への関与が疑われる場合、長期に及ぶ犯行継続が疑われる場合
- 背任事件に関する証拠物(預貯金通帳など)を隠滅するおそれがある場合
- 背任事件の被害額が高額な場合
- 背任事件に関する任意の出頭要請を拒絶した場合
- 背任事件に関する任意の事情聴取で犯行を否認した場合、供述内容に矛盾が存在する場合
- 背任事件の被害者の処罰感情が強い場合
過去の背任事件はいつまで通常逮捕の対象になるのか
過去に背任事件を起こしたとしても、未来永劫逮捕リスクを抱えるわけではありません。なぜなら、背任罪にも公訴時効が適用されるからです。
公訴時効とは、「犯罪行為から一定期間が経過することによって検察官の公訴提起権を消滅させる制度」のことです。
背任罪の公訴時効期間は5年なので(刑事訴訟法第250条第2項第5号)、任務違背行為から5年が経過した段階で警察に逮捕される心配もなくなります。
ただし、過去の背任事件について”時効逃げ切り”を狙うのは得策とは言えません。というのも、企業内部で起こした任務違背行為を5年もバレずにやり過ごすのは現実的に難しいからです。
したがって、過去に背任事件を起こした経験があるなら、会社にバレる前に弁護士へ相談することを強くおすすめします。会社との示談交渉や自首などについて具体的に検討してくれるでしょう。
背任罪の容疑で逮捕される前に会社から事情聴取されるのが一般的
窃盗事件や傷害事件とは異なり、背任事件を起こした場合、いきなり被害申告されるのではなく、被害者との間で話し合いの機会を設けられるのが一般的です。
なぜなら、会社内で背任事件が起きたことが世間に知られると、背任事件の被害者である会社の信用問題に発展するからです。
たとえば、従業員の背任行為を認知した企業側は、警察に被害申告する前に当該従業員との間で面談機会を設けます。そして、当該従業員との話し合いが決裂したときに、警察に被害届・告訴状を提出するなどの方法で被害申告されます。
つまり、過去の背任事件が会社にバレたとしても、いきなり警察からの捜査活動がスタートするのではなく、被害申告を防ぐための防御活動に専念する機会が与えられるということです。背任事件の実績豊富な弁護士なら早期の示談交渉や懲戒処分対策などに尽力してくれるでしょう。
背任事件は任意捜査の対象になることも多い
背任事件を起こしたことが警察に知られる状況になったとしても、常に逮捕状が発付されるわけではありません。
なぜなら、背任事件の態様・状況次第では、逮捕状発付要件の1つである「逮捕の必要性」を満たさないこともあり得るからです。
逮捕状が発付されないとき、背任事件は任意捜査の対象(在宅事件)として扱われます。たとえば、逮捕処分のような強制的な身柄拘束・取調べは存在しません。また、警察から連絡があったタイミングで事情聴取に応じ、取調べが終了すれば日常生活に戻ることが許されます。
背任事件が任意捜査の対象として扱われるのは以下のようなケースです。
- 氏名・住所・職業が明らかで逃亡のおそれがない場合
- 背任事件に関する事情聴取に誠実に対応して犯行を認めている場合
- 背任事件について被害者との間で示談が成立しており、被害者の処罰感情が薄い場合
- 容疑がかかっている任務違背行為が存在しない場合
- 背任罪における被害額が比較的低額に収まっている場合
- 背任行為に関する証拠物を素直に提出している場合
- 背任行為が単独犯として実行されて、共犯関係や組織的な違法行為の疑いがない場合
- 前科・前歴がない場合
なお、最初は在宅事件として捜査活動が進められた場合でも、事情聴取での対応が悪かったり後から更なる任務違背行為が発覚したときには途中から通常逮捕手続きに移行する危険性があります。
したがって、身柄拘束処分なしの在宅事件の状態での刑事手続き終結を達成するために、通常逮捕されなかったとしても、刑事事件に強い弁護士に相談をして、取調べへの対応方法などについてアドバイスを貰うべきでしょう。
背任罪が現行犯逮捕・緊急逮捕の対象になる可能性はゼロに近い
背任罪の性質上、捜査機関に発覚したときに実施されるのは「通常逮捕」が典型例です。
たとえば、背任罪において現行犯逮捕・緊急逮捕が実施される可能性は極めて低いと言えるでしょう。
したがって、過去に背任行為に及んだ場合には、「警察に被害申告される前に会社との間で話し合いによる解決を実現すること」「警察に被害申告されたとしても通常逮捕を回避して在宅事件を目指すこと」の2点が重要な防御方針になると考えられます。
弁護士に相談するタイミングが早いほど日常生活に生じるデメリットを軽減しやすくなるので、当サイトに掲載中の法律事務所まで適宜お問い合わせください。
背任罪の容疑で警察で取調べを受ける
背任行為の容疑で通常逮捕された場合、強制的に警察署に連行されて、警察段階の取調べが実施されます。
取調べ自体に対してどのような態度をとるかは自由ですが、取調べ自体を拒絶することはできません。また、逮捕処分に基づく身柄拘束期間中は、取調室で事情聴取が行われる以外のときは留置場・拘置所で過ごす必要があるため、帰宅することは不可能です。さらに、被疑者の所持品はすべて取り上げられるので、スマートフォンを使って家族や知人に連絡を入れることもできません。
警察段階で実施される取調べには「48時間以内」という時間制限が設けられています(刑事訴訟法第203条第1項)。なお、在宅事件として背任罪の捜査活動が進められる場合には捜査活動の期間制限は存在しないため、場合によっては警察段階の捜査活動だけでも数カ月に及ぶこともあり得ます。
背任罪の容疑で検察官から取調べを受ける
警察段階の取調べが終了すると、背任事件は検察官に送致されます(刑事訴訟法第246条本文)。
検察段階で実施される取調べの制限時間は「24時間以内」が原則です(刑事訴訟法第205条第1項)。つまり、背任罪の容疑で逮捕された場合には、「合計72時間以内(警察段階48時間と検察段階24時間)」の身柄拘束期間を耐える必要があるということです。
ただし、任務違背行為が長期間に及んでいたり、会社に生じた損害の算定に相当の労力を要する場合には、原則的な72時間の捜査活動だけでは公訴提起判断に必要な充分な証拠を収集できない可能性があります。
そこで、「やむを得ない理由」によって72時間の時間制限を遵守できないときには、検察官による勾留請求が認められています(同法第206条第1項)。検察官の勾留請求が認められて裁判所から勾留状が発付された場合、身柄拘束期間は例外的に「10日間~20日間」の範囲で延長されます(同法第208条各項)。
以上を踏まえると、背任罪の容疑で逮捕された場合には、起訴・不起訴が確定するまで最長23日間身柄拘束処分が継続する可能性があると考えられます。仮に不起訴処分を獲得できたとしても身柄拘束処分が数週間続くだけで日常生活にはさまざまな支障が生じるため、私選弁護人の協力を得ながら身柄拘束期間短縮化を目指した防御活動を展開してもらいましょう。
なお、勾留請求が実施される「やむを得ない事情」の具体例として以下のものが挙げられます。
- 任務違背行為が広範囲・長期間に及ぶため背任事件の全体像を把握するのに時間を要する場合
- 背任事件の全貌を掴むための参考人聴取に時間を要する場合
- 帳簿書類や銀行の取引履歴などの調査に時間を要する場合
- 取引先と共謀しているなど、任務違背行為に多数の関係者が存在する場合
- 背任罪に関する取調べで黙秘・否認をしている場合、供述内容に矛盾点や疑問が残る場合
背任罪について検察官が公訴提起するか否かを判断する
背任罪の容疑について警察段階・検察段階の取調べが終了すると、検察官が背任事件を公訴提起するか否か(起訴か不起訴か)を判断します。
まず、起訴処分とは、「背任事件を公開の刑事裁判にかける旨の訴訟行為」のことです。起訴処分が下された時点で刑事裁判の審理は避けられません。そして、日本の刑事裁判の有罪率は約99%以上とも言われていることも踏まえると、背任罪の容疑で逮捕・起訴された時点で有罪判決が事実上確定すると言えます。
次に、不起訴処分とは、「背任事件を刑事裁判にかけることなく検察限りの判断で刑事手続きを終結させる旨の意思表示」のことです。不起訴処分の獲得によって有罪・前科を回避できます。
つまり、背任罪の容疑で逮捕された場合には、「不起訴処分を獲得できるか」が今後の人生を大きく左右するということです。特に、逮捕・勾留されると公訴提起判断まで最長23日間しか猶予はないので、弁護士に効率的な示談交渉を展開してもらいましょう。
背任罪の容疑について公開の刑事裁判にかけられる
検察官が起訴処分を下した場合、背任事件は公開の刑事裁判にかけられます。
刑事裁判が開廷されるタイミングは「背任罪の容疑で起訴されてから約1カ月~2カ月後」です。公訴事実に争いがなければ第1回公判期日で結審します。これに対して、図利・加害目的などについて争う否認事件では、複数の公判期日をかけて弁論手続き・証拠調べ手続きが進められます。
背任罪の容疑で刑事裁判にかけられた場合、被害額の大きさや示談の成否、任務違背行為に至った動機、行為の悪質性などの諸事情次第では「一発実刑」の危険性も生じます。刑事裁判実績豊富な私選弁護人のサポートを受けながら、執行猶予付き判決や罰金刑の獲得を目指してもらいましょう。
背任罪の容疑で逮捕されたときに生じるデメリット3つ
背任罪の容疑で逮捕されたときに生じるデメリットは以下3点です。
- 背任事件を理由として会社から懲戒処分を下される
- 背任罪の容疑で逮捕されると実名報道のリスクに晒される
- 背任罪の容疑で逮捕・起訴されると前科によるデメリットに悩まされ続ける
背任事件を起こすと会社から懲戒処分を下される
背任事件は会社の社内調査や他の従業員からの密告で発覚するケースが多いです。
そして、会社が従業員の背任行為を把握すると、就業規則の懲戒規定に基づいて何かしらの懲戒処分が下されます。
懲戒処分の種類は、「戒告・譴責・減給・出勤停止・降格・諭旨解雇・懲戒解雇」に分類されます。会社内で背任行為・横領行為に及んだからと言って必ずしも懲戒解雇処分が下されるわけではなく、個別具体的な事情を前提に、任務違背行為とバランスのとれた処分内容が下されます。
たとえば、1回限り数万円程度の背任行為なら戒告や減給・降格などの軽い処分で済むこともあるでしょう。これに対して、経理担当者や営業担当者の地位を悪用して数年にも及ぶ高額の背任行為に及んでいたケースでは、諭旨解雇・懲戒解雇などの重い処分を下される可能性が高いです。
背任事件や横領事件の経験豊富な弁護士に相談をすれば、刑事事件対応だけではなく、会社との示談交渉や懲戒処分の有効性も争ってくれるでしょう。
背任事件が報道されるとネット上に氏名などが残り続ける
背任事件が警察に知られるに至って逮捕されると、実名報道のリスクに晒されます。
そもそも、どのような刑事事件を実名報道するかは報道機関側の裁量次第です。ただ、一般的には、「凶悪事件や話題性の高い事件、被害額が高額な事件などを起こした被疑者が逮捕されたとき」にニュースなどで配信される傾向にあります。たとえば、有名企業で背任事件が起こった場合や、担当者の悪質な任務違背行為によって数千万円~数億円規模の損失が生じた場合などでは、背任事件が報道される可能性が高いでしょう。
そして、報道番組やネットニュースなどで実名報道されると、インターネット上に一生背任事件の情報が残り続けてしまいます。これでは、再就職先を探すときや結婚を検討しているときに、過去のネット記事を理由に社会生活に支障が生じかねません。
したがって、実名報道による悪影響を回避したいなら、「会社と早期に示談交渉を進めて刑事事件化を防ぐこと」「警察に背任事件が知られたとしても在宅事件処理を目指すこと」が重要だと考えられます。防御活動をスタートするタイミングが早いほど実名報道のリスクを軽減できるので、現段階で会社側から聴取の打診があるか否かとは関係なく、過去に背任行為に及んだ経験があるなら、すみやかに刑事事件に強い弁護士までお問い合わせください。
背任事件が原因で逮捕・起訴されると前科がつく
背任事件が警察にバレて逮捕・起訴されると、有罪判決が下される可能性が高いです。そして、実刑判決・執行猶予付き判決・罰金刑のいずれであったとしても、有罪判決が確定した時点で「前科」がつきます。
前科とは、「有罪判決を下された経歴」のことです。前科者になると、今後の人生に以下のデメリットが生じ続けます。
- 前科情報は履歴書の賞罰欄への記載義務が生じるので、就職活動・転職活動の妨げになる
- 前科を理由に就業制限される職種・資格がある(士業、警備員、金融業など)
- 前科は「法定離婚事由」に該当するので、配偶者からの離婚申し出を最終的には拒絶できない
- 前科を理由にパスポート・ビザの発給制限を受けると、自由に海外旅行・海外出張できない
- 前科者が再犯に及んだ場合、刑事処分や判決内容が重くなる可能性が高い
前科によるデメリットを回避するには、「背任事件を刑事事件化しないこと」「検察官による不起訴処分を獲得すること」が最大の防御目標になります。いずれにしても会社側との示談交渉は避けられないので、刑事事件や示談交渉の実績豊富な私選弁護人までご相談ください。
背任罪で逮捕されそうなときに弁護士へ相談するメリット4つ
任務違背行為が発覚して背任罪の容疑で逮捕されそうなときに弁護士へ相談するメリットは以下4点です。
- 会社との間で早期の示談成立を目指してくれる
- 会社との間で示談成立を見込めないときは先手を打って自首を検討してくれる
- 背任罪で逮捕されたとしても軽い刑事処分獲得を目指してくれる
- 背任罪の容疑で逮捕・勾留中の被疑者と積極的に接見機会を設けてくれる
早期の示談交渉によって刑事事件化回避を目指してくれる
弁護士は、背任事件の被害者である会社との間で示談交渉を進めてくれます。
示談とは、「背任事件の加害者・被害者間で解決策について直接話し合いを行い、和解契約を締結すること」です。
背任事件では、会社側が警察に被害申告をする前に、背任行為に及んだ従業員との間で社内で直接的に協議をする機会を設けられるのが一般的です。
したがって、背任行為に関する示談交渉が成功すれば、被害届・告訴状を提出されることなく背任事件の解決を実現できるでしょう(背任事件が警察にバレることはないので、逮捕・起訴だけではなく、前科・前歴が残ることもありません)。
弁護士に背任事件の示談交渉を依頼するメリット
任務違背行為が会社にバレたとき、当該従業員本人が会社と直接話し合いをすることも可能です。
ただし、背任事件についての示談交渉は弁護士に依頼した方がスムーズです。なぜなら、示談交渉を弁護士に依頼することで以下4点のメリットを得られるからです。
- 任務違背行為によって生じた損害額を算出して適正価格の示談金での和解成立を目指してくれる
- 背任行為によって高額損害が生じて一括返済が難しいときでも、会社側が納得する示談条件(分割払い・担保など)を提示してくれる
- 会社から下される懲戒処分の内容が適正になるように交渉してくれる
- 示談交渉の成立が見込めないと予想されるときには、すみやかに自首などの先手を打った防御活動を進めてくれる
特に、背任行為が長期に及ぶ場合には、被疑者本人の経済力だけでは示談金を一括で返済しきるのが難しいケースも少なくありません。
示談金を一括払いできないときには、分割払いや担保提供などの条件提示が重要になるので、弁護士に粘り強い示談交渉を依頼してください。
示談状況を踏まえて臨機応変に自首を検討してくれる
背任事件の状況を踏まえて、弁護士は臨機応変に「自首するべきか否か」を検討してくれます。
自首とは、「まだ捜査機関に発覚しない前に、犯人自ら進んで任務違背行為に及んだ事実を申告し、刑事処罰を求める意思表示」のことです(刑法第42条第1項)。警察が背任事件を認知する前に犯人自身が自首をすれば、「刑の任意的減軽」という効果を得られます。
たとえば、会社に生じた損害額が高額で到底示談による解決を期待できない場合、会社側が警察に被害申告をする前に自首をすることで「刑の任意的減軽」というメリットを享受できます(これに対して、自首に先立って会社側に被害届・告訴状を提出されると自首は有効なものとは扱われません)。
示談実績豊富な弁護士は、交渉の推移や想定される和解条件などを総合的に考慮したうえで、どの段階で自首をするべきか否かを判断してくれます。また、自首をした後に実施される取調べでの供述方針についてアドバイスを提供してくれるでしょう。
背任罪で逮捕されても軽い刑事処分獲得を目指して尽力してくれる
背任事件を示談段階で解決するのに失敗して、警察に逮捕されたり捜査対象になったりしたとしても、弁護士は少しでも軽い刑事処分獲得を目指して尽力してくれます。
背任事件が警察にバレた後に目指すべき軽い処分・防御目標は以下の通りです。
- 勾留阻止
- 不起訴処分(起訴猶予)
- 保釈請求
- 略式手続き
- 執行猶予付き判決
勾留阻止
背任罪の容疑で逮捕されたとしても、「勾留請求されるか否か」が重要な分岐点になります。
なぜなら、勾留請求されると最長23日間身柄拘束される可能性があるものの、勾留阻止に成功すれば身柄拘束期間は72時間以内で済むからです。
勾留請求を回避するには、「逮捕段階の取調べに可能な限り誠実に対応し、早期に示談を成立させること」が何より重要な防御活動になります。悠長に示談交渉を進める余裕はないので、示談実績豊富な弁護士までご依頼ください。
不起訴処分(起訴猶予)
背任罪の容疑で逮捕されたときには、「不起訴処分(起訴猶予処分)を獲得できるか」が今後の人生を大きく左右します。
なぜなら、不起訴処分を獲得すれば有罪・前科を回避できるからです。起訴処分が下されるとほとんどの背任事件が有罪になるので、「刑事裁判で防御活動に尽力すること」よりも「検察官の不起訴処分を獲得すること」の方が重要と言えるでしょう。
不起訴処分は以下3種類に分類されます。背任事件を起こした場合、「起訴猶予処分の獲得」を目指すことになります。
- 嫌疑なし:背任事件を起こした証拠がない場合、誤認逮捕・冤罪の場合
- 嫌疑不十分:背任事件を立証するだけの充分な証拠がない場合
- 起訴猶予:背任事件を起こしたことに間違いはないが、諸般の事情を総合的に考慮すると刑事裁判にかける必要がない場合
起訴猶予処分を下すか否かを判断するときには、「犯人の性格・年齢・境遇・犯罪の軽重・情状・犯罪後の情況」などの事情が総合的に考慮されます(刑事訴訟法第248条)。
刑事事件に強い弁護士は不起訴処分獲得に役立つ情状証拠を揃えてくれるでしょう。
保釈請求
背任罪の容疑で逮捕・起訴された場合、出来るだけ早いタイミングで「保釈請求」を履践する必要があります。
なぜなら、背任罪の容疑で起訴された後、「起訴後勾留」が継続すると、刑事裁判に至るまでの数カ月間身柄拘束されるからです。刑事裁判の判決が確定するまで日常生活に戻ることができないと、会社生活や家族・恋人との関係も根底から崩れ去ってしまいます。
なお、保釈請求は以下3種類に分類されます。背任事件に関する捜査状況に応じて、適宜適切な保釈請求手続きを履践してもらいましょう。
- 権利保釈(保釈除外事由に該当しない限り認められる保釈)
- 裁量保釈(裁判官の裁量によって認められる保釈)
- 義務的保釈(身柄拘束期間が不当に長期化している場合に認められる保釈)
略式手続き
背任罪の法定刑は「5年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑」です。つまり、背任罪の容疑で逮捕・起訴されたときには、罰金刑が下される可能性もあるということです。
そして、罰金刑が想定されるケースでは、「略式手続き(略式起訴・略式裁判・略式命令)」が重要な選択肢に入ってきます。
略式手続きとは、「簡易裁判所の管轄に属する刑事事件について100万円以下の罰金刑が想定される場合に、被疑者側の同意がある場合に限って、公開の刑事裁判を省略して簡易・簡便な形で罰金刑を確定させる裁判手続き」のことです(刑事訴訟法第461条)。
略式手続きを選択すると公開の刑事裁判で反論を展開する機会は失われますが、起訴処分(在宅起訴)が下された時点で刑事手続きが終了するので、社会復帰を目指すタイミングを前倒しできます。
刑事手続きの経験豊富な弁護士に依頼をすれば、「略式手続きに同意するべきか否か」「罰金刑で済むような情状証拠の収集」に尽力してくれるでしょう。
執行猶予付き判決
背任罪で逮捕・起訴された場合には、「執行猶予付き判決の獲得」が最大の防御目標になります。
執行猶予付き判決とは、「所定の猶予期間中に何のトラブルもなく社会生活を過ごし切れば実刑判決を執行されずに済む制度」のことです。つまり、執行猶予付き判決によって刑務所への収監を回避できるということです。
ただし、執行猶予付き判決を獲得するには、「3年以下の懲役刑・禁錮刑・50万円以下の罰金刑の言渡しを受けたとき」という要件を満たさなければいけません(刑法第25条第1項)。背任罪の法定刑の上限は「5年」なので、適切な防御活動を展開しなければ執行猶予付き判決の対象からは外れてしまいます。
したがって、背任罪の容疑で逮捕・起訴された場合には、自首減軽・酌量減軽などの法的措置を尽くす必要があると考えられます。各法律事務所の公式HPなどでは、執行猶予付き判決獲得実績などが掲載されているので、実績等をご確認のうえ、信頼できる弁護士までご依頼ください。
背任罪の容疑で逮捕・起訴されても接見機会を通じてアドバイスを提供してくれる
背任罪の容疑で逮捕・勾留されると、接見禁止処分が付されることが多いため、身柄拘束中の被疑者は弁護士以外の第三者とは一切面会できません。
これに対して、被疑者には接見交通権が認められているので、弁護士とならいつでも自由に面会できますし、書類や物の授受も可能です(刑事訴訟法第39条第1項)。
そして、弁護士は接見機会を通じて以下のメリットをもたらしてくれるでしょう。
- 連日続く厳しい取調べに疲弊した被疑者の味方として励ましてくれる
- 被疑者ノートの差し入れによって違法捜査への予防線を張ってくれる
- 供述調書に署名・押印するときの注意点を教えてくれる
- 取調べにおける供述方針を明確化して矛盾・齟齬のある供述を避けてくれる
なお、身柄拘束中の被疑者は「当番弁護士制度」を利用できますが、軽い刑事処分獲得の可能性を少しでも高めたいのなら、ご自身の責任で「私選弁護人」と契約するのがおすすめです。実績・年齢・性別などを事前にチェックしたうえで、信頼できる私選弁護人までご依頼ください。
背任罪で逮捕される前に弁護士へ相談して被害申告回避を目指そう
背任罪の容疑をかけられたときには、警察にバレる前か後かとは関係なく弁護士へ相談することをおすすめします。
なぜなら、早期の示談交渉によって刑事事件化を回避しやすくなるからです。また、仮に示談交渉に失敗したとしても、弁護士が早い段階で就くことによって身柄拘束期間の短縮化や軽い刑事処分獲得の可能性を高めることができるでしょう。
当サイトでは、背任事件・横領事件の実績豊富な法律事務所を多数掲載中です。実績や年齢、所在地などから、アクセスの良い信頼できる弁護士までお問い合わせください。