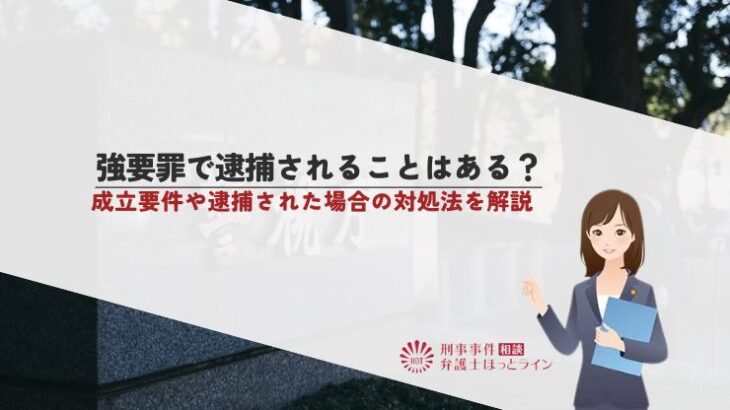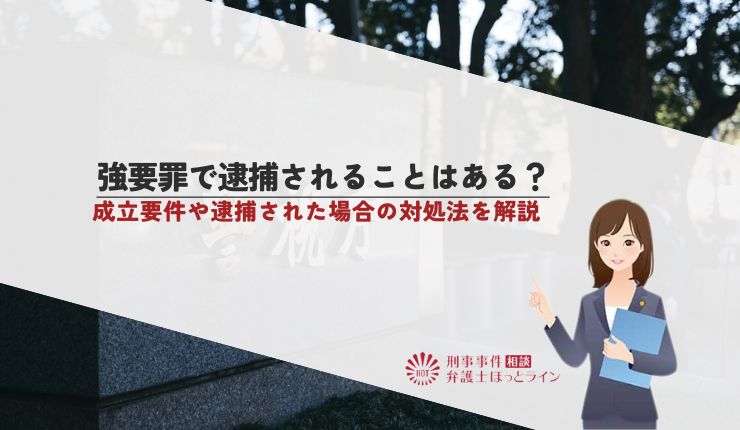
強要罪とは「人を脅かして義務のないことを行わせる犯罪」です。たとえばクレーマーが店員に対して土下座を強要させるような場合が同罪に該当します。
今回は、強要罪の成立要件や類似犯罪との違い、逮捕される可能性や逮捕された場合の流れについて詳しく解説します。強要罪について詳しく知りたい人は、ぜひ参考にしてください。
目次
強要罪とは
強要罪とは、本来行う義務のないことを強要させた場合に成立する犯罪です。また、「生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると告知したうえで脅迫する行為」と定められているため、上記の行為のうえで義務のないことを行わせると強要罪になり得ます。
まずは、強要罪の成立要件や法定刑等について詳しく解説します。
刑法第223条に定められている犯罪
強要罪は刑法第223条に定められている犯罪であり、以下のとおり明記されています。
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。引用元:刑法|第223条
つまり、本人もしくは親族の「生命・身体・自由・名誉・財産」に対して害を加える旨を告知し、何らかの行為を強要した場合に強要罪が成立します。
たとえば、「この場で土下座をしなければ殴る」と告知をし、土下座を強要した場合に強要罪が成立します。「殴る」というのは、人の身体に害を加える行為を指します。また、土下座をさせる行為は、本来すべきではない行為であり、不要な行為を強要しているためです。
ただし、たとえば「この場で土下座しなければ、お前の彼女を殴る」といったような場合は強要罪が成立しません。なぜなら、強要罪が成立するのは本人もしくは親族に対して害を加えると告知した場合に限られているためです。
親族ではない恋人に対して害を加えると言われ、何らかの行為を強要されたとしても強要罪は成立しないため注意しましょう。
強要罪の成立要件
強要罪の成立要件は以下のとおりです。
- 本人もしくは親族であること
- 生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加えると告知されていること
- 何らかの行為を要求されていること
上記条件を満たした場合は、強要罪が成立します。先ほども紹介したとおり、「〇〇をしなければ殴る」と告知する行為は強要罪が成立します。対象は本人のみならず親族であっても成立します。
また、強要とは無理強いすることを指します。簡単に言えば、行う必要のないことを行わせた場合に成立すると考えれば良いです。
よくある事例としてはクレーマーが店員に対して土下座を強要し、強要罪で逮捕されるケースです。土下座を意に反して行わせれば、当然に強要罪が成立します。
強要罪の公訴時効は3年
強要罪の公訴時効は3年です。そのため、強要罪となる事件を起こしてから3年経過した場合は、公訴(起訴)することができません。逆に言えば、強要罪を犯してから3年以内であれば、逮捕されたり起訴されて刑罰が下されたりする可能性もあるため注意が必要です。
万が一、強要罪に問われた場合は「3年以下の懲役」に処される可能性があります。罰金の規定がなく、執行猶予が付かなければ刑務所へ収容されてしまうことになる重罪です。
刑務所へ収容されてしまえば長期間の身柄拘束が発生し、社会的な影響も甚大であるため注意しましょう。
強要罪と類似犯罪の違い
強要罪は人や親族に対して生命等に危害を加えることを告知し、何らかのことを強要した場合に成立する犯罪です。強要罪に似た犯罪として「脅迫罪」や「恐喝罪」があります。
次に、強要罪と脅迫罪・恐喝罪の違いやそれぞれの成立条件について詳しく解説します。
脅迫罪との違い
脅迫罪とは、刑法第222条に定められている犯罪です。脅迫罪は「人を脅迫した場合」に成立する犯罪であり、強要罪との違いは何らかの行為を強要していない点です。
成立要件は「生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加えると告知されていること」です。たとえば、「殴るぞ」「殺すぞ」といった言葉を発すると成立する犯罪です。
脅迫とは「相手を脅すこと」であり、脅迫罪は脅した時点で成立する犯罪です。一方で、強要罪は脅したうえで何らかの行為を強要した場合に成立する犯罪である、という違いがあります。
なお、強要罪は未遂罪も罰せられるため、たとえば「〇〇しなければ殴る」と告知をし、相手が実際にその行為をしなかったとしても強要未遂罪が成立します。つまり、強要罪は要求した時点で(未遂罪が)成立すると考えれば良いです。
脅迫罪は、あくまでも「脅迫のみ」で成立する犯罪です。この違いについては覚えておくと良いでしょう。
恐喝罪との違い
恐喝罪とは、人を脅して財物等を交付させた場合に成立する犯罪です。強要罪は「人を脅して何らかの行為を強要すること」によって成立する犯罪である一方、恐喝罪は「人を脅して財物を交付させる行為」という違いがあります。
たとえばラーメン店で食事中、店員が誤ってラーメンをこぼしてしまった。という場面があったとしましょう。謝る店員がいる一方で「今すぐ土下座しろ!」と怒鳴り、実際に土下座を強要したとしましょう。この場合に成立するのは強要罪です。
しかし、店員の対応に納得のできなかった客は、店側に対して「おれはヤクザだ!今すぐ10万円を支払え!支払わなければ、どうなっても知らないぞ!」と脅かし、実際に店側から10万円を取ったとしましょう。この場合は、恐喝罪が成立します。
ただし、クリーニング代等、実際に発生した損害額であり、正当な請求である場合は恐喝罪は成立しません。あくまで脅して金銭を取る行為が恐喝罪という犯罪に抵触するということです。
強要罪で逮捕される可能性
強要罪は「3年以下の懲役」という罰則規定があるため。逮捕されてしまう可能性のある犯罪です。また、強要をして他の行為を行っている可能性もあり、この場合はさらに重い罪が科され、逮捕・勾留される可能性が高まるでしょう。
次に、強要罪で逮捕される可能性について詳しく解説します。
強要罪のみで逮捕される可能性はある
強要罪は、その他の犯罪を起こしていなかったとしても逮捕される可能性があります。過去には、店員に対して土下座を強要した罪で逮捕された事例もあります。
店の従業員が何らかの失敗をしたとしても、謝罪の方法は人それぞれです。こちら側から「謝る気があるなら土下座をしなさい」と言う行為は許されません。
ましてや、客という立場や相手の失敗をしたという事実をたてに土下座を強要する行為は、当然に強要罪が成立します。たとえ、強要行為だけであったとしてもその悪質性や被疑者の前科前歴の有無などを総合的に考慮し、必要であると判断された場合は逮捕される可能性もあるでしょう。
強要罪+他の犯罪が成立している場合は逮捕の可能性が高い
強要罪は、他の犯罪も成立している可能性が高く、この場合は逮捕される可能性が高まります。
たとえば、わいせつな行為を強要した場合、強要罪ではなく「不同意わいせつ罪」が成立します。性交等を行えば、不同意性交等罪という罪状に変わり、逮捕の可能性は高まります。
具体的な例をあげると「私と性交をしなければ、あなたに危害を加えます」と告知し、実際に性交等を行った事例です。この場合は、「行為を強要した」という意味では強要罪です。しかし、不同意性交等罪という犯罪が成立してしまうのです。
不同意性交等罪の場合は、5年以上の有期拘禁刑が下されます。よって、執行猶予の可能性がなく、重犯罪であることからほぼ確実に逮捕されてしまうでしょう。
また、強要はあくまでも「害を加えると告知し、何らかの行為を強要した場合」に成立する犯罪です。しかし、たとえば相手のことを小突いたり胸ぐらを掴んで強要した場合は、暴行罪が成立する可能性もあるでしょう。
強要罪で逮捕された場合の刑罰
強要罪のみで逮捕された場合、罰則規定は「3年以下の懲役」であるため、懲役刑となる可能性が高いです。もし、執行猶予が付かなければ刑務所へ収容されることになるため注意しなければいけません。
次に、強要罪で逮捕されてしまった場合の刑罰についても詳しく解説します。
前科の有無が大きく影響する
強要罪で逮捕された場合の刑罰は、これまでの前科の有無が大きく影響します。とくに、過去に何度も強要罪で逮捕された履歴がある人は、厳しい処分が下される可能性が高いです。
また、強要罪の前科前歴はなくても、その他の犯罪で前科がある場合は、前科前歴を考慮したうえで判決が下されます。
強要罪のみの場合は執行猶予付判決となる可能性が高い
強要罪のみで逮捕・起訴された場合は、執行猶予付の判決となる可能性が高いです。執行猶予とは、直ちにその刑罰を執行せずに一定期間猶予することを指します。
たとえば、強要罪の罰則は「3年以下の懲役」ですが、「懲役3年執行猶予5年」のように判決が下される可能性があります。
上記の判決が下された場合、被告人に対して下された判決は懲役3年です。しかし、この刑罰は直ちに執行せず、5年間執行を猶予します。執行猶予期間中に罰金刑以上の刑罰が確定しなければ、懲役3年の刑罰は消滅します。
しかし、執行猶予期間中に執行猶予取消となる何らかの行為を犯した場合は、新たな犯罪の刑罰に加え、執行を猶予されていた3年という刑罰が加算されて執行される仕組みです。
執行猶予判決は3年以下の懲役刑に対して付すことができる制度であるため、強要罪の場合は執行猶予付判決を下すことが可能です。とくに初犯の場合は、大半のケースで執行猶予付の判決が下されることになるでしょう。
その他犯罪がある場合は実刑判決の可能性もある
その他の犯罪も起こしてしまった場合は、実刑判決となる可能性があります。たとえば、強要罪に加えて名誉毀損罪に問われることがあります。名誉毀損罪とは、相手の名誉を毀損する行為です。
たとえば、店員の失敗に対してクレームを入れる際、土下座を強要するのみならず「バカ」や「アホ」などの罵言を吐いた場合は名誉毀損罪が成立する可能性があります。名誉毀損罪は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
上記の場合、強要罪で罪に問われることはなくても名誉毀損罪で有罪判決が下される場合があります。この場合、罰金刑の実刑判決が下される可能性が高いため注意しましょう。
強要罪で逮捕された場合の流れ
強要罪は逮捕される可能性のある犯罪です。万が一、逮捕されてしまった場合、どういった流れで事件は進んでいくのか、について詳しく解説します。
逮捕
逮捕とは、被疑者(犯罪を起こした疑いのある人)の身柄を拘束して取り調べを行うための手続きです。
逮捕されるためには、逮捕をして身柄の拘束をする必要性が認められなければいけません。つまり、強要罪などの犯罪を起こしたからといって、すべての人が逮捕されるわけではありません。
逮捕をされた場合は、初めに48時間の身柄拘束が認められます。48時間以内に事件について取り調べを行い、次のステップである「事件の送致」へ移行します。
なお、逮捕せずに取り調べを行う場合は、任意聴取という形で行います。あくまでも任意であるため、絶対に出頭する必要はありません。しかし、任意聴取に応じない場合は逮捕して強制的に取り調べを行割れる可能性もあるため要注意です。
事件の送致
逮捕後48時間以内に取り調べを行い、その後に事件を検察官へ送致しなければいけません。
被疑者を逮捕したまま事件を送致することを「身柄付送致」と言います。一方で、逮捕せずに送致(保釈して送致する場合も含む)することを「書類送検」と呼びます。
身柄付送致の場合は逮捕後48時間以内という時間制限があるものの、書類送検の場合は時間制限がありません。通常は、2カ月程度で送致されます。
勾留請求の判断
事件を引き継いだ検察官は、さらに24時間以内に引き続き被疑者の身柄を拘束する必要があるかどうかを判断しなければいけません。
勾留の必要があると判断された場合は、24時間以内に裁判所へ勾留請求を行います。勾留請求では、裁判官が被疑者に対して勾留質問を行い、最終的に勾留の有無を判断する流れです。
勾留請求が認められた場合は初めに10日間の勾留が認められますが、実務上さらに10日の勾留延長が認められます。逮捕〜勾留まで最長23日間の身柄拘束が認められることになるため、社会的な影響も大きくなるでしょう。
起訴・不起訴の判断
勾留請求が認められた被疑者については、勾留期間中に事件を起訴するか不起訴とするかを判断されます。起訴された場合は、被告人となり拘置所という場所へ移ります。また、起訴された場合は裁判所に対して保釈請求を行うことができ、認められれば社会へ戻って日常生活を送ることも可能です。
在宅事件の場合は、勾留という概念がありません。書類送検されてから複数回検察官等の取り調べに応じ、通常は2カ月〜3カ月程度で起訴・不起訴が判断されます。
なお、起訴には「正式起訴」と「略式起訴」の2種類があります。正式起訴とは、通常通り刑事裁判を行い、判決が下されるものです。
一方で、略式起訴とは刑事裁判を開かずに事件を終了させる手続きであり、正式起訴と比較して早期の社会復帰を目指せる点がメリットです。しかし、略式起訴は「100万円以下の罰金もしくは科料」の場合のみ可能な手続きです。
よって、罰則規定が懲役3年以下の強要罪には認められない制度であり、起訴=正式起訴となるため注意してください。
刑事裁判
正式起訴された場合は、刑事裁判を受けます。刑事裁判では、複数回の公判にて事件内容を確認し、有罪か無罪かを判断します。強要罪の事実がある以上、無罪となる可能性はゼロに近いです。
有罪となった場合は、どの程度の刑罰を科すのが妥当なのかを判断し、判決として言い渡します。
刑罰に従って刑に服する
有罪判決が確定した場合は、その刑罰に従って刑に服します。強要罪の場合は3年以下の懲役であり、執行猶予が付かなければ一定期間刑務所へ収容されます。
強要罪で逮捕されてしまった場合の対処法
強要罪で逮捕されてしまった場合、処分を軽くしたり早期に釈放を目指したりするために以下の対処法を検討されてみてはいかがでしょうか。
- 弁護士へ相談をする
- 被害者と示談交渉を進める
- 反省している態度を示す
次に、強要罪で逮捕されてしまった場合の対処法について詳しく解説します。
弁護士へ相談をする
初めに、弁護士へ相談をしましょう。逮捕された場合、一度だけ当番弁護人を呼ぶことができます。その後、呼べるのは起訴後もしくは勾留確定後のいずれかです。
すべて、当番弁護人から説明を受けられますが、可能であれば私選弁護人をつけて早期に弁護活動を行ってもらうのが良いでしょう。
私選弁護人の場合は、自分で弁護士費用を支払わなければいけませんが、被害者との示談交渉やその他弁護活動を行ってくれるため費用対効果は良いです。
被害者と示談交渉を進める
強要罪で逮捕された場合、相手と示談交渉を進めておいたほうが良いです。仮に、示談が成立した場合は、被害者の処罰感情はなくなります。そのため、寛大な処分が下されることが多くなります。
とくに強要罪の場合は不起訴処分となる可能性も高いため、できるだけ早めに弁護士へ依頼をし、被害者との示談交渉を進めてもらいましょう。
反省している態度を示す
反省の有無は判決に大きな影響を与えます。そのため、しっかり反省したうえで被害者に謝罪をするなど態度で示しましょう。
強要罪に関するよくある質問
強要罪に関するよくある質問について紹介します。
Q.クレーマーは強要罪になりますか?
A.度が過ぎたクレームは強要罪になり得ます。実際、過去に逮捕や実刑判決が下された事例もあるため要注意です。
クレームを言うこと自体に違法性はなく、当然強要罪も成立しません。しかし、クレームの結果、相手に何らかの行為を要求してしまうと、強要罪が成立する可能性が高くなります。
たとえば「謝罪の気持ちがあるなら土下座をしなさい!」と言う行為は強要罪が成立するため注意しなければいけません。一方で、「商品が壊れていたため、交換して欲しい」と伝える行為は正当な主張であり、強要罪は成立しません。
Q.強要をして相手がその行為を行わなかった場合、強要未遂罪が成立しますか?
A.刑法第223条3項にて「前2項について未遂は、罰する」と記載されています。つまり、未遂であっても未遂罪が成立するということです。
たとえば、「謝罪の気持ちがあるなら土下座をしなさい!」と言い、相手が土下座までしなかったような場合です。この場合、強要未遂罪が成立します。ちなみに、強要未遂罪の法定刑も同様に3年以下の懲役です。
Q.腕を引っ張ってその場に留める行為は暴行罪や強要罪が成立しますか?
A.腕を引っ張ってその場に留める行為は、暴行罪が成立します。
「腕を引っ張る」という行為はその程度にもよりますが、暴行罪が成立する可能性があります。たとえば、幼稚園教諭が子どもに対して「こっちに行きますよー」と言って手を引っ張る行為は安全上必要な行為であり、違法性はありません。
一方で、たとえば喧嘩をしているカップルの一方がその場を離れようとしたため、無理やり手を引っ張ってその場に留めた場合、暴行罪になり得ます。
そして「この場を離れたら殺す」など、人の生命に害を加えることを告知した上で義務のないことを行わせた場合は、強要罪が成立します。
Q.キャッチは強要罪になりますか?
A.強要罪になるとは考えにくいです。
いわゆるキャッチ行為は客引き行為として処罰の対象となります。各都道府県の迷惑防止条例や風営法といった法律によって処罰される可能性が高いです。
しかし、たとえばキャッチが「うちの店に来なければ危害を加えます」などと言った場合は、強要罪や強要未遂罪が成立します。ただ、このような発言をするようなキャッチはいないため、現実的に考えて強要罪は成立しません。
Q.業務上の命令は強要罪になりますか?たとえば、残業の強要などは犯罪ですか?
A.残業の強要が強要罪になるとは考えにくいです。
業務上は、指揮命令を行う人に従って業務を行う義務があります。つまり、「義務のないことを行わせる」という趣旨の強要罪には当てはまりません。
また、残業が可能かどうかはその状況や契約内容によって異なります。仮に、残業の強要が違法になったとしても、強要罪ではなく労働基準法違反によって処罰されることになるでしょう。
A.マスク着用の強制は強要罪になりますか?
A.強要した場合は強要罪が成立し得ます。
他人に対してマスク着用を強要した場合は、当然に強要罪が成立すると考えられます。しかし、民間事業者が「入店の際はマスク着用をお願いします」という行為は強要罪が成立しません。
なぜなら、あくまでも「お願い」である点、そしてその店に入店するもしないも客側の自由であり、マスク着用を強要されているわけではないためです。
まとめ
今回は、強要罪による逮捕の可能性について解説しました。
強要罪とは「人を脅かして義務のないことを行わせる犯罪」です。刑法223条に定められている犯罪であり、法定刑は「3年以下の懲役」という重い罰則規定が定められています。
よくある事例としては、クレーマーがつい熱くなって土下座を強要してしまうようなケースです。店員に対して自分よりも目下であると勘違いをし、無理な行為を強要してしまうことにより犯罪が成立します。
どのような状況下であっても、人に対して義務のない行為を行わせるのは犯罪です。くれぐれも注意しましょう。