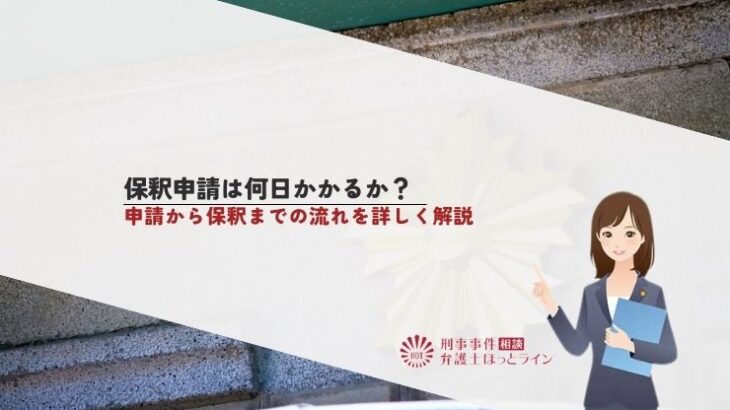起訴された被告人が一時的に社会に戻れる「保釈」は、申請を行って初めて審理されます。保釈申請を行ってから直ちに釈放されるわけではなく、数日程度かかるのが一般的です。
突然逮捕され、家族や会社、学校に行くことができなくなり、さまざまな不安を抱えている被疑者・被告人も少なくありません。
そこで今回は、保釈申請を行ってから保釈が認められるまでには何日かかるのか?保釈を認められるための条件は?など、保釈について詳しく解説しています。保釈について詳しく知りたい人は、本記事を参考にしてください。
目次
保釈申請から保釈までの日数とは
保釈申請を行ってから保釈されるまでは、最短即日〜3日程度かかります。まずは、保釈申請から保釈までの日数について詳しく解説します。
保釈申請後即日〜3日で決定
保釈申請を行った場合、最短で即日中に結論が出て即時保釈されます。ただ、一般的に即日中に保釈許可が出るケースは少なく、一般的には申請から2日〜3日程度かかると思っておいたほうが良いです。
保釈申請を行ってから保釈されるまでに日数がかかる理由は、手続きに時間がかかってしまうためです。詳しくは後述しますが、比較的スムーズに行った場合であっても2日程度はかかると思っておいたほうが良いです。
ただ、朝一番で保釈申請を行い、スムーズに手続きが行われた場合は、即日中の釈放も可能です。上記のことから、最短即日、長くても3日程度かかると思っておけば良いでしょう。
土日は審理されないため長引く
土日も保釈申請を行うことは可能ですが、審理が行われないため、保釈までに日数がかかります。そもそも、土日に保釈申請を行った場合は、月曜日の朝一で保釈申請されたものと同じ扱いになります。
たとえば、土曜日に保釈申請を行った場合、土曜日・日曜日で2日間です。さらに審理開始が月曜日となるため、最短でも月曜日、遅ければ水曜日頃になります。つまり、保釈申請から実際に保釈されるまでに最長で5日程度の期間が必要となる可能性があります。
とくに土日を挟む場合は土日に申請された保釈請求まとめて審理する必要があるため、余計に時間がかかる可能性があるため注意しましょう。
保釈請求とは
そもそも保釈請求とは、一時的に身柄の拘束を解除してもらうための請求を指します。次に、そもそも保釈請求とは何か?保釈請求の効力はいつまで及ぶのか?について、詳しく解説します。
身柄を一時的に解放する請求
保釈請求は、身柄を一時的に解放してもらうための請求です。そもそも、刑事事件においては逮捕・勾留・その後の身柄拘束に分けられます。
まず、逮捕された被疑者は最長72時間の身柄拘束が行われます。この期間は保釈されることはありません。その後、検察が勾留の必要があると判断した場合は勾留請求を行い、認められればさらに20日間の身柄拘束が可能となります。
身柄拘束されている事件は「身柄事件」と呼びます。身柄事件の場合、勾留期間中に被疑者を起訴するか不起訴とするかを検察官が判断する流れです。
不起訴となった場合や略式起訴された場合は、その時点で事件は終了するため保釈請求を検討する必要はありません。保釈請求を検討すべき人は、正式起訴された被告人です。
身柄事件で正式起訴された場合は、引き続き身柄拘束されるのが一般的です。ただし、起訴された被疑者は保釈請求を行うことができます。つまり、身柄事件で起訴されて初めて、保釈請求を検討すべき状況になるということです。
判決が確定するまでは保釈される
保釈請求が認められた場合は、保釈が認められたときから判決が確定するまでの間、保釈されます。通常、起訴から1回目の公判開始は1カ月〜2カ月程度かかります。さらに、公判開始から判決確定まで1カ月程度かかるため、約3カ月程度は社会生活を送ることができるのです。
また、判決で執行猶予付きの判決が下された場合や罰金刑が下された場合は、その後に身柄拘束されることはありません。あくまでも、禁錮刑もしくは懲役刑等の自由刑が下された場合のみ、刑務所等に収監されることとなります。
なお、保釈中であっても公判には出席しなければいけません。もし、呼び出しに応じなければ、保釈許可が取り消され、身柄拘束される可能性があるため注意しましょう。
3つの保釈の種類について
保釈には以下3つの種類があります。
- 権利保釈
- 裁量保釈
- 義務的保釈
次に、3つの保釈の種類について詳しく解説します。
権利保釈
権利保釈とは、原則認められる保釈のことです。そもそも、保釈請求がなされた場合は、例外を除いて保釈しなければいけません。このことを「権利保釈」と言います。
そもそも、日本の刑事裁判においては「推定無罪の原則」という原則があります。推定無罪の原則とは、刑事裁判で有罪判決が確定するまでは、無罪のものとして扱われなければいけないという原則です。
上記の原則を前提に話を進めると、勾留という行為は「無罪であるにも関わらず、身柄を拘束している」という状況になります。本来、このような状況は絶対にあってはいけません。
とはいえ、罪を犯した可能性がある人の話にしておくわけにもいきません。このことから、一定の条件のもとで身柄の拘束を認めています。これが権利保釈の「例外」に該当する部分です。
権利保釈の例外は以下のとおりです。
- 重大犯罪を犯した場合(死刑・無期・短期1年以上の懲役・禁錮にあたる罪)
- 過去に死刑・無期・長期10年を超える有罪判決を受けた
- 常習性のある犯罪で長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した
- 証拠隠滅の可能性があると疑うに足りる相当な証拠がある
- 被害者や証人、その親族に危害を加える可能性があると疑うに足りる相当な証拠がある
- 氏名・住所がわからない場合
上記に該当しない場合は、かならず保釈を認めなければいけません。これを「権利保釈」と言います。
裁量保釈
裁量保釈とは、裁判官の裁量で保釈を認める保釈を指します。たとえば、権利保釈の例外に該当する場合であっても、裁判官の裁量で保釈を認める権利が与えられています。
権利保釈では「短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪」であっても保釈は認められません。しかし、「短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪」は、1年程度の刑罰による犯罪であれば、比較的軽微な犯罪であるともいえます。
上記の場合で、被告人の身柄を拘束することによって社会的な影響を及ぼす恐れのある場合は、裁量保釈が認められやすいです。
たとえば、執行役員である被告人がいないことによって、会社に大きな不利益を与える可能性が高い場合です。その他事情等を総合的に考慮して、裁判官の裁量によって保釈を認める場合があります。
義務的保釈
義務的保釈とは、勾留が不当に長い場合にかならず許可しなければいけない保釈のことを指します。あまり一般的な保釈ではなく、認められるケースも少ないです。
「身柄拘束が不当に長い」とは言うものの、具体的にどの程度の期間をもって「不当に長い」とされるかの明確性がありません。そのため、実際に義務的保釈が認められるケースが少ないのです。
なお、義務的保釈が認められた場合は、勾留を取り消すか保釈を認めるかのうちいずれかを裁判官が決定します。
保釈の条件とは
保釈されるためには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 起訴されていること
- 身元保証人がいること
- 保釈保証金を用意できていること
次に、保釈の条件について詳しく解説します。
起訴されていること
保釈請求は、起訴されていることが条件です。起訴とは、訴訟を提起することです。身柄事件の場合は、勾留期間中に起訴・不起訴の判断がなされます。不起訴となった場合は、即時釈放されるため、そもそも保釈請求を行う必要はありません。
そして、起訴される前の被疑者はそもそも保釈されることはなく、保釈請求を行うこともできません。起訴されて初めて保釈請求が可能となることを覚えておきましょう。
身元保証人がいること
保釈請求が認められるためには、身元保証人がいなければいけません。そもそも保釈は、罪を犯した可能性のある人を一時的に社会に戻し、社会生活を送る中で裁判手続きを進めたり、社会的影響を最小限に抑えたりするために存在しています。
刑事裁判で有罪判決が下されるまでは、推定無罪の原則によって、無罪のものとして扱われなければいけません。とはいえ、「罪を犯した可能性」がある以上、逃亡や証拠隠滅の可能性も否定はできないため、身元保証人がいなければいけません。
身元保証人は、原則近親者である必要があります。たとえば、配偶者や両親・兄弟、もしくは会社の上司でも認められます。いずれかの身元保証人を用意していなければ、保釈が認められることはありません。
保釈保証金を用意できていること
保釈保証金を用意しなければ、保釈は認められません。保釈保証金とは、いわゆる「担保」のようなものです。被告人としても何も犠牲にするものがなければ、逃亡や証拠隠滅を図ることがあるかもしれません。
保釈中の逃亡や証拠隠滅を防止する目的から、被告人にとって痛手となる程度の金銭を預け入れなければいけません。これが保釈保証金です。
人によって保釈保証金の金額は異なるものの、通常は100万円〜300万円程度です。もし、保釈中に逃亡したり証拠隠滅を図ったりした場合は、保釈保証金は没収されます。ただし、しっかり裁判等に出廷して対応した場合は、保釈保証金は返還されます。もし、保釈保証金の用意が難しければ、保釈を認められることはありません。
保釈請求を行うメリット
保釈請求を行うメリットは以下のとおりです。
- 自宅へ帰れる
- 裁判の準備を進められる
- 会社・学校への復帰が可能
- 家族へのケアができる
次に、保釈請求を行うメリットについて詳しく解説します。
自宅へ帰れる
まず、保釈請求が認められた場合は、身柄拘束から解放されます。そのため、自分の自宅へ帰れます。自宅へ帰ることによって、一時的にでも日常に戻ってリラックスできるでしょう。
これからのことも落ち着いてゆっくりと考えられたり、準備を進められる点は大きなメリットになり得るでしょう。
裁判の準備を進められる
身柄拘束されている間は、留置所や拘置所にて生活を送らなければいけません。しかし、保釈請求が認められれば、自宅へ帰ることが許されます。今後行われる裁判に向けて証拠を揃えたり、弁護人と打ち合わせをしたりなど裁判準備を着実に進められる点もメリットです。
もちろん、身柄拘束されている間も弁護人との接見は自由に行えます。しかし、留置所や拘置所の中で生活を送らなければいけないため、準備が不十分となるケースも多いです。
この点、自宅へ帰ることができれば、裁判に必要な証拠を揃えられたり好きな時間、好きな場所で弁護人との打ち合わせができます。大きなメリットとなり得るでしょう。
学校・会社への復帰が可能
保釈請求が認められた場合は、ある程度自由な生活を送れます。当然、学校や会社へ行くこともできるため、社会的な影響を最小限に抑えられる点が大きなメリットです。
起訴後も身柄拘束が継続した場合、数カ月単位で学校や会社へ行くことができません。退学処分や解雇処分となる可能性もあるかもしれません。このような可能性を回避できる可能性が高まるため、保釈は大きなメリットになり得るでしょう。
家族へのケアができる
もし、裁判の傾向として懲役刑や禁錮刑となる可能性が高い場合、長期間にわたって刑務所へ収監されることとなります。そのため、事前に家族へのケアを行える点は保釈の大きなメリットです。
保釈が認められても刑事裁判で懲役や禁錮刑の実刑判決が下された場合は、刑務所に必ず収監されてしまいます。たとえ、保釈が認められていたとしても、いずれは刑務所へ収監される可能性があることを覚えておきましょう。
しかし、その可能性を理解し、事前に家族等と顔合わせて今後のことについて話をし、準備を整えて刑務所に入れば、家族の心情も少しは楽になるでしょう。突然逮捕されてそのまま外で会うことができずに何年も経過する場合と比べて、保釈のメリットはとても大きいといえます。
逮捕から保釈請求までの流れ
逮捕されてから保釈請求までの大まかな流れは以下のとおりです。
- 逮捕・送致
- 勾留決定
- 起訴・不起訴の判断
- 保釈請求
次に、逮捕されてから保釈請求までの大まかな流れについて詳しく解説します。
逮捕・送致
保釈請求を行うということは、身柄事件で事件が進んでいることを意味します。そのため、基本的には初めに逮捕されている可能性が高いでしょう。
逮捕された場合は、初めに逮捕から48時間の身柄拘束が可能です。逮捕から48時間以内に検察官へ事件を送致し、検察官が24時間以内に勾留の必要性を判断するのが大まかな流れです。
そもそも、罪を犯したからといってすべての人が逮捕されるわけではありません。逃亡や証拠隠滅の可能性がある、もしくはその他逮捕すべき理由がある場合に限って逮捕が許されています。身柄事件となる場合は、上記いずれかの可能性があると判断されているはずです。
勾留決定
検察官は送致から24時間以内に引き続き被疑者の身柄を拘束すべきかどうかについて判断しなければいけません。勾留の必要があると判断した場合は、裁判所に対して勾留請求を行い、裁判官が勾留の必要性を判断する流れです。
勾留が認められた場合は初めに10日間の身柄拘束が可能となります。その後、勾留延長されるケースが大半であり、さらに10日、合計20日間の身柄拘束が可能となるため覚えておきましょう。
この時点で最長23日間の身柄拘束が可能となります。突然逮捕された被疑者の場合、家族とも会えずにさまざまな不安を抱えていることでしょう。なお、勾留中は保釈請求を行うこともできません。
起訴・不起訴の判断
勾留されている被疑者の場合、勾留期間中に起訴・不起訴の判断を行います。不起訴となった場合は、今回の事件について何らかの刑罰が下されることはありません。略式起訴された場合も、罰金を支払って事件は終了します。
正式起訴された場合は、引き続き身柄拘束が続きます。期間に定めはなく、基本的には刑事裁判で刑罰が確定するまでです。
なお、起訴された場合は基本的に留置所から拘置所と呼ばれる場所に移動し、引き続き身柄が拘束されます。身柄拘束後は後は、刑事裁判に向けた準備を進めていくこととなります。
保釈請求を行える
正式起訴された場合は、保釈請求を行うことができます。起訴された即日から保釈請求を行うことが可能であるため、まずは担当弁護人へ相談をされてみてはいかがでしょうか。
なお、本記事冒頭でも解説したとおり、通常は保釈請求を行ってから即日〜3日程度で保釈可否が決定します。ただし、土日を挟む場合は、さらに長期化する可能性があるため注意しましょう。ここまでが逮捕から保釈請求までの大まかな流れです。
保釈の可否に関わらず、その後に刑事裁判が開かれます。判決次第では、刑務所へ収監される可能性があるため、保釈中に準備を進めておきましょう。
保釈申請の流れ
保釈申請を行う流れは以下のとおりです。
- 保釈申請を行う
- 裁判官面接・検察官意見を行う
- 保釈許可・不許可の決定
- 保釈金納付
- 保釈される
次に、保釈申請を行う大まかな流れについて詳しく解説します。
保釈申請を行う
保釈を目指す場合は、初めに保釈申請を行わなければいけません。保釈は待っていても自動的に行われるものではないため、被告人自身で保釈申請を行いましょう。
なお、保釈申請は被告人自身もしくは弁護人を介して行われます。起訴されている被告人であれば、私選弁護人もしくは国選弁護人がついているはずであるため、弁護人に相談をしたうえで保釈請求を行っても良いでしょう。
保釈申請の行い方は「保釈申請書」を裁判所に提出することで行います。口頭でも可能ですが、基本的には書面にて行われます。
裁判官面接・検察官意見を行う
保釈請求が行われた場合は、保釈許可決定を下す前に裁判官は検察官に対して意見を求めます。検察官は「相当(保釈を認める)」「不相当(保釈を認めない)」「しかるべく(裁判官に任せる)」の3つから意見を述べます。不相当の場合、検察官は理由を述べなければいけません。
なお、弁護人も希望すれば裁判官と面接することができます。このとき、保釈に関する話があった場合は、保釈が認められる可能性が高いとも判断できます。
保釈許可・不許可決定
保釈申請が行われ、裁判官面接・検察官意見を経て裁判官が保釈の許可もしくは不許可を決定します。保釈を認める場合は、同時に保釈金額や住居、保釈中の制限等について決定する流れです。
もし、不許可となった場合は準抗告を行うこともできます。準抗告を行った場合は、保釈申請を担当した担当裁判官以外の3人が担当し決定します。保釈請求は、被告人のみならず検察側も行えるため注意しなければいけません。
つまり、一度保釈不許可となった場合であっても準抗告によって覆り、保釈が認められる可能性があります。一方で、保釈許可決定を受けたにも関わらず、検察の準抗告によって、不許可になる可能性もあるため注意しなければいけません。
保釈金納付
保釈許可決定がなされた場合は、指定された保釈金を裁判所に対して支払います。身柄を拘束されている被告人は、お金を払うことができないため、通常は家族等が弁護人を介して裁判所に持っていきます。
また、最近ではネットバンキングを利用した電子納付も可能であるため利用を検討しましょう。いずれにせよ、早めに納付しなければ、保釈されるまでの日数も伸びてしまうため注意しましょう。
保釈される
保釈金の納付が確認出来次第、保釈されます。通常、保釈金を納付してから数時間程度で釈放されます。釈放中は、自宅へ帰ることは許されますが、ある程度の制限はあるため注意しましょう。
早めに保釈を目指すためには、事前に弁護人へお金を預けておくなど、できるだけスムーズに進むように準備しておくと良いでしょう。
保釈申請でよくある質問
保釈申請でよくある質問について解説します。
Q.保釈と釈放の違いは何ですか?
A.どちらも「身柄を解放する手続き」ですが、明確な違いがあります。
保釈は、本記事で解説しているとおり起訴後に保釈金を支払って身柄の解放を目指すための手続きです。一方で、釈放は警察や検察等が行う身柄解放手続きです。たとえば、「身柄を拘束する必要がないため、釈放する」というような場合に釈放と言われます。
Q.保釈申請は何度でも行えるのですか?
A.保釈申請は何度でも行えます。
まず、保釈申請は何度でも行えます。とはいえ、ひとつの事件において何度も保釈請求を行うのは非効率です。そのため、まず、保釈不許可となった場合は準抗告を行うのが一般的です。
Q.保釈中に逃亡したり証拠隠滅をしたりした場合どうなりますか?
A.保釈金が没収され、身柄を拘束されます。
まず、保釈中に逃亡した場合は預けていた保釈金は没収されます。さらに、当然ながら保釈は取り消され、改めて身柄拘束されることとなるため注意しなければいけません。なお、保釈中に逃亡もしくは証拠隠滅を図ったからといって、何らかの罪に問われることはありません。
Q.保釈申請は弁護士へ相談すれば良いのですか?
A.担当弁護人へ相談してください。
保釈申請は自分自身で行うこともできますが、準備で時間がかかったり外の人とやり取りをする必要があります。そのため、スムーズに進めるためには、弁護人への相談を検討したほうが良いでしょう。
Q.どのような罪でも保釈請求を行えるのですか?
A.どのような罪であっても保釈申請は可能です。
どのような罪を犯していたとしても、保釈申請を行うことは可能です。ただし、保釈が認められるかどうかは別です。先ほども解説したとおり、保釈が認められるためには、基本的に権利的保釈もしくは裁量保釈となります。
いずれの場合であっても、重大な事件を起こしている場合は保釈が認められるケースは少ないでしょう。
まとめ
今回は、保釈申請を行ってから何日で釈放されるのか?について解説しました。
保釈申請は起訴後に行える手続きであり、申請を行った場合、最短即日で釈放されます。しかし、即日中に釈放されるケースは少なく、通常は2日〜3日程度の日数がかかります。土日を挟む場合はさらに日数がかかります。
少しでも早く釈放され、家族の元へ帰るためにもできるだけ早めに弁護人へ相談をしたうえで、保釈申請を行い、保釈を目指しましょう。