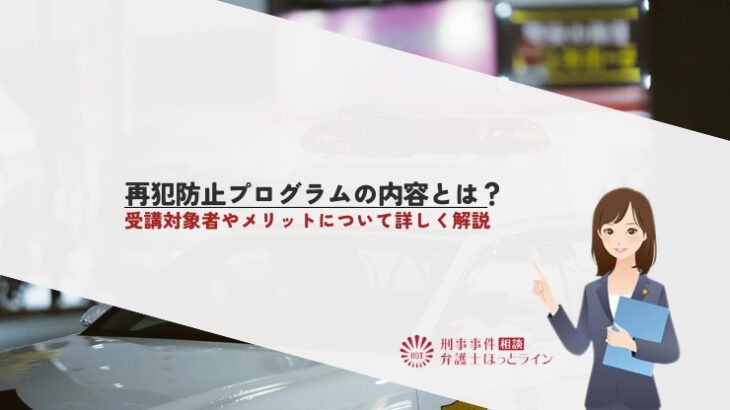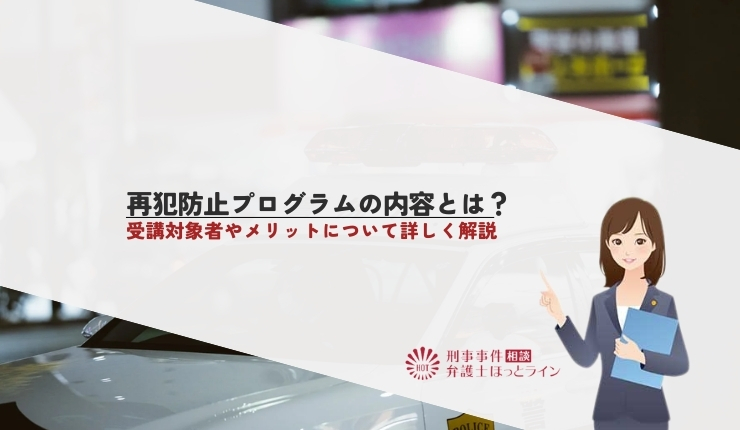
犯罪を繰り返させないためには、単に刑罰を与えるだけでは不十分です。そこで注目されているのが「再犯防止プログラム」です。これは、犯罪に至った背景や原因を個別に分析し、再び同じ過ちを繰り返さないための支援や教育を行う取り組みを指します。
しかし一口に再犯防止プログラムといっても、その内容は対象者の特性や犯罪の種類によって大きく異なります。たとえば、薬物依存による犯罪の場合、治療やカウンセリングが中心となり、暴力事件の場合は怒りのコントロール方法を学ぶプログラムが用意されることもあります。
この記事では、再犯防止プログラムの具体的な内容や種類、さらにはプログラムが果たす役割について詳しく解説していきます。再犯リスクを減らし、社会復帰を目指すための取り組みに興味がある人は、ぜひ参考にしてください。
目次
再犯防止プログラムとは
再犯防止プログラムとは、犯罪や非行を行った人を対象に再犯を防止するために行われるプログラムのことを指します。何らかの犯罪を行ってしまった人の中には、さまざまな事情を抱え、再犯を繰り返してしまう人がいます。
たとえば、病気であったり刑務所にはいることを希望していたりなどが考えられるでしょう。それぞれの状況に合わせた適切なプログラムを行い、再犯防止を目指します。また、犯罪の再犯を防止して多くの国民が安心して生活できる環境を作るために行う目的もあります。
まずは、再犯防止プログラムとは何か?について詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。。
再犯防止のために行われるプログラム
再犯防止プログラムとは、再犯防止を目的としたプログラムを指します。再犯防止プログラムを行う主な目的は、以下のとおりです。
- 国民の安全を保障するため
- 立ち直りを支援して社会復帰を促すため
- 安全な社会を実現するため
犯罪が多い社会では、多くの国民が不安を抱えながら生活をしなければいけません。そのため、犯罪者の再犯を防止し、多くの国民が安心して生活を送れるように再犯防止プログラムが行われます。
そして、犯罪者の中にはさまざまな事情を抱えて再犯を繰り返してしまう人がいます。2度と同じ過ちを犯さないよう、適切なプログラムを組んで実行し、再犯防止を目指していくのが目的です。
たとえば、クレプトマニア(病的窃盗)という病気があります。クレプトマニアは「モノを盗みたい」という欲求を抑えられず、衝動的に窃盗を行ってしまう病気です。
あまり身近な病気ではないため、理解されないことが多いです。しかし、こういった病気を抱えている人が社会に多くいる場合、多くの国民が不安な中で生活を送らなければいけません。そのため、適切な治療を行うために、必要なプログラムを実施します。
犯罪率と社会の安全性は直接関係しています。犯罪率が高ければ、当然安全性は低く、多くの国民が不安や恐怖を抱えながら生活を送らなければいけません。
日本は観光客も多い国であるため、国民のみならず海外から来る人たちにも安心して楽しんでもらえる環境を整える必要があります。そのため、犯罪防止プログラムを通して、犯罪者の再犯を防止しています。
再犯を防止するためのトレーニングが主
再犯防止プログラムで行われる内容は、主にトレーニングと呼ばれるものです。トレーニングとは、具体的に「認知行動療法」や「専門的処遇プログラム」と呼ばれます。
認知行動療法とは、まずは自分の行動や認知パターンを把握することから開始されます。そのうえで、何が犯罪に繋がっているのか?を考え、理解し、再犯防止を目指していくトレーニングです。
認知行動療法は性犯罪等で効果を発揮するケースが多いと言われています。性犯罪者のうち、認知行動療法を行った犯罪者の再犯率は低いため、一定の効果が期待できます。
専門的処遇プログラムとは、各犯罪に応じた専門的なプログラムのことです。たとえば、性犯罪者であれば性犯罪に特化した専門的なプログラム(トレーニング)を実施します。違法薬物利用者であれば、違法薬物に特化したプログラムが実施されます。
再犯防止プログラムの内容とは
再犯防止プログラムで実際に実施される内容は、主に以下のとおりです。
- 導入プログラム
- コアプログラム
- メンテナンスプログラム
- 家族プログラム
次に、再犯防止プログラムで実施される主なプログラム内容について詳しく解説します。
導入プログラム
導入プログラムでは、プログラムの内容や次ステップである「コアプログラム」につながるためのサポートを行います。具体的には、プログラムの目的や内容の説明、アセスメントです。アセスメントとは、犯罪者の再犯のリスク、犯罪を誘発する要因等を評価します。
なぜ、プログラムが必要なのか、プログラムを通してどう変わるのか、などの説明があり、次につながる準備を行うと考えておけば良いでしょう。
コアプログラム
コアプログラムでは実践的なトレーニングを行います。認知行動療法に基づく指導を行ったり、再犯防止計画の作成をしたりします。トレーニング内容は、犯罪の内容によって大きく異なります。
たとえば、性犯罪者であれば以下5つのセッションを行います。
- 性加害のプロセス
- 性加害につながる認知
- コーピング
- 被害者の実情理解
- 2度と性犯罪を行わないために
ひとつのセッションをおおむね2週間程度で行い、5つのセッションを行って完了となります。
性加害のプロセスでは、なぜ自分が性加害を行ってしまったのか?についてセッションします。具体的には、自らの犯罪を改めて振り返り、性加害に至ってしまった経緯を洗い出すまでが一連の流れです。
その後、性加害に繋がる認知を行います。性加害に繋がる認知とは、偏った認知や誤り、偏見を正すために行われるセッションです。
たとえば、性犯罪者の中には「相手から誘惑されて性加害を行った」と、相手のせいにしたり自分は悪くないと正当化したりするケースがあります。このような偏った認知を正すために行われるセッションであると考えておきましょう。
コーピングは、同じ衝動にかられた場合にどのように対応するべきか?について考えることを指します。性犯罪であれば、同じ状況、場面があった場合に今後どのように自己処理するのか?について考えるものであるとおきましょう。
その後、被害者の実情を知って理解し、最後に2度と同じ過ちを繰り返さないためにどうするべきか?を考え、理解してセッションは終了します。
上記は、あくまでも性犯罪を例にみたプログラムです。そのため、犯罪の内容次第では、まったく異なるプログラムが実施されます。
メンテナンスプログラム
上記までのプログラムを終了したものを対象として、定期的に面談を行うプログラムです。面談が行われる頻度は人によって異なりますが、定期的に面談を行うことを「メンテナンスプログラム」と呼ぶことを覚えておけば良いでしょう。
家族プログラム
これまで解説したプログラム以外に「家族プログラム」と呼ばれるものがあります。家族プログラムは、犯罪を犯した者の家族を対象に行われるプログラムです。
内容としては、家族に対して必要な知識の付与、家族のサポートを行います。再犯を防止するためには、家族のサポートが必要不可欠です。そのため、家族に対してもプログラムを実施し、再犯の防止を目指すケースがあります。
再犯防止プログラムが行われる目的
再犯防止が行われる主な目的は、以下のとおりです。
- 犯罪や非行を繰り返さないため
- 新たな被害者を発生させないため
次に、再犯防止プログラムが実施される主な目的について詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
犯罪や非行を繰り返さないために行われる
犯罪や非行を繰り返さないために、再犯防止プログラムが実施されます。そもそも、犯罪防止プログラムの対象者は、犯罪や非行を行った人です。なぜ、そのようなことを行ってしまったのか?を理解し、今後同じことを繰り返さないためにはどうするべきか?を、理解してもらう目的があります。
再犯を繰り返してしまう人の中には、衝動を抑えられないなど、内面的なことが原因であることも多いです。そのため、まずは自分の状況を把握したうえで、今後に活かして行こうという目的があるのです。
新たな被害者を発生させないために行われる
新たな被害者を発生させないためという目的もあります。再犯が繰り返されていると、その分被害者も多く発生しているということです。そういったことが起こらないよう、再犯防止プログラムを実施しています。
もちろん、前提としては犯罪を犯さない、発生させないことが大切です。しかし、犯罪を未然に防ぐには限界があります。そのため、少しでも再犯による被害者を減らそうと考えられているのです。
再犯防止プログラムの対象者
再犯防止プログラムの対象者は、犯罪を繰り返す可能性のある人であり、主に以下のとおりです。
- 受刑者
- 保護観察対象者
- 犯罪歴のある人
- 非行少年
次に、再犯防止プログラムの対象者となる人について詳しく解説します。
受刑者
犯罪を繰り返す恐れのある受刑者は、再犯防止プログラムの実施対象者となります。「受刑者」と言っても一括りではなく、あくまでも「再犯の恐れがある人」が対象です。
たとえば、交通事故で人を死傷させてしまった受刑者は、再犯の可能性がゼロであると言っても良いです。そのため、受刑者ではあるものの、再犯防止プログラムを実施する必要はありません。
一方で、違法薬物によって服役している受刑者の場合は、再犯の可能性が高いです。そのため、違法薬物に特化した再犯防止プログラムを実施する必要があるでしょう。
再犯防止プログラムは、出所後のみならず刑務所の中で実施されるケースがあります。そのため、受刑者であっても再犯防止プログラムが可能です。
保護観察対象者
保護観察対象者も再犯防止プログラムを実施する対象者になり得るでしょう。保護観察対象者とは、犯罪を行った人や非行少年のうち、社会で更生を目指している人を指します。
保護観察となっている人は、定期的に保護観察官や保護司と呼ばれる人たちと定期的に面談を行います。これを一般的には保護処分と言いますが、保護処分とは別に再犯防止プログラムが実施される場合があります。
犯罪歴のある人
犯罪歴のある人のうち、再犯の恐れがあると判断された者は、再犯防止プログラムを実施します。たとえば、満期出所した場合は原則保護観察が付きません。そのため、保護観察官や保護司との面談は行われません。
また、満期出所した場合は、すべての刑期を全うしているため、仮釈放されたものと比較して自由度が高いです。しかし、再犯の可能性が高い元受刑者(犯罪歴のある人)は、再犯防止プログラムを実施する可能性があります。
非行少年
少年が犯罪を犯した場合、「非行少年」と呼びます。非行少年の中には、犯罪少年、虞(ぐ)犯少年、触法少年などの呼び方がありますが、一括りにすると「非行少年」と呼びます。
つまり、犯罪を犯した少年を対象に再犯防止プログラムを実施されることがあるということです。そもそも、再犯防止プログラムは刑事罰等ではなく、あくまでも「再犯を犯さないためのプログラム」であるため、非行少年に対しても行うことが可能です。
再犯防止プログラムに参加するメリット
再犯防止プログラムは、性犯罪再犯防止プログラムを除いて義務ではありません。つまり、性犯罪以外の犯罪を行った人は、再犯防止プログラムを受講する必要はありません。
しかし、受講することによって以下のようなメリットがあるため、積極的に参加したほうが良いでしょう。
- 更生意欲につながる
- 社会生活にできる能力を身に付けられる
- 自分の犯した罪と向き合える
- 再犯防止に期待ができる
次に、再犯防止プログラムに参加するメリットについて詳しく解説します。
更生意欲に繋がる
再犯防止プログラムに参加することによって、更生意欲につながります。犯罪を犯した多くの人は「更生したい」と考えていることでしょう。しかし、「更生したい」と考えていても、実行できなければ意味がありません。
もちろん、刑罰を受けて更生できたと考える人もいるかもしれませんが、2度と同じことを繰り返さないという強い意思がある人は、積極的な参加を検討しましょう。
再犯防止プログラムに参加することによって、自分の状況を把握できるため、再犯意欲の向上にもつながります。結果的に、再犯防止プログラムで得られたことも踏まえて再犯の可能性を低下できるでしょう。
社会生活に適応できる能力を身に付けられる
再犯防止プログラムを受講することで、社会生活に適応できる能力を身に付けられるようになるでしょう。
そもそも、これまでに何らかの犯罪を犯してしまい、受刑者として長期間過ごしていた人は、社会に適応しにくいと考える人もいます。結果的に「刑務所に戻りたい」と考え、再犯を繰り返してしまう人も少なくありません。
再犯防止プログラムに参加することで、自分と向き合うことができ、社会生活に適応できるようになっていきます。
また、衝動的に何らかの犯罪を犯してしまう人の中には、「社会に受け入れてもらえないのではないか?」と不安を抱えている人もいます。そういった悩みや不安を抱えている人が再犯防止プログラムに参加し、自分と向き合って社会適応を目指していくのです。
自分の犯した罪と向き合える
再犯防止プログラムに参加することで、自分の犯した罪と向き合うことができます。自分がなぜその罪を犯してしまったのか?について考えるきっかけになります。
そのため、更生スピードも早く、再犯の可能性を低減できるのです。「絶対に再犯を犯したくない」「絶対に刑務所に戻りたくない」と考えている人こそ、自分自身と向き合うきっかけが必要であるため、再犯防止プログラムへの参加を検討すべきでしょう。
再犯防止に期待ができる
再犯防止に大きな期待ができます。再犯防止プログラムを通して自分の犯した罪と向き合うことで、再犯を犯さない自分に変われるようになるでしょう。
なぜ自分が罪を犯してしまったのか?を客観的に分析できなければ、再犯の可能性が高いです。刑事罰を受けて反省をしたとしても、また同じ状況になれば、犯罪を犯す可能性があるでしょう。
そのため、客観視して改善していくためにも再犯防止プログラムへの参加を検討したほうが良いでしょう。
再犯防止プログラムの内容に関するよくある質問
再犯防止プログラムの内容に関するよくある質問を紹介します。
Q.再犯防止プログラムに一定の効果を期待できるのでしょうか?
A.再犯防止の効果に期待できます。
再犯防止プログラムを受講した参加者と受講していない犯罪歴のある人を比較した場合、前者の再犯率は低い傾向にあります。
もちろん、再犯防止プログラムを受講したからといって、すべての人が再犯しないわけではありません。中には、再犯を繰り返してしまう人がいるのも事実です。しかし、統計を見ると一定の効果があるため、受講をする価値は十分にあるでしょう。
ある程度、本人の気持ち次第という部分もありますが、再犯防止プログラムを受講する人の多くは「再犯したくない」という気持ちを持っている人が多数です。このことも再犯率に影響を与えていると考えられます。
Q.どのような犯罪を犯した人が対象なのでしょうか?
A.主に性犯罪や薬物、飲酒による犯罪等です。
性犯罪の場合は、衝動的であったり自分の欲求を抑えられなかったりなど、さまざまな事情を抱えて犯罪に至ってしまうケースが多いです。そのため、性犯罪者の場合は再犯防止プログラムの受講が義務化されています。
そして、違法薬物を乱用した人を対象とした再犯防止プログラムもあります。違法薬物は非常に依存性が高く、たった一度でも利用してしまうと、なかなか抜け出せません。そのため、適切な治療とともに再犯防止プログラムを受講して再犯防止を目指します。
その他、飲酒による犯罪歴がある人も対象です。飲酒も違法薬物同様に依存性が高いため、飲酒に特化した再犯防止プログラムの受講を進められています。
たとえば、飲酒が原因で暴力事件を起こした、飲酒運転を繰り返していたなど、社会に多大な迷惑をかけた人を対象に実施されます。
Q.再犯防止プログラムの受講は義務ですか?
A.性犯罪は義務です。
再犯防止プログラムは、性犯罪を犯した場合のみ義務です。また、性犯罪再犯プログラムは、少年であっても成人している場合は義務化されています。
その他犯罪の場合は、義務ではありませんが更生を目指す上で受講を検討したほうが良いでしょう。また、人によっては、受講を勧められる場合があるため、前向きに検討してみましょう。
Q.窃盗や性犯罪など、病名がついている場合も効果はありますか?
A.病名がついている人であっても、再犯防止プログラムが有効である場合があります。
病名がついている、つまり病気であるからといって何をしても許されるわけではありません。まずは、自分の心の中を知り、向き合い、更生を目指していくべきです。そのため、再犯防止プログラムへの参加を前向きに検討したほうが良いでしょう。
なお、病気であっても再犯防止プログラムを通して改善されていく可能性は十分に考えられます。必要な治療等と同時に、再犯防止プログラムへの参加を検討してください。
Q.保護観察と再犯防止プログラムは異なるのですか?
A.保護観察は社会で更生を目指していくためのサポート、再犯防止プログラムは、再犯防止を目的としたプログラムを指します。
保護観察は、非行少年や仮釈放された人を対象に社会生活を送りながら、悪い道に戻らないようサポートをすることを目的としています。保護観察官や保護司と呼ばれる人と定期的に面談を行い、今の現況などを話して更生を目指していきます。
一方で、再犯防止プログラムは、再犯を行わないために特別に組まれたプログラムを受講することを指します。対象者は同じですが、まったく異なる制度であることを覚えておきましょう。
まとめ
今回は、再犯防止プログラムについて解説しました。
再犯防止プログラムは、再犯を防止するために大きな役割のあるものです。2度と同じことを繰り返さないという強い意志のある人は、積極的に参加すべきでしょう。
また、犯罪を犯している時点で少なからず社会に影響を与えています。少なからず、被害者もいることでしょう。再犯し、新たな被害者等を発生させないためにも、義務かどうかに関係なく、再犯防止プログラムの受講を検討してください。