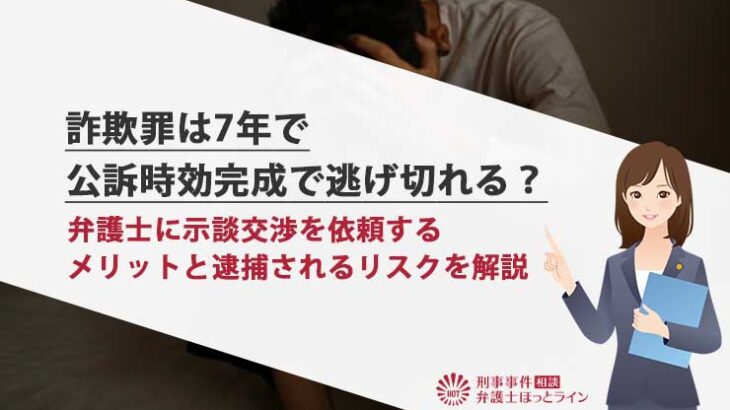詐欺罪に問われる行為を働いたとき、「7年」の公訴時効が完成するまでの間は、「刑事責任」を追及される可能性があります。つまり、「詐欺行為に及んでから数カ月経過しても警察にバレていないので捕まることはないだろう」と油断するのは厳禁だということです。たとえば、詐欺被害額が高額だったり、被害者の処罰感情が強かったりするケースでは、事件から数年経過後でも警察が本格的な捜査に着手する可能性は否定できません。
また、詐欺に及んだ場合には、刑事責任とは別に「民事責任」が発生する点にも注意が必要です。民事責任の時効(消滅時効)は3年もしくは20年なので、状況次第では、仮に公訴時効が完成して刑事責任を問われることがなくなったとしても、別途詐欺被害者からの損害賠償請求に応じなければいけないこともあり得るでしょう。
そこで今回は、過去に働いた詐欺が原因で逮捕されるのではないかと不安を抱える方のために、以下5点について分かりやすく解説します。
- 詐欺罪についての刑事責任はいつまで問われる可能性があるのか(公訴時効)
- 詐欺罪についての民事責任はいつまで問われる可能性があるのか(消滅時効)
- 詐欺罪で逮捕されるときの犯罪類型・法定刑
- 公訴時効完成直前でも警察が本格的な捜査を開始することがある詐欺事件の特徴
- 詐欺罪で逮捕されるか不安なときに弁護士に相談するメリット
「過去の犯罪行為がバレるまでは逃げきることだけに専念すれば良い」「捜査活動に対する防御活動は逮捕された後にスタートすれば大丈夫」というのは間違いです。詐欺罪で逮捕される前にも尽くせる防御活動はありますし、後に逮捕されることがあったとしても、事前に示談が成立しているだけで軽い刑事処分を期待できます。
過去の詐欺行為がいつ露見するか分からない不安定な状態では建設的な人生を歩むこともできないので、まずは刑事事件に強い弁護士に相談のうえ、現在のリスク状況や今後目指すべき方向性についてアドバイスを貰いましょう。
目次
詐欺罪の時効とは
詐欺罪の犯人に科される法的責任は、刑事責任・民事責任の2種類です。
ただし、「詐欺行為を働いたら死ぬまで法的責任を追及され得る」というわけではありません。なぜなら、「『法的責任をいつまでも追及できる』『法的責任をいつまでも追及され得る』という不安定な状態が継続すること」は法秩序の安定性を阻害する事態だと考えられており、刑事・民事双方において時効制度という”区切り”が設けられているからです。
つまり、刑事責任については「公訴時効」が、民事責任については「消滅時効」が完成すれば、法的責任は追及されなくなるということです。
ここからは、詐欺犯人に科される刑事責任・民事責任の時効について、それぞれ解説します。
詐欺罪の公訴時効(刑事責任)
公訴時効とは、「犯罪行為が終わった時から一定期間が経過すると、検察官が起訴処分を下すことができなくなる(公訴を提起できなくなる)」という制度のことです。
検察官による公訴提起が認められなくなるということは、事件が刑事裁判にかけられることもないということです。その結果、公訴時効が完成した事件について有罪判決が下される可能性はゼロになります。
なお、公訴時効は「検察官の起訴処分権限」を消滅させるものであることを踏まえると、公訴時効が完成したとしても「逮捕」はできるかのようにも思えるでしょう。しかし、警察官などによる逮捕や取調べは「将来的に想定される起訴処分や刑事裁判」を目的として実施されるものである以上、ターゲットである起訴処分が認められなくなった以上、公訴時効の完成によって逮捕もされなくなると解するのが素直です。
詐欺罪の公訴時効は7年
後述するように、詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役刑」です(刑法第246条第1項)。
そして、「『人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの』以外の罪」のうち、長期15年未満の懲役刑または禁錮刑に該当する犯罪の公訴時効は7年と定められています(刑事訴訟法第250条第2項第4号)。
したがって、詐欺罪の公訴時効は7年です。詐欺行為から7年が経過するまではいつ逮捕されるか分かりませんし、詐欺行為から7年が経過して公訴時効が完成すれば、もはや過去の詐欺罪で逮捕されるリスクに怯える必要はなくなります。
詐欺罪の公訴時効の起算点
詐欺罪の公訴時効の起算点は「犯罪行為が終わったとき」からカウントをスタートします(刑事訴訟法第253条第1項)。
たとえば、詐欺既遂罪であれば、欺罔行為によって被害者等が財物を交付したタイミングで「犯罪行為が終了」したと扱われるでしょう。これに対して、詐欺未遂罪であれば、実行行為である欺罔行為が終了した時点が「犯罪行為の終了」時点です。
なお、詐欺罪が複数人で実施されて共犯関係が存在する場合、詐欺罪の公訴時効の起算点は「最終の行為が終わったとき」とされて、その時点からすべての共犯者について公訴時効の期間が数えられます(同法第253条第2項)。特殊詐欺事件のように組織的な犯行行為が次々と明らかになるケースでは、自分が関与したタイミングよりも遅れて公訴時効のカウントがスタートすることもあるでしょう。
詐欺罪の公訴時効の停止
詐欺罪の公訴時効は7年で完成するのが原則です。
ただし、詐欺事件を起こした犯人が日本国外にいる場合には、国外にいる期間分だけ公訴時効の進行が停止します。また、日本国内にいたとしても、詐欺犯人が逃げ隠れているために有効に起訴状の謄本の送達・略式命令の告知ができなかった場合には、逃げ隠れている期間分だけ時効カウントがストップします(刑事訴訟法第255条第1項)。
たとえば、詐欺事件を起こした後、6カ月間海外逃亡していた場合には、日本国外に居た半年分を除外したうえで7年間の公訴時効期間を数えることになります。
詐欺罪の消滅時効(民事責任)
詐欺を働いた場合、詐欺犯人には「不法行為に基づく損害賠償責任」が発生します(民法第709条、第710条)。
たとえば、オレオレ詐欺事件で被害者からお金を騙し取ったときには、詐欺被害額だけをそのまま弁償すれば良いという話ではなく、遅延損害金と精神的苦痛に対する慰謝料も合わせて支払わなければいけません。特に、慰謝料額については事件ごとに金額が異なるので、場合によっては相当高額の賠償責任を問われかねないでしょう。
そして、詐欺被害者から詐欺加害者に対する損害賠償請求権については「消滅時効」制度が規定されているので、刑事責任が公訴時効完成によって消滅するのと同じく、消滅時効の完成によって民事責任である損害賠償責任も追及されなくなります。
詐欺罪の賠償責任の消滅時効期間は3年もしくは20年
詐欺事件の犯人が被害者に対して負っている不法行為に基づく損害賠償責任は、以下のタイミングで消滅します(民法第724条各号)。
- 詐欺被害者または被害者の法定代理人が損害及び詐欺加害者を知った時から損害賠償請求権を3年間行使しないとき
- 不法行為に基づく損害賠償請求権を詐欺事件から20年間行使しないとき
たとえば、詐欺被害にあったことは分かっていても、加害者が誰か分からない状況だと、3年の消滅時効期間は適用されません。このケースでは、詐欺事件から20年が経過するまでは損害賠償請求権は残り続けるので、公訴時効が完成して刑事訴追を免れることに成功したとしても、詐欺被害者に特定されて法的措置に踏み切られると、不法行為に基づく損害賠償請求に応じる必要に迫られます。
ここで注意を要するのが、「損害及び加害者を知った時」の意味するところです。というのも、特殊詐欺のように対面で被害者から現金やキャッシュカードを騙し取ったようなケースでは、被害者は詐欺犯人と一応は面識があるわけで、ある意味では「加害者のことを知っている」とも言えるからです。
しかし、このようなケースで「損害及び加害者を知っている」と認定されて、詐欺被害者の損害賠償請求権が3年で消滅時効にかかるとするのはあまりに酷でしょう。なぜなら、見ず知らずの詐欺加害者の身元を被害者の責任においてたった3年で特定しなければいけないことに他ならないからです。
そこで、単に詐欺犯人の容貌を知っていただけでは足りず、「加害者の氏名・住所を知ったとき」をもって「加害者を知った」とするのが判例実務です(最判昭和48年11月16日)。
詐欺罪の消滅時効の完成猶予・更新
詐欺の犯人が負う民事責任は3年ないし20年で消滅時効にかかるのが原則ですが、「消滅時効の完成猶予事由」「消滅時効の更新事由」が発生すると例外的な取扱いが行われます。
消滅時効の完成猶予とは、以下の事由が発生した場合に、消滅時効期間のカウントが一時的に停止することです。
- 裁判上の請求・支払督促・和解・調停(民法第147条第1項)
- 強制執行・担保権の実行・競売・財産開示手続き・情報取得手続き(同法第148条第1項)
- 仮差押え・仮処分(同法第149条)
- 催告(同法第150条)
- 権利紛争についての協議を行う旨の合意が書面でされたとき(同法第151条第1項)
- 天災などの不可抗力事態が発生したことが原因で、裁判上の請求や強制執行に着手できないとき(同法第161条)
そして、消滅時効の更新とは、以下の事由が発生した場合に、消滅時効期間のカウントがリセットされて再びゼロからリスタートすることを指します。
- 裁判上の請求等について、確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって、権利が確定したとき(同法第147条第2項)
- 強制執行等が終了したとき(同法第148条第2項)
- 権利の承認があったとき(同法第152条第1項)
たとえば、詐欺の被害者が「詐欺で損害を受けたこと」「詐欺の犯人がどこの誰か」を知っていたにもかかわらず、5年間が経過したタイミングでようやく不法行為に基づく損害賠償請求権を行使してきた場合、時効の援用を適法に行えば消滅時効完成の効果を主張できますが、「一括払いは難しいですが分割払いなら対応できます」などと返事をしたり、一部額だけでも入金したりすると、賠償責任を負う側が「債務の存在を承認」したことになるので、消滅時効の効果を主張できなくなってしまいます。賠償責任を追及されたのに応じることができなければ、自分名義の財産に対して差押えが実行される可能性も否定できません。
このように、詐欺事件を起こしてしまうと、刑事手続き面だけではなく、民事手続き面においてもさまざまな注意事項に配慮する必要に迫られます。順風満帆に更生プロセスを歩むには無用な金銭トラブルは避けるべきなので、民事的な問題についてもかならず弁護士に相談してください。
時効完成前に詐欺罪で逮捕されるときの罪責と法定刑
公訴時効が完成しない限り、過去に起こした詐欺事件を理由として常に逮捕リスクに晒されるでしょう。
詐欺行為に及んで逮捕されるときは、以下6つの犯罪類型について容疑をかけられます。
- 1項詐欺罪
- 2項詐欺罪
- 電子計算機使用詐欺罪
- 準詐欺罪
- 詐欺未遂罪
- 組織犯罪処罰法違反
なお、以下で紹介する各犯罪類型の成立要件のうち、主観的構成要件要素である「故意」については省略します。
1項詐欺罪
1項詐欺罪とは、「人を欺いて財物を交付させたとき」に成立する犯罪類型のことです(刑法第246条第1項)。1項詐欺罪の法定刑は、「10年以下の懲役刑」と定められています。
1項詐欺罪の構成要件は以下4点です。
- 欺罔行為
- 財物
- 交付行為
- 欺罔行為と財物交付行為との間に因果関係があること
分かりやすく1項詐欺罪のイメージを伝えるならば、「欺罔行為→相手が騙される→錯誤が原因で交付行為に至る→財物が移転する」という一連のプロセスを経ることが1項詐欺罪の成立に不可欠だということです。
たとえば、返済するつもりがないのに「来月には返すから融資をして欲しい」と友人に話をもちかけて(欺罔行為)、「来月に返済してくれるなら貸しても良いか」と相手が誤信し(錯誤)、その間違いに気付かずに言われた金額を手渡す(交付行為・財物の移転)場合が、1項詐欺罪の典型例として挙げられるでしょう。
2項詐欺罪
2項詐欺罪とは、「人を欺いて、財産上不法の利益を得たとき、または、他人に財産上不法の利益を得させたとき」に成立する犯罪類型のことです(刑法第246条第2項)。2項詐欺罪の法定刑は、「10年以下の懲役刑」と定められています。
2項詐欺罪の構成要件は以下4点です。
- 欺罔行為
- 財産上の利益
- 自分が利益を得ること、または、他人に利益を得させること
- 欺罔行為と財産上の利益を交付させる行為との間に因果関係があること
1項詐欺罪と2項詐欺罪では「客体」が違います。つまり、1項詐欺罪の客体が「財物」であるのに対して、2項詐欺罪の客体は「財産上(不法)の利益」であるという点です。
たとえば、債権を取得する・債務の支払いを免れる・支払いを猶予してもらう・労務を提供させるなど、財産的価値を有するものの財物性は否定されるものが2項詐欺罪の客体に含まれます。
電子計算機使用詐欺罪
電子計算機使用詐欺罪とは、「人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報・不正な指示を与えて財産権の得喪・変更に関する不実の電磁的記録を作出したり、財産権の得喪・変更に関する虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に提供したりすることによって、財産上不法の利益を得たり、他人に財産上不法の利益を得させたりしたとき」に成立する犯罪類型のことです(刑法第246条の2)。電子計算機使用詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役刑」と定められています。
たとえば、不正に取得した他人のキャッシュカードを使用して預金を入手しようというケースについて、窓口の係員を騙して現金を引き出した場合と、ATMを操作して現金を手に入れた場合とを比較してみましょう。
そもそも、窓口の係員を経由しようが、ATMを経由しようが、他人のお金を”騙し取っている”という点では共通しているので、両ケースの可罰的違法性には大きな差はないと考えるのが素直です。
しかし、係員を経由して現金を引き出した場合には「窓口の係員の錯誤」が因果の流れにあるので1項詐欺罪が成立するのに対して、ATMを経由して現金を手に入れた場合には「交付行為者の錯誤」が存在しないので1項詐欺罪は不成立です(ATMのような機械が「錯誤」に陥ることはあり得ないからです)。また、ATMから現金を引き出した場合はまだしも、ATMを不正操作して別口座に送金した場合には「財物の占有移転」も観念し得ないので、窃盗罪(刑法第235条)も成立せずに不可罰となってしまいます。
ただ、後者のケースにも詐欺罪と同程度の可罰的違法性があるにもかかわらず、詐欺罪で立件できないというのは均衡を欠いて不当でしょう。
そこで、昭和62年の刑法改正で新設されたのが電子計算機使用詐欺罪です。これによって、コンピュータ等の不正操作によって財産上不法の利益を得る「詐欺罪相当の行為」が刑事処罰の対象として扱われます。
準詐欺罪
準詐欺罪とは、「未成年者の知慮浅薄や人の心神耗弱に乗じて、財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たり、他人に財産上不法の利益を得させたりしたとき」に成立する犯罪類型のことです(刑法第248条)。準詐欺罪の法定刑は、「10年以下の懲役刑」と定められています。
1項詐欺罪や2項詐欺罪では、交付行為は「欺罔行為による錯誤」によってもたらされるのに対して、準詐欺罪では、交付行為が「未成年者の知慮浅薄や人の心神耗弱」によって引き起こされる点に違いがあります。
たとえば、とても欺罔行為とは呼べないようなあからさまな嘘によって財物が交付された場合でも、対象者が未成年者・心神耗弱の状態の人であれば、準詐欺罪として処罰されることになります。
詐欺未遂罪
1項詐欺罪・2項詐欺罪・電子計算機使用詐欺罪・準詐欺罪は未遂犯も処罰対象です(刑法第250条)。
詐欺未遂罪の法定刑は、詐欺既遂罪と同じ「10年以下の懲役刑」です。ただし、個別具体的な事情を総合的に考慮して、刑が減軽されることがあります(刑法第43条本文)。
詐欺未遂罪として処罰されるには、「詐欺罪の実行の着手」が必要です。具体的には、「『欺罔行為による財物の移転』という既遂結果を惹起する現実的な危険が発生した」時点で未遂犯が処罰対象になるということです(最決平成16年3月22日)。
たとえば、欺罔行為に着手したが相手が錯誤に陥らずに財物交付を受けられなかった場合や、欺罔行為によって相手が錯誤に陥ったが財物交付に至る前に犯行がバレて逮捕された場合などが、詐欺未遂罪の具体例として挙げられます。
組織犯罪処罰法違反
詐欺行為が複数人で実施された場合には、刑法に規定される詐欺罪の共犯が成立するのが原則です。
ただし、詐欺行為が、団体の活動として、詐欺行為の実行を目的として組織化された集団によって実施された場合には、法定刑が「1年以上の有期懲役刑」に引き上げられます(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条第1項第13号(通称「組織犯罪処罰法」))。
たとえば、暴力団・半グレ集団・振り込め詐欺グループ・特殊詐欺グループのように綿密な計画のうえ組織的に詐欺行為を働く団体の末端構成員だった場合は当然組織犯罪処罰法の適用を受けますし、地元の不良グループや友達同士で日常的に詐欺行為に及んでいたような軽はずみなケースでも同法の処罰対象になる場合があります。
詐欺罪の時効完成前に逮捕される可能性が高い5つのケース
詐欺事件が以下の要素を備えている場合、事件を起こしてから数年が経過したとしても、公訴時効が完成しない限りはいつ逮捕されるか分かりません。
- 詐欺事件の被害額が大きいケース
- 組織的に特殊詐欺事件が引き起こされたケース
- 被害者の処罰感情が強いケース
- 被疑者の逃亡・罪証隠滅のおそれが高いケース
- 詐欺での前科・前歴があるケース
詐欺罪は「10年以下の懲役刑」という比較的厳しい刑罰が科される犯罪類型であることを踏まえると、軽い刑事処分獲得を目指すには丁寧な防御活動が不可欠です。
特に、ここに挙げた特徴を有する詐欺事件では刑事手続きの初期段階からの防御活動が命運を分けると言っても過言ではないので、かならず刑事事件を専門に力を入れている弁護士にご相談ください。
詐欺事件で高額被害が発生している場合
警察が本格的な捜査に着手するか否かは、被害額の大きさに左右されるのが実情です。
もちろん、被害額の多寡にかかわらず、詐欺の疑いがあれば逮捕される可能性がありますが、警察の捜査リソースにも限りはあるので、被害額が少額だと捜査が後回しになることも少なくないでしょう。たとえば、数百円程度の寸借詐欺と、数千万円の大規模詐欺事件では、捜査活動の力の入れ具合に差が生じるのも仕方ありません。
したがって、過去に起こした詐欺事件で高額被害を発生させた場合や、複数の詐欺行為によって被害総額がある程度累積している場合には、犯行からしばらく時間が経過して公訴時効完成が近づいていても逮捕される可能性があると考えられます。
組織的な詐欺行為や特殊詐欺の場合
劇場型詐欺事件や特殊詐欺事件が社会問題化している現状を踏まえると、単独犯ではなく共犯関係が疑われる組織的詐欺事件は警察が捜査に力を入れる可能性が高いと言えるでしょう。
たとえば、個人間の金銭トラブルが詐欺事件に発展したようなケースでは、当該事件がそれ以上社会的に悪影響を及ぼすリスクは大きくありません。これに対して、特殊詐欺事件のように犯罪グループが関わっている場合には、捜査機関が未だ把握できていない被害者が既に発生していたり、詐欺以外の犯罪行為によって社会に数々の弊害が生じる危険性も高いです。
したがって、捜査機関は「治安を維持して社会全体の安全性を守る」という職責を担っている以上、大規模詐欺集団に対する摘発は本格的に行われると考えられます。受け子・出し子のような末端構成員として詐欺事件に関与しただけでも厳しい捜査対象になるのは間違いないので、「将来的に詐欺罪で捕まるかもしれない」「組織から見限られて実行犯・主犯の責任を押し付けられるかもしれない」と不安を抱えているのなら、逮捕に至っていない段階で弁護士に相談をして自首・示談などの方策を検討してもらうべきでしょう。
詐欺被害者の処罰感情が強い場合
警察が詐欺事件について本格的な捜査活動を取り組むかどうかは「被害者の処罰感情の強さ」に左右されます。
たとえば、被害額が少額で、単独で詐欺事件が引き起こされた場合でも、被害者が強く刑事処罰を望んでいるのなら、警察は捜査に力を入れざるを得ません。もちろん、被害届が提出されただけで捜査義務が生じるわけではありませんが、何度も被害者側から捜査進捗について問い合わせがあるような状況だと、警察が被害者を無碍にできないのは当然でしょう。
したがって、特に軽微な詐欺事件については、警察が本格的な捜査に取り組む前に被害者との間で示談を成立させることが鍵になると考えられます。丁寧に謝罪をしたうえで示談金の支払いを済ませれば被害届を取り下げてくれるので、刑事弁護や示談実績豊富な弁護士を頼りましょう。
詐欺事件の証拠隠滅や逃亡のおそれが高い場合
警察が詐欺事件についての捜査を開始して犯人を特定したとしても、(初犯で軽微な詐欺事件に限って)逃亡や罪証隠滅のおそれがないケースでは任意の事情聴取・取調べベースで手続きが進められることもあります。
最終的な起訴・不起訴は検察官の判断に委ねられますが、在宅事件として刑事手続きを進めてもらうことができれば、逮捕・勾留による長期間の身柄拘束付き取調べを回避できるので、日常生活に過度な支障が生じることはないでしょう。
つまり、詐欺事件について共犯者や黒幕の存在を隠しているケースや、詐欺事件について供述を拒んでいるケース、共犯者などと口裏を合わせて嘘の供述を創作する危険性があるようなケースでは、「早期に身柄を押さえなければ詐欺事件の真相究明ができない」と判断されるので、逮捕手続きに移行する可能性が高いということです。
したがって、詐欺罪の容疑で逮捕されるのを回避するには、身元や所在を明らかにして任意の事情聴取に対して丁寧に向き合うのが重要だと考えられます。逮捕前の段階から弁護士に相談していれば、事情聴取等への対応方法などについてもアドバイスを期待できるので、逮捕による身柄拘束リスクを回避・軽減できるでしょう。
詐欺罪の前科・前歴がある場合
警察が捜査に着手して被疑者を特定したところ、当該人物に詐欺罪の前科・前歴があることが判明すると、どれだけ警察からの問い合わせに真摯・誠実に対応しようとしても、任意の事情聴取の段階を飛ばして逮捕手続きに移行する可能性が高いでしょう。
そもそも、詐欺罪の前科がある人物がふたたび罪を犯したことが疑われる状態である時点で、適切な形で更生できていない証拠です。そのような人物が「任意の事情聴取には応じる」「真摯に反省をしている」と言ったところで、信用してもらえないのは仕方ありません。また、前歴と前科はまったく別物とは言っても、過去に捜査対象になった事実がある人物がふたたび捜査線上にあがってきた以上、ある程度の容疑が固まっている状態なら、「逮捕状を請求して逃げ道のない状態で本格的な取調べを行おう」と警察側が判断するのも当然です。
以上を踏まえると、詐欺の前科・前歴がある人物がふたたび刑事訴追されるリスクに晒されている場合には、「逮捕されないこと」を目指すのではなく、「できるだけ身柄拘束期間を短縮化すること」「実刑判決を避けること」をターゲットにして防御活動を展開するのが適切だと考えられます。弁護士に相談すれば個別具体的な事情を総合的に考慮して筋の通った戦略を示してくれるでしょう。
時効完成前に詐欺罪で逮捕されるか不安なときに弁護士へ相談するメリット6つ
公訴時効が完成するまでに詐欺罪が警察にバレて逮捕されるか不安なときや、「警察に逮捕されたときに備えて事前にできる限りの防御活動を尽くしておきたい」と希望するときは、弁護士に相談することをおすすめします。
なぜなら、刑事弁護の実績豊富な専門家に相談することで以下6点のメリットが手に入るからです。
- 詐欺被害者との間で早期に示談をまとめてくれる
- 警察に逮捕される前に詐欺事件について自首するべきかを判断してくれる
- 詐欺罪の容疑で逮捕されても身柄拘束期間短縮化を目指してくれる
- 詐欺罪の容疑で逮捕されても前科回避を目指して尽力してくれる
- 詐欺罪の容疑で起訴されても執行猶予付き判決獲得を目指してくれる
- 逮捕勾留された後でも弁護士接見の機会を有効活用してくれる
防御活動に着手するタイミングが早いほど防御活動の選択肢は増えます。些細な不安でも丁寧に回答してくれるので、どうぞお気軽に信頼できる弁護士までご相談ください。
詐欺罪で逮捕される前に被害者との間で示談交渉を進めてくれる
弁護士に依頼すれば、詐欺被害者と連絡をとって早期に示談をまとめてくれます。
被害者との間で示談が成立すれば、逮捕前であれば被害届を提出しない旨を、逮捕後であれば被害届の取り下げを和解契約の内容に掲げることができます。その結果、被害者の処罰感情が薄いことを理由に、軽い刑事処分獲得を目指しやすくなるでしょう(ただし、詐欺事件の被害額が高額だったり、組織的犯行を伺わせる事情があったりすると、有罪になる可能性を否定できません)。
詐欺事件についての示談金相場は事案によって異なりますが、一般的には、損害額に加えて数十万円程度の慰謝料を支払うことで合意に至ることが多いです。示談金の支払い方法は和解契約の内容次第ですが、示談金を全額支払いきって被害弁償が済んでいる方が、捜査機関の心証は良くなるでしょう。
詐欺罪で逮捕される前に自首するべきか否かを判断してくれる
弁護士に相談すれば、詐欺罪で逮捕される前に自首する有効性を判断してくれます。
そもそも、捜査機関が事件を認知する前に犯人自ら自首をすれば、刑罰の減軽や軽い刑事処分を期待できるのが実情です(刑法第42条第1項)。とはいえ、詐欺事件が悪質で逮捕を回避できない状況であるのなら、自首という情状要素を考慮したとしても有罪判決が下される可能性も否定できません。たとえば、公訴時効完成直前で捕まる可能性がほとんどゼロに近い状況において、わざわざ自首をするのは賢い選択肢とは言えないでしょう。
もちろん、弁護士が率先して「警察から逃げ続けてください」と勧めることはありませんが、依頼人の利益を最大化することを使命として守秘義務を負っている弁護士がわざわざ警察に通報することもありません。諸般の事情を総合的に考慮して、今すぐに自首する必要があるのか、自首する前にもう少し様子を見るべきか否か、自首する前に被害者との示談を進めておくべきかなどを分析して方向性を決定してくれるでしょう。
詐欺罪で逮捕されたとしても身柄拘束期間の短縮化を目指して尽力してくれる
詐欺罪の容疑で逮捕された場合、逮捕段階で48時間、検察段階で24時間、勾留請求されると10日間~20日間身柄が拘束されます。
身柄拘束期間中は外部と一切連絡を取れずに取調べだけに向き合い続けなければいけないので、たとえば、会社や学校に連絡を取ることも許されません。その結果、学校や会社、家族、親族などに逮捕されたことが知られてしまい、さまざまな社会的リスクを強いられることになってしまいます。
弁護士に相談すれば、このような身柄拘束期間を短縮化するために尽力してくれます。たとえば、留置の必要性がないことを積極的に主張して逮捕処分の取消し・勾留処分の取消しを目指してくれたり、逃亡・罪証隠滅のおそれがないことを示して在宅事件としての取扱いを希望してくれたりするでしょう。
詐欺罪で逮捕されたとしても前科回避を目指して尽力してくれる
詐欺罪で逮捕されて事件が検察官送致されたとしても、弁護士に相談すれば、不起訴処分獲得を目指して尽力してくれます。
そもそも、日本の刑事裁判の有罪率は約99%とも言われている現状を踏まえると、検察官が起訴処分を下した(公訴を提起した)時点で有罪判決が下されるのが確定的になります。つまり、有罪判決や前科回避を目指すなら、何としても検察官による不起訴処分を獲得しなければいけないということです。
たとえば、被害額が少額で初犯であれば、真摯な姿勢で取調べに向き合い、被害者に対して示談金の支払いを済ませ、更生をサポートしてくれる家庭環境などがあることを説明できれば、「起訴猶予」を理由とする不起訴処分を獲得できるでしょう。また、詐欺罪における「欺罔行為」は立証が難しい成立要件だと言われていることを踏まえたうえで、”犯行”と呼ばれている行為当時に騙す意図がなかったことを示すような客観的証拠を収集して、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」を理由とする不起訴処分獲得も視野に入れてくれます。
以上を踏まえると、「公訴時効完成前に詐欺罪で逮捕されたとしても、かならずしも有罪判決が確定するわけではない」ということがご理解いただけるかと思います。前科がない方が社会復帰を目指しやすいので、状況が許す限り、不起訴処分獲得を目指して尽力してもらうべきでしょう。
詐欺罪で逮捕されたとしても執行猶予付き判決獲得を目指して尽力してくれる
詐欺罪の容疑で起訴処分が下されると公開の刑事裁判にかけられますが、刑事事件の実績豊富な弁護士なら、執行猶予付き判決を獲得して実刑判決を回避してくれるでしょう。
執行猶予とは、「公判において得られた証拠等を総合的に考慮した結果、有罪判決による刑の執行を一定期間(執行猶予期間)先送ることとし、執行猶予取消し事由が生じることなく無事に当該を満了したときには、有罪判決による刑の執行自体が消滅する」という制度のことです(刑法第25条~第27条の7)。実刑判決が確定すると刑務所に収監されますが、執行猶予付き判決が確定すれば社会生活を送りながら更生を目指すことが可能となります。
ただし、執行猶予付き判決の対象になるのは、「3年以下の懲役刑・禁錮刑または50万円以下の罰金刑」である点に注意しなければいけません。つまり、詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役刑」なので、事案の状況次第では、「3年以下の懲役刑を言い渡される予定」という執行猶予の要件を満たさない可能性があるということです。
したがって、詐欺事件が刑事裁判にかけられる場合には、執行猶予付き判決の対象に含まれるように、情状要素を丁寧に主張立証する必要があると考えられます。刑事事件に強い弁護士なら、示談が成立していること、真摯に反省していること、犯行に至った背景や動機に同情すべき点があることなどを上手に組み立てて主張を展開してくれるので、初犯なら執行猶予付き判決獲得も充分目指せるでしょう。
詐欺罪で逮捕されたとしても接見機会を利用して明確なアドバイスを提供してくれる
逮捕・勾留中の被疑者と直接面会できるのは弁護士だけです。最大23日に及ぶ孤独な身柄拘束期間中、自分の唯一の味方である弁護士と会話をできるだけでも心強い存在になります。
さらに、接見機会を利用して、弁護士がさまざまなアドバイスを提供してくれる点も大きなメリットです。たとえば、取調べ中の質問内容から捜査機関がどこまでの証拠を掴んでいるのかを分析して、供述範囲や供述の方向性を確立してくれるでしょう。また、安易に供述調書にサインしてはいけない、誘導尋問に応じてはいけないなどのコツも提供してくれます。さらに、不当な取調べに対しては異議を申し立てて証拠の有効性を争ってくれます。
このように、弁護士は逮捕・勾留段階から被疑者の味方として捜査機関に対峙してくれるので、孤独な取調べ期間を乗り切る助けとなるでしょう。
詐欺罪の公訴時効完成を待つのはハイリスク!弁護士に相談して適切な対処法を提案してもらおう
詐欺罪の公訴時効は7年なので、公訴時効完成によって刑事罰から逃げ切るのは現実的ではありません。特に、近年では特殊詐欺などが社会問題化しているので、事件が明るみになると、警察はありとあらゆる手を尽くして本気で捜査を行うことが予測されます。
したがって、詐欺行為に関与してしまった場合には、警察による捜査が進んでいるか否かにかかわらず、現段階で被害者との間で早期に示談を進めるのが重要だと考えられます。詐欺事件について民事的な解決が済んでいるのなら、警察が事件を認知しても逮捕に至る可能性は低くなりますし、万が一逮捕されたとしても、軽い刑事処分を期待できるからです。
刑事事件に強い弁護士に相談すれば、捜査の手が及ぶ前の段階で早期に被害者との間で示談を成立させてくれます。専門家である弁護士が代理人として示談交渉を申し入れれば、感情的になっている詐欺被害者も謝罪を受け入れてくれやすくなるでしょう。