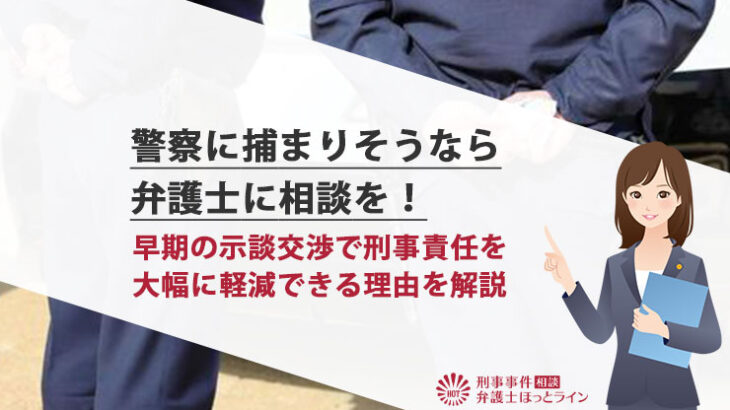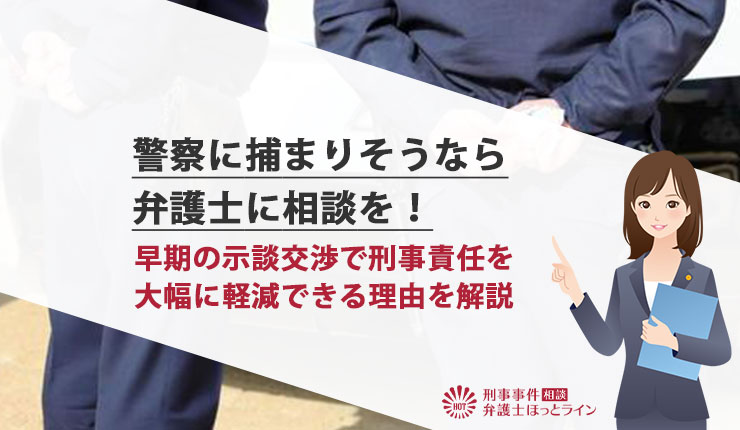
犯罪行為がバレて捕まりそうなときには、被疑者が気付かないうちに警察の内定調査が着々と進められていることがほとんどです。警察から任意の出頭要請を求められたりした段階では、すでに過去の犯罪行為に関する捜査の大部分が終了していると言っても過言ではないでしょう。
そのため、捕まりそうだからと言って逃亡や証拠隠滅を図ったりすることに意味はありません。そもそも、公訴時効が完成するまで逃亡生活を続けるのは現実的にかなり難しいですし、捜査を撹乱・妨害する意図があるとみなされて刑事処分や判決内容が不利になるだけだからです。
そこで今回は、過去の犯罪行為を理由に捕まりそうな方や、警察から任意の出頭要請がかかって不安を抱えている方のために、以下4点について分かりやすく解説します。
- 捕まりそうなときに被疑者の周辺で起きる出来事
- 捕まりそうなときに絶対にやってはいけないこと
- 警察に捕まった後の刑事手続きの流れ
- 捕まりそうなときに弁護士へ相談するメリット
警察から何かしらの方法で接触があったか否かにかかわらず、過去の犯罪行為が公訴時効を迎えていないのなら、念のために現段階で弁護士に相談することを強くおすすめします。
刑事事件を専門に扱っている弁護士に相談をすれば、早期に犯罪被害者との間で示談交渉を開始して刑事事件化自体を防いだり、今後の捜査活動に先回りする形で証拠集めなどの防御活動に力を入れてくれるでしょう。
目次
捕まりそうなときに弁護士へ相談するべき理由5つ
捕まりそうなときに最優先でするべきことは「弁護士への相談」です。
なぜなら、警察に捕まる前の段階で専門家の意見を仰ぐことによって以下5点のメリットが得られるからです。
- 被害者との間で早期に示談交渉を開始してくれる
- 先回りした防御活動によって、身柄拘束自体を回避したり捕まった後の身柄拘束期間を短縮できる
- 有利な刑事処分獲得に役立つ証拠を収集してくれる
- 捕まった後すぐに接見機会を設けて今後の防御方針を明確化してくれる
- 刑事手続きによって日常生活・社会生活に生じる悪影響に配慮して防御活動を展開してくれる
なお、「弁護士が警察に通報するかもしれないので相談できない」と不安を抱える犯罪加害者は少なくありませんが、弁護士は依頼人の利益を最大化する責務を担っており「守秘義務」が課されているので、余程特殊な事情が存在しない限り、警察に通報されることはないのでご安心ください。
被害者が存在する事件なら示談交渉による民事的解決を期待できるから
警察に捕まりそうな段階で弁護士に依頼すれば、早期に被害者との間で示談交渉を開始してくれます。
示談とは、「私人間の紛争を当事者間の話し合いによって民事的に解決すること(和解契約を締結すること)」です。
刑事事件の当事者間における示談交渉では、「加害者が被害者に一定額の示談金を支払う」代わりに、「被害届・告訴状を取り下げること」「警察に被害申告しないこと」「”民事的解決が済んだので処罰感情がない”と捜査機関や裁判所に伝えること」が示談条件に掲げられるのが一般的です。
たとえば、器物損壊罪のような親告罪の容疑がかかっているケースで示談が成立して告訴状を取り下げてもらえれば、その時点で公訴提起される可能性が消滅するので、逮捕されたり有罪になったりするリスクを回避できます。
また、傷害罪や窃盗罪の非親告罪の容疑をかけられている場合でも、「当事者間で示談が成立して民事的解決が済んでいること」は刑事処分や判決内容を有利にする機能を有します。示談が成立しているだけで逮捕・勾留を回避できたり、不起訴処分を獲得しやすくなるでしょう。
さらに、被害者が警察に通報する前に示談交渉に着手して民事的解決を済ますことができれば、過去の犯罪行為の刑事事件化自体も回避できます。この場合には、警察が事件のことを知ることもないので、前科どころか前歴も残りません。
確かに、「民事事件と刑事事件は別物」とよく言われますが、刑事責任を決定する過程では「民事的解決が済んでいるか」「被害者の処罰感情は強いのか弱いのか」が重視されるのが実情です。
弁護士に相談するタイミングが早いほど示談成立の恩恵を享受しやすくなるので、警察から連絡があるか否かに関わらず、できるだけ早いタイミングで示談交渉や刑事事件の実績豊富な弁護士までご相談ください。
- 不安や怒りを抱いている犯罪被害者と加害者本人同士では冷静に話し合いを行うのが難しい
- 盗撮や下着泥棒、痴漢などの性犯罪の場合、そもそも被害者側が示談交渉にさえ応じてくれない
- 弁護士が着任していなければ、警察から犯罪被害者の連絡先を教えてもらえないことが多い
- 示談相場から乖離した示談金を提示されるなど、足元を見られて常識的な示談条件での合意を形成できない
- 示談交渉が長引くうちに着々と刑事手続きが進行してしまう(防御活動の選択肢が狭まる)
- 犯罪被害者による嫌がらせを受けるリスクが生じる(家族や会社への連絡、ネットへの書き込みなど)
刑事手続きには時間制限があるので、示談成立のタイミングが遅れるほど不利になります。「迅速かつ冷静に、常識的な示談条件で被害者の納得を得る」ためには弁護士が有する交渉ノウハウを頼るのが一番なので、今後の社会生活のためにも迷わず専門家の支援を受けるようにしてください。
早期の弁護活動により身柄拘束される期間を短縮化・回避できるから
警察に捕まりそうな段階で弁護士に相談をしておけば、「身柄拘束」という刑事手続きのデメリットを回避・軽減できるでしょう。
後述のように、警察に捕まってしまうと、逮捕・勾留という身柄拘束処分によって数日~数週間身柄拘束されるリスクに晒されます。また、起訴後勾留が続いたり、本罪だけではなく余罪についても再逮捕・再勾留が繰り返されたりすると、最終的な刑事責任が確定する前の段階で数カ月に及ぶ身柄拘束期間が生じる可能性も否定できません。
たとえば、被疑者が会社員の場合、数日無断欠勤が続くだけで勤務先から不信感を抱かれます。数週間に及ぶ欠勤になると理由を説明せざるを得なくなりますし、会社での立場も悪くなるでしょう。さらに、会社に刑事事件を起こしたことがバレた結果、懲戒処分を下される可能性も生じかねません。
警察に捕まる前の段階で弁護士に相談すれば、早期の示談成立によって逮捕自体を回避できる可能性が高まるので、会社にバレる心配も軽減できます。また、事前に弁護士との間で今後の防御方針・供述方針について用意できるので、捕まった後に実施される取調べにも準備万端で臨んでスムーズな刑事手続きの進行を期待しやすくなるでしょう。
防御活動に役立つ証拠を収集してくれるから
捕まる前に弁護士に相談をしておけば、警察の捜査が及んだときに役立つ「有利な証拠」を事前に収集してくれます。
たとえば、量刑を争う際に重要になる情状証人や、犯罪に及んだやむにやまれぬ理由を証明する物証、アリバイを証明する防犯カメラ映像や通話履歴など、さまざまな下準備をしておけば、刑事手続きの早期終結、刑事責任の軽減を実現しやすくなるでしょう。
なお、「捕まる前に弁護士に相談」と言っても、弁護士に相談をした翌日に逮捕されてしまうと意味がありません。時間の余裕はあればあるほど良いので、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談してください。
逮捕されてもすぐに接見機会を作ってくれるから
捕まりそうな段階で弁護士とのパイプを作っておけば、逮捕された後の接見がスムーズです。
そもそも、警察に捕まってしまうと、接見禁止処分が付されることが多いので、弁護士以外の第三者とは面会できません。自分の味方がいない状況で厳しい取調べが実施されると、孤独な環境で心身が疲弊してしまいます。
これに対して、事前に信頼できる弁護士と関係性を築いておけば、逮捕された後の孤独な状況でも、弁護士と接見するだけで励みになるでしょう。また、事件についてすでに情報を共有できているので、限られた接見時間のなかでも効率的なアドバイスを期待できます。
被疑者の状況を踏まえた弁護活動を期待できるから
警察に捕まりそうな段階で弁護士に相談すれば被疑者の属性・性格等を共有できているので、被疑者の個別事情を踏まえた弁護活動を期待しやすくなります。
たとえば、被疑者が独身で無職なら、刑事事件を起こして逮捕されたことを会社や配偶者に知られる心配をする必要はありません。このようなケースでは、今後の社会生活のために「実刑判決を回避すること」「前科をつけないこと」が防御目標の最低ラインになるので、ある程度時間の幅をもって入念な防御活動が可能になります。
これに対して、被疑者が会社員の場合で「どうしても会社に知られたくない」という希望を抱いているのなら、「逮捕による身柄拘束」を回避することが防御活動の第一目標に掲げられるでしょう。この場合、「警察から接触がある前に示談を成立させること」が不可欠になるので、捜査活動の進捗状況が明確でない以上、できるだけ早いタイミングで弁護士に依頼をして示談条件をすり合わせてもらわなければいけません。
さらに、被疑者が学生の場合には「今後の就職活動等に影響を与えたくない」「学校にバレたくない」、未婚だが恋人がいる場合には「報道されずにできるだけ穏便に解決したい」、被疑者が専門職従事者なら「前科による資格制限を回避したい」など、さまざまなニーズがあるはずです。
以上のように、きめ細やかで柔軟な防御活動を期待するには、警察に捕まってから弁護士に相談するのでは遅すぎます。「捕まりそう」と不安を抱えている段階だからこそ着手できる防御活動は少なくないので、できるだけ早い段階で刑事実務に精通した弁護士までご相談ください。
捕まりそうなときに身の回りで起こることや逮捕の前兆
警察に捕まりそうなときに被疑者の身の回りでは以下のようなことが起こります。
- 被害届・告訴状・告発状が提出される
- 内定調査・張り込み・尾行などの捜査活動が実施される
- 警察から任意の事情聴取を求められる
- 家宅捜索が実施される
被害届・告訴状・告発状の提出などによって警察が犯罪行為を知る
大前提として、警察が捜査活動を開始するには「犯罪を知る」必要があります。
そして、犯罪行為の種類によって”捜査の端緒”はさまざまですが、被害者がいるタイプの犯罪類型(万引き、痴漢など)では、被害者等による被害申告がきっかけになるのが一般的です。
- 被害届:犯罪被害者が捜査機関に対して「犯罪被害の事実を申告」すること
- 告訴状:被害者及びその他の告訴権者が捜査機関に対して「犯罪被害の事実を申告」して「刑事訴追を求める」こと
- 告発状:告訴権者及び犯人以外の者が捜査機関に対して「犯罪被害の事実を申告」して「刑事訴追を求める」こと
そもそも、犯罪に及んでから逃げ回っている状況なら、被害者が被害届を提出した事実を知ることはできません。
これに対して、被害申告される前に被害者と示談交渉を進めているケースなら、被害者側の反応によって被害届が提出されたか否かを判断することが可能です。たとえば、被害者によっては警察に相談したことを面と向かって教えてくれる場合もあります。また、「示談条件について誠意を感じられない」などのニュアンスが含まれるようになると、刑事告訴が迫っていると理解できるでしょう。
警察が内定調査・張り込み・尾行などの捜査活動を実施する
警察が逮捕状を請求して通常逮捕手続きに着手するには、「逮捕状の発付要件を満たすだけの客観的証拠」が必要です。
つまり、警察に捕まりそうな段階では、すでに警察がかなりの捜査活動を展開している可能性が高いということです。
たとえば、痴漢犯人の身元特定が済んでいるなら、尾行によって現行犯逮捕のチャンスが狙われることもあるでしょう。また、覚醒剤などの薬物事犯の容疑がかかっているケースでは、密売ルートの内定調査や取引現場周辺の張り込みが行われることも多いです。
警察から任意の出頭要請を求められる
警察から任意の出頭要請を求められると、近い将来逮捕される可能性があると理解できます。
たとえば、容疑がある程度固まった段階において、いきなり逮捕手続きに着手するのではなく、電話連絡や自宅訪問などの方法によって「警察に出頭して事情を聞かせて欲しい」という旨が伝えられます。
出頭後の取調べにおいて「逮捕の必要性がある」と判断された場合、その場で逮捕状が請求されて身柄拘束されることもあるでしょう。その一方で、任意の事情聴取を経ても「身柄拘束をする必要性はない」と判断されると、そのまま帰宅を許されるパターンもあり得ます。後者のケースでは、在宅のまま刑事手続きが進められて最終的な処分が決定されることになります。
ただし、警察からの呼び出しに応じなかったり、誠実な姿勢で取調べに対応しなかったりすると、それだけで「逃亡・証拠隠滅のおそれが高い」と評価されるので、逮捕状が請求される可能性が高まります。
警察からの出頭要請がかかると恐怖心が芽生えるかもしれませんが、出頭要請に素直に応じた方が結果的に身柄拘束処分を回避できる可能性が高いです。警察に出頭する前に弁護士へ相談をして、供述方針などについてアドバイスを求めるべきでしょう。
捜査機関によって家宅捜索が実施される
押収や捜索が実施されると逮捕が近付いていると言えるでしょう。
押収とは、物の占有を取得する処分のことです。押収は、強制処分としての「差押え」と、遺留品や任意提出物に対する「領置」に分けられます。捜索とは、一定の場所において差し押さえる物を探す処分のことです。
たとえば、薬物の使用が疑われる被疑者の自宅に対して捜索差押えが実施されるのは、捜査機関が「被疑者宅に薬物や薬物使用時に使用した注射器などの証拠物が存在する」と判断しているからです(捜索差押えをするには令状が必要なので、令状が発付されるほどの証拠がすでに揃っているということです)。
捜索差押えによって犯罪を決定付ける証拠が発見された場合には、その場で現行犯逮捕や緊急逮捕が実施されたり、逮捕状が請求されることになるでしょう。
【注意!】多くの逮捕手続きはある日前触れもなく実行される
警察に捕まりそうなときには被疑者の身の回りで数々のことが起こりますが、残念ながら、被疑者本人が予兆を察知するのはかなり難しいのが実情です。
なぜなら、警察は被疑者に知られないように捜査活動を進めて着々と犯罪の証拠を集めるからです。警察側は、通常逮捕が迫っていることを被疑者が察知して逃亡を図ったり証拠を隠滅したりすることを怖れています。
したがって、ほとんどの逮捕手続きは被疑者にとっては「ある日いきなり」実行されるものなので、過去の犯罪行為に心当たりがあるなら、警察から接触がある前に弁護士へ相談するのが賢明だと考えられます。逮捕処分が実行されると限られた時間制限のなかで防御活動を展開しなければいけません。時間に余裕がある状況で余裕をもって防御活動を展開してもらいましょう。
捕まりそうなときにやってはいけないこと4つ
警察に捕まりそうだからと言って、以下4つの行為は厳禁です。
- 証拠を隠滅する
- 逃走する
- 警察からの出頭要請を無視する
- 供述調書の内容を確認せずにサインする
証拠を隠滅する
「証拠がなくなれば逮捕されないはず」という気持ちになるのも理解できますが、捕まりそうだからと言って、証拠を隠滅するのは厳禁です。
なぜなら、日本の警察は優秀なので「証拠を隠滅したこと」自体がすぐにバレますし、隠滅した証拠は簡単に復元されるからです。また、証拠を隠滅する悪質な態度を見せてしまうと、「留置の必要性が高い」と判断されるので、逮捕状の発付を免れにくくなってしまいます。さらに、証拠の復元等に時間を要することを理由に、勾留請求が実施されて身柄拘束期間が長期化するリスクも高まるでしょう。
以上を踏まえると、身柄拘束期間を短縮化して軽い刑事処分獲得を目指すなら、最初から犯罪の証拠を素直に提出した方が良いと考えられます。
逃走する
捕まりそうだからと言って、逃走することもおすすめできません。
なぜなら、罪状によって公訴時効期間は異なるものの、公訴時効が完成するまでの数年間、捜査機関にバレずに逃げ切るのは不可能に近いからです。
また、仮に数カ月程度の逃走に成功したとしても、その後逮捕されると刑事処分や判決内容が重くなる可能性が高いです。最初から素直に出頭して罪を認めていれば不起訴処分を獲得できたのに、中途半端に逃げてしまったために実刑判決が下されてしまうこともあり得ます。
そもそも、警察に捕まったからと言って、刑事責任が確定するわけではないということをご理解ください。たとえば、勾留を回避できれば数日で身柄が釈放されますし、不起訴処分を獲得できれば前科もつきません。起訴処分が下されたとしても執行猶予付き判決・罰金刑を確定させることに成功すれば、日常生活を送りながら刑事責任を果たすことも可能です。
警察からの連絡を無視する
捕まるのが怖いからと言って、警察からの連絡を無視してはいけません。
なぜなら、警察からの出頭要請や呼び出しを無視すると、それだけで「逃亡・証拠隠滅のおそれがある」と評価されて、逮捕状が発付される可能性が高くなるからです。
いっけん遠回りのように思えるかもしれませんが、警察からの連絡に素直に応じた方が、結果として刑事処分や判決内容を軽くすることができます。弁護士と相談のうえ、警察からの連絡には誠実に対応してください。
事情や被疑事実も確認せずに供述調書にサインする
捜査機関に対して不必要なほど反抗的な態度をとる必要はありませんが、逆に、警察の言いなりになるのも危険です。たとえば、捜査機関からの印象を良くしたいがために、事実に反することに同意をしたり、供述調書の内容を確認せずにサインをしてはいけません。
捜査段階の取調べで作成される供述調書に記名押印すると、「被疑者が供述調書の内容に同意していること」が証明されてしまいます。仮に供述調書が間違っていて警察に都合の良い内容に捻じ曲げられていたとしても、被疑者のサインがある以上、供述調書の内容に反する事実を主張立証するのは難しくなるでしょう。
したがって、取調べ段階で供述調書が作成された場合には、時間をかけてゆっくりと内容を確認して、間違いがあれば修正を依頼し、どうしても納得できない調書にはサインしないようにしてください。刑事事件に強い弁護士に相談すれば供述調書対策についてもアドバイスを貰えるでしょう。
警察に捕まった後の刑事手続きの流れ
捕まりそうなときだからこそ、警察に逮捕された後の刑事手続きの流れを理解することをおすすめします。
というのも、今後予測される刑事手続きの流れがあらかじめ分かっていれば、刑事手続きの各段階に応じて目指すべき防御方針が最初からはっきりするからです。
どのような罪状で逮捕されるかによって刑事手続きの流れは異なりますが、一般的な刑事手続きは以下の流れで進行することが多いです。
- 警察に逮捕されて身柄を確保される
- 身柄が捕まった状態で警察段階の取調べが実施される
- 警察段階の取調べが終わると検察官に身柄が送致される
- 身柄が捕まった状態で検察段階の取調べが実施される
- 検察官が事件を刑事裁判にかけるか否か(公訴提起するか否か)決定する
- 捕まった事件が公開の刑事裁判にかけられる
警察に身柄を確保される
過去の犯罪行為について警察が本格的な捜査活動を実施して容疑が固まると、逮捕手続きによって被疑者の身柄が確保されます。
逮捕とは、「被疑者の身柄を確保する強制処分」のことです。強制処分なので、警察が逮捕手続きに着手した時点で被疑者の身体・行動の自由は奪われます。
逮捕手続きは以下3種類に大別されます。
- 通常逮捕
- 現行犯逮捕
- 緊急逮捕
通常逮捕
通常逮捕とは、「裁判官の事前審査を経て発付される逮捕状に基づいて実施される身柄拘束処分」を意味します(刑事訴訟法第199条第1項)。「強制処分には裁判官の発付する令状が必要」という令状主義の原則が素直に適用される逮捕手続きです。「後日逮捕」と表現されることも多いですが、「通常逮捕」が正式な呼称です。
過去の犯罪行為について逮捕状が発付されるのは、以下2つの要件を満たすときです(犯罪捜査規範第122条第1項)。
- 逮捕の理由
- 逮捕の必要性
第1に、「逮捕の理由」とは、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること」です。被疑者が犯罪行為に及んだ客観的な証拠や事前に実施された取調べの供述内容などから、構成要件に該当する事実があるかどうかが判断されます。
第2に、「逮捕の必要性」とは、「逃亡や証拠隠滅のおそれが高いために留置する必要性があること」です。被疑者が犯行を否認している、共犯者と口裏を合わせる可能性が高い、住所や職業が不明などのケースでは、逮捕の必要性があると判断されやすいでしょう。
逮捕状に基づいて通常逮捕が実施される場合、早朝など被疑者が所在することが確実なタイミングで捜査員が自宅などにやってきて「逮捕状が呈示」されます(刑事訴訟法第201条第1項)。
「過去の犯罪行為を理由に捕まりそう」と不安を抱えている方がもっとも心配する必要があるのが「通常逮捕」と言えるでしょう。
事前に示談交渉等を進めておくだけで今後の刑事手続きを有利に進めることができるので、捕まりそうな前兆があるか否かにかかわらず、できるだけ早いタイミングで刑事事件に強い弁護士までご相談ください。
現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、「現行犯人(現に罪を行い、または、現に罪を行い終わった者)を対象とする逮捕処分」のことです(刑事訴訟法第212条第1項)。
現行犯逮捕は捜査機関以外の一般私人が令状なしで行うことができます(同法第213条)。通常逮捕とは異なり、「令状主義の例外」に位置付けられるものです。一般私人によって身柄が押さえられた場合には、地方検察庁・区検察庁の検察官や司法警察職員に身柄が引き渡されます(同法第214条)。
また、犯行現場から逃走を図った場合でも、「以下4つの要件のいずれかを満たす者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるとき(準現行犯人)」は現行犯人と扱われて、現行犯逮捕の対象に含まれます(同法第212条第2項)。
- 犯人として追呼されているとき
- 贓物または明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき
- 身体または被服に犯罪の顕著な証跡があるとき
- 誰何されて逃走しようとするとき
「捕まりそう」と不安を抱えている人の場合、現行犯逮捕を心配する必要はないでしょう。
その一方で、犯行現場から逃走をして間もない状況なら「準現行犯人」として現行犯逮捕のリスクに晒された状態です。仮にそのまま逃走を続けても防犯カメラ映像などから身元特定されて後日逮捕されるのは目に見えています。
そのため、犯行に及んで逃走中の場合には、「このまま公訴時効が完成するまで逃げ切りを狙う」のではなく、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談をしたうえで、警察から連絡が来る前に示談交渉を開始したり、自首をすることを前向きに検討するべきと言えるでしょう。
緊急逮捕
緊急逮捕とは、「一定の重大犯罪について犯人であることが明らかな状況において、逮捕状の発付手続きを履践していると被疑者が逃亡してその後の逮捕が困難になる場合を対象とする逮捕処分」のことです(刑事訴訟法第210条第1項前段)。
たとえば、警察官が重大犯罪の容疑で指名手配されている被疑者と偶然街中で遭遇したケースや、職務質問の過程で重大犯罪の被疑者であることが発覚したケースなどにおいて、緊急逮捕が実施されることがあります。
緊急逮捕は現行犯逮捕とは異なるものの、被疑者の身柄を拘束する段階で「逮捕状」は不要です。その代わりに、身柄拘束処分に着手する際には「理由を告げること」が求められ、また、身柄拘束処分を終えた後は、直ちに裁判官に対して逮捕状を求める手続きを行わなければいけません(逮捕状の発付が認められない場合には、すみやかに被疑者の身柄は釈放されます)。
なお、緊急逮捕の対象になる「一定の重大犯罪」とは、「死刑または無期懲役刑、長期3年以上の懲役刑・禁錮刑に当たる罪」のことです。重大犯罪と言われると強制性交等罪や殺人罪・強盗罪などの凶悪犯罪を思い浮かべる方も多いでしょうが、窃盗罪などの身近な犯罪も緊急逮捕の対象に含まれる点に注意が必要です。
警察段階の取調べが実施される
警察に捕まった後は、警察署に身柄が押さえられた状態で取調べが実施されます。
逮捕処分に基づく身柄拘束中は、自宅に戻ることができません。取調べ室で警察官から事情聴取を受けていない間は、拘置所や留置場に身柄が留められます。また、捕まった段階でスマートフォンなどの所持品はすべて取り上げられるので、家族や会社などに電話連絡を入れることもできません。さらに、逮捕段階は接見禁止処分が下されることが多いので、弁護士以外との面会も不可能です。
なお、捕まった後に警察段階で実施される取調べには「48時間以内」という時間制限が設けられています(刑事訴訟法第203条第1項)。これは、身柄拘束された状態の厳しい取調べが無制限に行われて被疑者が過度な人権侵害を受けないようにするためです。
警察から検察に身柄が送致される
警察段階での取調べが終了すると、事件・身柄・証拠物すべてが検察官に送致(送検)されます(刑事訴訟法第246条本文)。
事件を受け取った検察官が「留置の必要はない」と判断した場合にも、すみやかに身柄が釈放されて在宅事件に切り替わります。
- 検察官から事前に指定された比較的軽微な罪状の容疑をかけられていること(窃盗罪、占有離脱物横領罪など)
- 犯情が軽微であること(計画性がない突発的な犯行など)
- 被害額が軽微であること(被害額2万円以内、全治1週間程度が目安のライン)
- 被害者との間で示談が成立しており、被害弁償も済んでいること
- 素行不良者ではないこと(前科前歴のない初犯)
- 身元引受人がいること(家族、親戚、上司など)
警察に捕まったとしても、微罪処分なら早期に刑事手続きを終結できるので、日常生活への悪影響を最大限軽減できます。また、前歴は残るものの、前科がつかないのもメリットです。極めて軽微な刑事事件については、捕まってからすぐに私選弁護人に防御活動を展開してもらうことで、微罪処分獲得の可能性を高められるでしょう。
検察段階の取調べが実施される
警察に捕まって送検されると、検察段階の取調べが実施されます。
警察官に逮捕されて送検された場合、検察段階で実施される取調べの制限時間は「24時間以内」です(刑事訴訟法第205条第1項)。
24時間の逮捕処分の身柄拘束期限が満了するまでに、取調べでの供述内容や証拠を前提に、検察官が公訴提起するか否かを判断します。
ただし、「警察段階48時間と検察段階24時間の合計72時間以内」の原則的な取調べ時間だけでは、公訴提起判断に必要な証拠を収集できないケースも少なくありません。
そこで、検察段階の取調べには「勾留」という例外措置が認められています。具体的には、やむを得ない事情によって逮捕段階の取調べ時間を遵守できない場合には検察官による勾留請求が行われ、裁判官がこれを認めたときには「10日間~20日間」の範囲で身柄拘束期間が延長される、というものです(同法第206条第1項、同法第208条各項)。
なお、勾留請求が認められる「やむを得ない事情」として、以下のものが挙げられます。
- 組織的な犯行や複雑な共犯関係が疑われる場合
- 同種余罪や別の犯罪行為への関与が疑われる場合
- 被害者や目撃者の数が多いため、参考人聴取に相当の時間を要する場合
- 膨大な防犯カメラ映像や証拠書類などの解析・チェックに相当の時間を要する場合
- 証拠物の鑑定や実況見分に時間を要する場合
- 被疑者が黙秘・否認をしていたり、供述内容に矛盾点が多い場合
検察官が起訴・不起訴を決定する
逮捕期限・勾留期限が到来するまでに、検察官が公訴提起するかどうか(刑事裁判にかけるかどうか)を判断します。その際にポイントになるのが「起訴処分」「不起訴処分」です。
起訴処分とは、「事件を公開の刑事裁判にかける旨の訴訟行為」のことです。これに対して、不起訴処分とは、「事件を刑事裁判にかけずに検察官限りの判断で刑事手続きを終結させる旨の意思表示」を指します。
不起訴処分が下された時点で捜査活動は終結するので、裁判手続きに対応するコストや有罪になるリスクから解放されます。当然ながら、前科がつくこともありません(前歴は残ります)。
起訴処分が下された場合には、1カ月~2カ月後に開廷される刑事裁判で審理を受けなければいけません。ただし、日本の刑事裁判の有罪率は99%以上なので、刑事裁判にかけられた時点(検察官が起訴処分を下した時点)で有罪になることがほぼ確定するのが実情です。
- 嫌疑なし:捜査活動の結果、罪を犯していないことが判明した場合
- 嫌疑不十分:捜査活動の結果、罪を犯したことを立証する充分な証拠が得られなかった場合
- 起訴猶予:捜査活動によって罪を犯したことは判明したが、諸般の事情を総合的に考慮した結果、刑事裁判にかける必要がないと判断される場合
起訴猶予処分を獲得するには「早期の示談交渉」「誠実な取調べ対応」が不可欠です。警察に捕まってすぐに私選弁護人へ相談をすれば早期に供述方針を明確化してくれるので、一貫した供述内容によって不起訴処分獲得を実現しやすくなるでしょう。
公開の刑事裁判にかけられる
検察官が起訴処分を下した場合、事件が公開の刑事裁判にかけられます。弁論手続きや証拠調べ手続きを経て裁判官が最終的な判決内容を決定するという流れを経るのが一般的ですが、公訴事実に争いがなければ第1回の公判期日で結審することもあります。
日本の刑事裁判の有罪率が99%を超える実情を踏まえると、冤罪事件などの無罪を主張する特殊なケースを除いて、「執行猶予付き判決や罰金刑の獲得」を目指して防御活動を展開することになります。なぜなら、懲役刑や禁錮刑と言った実刑判決が確定すると刑期を満了するまで刑事施設に収監されるので、服役後の社会復帰が困難になるからです。
そして、執行猶予付き判決や罰金刑獲得のためには、「被害者との示談が成立していること」「反省の態度を示していること」に加えて、酌量減軽や未遂減軽、正当防衛、緊急避難などの多方面に渡る防御活動を展開する必要があります。刑事事件の実績がない弁護士に依頼をすると検察官主導で公判手続きが進められてしまうので、かならず刑事裁判実績豊富な私選弁護人に依頼してください。
なお、検察官が起訴処分を下してから刑事裁判までは1カ月~2カ月の期間が空くのが一般的です。起訴後勾留が続くと刑事裁判までの期間中も留置場・拘置所から出ることができないので、検察官が起訴処分を下した後は、すみやかに弁護士に保釈請求手続きを履践してもらいましょう。
警察に捕まりそうなときは刑事事件に強い弁護士へ相談しよう
警察に捕まりそうだと感じているのなら、余計なことは考えず、とにかく刑事事件に強い弁護士までご連絡ください。
なぜなら、被害者がいるタイプの事件なら早期に示談交渉を開始してくれますし、捕まったときに備えて防御活動の準備をしてくれるからです。また、後々逮捕されたとしても弁護士との間でコミュニケーションがとれている状態なので、供述方針や防御方針を一貫できるでしょう。
少しでも有利な形で刑事手続きを進めたいなら、時間に余裕をもって「被疑者主導」の状況を作り出すのがポイントです。刑事事件や示談実績豊富な弁護士のサポートを受けながら、社会復帰しやすい環境獲得を目指してください。