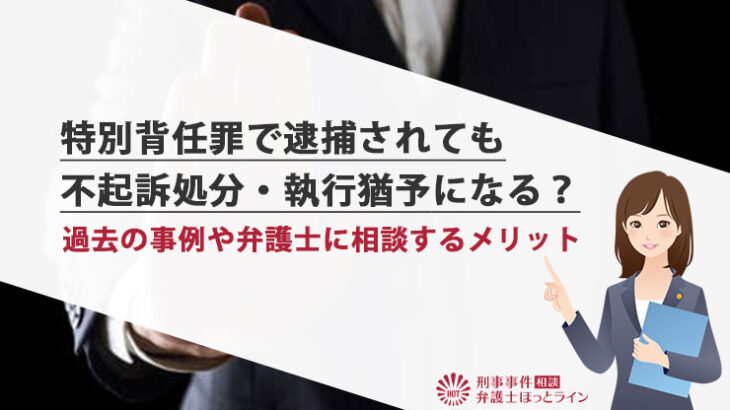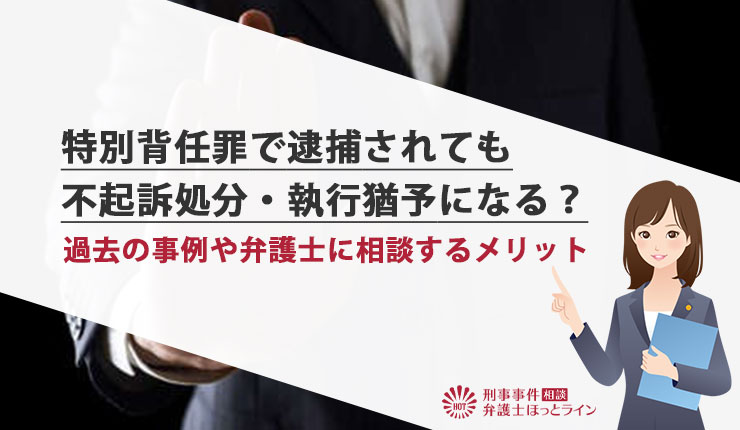
株式会社などで一定範囲の重大なポジションに就いている人物が任務違背行為に及んで損害を生じたときには「特別背任罪」の容疑で逮捕されます。
特別背任罪は刑法の背任罪の加重類型に位置する犯罪類型なので、初犯でも厳しい刑事処分が予想されます。
そこで今回は、特別背任罪の容疑で刑事訴追されるか不安を抱えている方や、ご家族が特別背任事件を起こして立件された方のために、以下4つの事項について分かりやすく解説します。
- 特別背任罪の構成要件・法定刑・公訴時効
- 特別背任罪の容疑で逮捕されるときの刑事手続きの流れ
- 特別背任罪の容疑で逮捕されたときに生じるデメリット
- 特別背任罪の容疑で逮捕されるか不安なときに弁護士へ相談するメリット
当サイトでは、特別背任事件や企業法務に強い弁護士を多数掲載中です。「身柄拘束の回避、期間短縮化、軽い刑事処分獲得」を実現するために、できるだけ早いタイミングでお近くの法律事務所までご相談ください。
目次
特別背任罪の基礎知識
特別背任罪は、刑法第247条に規定される背任罪の加重類型に位置付けられる犯罪のことです。
まずは、特別背任罪の構成要件や他罪との関係性について解説します。
特別背任罪の構成要件
特別背任罪とは、「会社法第960条第1項各号に規定された人物が、自己もしくは第三者の利益を図り、または、株式会社に損害を与える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたとき」に成立する犯罪類型のことです(会社法第960条第1項)。
ここから、特別背任罪の構成要件として以下5点が導かれます。
- 会社法第960条第1項各号に規定された人物
- 任務違背行為
- 財産上の損害
- 特別背任の故意
- 図利・加害目的
会社法第960条第1項各号に規定された人物
刑法の背任罪の主体は「他人のためにその事務を処理する者(事務処理者)」です。
これに対して、特別背任罪の主体は以下の人物に限定されています。
- 発起人
- 設立時取締役、設立時監査役
- 取締役、会計参与、監査役、執行役
- 民事保全法第56条に規定する仮処分命令によって選任された取締役、監査役または執行役の職務を代行する者
- 会社法第346条第2項、同法第351条第2項、同法第401条第3項の規定によって選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役または代表執行役の職務をおこなうべき者
- 支配人
- 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
- 検査役
任務違背行為
背任罪の実行行為は、「任務に背く行為(任務違背行為)」です。
そもそも、株式会社において取締役などの一定の重要な責任を担うポジションに就く人物は、さまざまな経営判断をする機会にぶつかります。誤った経営判断によって株式会社に損害を与えたすべての行為が任務違背行為に該当するとされると、取締役などの経営方針に委縮効果が生まれかねません。
そのため、任務違背行為への該当性は、株式会社において果たす役割・職務内容・義務などの個別具体的な客観的事情を総合的に考慮して、「株式会社において与えられた役割に対する法的期待に違反したか否か」という観点から判断するのが判例通説です(背信説)。
たとえば、取締役などが以下のような行為をした場合、任務違背行為に及んだことを理由に特別背任罪の容疑で逮捕されかねないでしょう。
- 不良貸し付け
- 蛸配当・粉飾決算
- 自己取引
- 債務負担行為
- 冒険的取引
財産上の損害
特別背任罪が成立するためには、「任務違背行為の結果、当該株式会社に財産上の損害が発生すること」が必要です。
特別背任罪における「財産上の損害」は「全体財産の減少」を意味します。
たとえば、任務違背行為によって会社財産が減少したとしても、反対給付が存在するケースが挙げられます。減少分に見合った財産状態の増加が認められる場合には「株式会社の財産全体として減少は存在しない」と判断されるので、背任既遂罪の容疑で逮捕されることはありません。
ただし、全体財産に減少があったか否かは形式的に判断されるわけではない点に注意が必要です。たとえば、他社に対して一定額を貸し付けた代わりに同額の債権を取得したとしても、他社の経営状況が芳しくなく当該債権の回収可能性がゼロに近いような状況だと、“実質的に株式会社の全体財産が減少している”と判断されかねないでしょう。
以上を踏まえて、「経済的見地における株式会社の財産状態を評価し、任務違背行為によって株式会社の財産の価値が減少しているか否か、または、増加するべき価値が増加しなかったか否か」という観点に基づいて特別背任罪における「財産上の損害」を判断するのが判例通説です(最決昭和58年5月24日)。
特別背任の故意
特別背任罪は故意犯なので、「以下の構成要件該当事実に対する認識・認容」が必要です。
- 自分が特別背任罪の適用対象である役職などに就任していること
- 任務違背行為をすること
- 自らの任務違背行為によって株式会社に財産上の損害が生じること
図利・加害目的
特別背任罪の容疑で立件されるのは、故意とは別に「自己もしくは第三者の利益を図る目的(図利目的)、または、株式会社に損害を加える目的(加害目的)」という主観的構成要件を満たす必要があります。
具体的には、「『株式会社の利益を図る目的(本人図利目的)』が存在しないこと」「積極的な本人図利目的がないこと」を意味します(大判大正3年10月16日)。
なお、特別背任罪の容疑をかけられるような事案では、取締役が図利加害目的と本人図利目的の両方を有するケースが少なくありません。「株式会社の利益にもなるし、自分の財布も潤うから好都合だ」という動機で何かしらの経営判断をしたとしても、併存する2つの動機の主従関係を確認した結果、図利加害目的の方に重きを置かれるケースでは、特別背任罪の容疑で逮捕される可能性が高いです(最決昭和63年11月21日、最決平成10年11月25日)。
特別背任罪に問われた事例
特別背任罪に問われた実際の事例・判例を紹介します。
拓銀特別背任事件(最決平成21年11月9日)
拓銀特別背任事件は、北海道拓殖銀行の代表取締役頭取が、実質倒産状態にある融資先企業グループに対して、赤字補填資金などを実質的に無担保で融資した事件です。被告人らに2年6カ月の懲役刑が下されました。
本来、銀行が企業に対して融資をする際には、融資先企業に返済能力があるか否かを客観的資料に基づいて判断しなければいけません。しかし、本件では、融資先企業グループには客観性のある再建・整理計画は存在せず、融資をすることによって損失を軽減する効果も認められない状況であったため、当該融資には経営上の合理的な理由が存在せず、取締役らは債権保全に関する義務に違反していると判断されました。
イトマン事件(最決平成17年10月7日)
イトマン事件とは、住友銀行系の中堅総合商社であった伊藤萬(現イトマン)の代表取締役が、共犯者らと共謀のうえ、ゴルフ場開発資金名目で数千億円を引き出した特別背任事件のことです。被告人らに7年の懲役刑が下されています。
融資時には十分な担保が徴求されることはなく、また、融資された資金が株・土地・絵画・ゴルフ会員権・暴力団資金源などに流用されたことから、当該融資が任務違背行為であると認定されました。
平和相互銀行特別背任事件(最決平成10年11月25日)
平和総合銀行特別背任事件とは、当行の役員らが、密接な関係にある融資先に必要な担保を供させずに土地の購入資金・開発資金などを融資した事件です。
1人に対しては3年の懲役刑、もう1人に対しては3年6カ月の懲役刑が確定しています。
特別背任罪の法定刑
特別背任罪の法定刑は、「10年以下の懲役刑または1,000万円以下の罰金刑(併科あり)」と定められています(会社法第960条第1項)。
特別背任罪で立件された被疑者が注意をする必要があるのは、執行猶予との関係です。
というのも、執行猶予付き判決を獲得するには、「3年以下の懲役刑・禁錮刑・50万円以下の罰金刑の言渡しを受けたとき」という要件を満たさなければいけないからです(刑法第25条第1項)。
つまり、特別背任罪の容疑で逮捕・起訴されたときには、執行猶予付き判決獲得を目指して丁寧に情状証拠を積み上げる必要があるということです。
特別背任罪のような専門性の高い事件の刑事裁判では、会社法関連知識や特有のノウハウを有する弁護士のサポートが不可欠です。当サイトでは特別背任事件の実績豊富な弁護士を多数掲載中なので、捜査機関から問い合わせがある前にお近くの法律事務所までお問い合わせください。
特別背任罪の公訴時効
過去の特別背任事件は、公訴時効が完成するまでは逮捕リスクを抱えたままです。
公訴時効とは、「任務違背行為から一定期間が経過することによって検察官の公訴提起権が消滅する制度」のことです。起訴することが物理的に不可能になるため、警察が特別背任事件を立件することもなくなります(刑事訴訟法第253条第1項)。
公訴時効期間は各犯罪の法定刑によって決定されます。たとえば、刑法に規定される背任罪の法定刑は「5年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑」なので5年で公訴時効が完成します。
これに対して、特別背任罪の法定刑は「10年以下の懲役刑または1,000万円以下の罰金刑(併科あり)」と定められているので、任務違背行為から7年が経過しなければ特別背任罪の公訴時効は完成しません(同法第250条第2項第4号)。
つまり、過去の特別背任事件について現段階で捜査機関から問い合わせがない状況でも、犯行から数年が経過してある日突然捜査の手が伸びかねないということです。
警察が捜査活動を開始する前に弁護士に相談することで先手を打った防御活動が可能になるので、すみやかに当サイト掲載中の法律事務所までお問い合わせください。
特別背任罪は未遂犯も処罰される
特別背任罪は未遂犯も処罰対象です(会社法第962条)。
特別背任罪の既遂犯と未遂犯を区別するポイントは「株式会社に財産上の損害が生じたか否か」です。
取締役などが任務違背行為に及んだものの、財産上の損害が生じなかったときには、特別背任未遂罪の容疑で逮捕されます。
特別背任罪と背任罪の違い
刑法に規定されているのが、背任罪の基本類型です。「他人のためにその事務を処理する者が、自己もしくは第三者の利益を図り、または、本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたとき」に成立します(刑法第247条)。
これに対して、特別背任罪は、会社法などに規定されている加重類型です。与えられた職責や役割の重要性に鑑みて、法定刑が重く設定されています。
特別背任罪と横領罪の違い
背任罪と類する犯罪として「横領罪」が挙げられます。
横領罪とは、「自己の占有する他人の財物を横領したとき」に成立する犯罪類型のことです(刑法第252条、同法第253条、同法第254条)。
横領罪は自分の占有する他人の財物に対する「不法領得の意思」が必要ですが、特別背任罪は「自分ではなく第三者の利益を図る目的」でも処罰対象に含まれるという違いがあります。
なお、特別背任罪が問題になる事案では、特別背任罪と業務上横領罪の両方が問題になり得ます。
たとえば、会社の取締役が経済的信用力のない取引先企業に無担保で融資をした場面では、「取締役が、自己の占有する会社の財物(会社所有の金銭)を不法に処分している」とも評価できるので、特別背任罪だけではなく横領罪の構成要件該当性も認められるでしょう。判例通説では、業務上横領罪の成否を検討したうえで、業務上横領罪の成立が認められない事案において特別背任罪の成否を検討するという取扱いがおこなわれています。
特別背任罪の容疑で逮捕されるときの刑事手続きの流れ
特別背任罪の容疑で立件されるときの刑事手続きの流れは以下の通りです。
- 特別背任罪の容疑で警察に通常逮捕される
- 特別背任罪の容疑について警察段階の取調べが実施される
- 特別背任事件が検察官に送致される
- 特別背任罪の容疑について検察段階の取調べが実施される
- 特別背任事件について検察官が公訴提起するか否かを判断する
- 特別背任事件が公開の刑事裁判にかけられる
特別背任罪の容疑で警察に通常逮捕される
特別背任事件が捜査機関に発覚した場合、通常逮捕されるのが一般的です。
通常逮捕とは、「裁判官の事前審査を経て発付される逮捕令状に基づいて実施される身柄拘束処分(強制処分)」のことです(刑事訴訟法第199条第1項)。
逮捕状が発付されると、被疑者の身体・行動の自由は大幅に制限されます。たとえば、「連行される前に家族や会社に電話をかけさせて欲しい」「業務の都合上、逮捕状の執行日を後日にずらして欲しい」などの要望を出すことはできません。
特別背任事件が警察にバレるきっかけ
特別背任事件はさまざまな端緒で捜査機関に発覚します。
たとえば、社内で対立している派閥に属する社員や株主が告発した場合、税務調査で不正なお金の流れが判明した場合、報道機関が関係者から情報を入手してニュースにした場合などが挙げられます。
万引きや置き引きなどの比較的軽微な犯罪類型とは異なり、特別背任罪が問題になる事案では、第三者によるチェック・リークが入る可能性が高いです。そのため、現段階で捜査機関から一切問い合わせがない状況でも、今後いつどこから捜査機関に犯行が露見するかわかりません。
したがって、過去に特別背任罪の容疑をかけられかねない行為に及んだときには、今後捜査機関から追及される事態に備えるために、念のために現段階で企業法務や刑事事件に強い弁護士に相談しておくべきでしょう。
特別背任罪の容疑で逮捕される具体例
特別背任罪を被疑事実とする逮捕状が発付されるのは、以下2つの要件を満たすときです(犯罪捜査規範第118条、同規範第122条)。
- 逮捕の理由:被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること
- 逮捕の必要性:留置の必要性があること、証拠隠滅や逃亡のおそれがあること
たとえば、事件の経過や被疑者自身に以下のような事情があるとき、特別背任罪の容疑で逮捕状が発付される可能性が高いでしょう。
- 住所不定・無職・職業不詳で逃亡するおそれがある場合
- 前科・前歴がある場合
- 任務違背行為によって高額の損害が生じた場合
- 特別背任事件をめぐる証拠品を隠滅するおそれがある場合
- 特別背任事件の共犯者などとの間で口裏を合わせるおそれがある場合
- 複数の任務違背行為が中長期的におこなわれて余罪での立件も視野に入っている場合
- 特別背任事件についての任意の出頭要請を拒絶した場合
- 特別背任事件に関する任意の事情聴取で黙秘・否認した場合、供述内容に矛盾点が存在する場合
- 被害者である株式会社側の処罰感情が強い場合
なお、特別背任事件を起こしたこと自体に間違いがなくても、逃亡または証拠隠滅のおそれがない場合には、逮捕状は発付されません。
ただし、「逮捕状が発付されない=立件されない」ということではなく、身柄拘束処分なしの任意捜査の一環として特別背任罪の容疑で刑事訴追される点にご注意ください。
特別背任事件は通常逮捕が一般的
逮捕処分は、通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕の3種類に分類されます。
現行犯逮捕とは、「現に罪を行い、または、罪を行い終わった者(現行犯人)に対する身柄拘束処分」のことです(刑事訴訟法第212条第1項)。また、緊急逮捕とは、「一定の法定刑以上の罪にあたる犯罪に及んだことを疑うに足りる充分な理由がある場合に、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときに、その理由を告げるだけで身柄拘束処分をできるとする逮捕処分」を意味します(同法第210条第1項)。
特別背任罪の容疑をかけられる刑事事件では、被疑者が株式会社の重要なポジションに就いていることが多いです。また、捜査機関が逮捕手続きに着手する前段階で繰り返し関係者に事情聴取が実施されることも多いため、「被疑者の所在や身元がわからなくなる」という事態は想定しにくいでしょう。
そのため、特別背任罪の容疑で立件されるときには、現行犯逮捕・緊急逮捕によって身柄拘束される可能性は極めて低く、その多くが通常逮捕手続きによることになります。
この意味で、特別背任罪の容疑をかけられた場合や、近い将来捜査機関から出頭要請がかかることが予想される場合には、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談をして、今後の防御方針を明確化しておくことが重要だと考えられます。
特別背任罪の容疑について警察段階の取調べが実施される
特別背任罪の容疑で通常逮捕された場合には、強制的に警察署に連行されて、「警察段階の取調べ」が実施されます。
警察段階で実施される取調べの制限時間は「48時間以内」です(刑事訴訟法第203条第1項)。
黙秘しようが自白しようが、取調べ自体に対してどのような態度をとるかは自由です。しかし、逮捕状に基づいて身柄拘束をされている以上、取調べ自体を拒絶することはできません。
また、警察段階の取調べが実施されている間は、取調室で尋問等が行われる以外のときは留置場・拘置所で過ごす必要があります。取調べ以外のタイミングで自宅に戻ったり買い物に行ったりすることは禁止されます。接見禁止処分が付されることが多いので、家族や会社関係者などと面会することも許されません。
さらに、逮捕された段階でスマートフォンなどの所持品がすべて取り上げられるので、家族や会社に連絡することも不可能です。
特別背任事件が検察官に送致される
特別背任事件について警察段階の取調べが終了すると、身柄・事件・証拠物がすべて検察官に送致(送検)されます(刑事訴訟法第246条本文)。
なお、一定の刑事事件については「微罪処分」が下される場合があります。
微罪処分とは、「捜査活動を開始した刑事事件を送検せずに、警察限りの判断で刑事手続きを終結させる事件処理類型」のことです(刑事訴訟法第246条但書、犯罪捜査規範第198条)。検察官があらかじめ指定した極めて軽微な犯罪類型に該当する事件についてのみ、警察からの厳重注意のみで刑事手続きが終了します。
ただし、特別背任罪は複雑かつ悪質な犯罪なので、微罪処分の対象になる可能性は極めて低いのが実情です。そのため、特別背任罪の容疑で立件されたときには、かならず検察段階の捜査活動に対応するための防御活動が不可欠になるでしょう。
特別背任罪の容疑について検察段階の取調べが実施される
特別背任事件について警察段階の取調べが終了すると、送検後、検察段階の取調べが実施されます。
検察段階で実施される取調べの制限時間は「原則24時間以内」です(刑事訴訟法第205条第1項)。警察段階48時間と検察段階24時間を合わせた「合計72時間以内」の取調べで得られた証拠・供述内容を前提として、検察官が公訴提起判断を下します。
ただし、特別背任事件のような専門性の高い刑事事件では、72時間以内の取調べだけでは十分な証拠・供述が得られない可能性も否定できません。
そのため、「やむを得ない理由」によって取調べ期間を延長する必要があるケースでは、検察官による勾留請求が認められています(同法第206条第1項)。
検察官の勾留請求を裁判所が認めて勾留状が発付されると、身柄拘束期間は「10日間~20日間」の範囲で延長されます(同法第208条各項)。
つまり、特別背任罪の容疑で逮捕・勾留されると、検察官の公訴提起判断までに「最長23日間」の身柄拘束期間が生じる可能性があるということです。
特別背任事件で勾留請求される可能性が高い「やむを得ない理由」として以下のケースが挙げられます。
- 複数の背任行為への関与が疑われる場合
- 特別背任事件の関係者が多く、参考人聴取に相当の時間を要する場合
- 帳簿関係書類やお金の流れの精査に時間を要する場合
- 特別背任事件について被疑者が黙秘・否認している場合
- 特別背任事件に関する供述内容に矛盾点や疑問点が存在する場合
不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得できたとしても、身柄拘束期間が数週間に及ぶだけで日常生活にさまざまなデメリットが生じかねません。
刑事事件に強い弁護士へご相談のうえ、「軽い刑事処分を獲得すること」だけではなく「身柄拘束期間を短縮化すること」も目指してもらいましょう。
特別背任事件について検察官が公訴提起するか否かを判断する
逮捕期限や勾留期限が到来するまでに、それまでに得られた証拠や被疑者の態度などを総合的に考慮して、検察官が特別背任事件を公訴提起するか否か(起訴処分か不起訴処分か)を決定します。
起訴処分とは、「特別背任事件を公開の刑事裁判にかける旨の訴訟行為」のことです。日本の刑事裁判の有罪率は約99%とも言われているので、起訴処分が下された時点で有罪判決が下されて前科がつくことが事実上確定します。
これに対して、不起訴処分とは、「特別背任事件を公開の刑事裁判にかけずに、検察官独自の判断で刑事手続きを終結させる旨の意思表示」のことです。不起訴処分によって刑事裁判以降の手続きをすべて回避できるので、有罪や前科のリスクがゼロになります。
特別背任罪の容疑で逮捕された場合、「不起訴処分を獲得できるか」が最大の防御目標になります。捜査機関から問い合わせがきた時点で弁護士へ相談をして、適切な防御活動に注力してもらいましょう。
特別背任事件が公開の刑事裁判にかけられる
特別背任罪の容疑で逮捕された場合、公開の刑事裁判にかけられます。
公開の刑事裁判が開廷される時期は、起訴処分から1カ月~2カ月後が目安です。公訴事実に争いがなければ第1回公判期日で結審して後日判決が言い渡されます。これに対して、否認事件の場合には複数の公判期日をかけて弁論手続き・証拠調べ手続きが行われて判決言い渡しに至ります。
特別背任罪の法定刑は「10年以下の懲役刑または1,000万円以下の罰金刑(併科あり)」なので、初犯でも実刑判決が下される危険性が高いです。
実刑判決が下されると刑期を満了するまで服役を強いられるので、かならず刑事裁判経験豊富な弁護士に相談のうえ、執行猶予付き判決や罰金刑獲得を目指してもらいましょう。
特別背任罪の容疑で逮捕されたときに生じるデメリット4つ
特別背任罪の容疑で逮捕されたときに生じるデメリットは以下4つです。
- 特別背任罪の容疑で逮捕された時点で実名報道される可能性がある
- 特別背任罪の容疑で刑事訴追されると長期間身柄拘束されるリスクに晒される
- 特別背任罪の容疑で逮捕されると懲戒解雇されたり委任契約を解除されたりする
- 特別背任罪の容疑で逮捕・起訴されると前科によるデメリットに悩まされ続ける
特別背任罪の容疑で逮捕されると実名報道リスクに晒される
刑事事件を起こすと、報道番組やネットニュースで実名報道される可能性があります。
特に、特別背任事件は社会的な関心を集めるトピックなので、逮捕段階で配信される可能性が高いです。
一度でも逮捕された事実が実名報道されると、インターネット上に特別背任事件を起こした情報が一生残ってしまいます。
これでは、身近な人に知られるだけではなく、結婚や子どもの進学、今後の転職活動やキャリア形成に支障が生じかねません。
実名報道リスクを軽減するには「逮捕されないこと」が重要になるので、警察からアクションがある前の可能な限り早いタイミングで弁護士に相談することを強くおすすめします。
特別背任罪の容疑で逮捕されると長期間身柄拘束される可能性が高い
特別背任罪の容疑で逮捕されると、長期間身柄拘束される可能性が高いです。
まず、逮捕された時点で「72時間以内(警察段階48時間と検察段階24時間)」の身柄拘束を覚悟する必要があります。
次に、勾留されてしまった場合には「10日間~20日間」の範囲で身柄拘束期間が延長されます。
さらに、起訴処分が下された後も勾留状態が続くと(起訴後勾留)、刑事裁判までの2カ月(以後1カ月ごとに更新)日常生活に復帰できません(刑事訴訟法第60条)。
注意が必要なのは、特別背任罪の容疑で再逮捕・再勾留が繰り返されたケースです。刑事手続きの各制限時間は「事件単位」でカウントされるので、再逮捕が繰り返されると、最終的な起訴判断が確定するまでに数カ月の身柄拘束期間が生じる可能性があります。
身柄拘束期間を少しでも短縮化すれば心身の負担や日常生活に生じるデメリットを大幅に軽減できるので、在宅事件への切り替えなど、早期の身柄釈放を目指した防御活動を展開してもらいましょう。
特別背任罪の容疑で逮捕・起訴されると職を追われる可能性が高い
特別背任罪の容疑で逮捕・起訴されると、現在の職を追われる可能性が高いです。
まず、株式会社との間で委任契約を締結している場合、任務違背行為によって株式会社との信頼関係は崩れてしまうので、契約を解除されるでしょう。
次に、株式会社に雇用されているとしても、就業規則の懲戒規定に抵触することを理由に懲戒処分が下される可能性が高いです。
懲戒処分の種類は、「戒告、譴責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇」に分類されます。特別背任罪の容疑に問われるような事案では、株式会社に対する背信の程度が大きいため、懲戒解雇を下されかねません。
特別背任罪の容疑で逮捕・起訴されると前科がつく可能性が高い
特別背任罪の容疑で逮捕・起訴されると、有罪判決が下される可能性が高いです。
そして、有罪判決が確定すると、刑事罰以外に「前科」によるデメリットが生じます。
前科とは、「有罪判決を受けた経歴」のことです。前科者になると、今後の社会生活で以下のリスクに晒され続けます。
- 前科情報は履歴書の賞罰欄への記載義務が生じるので、今後のキャリア形成が困難になりかねない
- 前科を理由に就業できない職種・資格がある(士業、警備員、金融業など)
- 前科は「法定離婚事由」に該当するので配偶者から離婚を求められると最終的には拒絶できない
- 前科を理由にビザ・パスポートの発給制限を受けると、自由に海外旅行・海外出張できない
- 前科者が再犯に及ぶと刑事処分が重くなる可能性が高い
前科によるデメリットを避けたいなら、「起訴されないこと」が重要です。
特別背任罪の容疑で逮捕された後、検察官の公訴提起判断までに、適切な情状証拠を収集する必要があるので、すみやかに刑事事件や企業法務に強い弁護士までお問い合わせください。
特別背任罪の容疑で逮捕されるか不安なときに弁護士へ相談するメリット
特別背任罪の容疑で逮捕されたときや、今後刑事訴追されるか不安を抱えているときには、弁護士に相談することを強くおすすめします。
なぜなら、刑事事件に強い弁護士の力を借りることで、以下3つのメリットを得られるからです。
- 株式会社側と早期の示談成立を目指してくれる
- 少しでも軽い刑事処分獲得を目指してくれる
- 接見機会を身柄拘束中の被疑者にさまざまなメリットをもたらしてくれる
弁護士は会社側と早期の示談成立を目指してくれる
刑事事件に強い弁護士は、被害者である株式会社との間で示談交渉を開始し、早期の和解契約締結を目指してくれます。
示談とは、「刑事事件の加害者・被害者間で特別背任事件の解決策について直接話し合いを行い、和解契約を締結すること」です。
示談契約が成立することによって、軽い刑事処分(不起訴処分、執行猶予付き判決、罰金刑)を獲得したり、早期の身柄釈放を実現しやすくなります。
もちろん、示談交渉は当事者本人自身でおこなうことも可能です。しかし、背任事件を起こしたような被疑者と株式会社側が冷静な状況で交渉するのは難しいです。
以下の理由から、弁護士に依頼をすれば示談交渉を有利に進めることができるでしょう。
- 株式会社側との冷静な交渉が可能になる
- 逮捕後身柄拘束中の被疑者に代わって株式会社側と示談交渉を進めてくれる
- 示談金額や支払い方法について現実的な条件を引き出すことができる
- 提出済みの被害届・告訴状の取り下げをスムーズに実現できる
- 被害申告前の示談成立によって特別背任事件の刑事事件化自体を回避できる
示談は成立するタイミングが早いほどメリットが大きくなります。任務違背行為について株式会社側から指摘をされたり、過去の背任行為が発覚しそうなときには、すみやかに刑事事件を得意とする法律事務所までお問い合わせください。
弁護士は少しでも軽い刑事処分獲得に向けて尽力してくれる
弁護士は、刑事手続きの段階に応じた適切な防御活動を展開することで、少しでも軽い刑事処分獲得を目指してくれます。
自首
自首とは、「まだ捜査機関に発覚しない前に、犯人自ら進んで特別背任事件を起こした事実を申告し、刑事処罰を求める意思表示」のことです(刑法第42条第1項)。
捜査機関に特別背任事件が発覚する前に自首をすれば、「刑の任意的減軽(自首減軽)」というメリットを得られます。たとえば、特別背任罪の容疑で逮捕・起訴されたとしても罰金刑や執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高まるでしょう。
特別背任事件を起こした場合、株式会社がいきなり捜査機関に被害申告をするケースは稀です。株式会社側も特別背任事件が世間に明るみに出ることを嫌うため、多くのケースでは、事前に株式会社側から聴取の機会を設定されます。その際に、株式会社との話し合いで円満な解決を期待しにくいときには、株式会社側の被害申告に先んじて自首をするのが効果的です。
このように、特別背任事件を起こした後に自首するタイミングは慎重な判断を要します。可能な限り早いタイミングで弁護士に依頼をして、民事・刑事の両面での対応を検討してもらいましょう。
自首前に弁護士へ相談するメリット
特別背任事件について自首を検討している段階で弁護士に相談するメリットは以下の通りです。
- 特別背任事件の全体像から現段階で自首をするべきか否かを判断してくれる
- 自首後に実施される事情聴取での供述方針を事前に明確化してくれる
- 警察に出頭する際に弁護士が同行してくれる
- 逮捕処分を免れて在宅事件として扱われる可能性が高まる
在宅事件
特別背任事件が捜査機関にバレたとしても、常に逮捕処分が下されるわけではありません。
なぜなら、逮捕処分が下されるのは「逮捕の理由」「逮捕の必要性」の2つの要件を満たしたときに限られるからです。つまり、特別背任事件を起こした事実に間違いがなかったとしても、「逮捕の必要性」がないことを理由に逮捕処分を免れることができるということです。
逮捕処分を回避できた場合、「在宅事件」として特別背任事件の捜査活動が実施されます。
在宅事件とは、「逮捕・勾留という身柄拘束処分を受けることなく、特別背任事件に関する捜査手続き・裁判手続きが進められる事件処理類型」のことです。
特別背任事件が在宅事件の対象になれば、身柄拘束処分によるデメリットが回避されます。警察や検察から出頭要請がかかったタイミングで事情聴取を受けて、その日のうちに帰宅することができます。
特別背任事件が在宅事件の対象になる可能性が高いのは以下のケースです。
- 氏名・住所・職業が明らかで逃亡のおそれがない場合
- 特別背任行為について自供して真摯に反省の態度を示している場合
- 特別背任行為に関する証拠を隠滅せずに自ら素直に提出している場合
- 株式会社との間で示談が成立している場合、近い将来示談が成立しそうな見込みがある場合
- 問題になっている特別背任行為以外の余罪に関与した疑いがない場合
- 特別背任事件で生じた損害額が少額の場合
- 特別背任事件の共犯や関係者と口裏を合わせるリスクがない場合
- 前科前歴がない場合
- 捜査機関からの出頭要請・事情聴取に誠実に応じている場合
なお、逮捕・勾留という強制処分とは異なり、在宅事件には時間制限が設けられていません。場合によっては、公訴提起の判断に至るまでに数カ月の期間を要するケースもあります。
また、最初は逮捕・勾留されたものの途中から在宅事件に切り替わるパターンもあれば、最初は在宅事件で刑事手続きがスタートしたのに途中で逮捕手続きに切り替わるケースも存在するので注意が必要です。
「逮捕されなかったから自分自身で対応できる」と思い込まずに、在宅事件の対象になったときこそ弁護士に相談をして不起訴処分獲得を目指した防御活動を展開してもらうべきでしょう。
勾留阻止
特別背任罪の容疑で逮捕されたときには「勾留阻止」に向けた防御活動が重要です。
なぜなら、逮捕段階だけで公訴提起判断に至れば身柄拘束期間は「72時間以内」で済むのに対して、勾留請求されると「最長23日間」まで身柄拘束期間が延長されるからです。
勾留を阻止するには、以下のポイントを踏まえて逮捕後の捜査活動に対応する必要があるので、かならず刑事事件実績豊富な私選弁護人までご依頼ください。
- 取調べにおける供述方針を明確化する
- 客観的証拠に反する供述は避ける
- 証拠が存在する状況で黙秘・否認はしない
- 捜査機関から提出を求められた証拠は素直に提出する
不起訴処分
特別背任罪の容疑で逮捕されたときには「不起訴処分獲得」を目指した防御活動が必要です。不起訴処分を獲得することで有罪・前科のリスクが消滅します。
「特別背任罪の容疑で逮捕された以上、刑事裁判にかけられるのは仕方ない」というのは間違いです。というのも、不起訴処分は以下3種類に分類されており、実際に任務違背行為によって会社に損害が生じたとしても「起訴猶予処分」獲得の余地が残されているからです。
- 嫌疑なし:特別背任行為に及んだ証拠が存在しない場合、誤認逮捕・冤罪の場合
- 嫌疑不十分:特別背任罪を立証する証拠が不足している場合
- 起訴猶予:特別背任事件を起こした事実に間違いはないが、諸般の事情を総合的に考慮した結果、刑事裁判にかける必要性がない場合
起訴猶予処分を下すかどうかを判断するときには、「犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の情況」などの諸般の事情が総合的に考慮されます(刑事訴訟法第248条)。
特に、特別背任罪の容疑をかけられたときには「示談交渉の状況」「犯行に対する認否」「反省の態度」が重視されるので、可能な限り早いタイミングで弁護士へ相談をして、起訴猶予処分獲得に向けた防御活動を尽くしてもらいましょう。
保釈請求
特別背任罪の容疑で逮捕・起訴されたときには、すみやかに保釈手続きを履践する必要があります。なぜなら、起訴後勾留が続くと、刑事裁判までの数カ月間身柄拘束状態が継続するからです。
起訴後も勾留状態が続くのは、「被告人が定まった住居を有しないとき」「被告人が証拠を隠滅するおそれがあるとき」「被告人が逃亡するおそれがあるとき」です(刑事訴訟法第60条第1項各号)。特別背任事件のような犯罪類型の場合には、共犯者や取引相手などと口裏を合わせるリスクがあるため、起訴後勾留が継続する危険性が高いです。
起訴後勾留によって身柄拘束期間が数カ月に及ぶだけで日常生活にはさまざまな支障が生じかねないので、状況に応じて適切な保釈手続きを履践してもらいましょう。
- 権利保釈(保釈除外事由に該当しない限り認められる保釈)
- 裁量保釈(裁判官の裁量によって認められる保釈)
- 義務的保釈(身柄拘束期間が不当に長期化している場合に認められる保釈)
略式手続き
特別背任事件の状況次第では、「略式手続き」を利用できる場合があります。
略式手続き(略式起訴・略式裁判・略式命令)とは、「簡易裁判所の管轄に属する刑事事件について100万円以下の罰金刑が想定される場合に、被疑者側の同意がある場合に限って、公開の刑事裁判を省略して簡易・簡便な形で罰金刑を確定させる裁判手続き」のことです(刑事訴訟法第461条)。
略式手続きのメリットは以下の通りです。
- 刑事裁判手続きがすべて省略されるので社会復帰のタイミングを前倒しできる
- 罰金刑が最終的な着地点になるので実刑判決のリスクを大幅に軽減できる
ただし、略式手続きの対象になるのは「検察官が100万円以下の罰金刑を求刑する予定の刑事事件」に限られます。つまり、特別背任事件のような重い法定刑が定められている犯罪類型の場合には、警察段階及び検察段階の捜査活動段階で相当有力な情状証拠を収集する必要があるということです。
また、略式手続きに同意をするということは、刑事裁判で反論する機会を喪失するということを意味します。公訴事実に同意をせずに無罪を目指すケースでは、略式手続きに同意をするべきではないでしょう(ただし、実刑判決のリスクは伴います)。
したがって、略式手続きを利用するべきか否かを決めるときには、特別背任事件の全体像を把握したうえで刑事裁判の行く末を予測する必要があると考えられます。かならず特別背任事件の弁護実績を有する専門家までご依頼ください。
執行猶予
特別背任罪の容疑で逮捕・起訴されて刑事裁判にかけられることが確定したときには、「執行猶予付き判決の獲得」を目指した防御活動が不可欠です。
執行猶予とは、「被告人の犯情や事件の諸般の事情を考慮して刑の執行を一定期間猶予できる制度」のことです。執行猶予期間中は今まで通りの日常生活を送ることができます。また、何のトラブルも生じることなく執行猶予期間中を満了できれば刑が執行されることもありません。
ただし、執行猶予付き判決の対象になるには、「3年以下の懲役刑・禁錮刑・50万円以下の罰金刑の言渡しを受けたとき」という要件を満たさなければいけません(刑法第25条第1項)。特別背任罪の法定刑は「10年以下の懲役刑または1,000万円以下の罰金刑」と定められているため、状況次第では執行猶予が付かない可能性があります。
したがって、特別背任罪の容疑で逮捕・起訴された場合、自首減軽や酌量減軽などの効果的な防御活動が不可欠だと考えられます。かならず刑事裁判実績豊富な私選弁護人までご依頼ください。
- 任務違背行為の回数、行為態様、期間
- 会社に生じた損害額
- 計画性の程度(巧妙か、衝動性はあるのか)
- 動機の内容(会社にも利益になると考えていたのか、自己の利益のためかどうか)
- 会社の社会的地位、世間に与える影響
- 被告人が会社に貢献してきた程度
- 任務違背行為に至った経緯
接見機会を通じて特別背任罪で逮捕された被疑者にメリットをもたらしてくれる
特別背任罪の容疑で逮捕された後の身柄拘束期間中は接見禁止処分が下されることが多いため、家族や知人、会社関係者などと面会することは許されません。
ただし、被疑者には「接見交通権」が認められているので、弁護士とだけはいつでも立会人なく面会できますし、物の授受をすることも可能です(刑事訴訟法第39条第1項)。
弁護士は接見機会を積極的に活用することで、以下のメリットを与えてくれるでしょう。
- 捜査状況を踏まえて適切な供述方針を明確化してくれる
- 今後の捜査手続き・裁判手続きの展望を分析してくれる
- 身柄拘束中の被疑者の唯一の味方としてサポートしてくれる
- 被疑者ノートを差し入れて違法捜査対策をしてくれる
- 被疑者家族とも連絡をとって常時状況を伝えてくれる
特別背任罪は早期の示談交渉がポイント!弁護士に依頼して刑事事件化や逮捕を回避しよう
特別背任罪の容疑で逮捕されると初犯でも実刑判決が下される危険性が高いです。実刑判決が確定すると刑務所生活を強いられるので、今後の社会復帰が困難になりかねません。
そのため、特別背任罪の容疑で逮捕されたときには、「刑事事件化自体を回避すること」「立件されたとしても不起訴処分や執行猶予付き判決・罰金刑を獲得すること」が重要な防御目標に掲げられます。
可能な限り早い段階で背任事件を得意とする弁護士に相談をして、会社側との示談交渉を開始してもらいましょう。