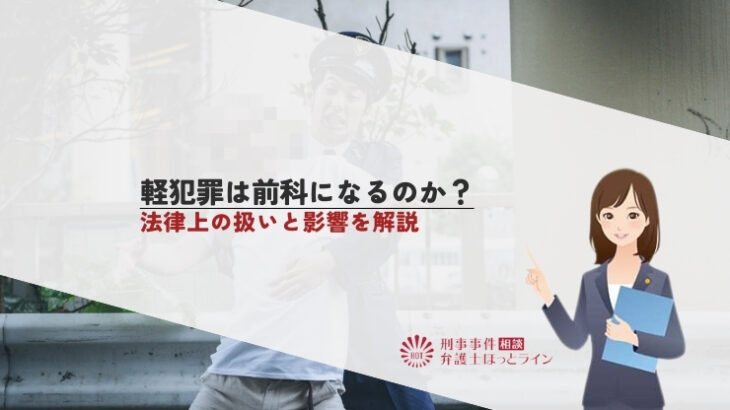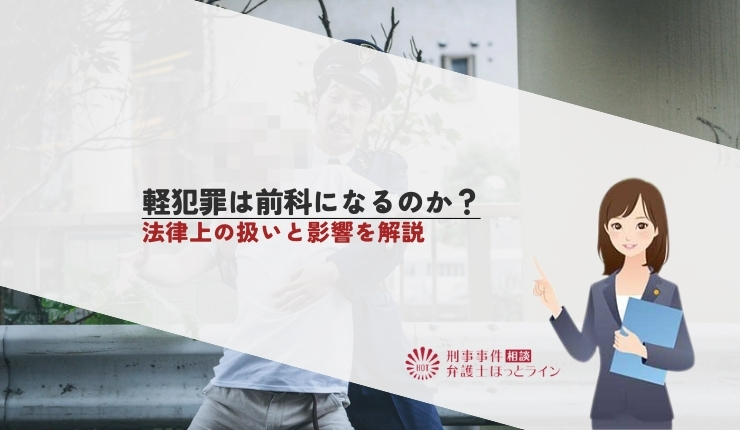
「軽犯罪」という言葉を耳にしたことはあっても、その具体的な内容や前科との関係性、逮捕の可能性について正しく理解している人は多くありません。軽犯罪とは、軽犯罪法という特別法に規定された33種類の比較的軽い犯罪行為を指します。主に、潜伏行為や凶器の携帯、行列割り込み、のぞき見、排せつ行為など、日常生活の中で起こり得る行為も含まれています。
「軽い」とはいえ、軽犯罪もれっきとした犯罪であり、有罪判決を受ければ前科が付きます。実際に、軽犯罪法違反の法定刑は「拘留」または「科料」とされ、刑事裁判を経て有罪が確定すれば履歴として残ります。
さらに、逮捕・勾留される可能性もゼロではなく、就職や転職、海外渡航、ビザ申請などに影響する場合もあります。本記事では、軽犯罪法の概要や対象となる行為、刑罰の種類、前科との関係、そして軽犯罪で逮捕された場合の流れまで詳しく解説します。
また、前科を避けるためにできる具体的な対策についても紹介しているため、「軽犯罪で前科がつくのか不安」「逮捕されたらどうなるのか知りたい」という人に役立つ内容です。ぜひ参考にしてください。
目次
軽犯罪法とはどんな法律か
軽犯罪も「犯罪行為」であるため、当然に有罪判決が下されれば前科が付きます。そもそも、軽犯罪とは「比較的軽い犯罪」として軽犯罪法という法律に記載されている犯罪行為を指します。
まずは、軽犯罪法とはどのような法律であり、どのような行為が該当するのか?について詳しく解説します。
軽犯罪法の概要と対象となる行為
軽犯罪とは、「比較的軽い犯罪」のことを指し、軽犯罪法という法律によって明記されています。軽犯罪法に明記されている犯罪はさまざまですが、主に「軽微な秩序違反行為」を指します。
軽犯罪法違反となる行為は全部で33種類あり、以下のとおりです。
- 潜伏行為
- 凶器の携帯
- 侵入具の携帯
- 浮浪行為
- 粗野・乱暴
- 消灯
- 水路交通妨害
- 変事非協力
- 火気乱用
- 爆発物使用等
- 危険投注等
- 危険動物解放等
- 行列割り込み等
- 静穏妨害
- 称号詐称・標章等窃用
- 虚偽申告
- 氏名等不実申告
- 要扶助者・死体等不申告
- 変死現場等変更
- 身体露出
- こじき
- のぞき見
- 儀式妨害
- 水路流通妨害
- 排せつ等
- 汚廃物投棄
- つきまとい等
- 暴行等共謀
- 動物けしかけ・驚奔
- 業務妨害
- 田畑等侵入
- はり札、標示物除去等
- 虚偽広告
参考:軽犯罪法違反|第1条
上記に該当する行為を行った場合は、軽犯罪法違反として処罰対象になります。軽犯罪法違反の法定刑は、拘留または科料に処せられます。
拘留とは、1日以上30日未満の間、刑事施設へ収監する刑事罰です。刑事罰の内容としては、拘禁刑と同様ですが、収監される期間によって 拘禁刑と拘留で分けられます。また、「拘留」と同じ呼び方で「勾留」というものがあります。勾留は、未決勾留者の身柄を拘束するために行われる手続きであり、まったく異なる内容です。
科料とは罰金刑の一つで、1000円以上1万円未満の金銭納付を命じる刑事罰です。「金銭納付」という意味では、罰金刑と同じですが金額によって、科料と罰金刑、刑罰の種類が変わります。
日常生活で起こり得る軽犯罪の具体例
軽犯罪法では、さまざまな秩序違反行為について明記しています。日常生活でも起こり得る軽犯罪法について、いくつか紹介します。
- 潜伏行為
- 凶器の携帯
- 侵入具の携帯
- 行列割り込み等
- 排せつ等
たとえば、肝試しをしようと考え、廃墟等に侵入する行為は軽犯罪法の「潜伏行為」に該当します。
凶器の携帯や侵入具の携帯も軽犯罪法に該当します。たとえば、仕事で使用する調理道具や工具を車にそのまま積んでいた場合は、軽犯罪法違反になる恐れがあるため注意しなければいけません。「使用しないときはおろす」といったことを徹底しましょう。
たとえば、人気ラーメン店で長蛇の列ができている間に、威勢を示して割り込む行為は軽犯罪法違反になります。仮に犯罪として成立しなくても、トラブルの原因となるため絶対にやめましょう。
また、酔っ払って路上で排せつ等をしてしまった場合は、軽犯罪法違反になり得ます。また、局部を露出していることから、公然わいせつ罪が成立する可能性もあるため、注意しましょう。
刑罰の種類と罰則規定
軽犯罪法違反によって処せられる可能性のある刑罰は、「拘留」または「科料」です。拘留については拘禁刑と同様、科料については罰金刑と同様の刑事罰です。ただ、期間や金額が異なることによって、呼び方が異なります。
そのため、改めて日本国内に存在する刑罰の種類について確認しておきましょう。
| 日本の刑罰 | 内容 |
|---|---|
| 拘留 | 1日以上30日未満刑事施設に拘置する |
| 科料 | 1,000円以上1万円未満の金銭納付を命じる |
| 罰金 | 1万円以上の金銭納付を命じる |
| 拘禁刑 | 30日以上の期間、刑事施設へ拘置する |
| 死刑 | 犯罪者の生命を剥奪 |
| 没収(その他) | 犯罪に関連する物の所有権を剥奪し、国庫に帰属させる刑罰 |
2025年6月1日以前は、懲役刑と禁錮刑という別々の刑罰がありました。しかし、法改正に伴い、懲役刑と禁錮刑が一本化され、「拘禁刑」という刑罰が新設されています。
このことにより、現在は5つの刑罰と1つの付加刑となりました。没収は、犯罪に使用された物の所有権を没収する際に科される刑罰を指します。たとえば、覚せい剤取締法違反で有罪判決が下された場合に、「被告人が所持していた覚せい剤を没収する」といった場合に利用されます。
軽犯罪と前科の関係
軽犯罪法は比較的軽い犯罪ではあるものの、犯罪であることに変わりはありません。よって、有罪判決を受けた場合は、前科として残るため注意しましょう。
次に、軽犯罪と前科の関係についても詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
軽犯罪で有罪判決を受けた場合
前科が付く条件は「有罪判決が確定した場合」です。有罪判決とは、刑事裁判によって有罪判決が言い渡され、刑罰が確定した場合です。
つまり、「逮捕されたけど不起訴となった場合」や「起訴されたけど無罪となった」という場合は前科が残りません。ただし、前科は残らなくても「前歴」が残る点には注意が必要です。
前歴とは、犯罪の捜査対象となった経歴のことを指します。前歴は、前科ほどの影響はないものの、今後、同様の犯罪を犯した場合に不利に働く可能性があるため注意しましょう。
略式命令と前科の関係性
軽犯罪法違反の法定刑は、科料もしくは拘留です。そのため、略式起訴が選択される可能性があります。
拘留とは、1日以上30日未満の間、刑事施設へ収監する刑事罰です。刑事罰の内容としては、拘禁刑と同様ですが、収監される期間によって 拘禁刑と拘留で分けられます。また、「拘留」と同じ呼び方で「勾留」というものがあります。勾留は、未決勾留者の身柄を拘束するために行われる手続きであり、まったく異なる内容です。
科料とは罰金刑の一つで、1000円以上1万円未満の金銭納付を命じる刑事罰です。「金銭納付」という意味では、罰金刑と同じですが金額によって、科料と罰金刑、刑罰の種類が変わります。
略式起訴とは、100万円以下の罰金もしくは科料の刑罰を下す際に選択できる起訴方法のひとつです。通常は刑事裁判を行って有罪無罪を判断し、有罪である場合は量刑判断を行います。
一方で、略式起訴が選択された場合は、刑事裁判を行いません。科料の刑罰が確定し、略式命令として言い渡されます。刑事裁判が開かれた場合と比較して、早期に事件解決をできる点がメリットです。
ただし、無罪を主張する場合や公の場で弁解したいと考えている人にはおすすめできません。略式起訴は断ることができるため、断って刑事裁判を行うのもひとつの手段です。
なお、略式起訴された場合も有罪判決と同様の効果が生じます。よって、前科として残るため注意しましょう。絶対に前科を残したくない場合は、略式起訴を断り、無罪判決の獲得を目指します。
ただ、軽犯罪を犯した事実がある以上は、無罪判決を得られる可能性はゼロに近いです。まずは、弁護人とよく話し合ったうえで今後の対応について検討すべきでしょう。
不起訴や微罪処分の場合は前科にならない
軽犯罪法は、何度もお伝えしているとおり「比較的軽微な犯罪」です。そのため、犯罪事実があったとしても、不起訴処分や微罪処分で事件が終了するケースもあります。
不起訴処分とは、検察官が「この人を刑事裁判にかける必要がない」と判断した場合に行われる処分です。不起訴処分の時点で事件は終了し、今後同じ事件で罪に問われることはありません。
微罪処分とは、軽微な犯罪を犯した被疑者に対して検察官へ事件を送致せずに事件を終了させる処分を指します。通常は、すべての事件を検察官へ送致(全件送致の原則)しなければいけませんが、比較的軽微な犯罪である場合は、微罪処分が認められています。
不起訴処分や微罪処分で事件が終了した場合は、前科は残りません。なぜなら、有罪判決を受けたわけではないためです。最悪でも、不起訴処分となるために、早期に弁護士へ相談することを検討しましょう。
軽犯罪で前科がつくことの社会的影響
軽犯罪法による行為であっても、有罪判決を受ければ前科が残ります。どのような犯罪であっても「前科」であることに変わりはありません。そのため、以下のような影響が出る可能性があるため注意しましょう。
- 就職や転職での影響
- 海外渡航やビザ申請への影響
次に、軽犯罪法で前科がついた場合の影響について詳しく解説します。
就職や転職での影響
前科がついていることにより、就職や転職に影響を与える可能性があります。たとえば、就職や転職をする際、履歴書に「賞罰欄」が記載されている場合は、過去の前科についても記載して報告しなければいけません。
また、面接時に過去に逮捕された経験や前科がついた経験があるかどうか?と尋ねられた場合に、正直に答えなければいけません。そのため、上記のように尋ねられた場合は、就職や転職をする際に影響する可能性があると思っておいたほうが良いでしょう。
海外渡航やビザ申請への影響
前科がある場合は、パスポートの発給やビザの申請ができない可能性があります。そのため、海外渡航ができなくなる可能性があるため注意しなければいけません。
前科の内容や有罪判決を受けてから一定期間など、条件は国によっても異なります。軽犯罪法であれば、比較的軽微な犯罪であることから、ほとんどの国と地域に入国できますが、今後各国の法律等が変わる可能性もあるため注意しましょう。
その他|軽犯罪法は資格制限の対象外
前科の内容によっては、資格制限を受ける可能性があります。しかし、軽犯罪法違反の場合は拘留もしくは科料であるため、資格制限等は受けません。
つまり、「前科によってさまざまな制限を受けるかもしれない……」と不安を感じる必要はないため安心してください。
ただし、軽犯罪法ではなく他の刑法犯が適用された場合は、資格制限を受ける可能性があります。具体的には罰金刑を受けた場合や拘禁刑以上の刑罰が確定した場合に、一定期間取得できなくなる資格があります。
たとえば、潜伏行為は軽犯罪法違反ですが、他人が居住する家に侵入した場合は住居侵入罪が成立します。住居侵入罪は、刑法犯であり罰金刑もしくは拘禁刑の刑罰に処されます。よって、資格制限を受ける可能性があるため注意しましょう。
軽犯罪で逮捕された場合の流れ
軽犯罪法違反は、比較的軽微な犯罪であることから逮捕される可能性は低いです。しかし、犯罪である以上、逮捕の可能性はゼロではありません。次に、軽犯罪で逮捕された場合の流れについても詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
逮捕
軽犯罪法は犯罪であるため、逮捕される可能性があります。逮捕は、「罪を犯した疑いのある被疑者の身柄を一時的に拘束するための手続き」を指します。罪を犯した人すべてが逮捕されるわけではなく、以下の条件を満たしている場合に限って逮捕できます。
- 証拠隠滅の可能性がある
- 逃亡の可能性がある
- その他逮捕すべき理由がある
軽犯罪法は、比較的軽微な犯罪であることから、証拠隠滅や逃亡の可能性は低いと判断されやすいです。そのため、基本的には逮捕せずに在宅捜査となることが多いです。
しかし、逮捕される可能性はゼロではありません。万が一逮捕された場合は、初めに48時間以内の身柄拘束が可能となります。この間は、当然自宅へ帰ることはできず、警察署内にある留置所と呼ばれる場所で生活を送らなければいけません。
勾留請求
逮捕から48時間以内に検察官へ事件を送致します。これを「身柄付送致」と呼びます。身柄付送致された被疑者は、送致からさらに24時間以内に「引き続き被疑者の身柄を拘束する必要ががあるかどうか?」について判断されます。
身柄拘束の必要があると判断された場合は、裁判所にて手続きを行って、勾留が認められる流れです。初めに10日間の身柄拘束が可能となり、さらに勾留延長が認められれば、プラス10日間、合計20日間の身柄拘束が行われます。
なお、勾留するためには逮捕時同様に「証拠隠滅の恐れ」や「逃亡の恐れ」が必要です。これらの要件を満たしていなければ、勾留は認められません。
起訴・不起訴の判断
勾留されている被疑者の場合、勾留期間中に被疑者を起訴するか不起訴とするかを判断します。在宅捜査で事件が進んでいる場合は、期間に定めはありません。一般的には事件から2カ月程度で起訴・不起訴の判断がなされます。
なお、先ほども解説したとおり、軽犯罪法の場合は略式起訴が選択されるケースがあります。略式起訴とは、刑事裁判を行わずに略式命令を言い渡して事件が終了する手続きを指します。
科料の刑罰が選択された場合は、略式命令の可能性があり、事件を早期に解決できるため大きなメリットになり得るでしょう。
刑事裁判を受ける
正式起訴された場合は、刑事裁判を行います。刑事裁判では、あなたの犯した罪について審理し、有罪か無罪かを判断します。その後、有罪である場合はどの程度の刑罰に処するべきかを判断し、判決を言い渡します。
判決に従って刑に服する
判決が言い渡され、刑罰が確定した場合は、その刑罰に従って刑に服します。科料であれば金銭を納付して事件が終了します。拘留であれば、1日以上30日未満の期間刑事施設へ拘置されることになるでしょう。
いずれの場合も、前科は残ってしまうため、起訴・不起訴の判断がなされる前に弁護人へ相談をしたうえで不起訴処分を目指すことが好ましいでしょう。
軽犯罪で前科を避けるためにできること
軽犯罪で前科を避けるために、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 弁護士への早期相談が重要
- 示談成立を目指す
- 再発防止への取り組みを示す
次に、軽犯罪で前科を避けるためにできることについても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
弁護士への早期相談が重要
弁護士への早期相談は、不起訴処分を得るために非常に重要です。犯罪の被疑者となった場合は、実費で弁護士費用を用意できなくても、国選弁護人が選任されます。
しかし、軽犯罪は逮捕・勾留される可能性が低い犯罪であり、起訴後に国選弁護人が選任されることとなります。起訴後であれば、99%の確率で有罪判決が確定し、前科が残ってしまうため注意が必要です。
そのため、とくに逮捕・勾留されていない被疑者については、私選弁護人への相談が必要不可欠です。費用は自分で負担をしなければいけないものの、自分のタイミングで刑事弁護に強い弁護人を選任できます。
示談成立を目指す
被害者がいる犯罪である場合は、被害者との示談交渉を済ませておきましょう。軽犯罪は、比較的軽微な犯罪であることから、被害者の処罰感情がなくなれば、不起訴処分となる可能性が高いです。
示談交渉は、通常、弁護人を通じて行うものです。そのため、できるだけ早めに弁護人への相談をしておくことが、不起訴への近道となるでしょう。
再発防止への取り組みを示す
再犯防止へ向けた取り組みとして、具体的な方法を提案することも大切です。なぜ、そのようなことをしてしまったのか?を明確にし、今後同じことを繰り返さないためにはどうすれば良いのか?について、具体的な解決策を提示しましょう。
また、同時に反省している態度を示す必要があります。軽犯罪は、比較的軽微な犯罪であることから、再犯の可能性が低く、反省の態度が明らかであれば、不起訴となる可能性が高いです。
軽犯罪と前科に関するよくある質問
軽犯罪と前科に関するよくある質問を紹介します。
Q.軽犯罪でも必ず前科がつきますか?
A.必ず前科がつくとは限りません。
前科が付くのは「有罪判決が確定した場合」です。つまり、軽犯罪法違反によって罪に問われたとしても、不起訴処分となったり無罪判決が言い渡された場合は、前科は付きません。
一方で、軽犯罪法であっても有罪判決が言い渡された場合は、前科として残るため注意しなければいけません。
Q.前科と前歴はどう違うのですか?
A.前科は「有罪判決の経歴」前歴は「被疑者になった履歴」です。
前科は、何らかの犯罪を犯して有罪判決が下された場合に残る経歴です。前歴は、何らかの犯罪の疑いをかけられ、捜査対象になった履歴を指します。
たとえば、就職や転職をする際に賞罰欄の申告が必要な場合、前科があれば申告しなければいけません。しかし、前歴であれば、申告する必要はありません。
たとえば、捜査対象となったものの無罪判決を受けた場合は、誤認逮捕であったということです。しかし、捜査対象になっている事実があるため、前歴は残ります。何も罪を犯していない人が、この前歴によって何らかの影響が出ることは起きてはいけません。
よって、前歴による影響はほとんどないと考えておいて良いです。一方で、前歴が残っていながら同様の犯罪を犯した場合は、過去の履歴を元に厳しい判決が言い渡される可能性があるため注意しましょう。
たとえば、軽犯罪法違反の罪に問われ、初めは不起訴処分で事件が終了したとします。しかし、後に再度同じ内容で軽犯罪法違反に問われた場合、前歴が影響して起訴される可能性があるということです。
Q.初犯で軽犯罪なら不起訴になりますか?
A.初犯か再犯かに関わらず、不起訴になる可能性もありますし、起訴される可能性もあります。
初犯で軽犯罪法であっても、起訴される可能性があります。一方で、再犯であっても不起訴となる可能性があります。一概に「〇〇だから起訴される・起訴されない」といった判断がなされることはありません。
Q.前科がついた場合、何年で消えますか?
A.前科は一生消えません。
前科が消えることはありません。しかし、前科による影響は一定期間経過した時点で消滅します。
たとえば、軽犯罪法であれば影響はないものの、他の罪で罰金刑や拘禁刑以上の刑罰に処せられた場合は、一定期間資格制限を受けます。資格制限は、一生涯受けるものではなく、一定期間(資格による)です。
Q.軽犯罪で前科がついた場合、就職や資格取得に影響はありますか?
A.就職に影響を与える可能性はあるものの、資格制限は受けません。
就職をする際は、賞罰欄に前科について記載しなければいけません。このことにより、少なからず影響が出る可能性があるでしょう。一方で、資格制限は「罰金刑以上」であるものが大半であるため、軽犯罪の法定刑である科料や拘留は対象外です。
まとめ
軽犯罪法に規定される行為は、比較的軽いものが多いとはいえ、犯罪であることに変わりはなく、有罪判決が確定すれば前科として残ります。前科は、就職や転職活動の際の賞罰欄や面接対応、さらには海外渡航やビザ申請など、社会生活に一定の影響を与える可能性があります。
ただし、軽犯罪法違反の多くは拘留または科料といった軽い刑罰にとどまるため、資格制限などは基本的に生じません。また、検察官の判断によっては、不起訴処分や微罪処分により前科が残らないケースも存在します。
さらに、略式起訴が選択されることもあり、この場合は正式な裁判を経ずに比較的早期に解決できる点も特徴です。とはいえ、軽犯罪だからといって油断せず、弁護士への早期相談や被害者との示談成立、再発防止への取り組みを示すことは、不起訴や寛大な処分を得るうえで重要です。
軽犯罪法違反であっても、逮捕・勾留の可能性はあり、前科が付けば長期的な影響を避けられません。本記事で解説したポイントを参考に、軽犯罪のリスクと適切な対処法を理解しておくことで、将来的な不利益を最小限に抑えることができるでしょう。