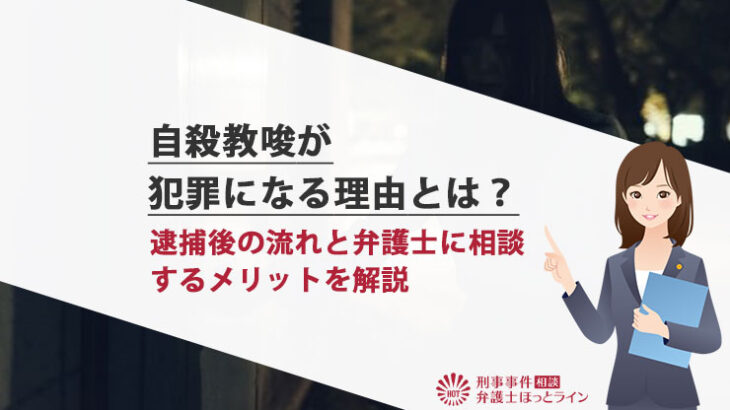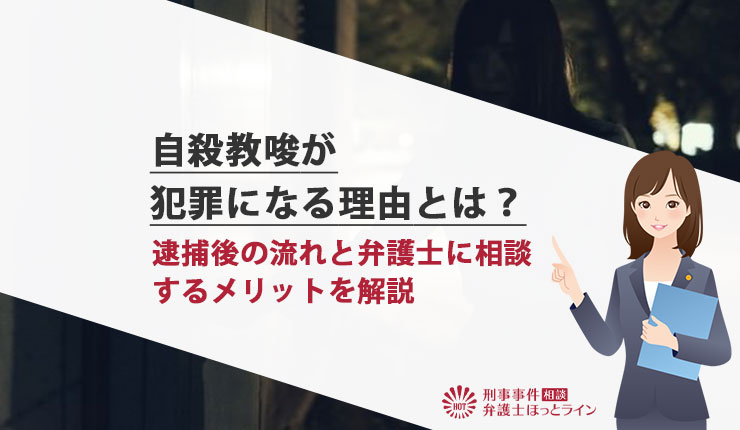
自殺すること自体は犯罪ではないので、自殺をした本人に対して刑事罰が科されることはありません。これに対して、自殺するように唆したり手助けしたりすると、教唆・幇助をした人物は「自殺関与罪(自殺教唆罪・自殺幇助罪)」の容疑で逮捕されます。
つまり、自殺した本人がどのような事情を抱えていたとしても、自分以外の第三者を自殺するように仕向けることは犯罪だということです。刑事事件化すると、逮捕・勾留によって長期間身柄拘束されるだけではなく、実刑判決や前科が原因で今後の社会生活にさまざまな支障が生じかねません。
そこで今回は、誰かに自殺を薦めてしまった経験をもつ方や、ご家族が自殺教唆罪で逮捕された方のために、以下4点について分かりやすく解説します。
- 自殺教唆罪の詳細と罰せられる理由
- 自殺教唆罪の容疑で逮捕されるときの刑事手続きの流れ
- 自殺教唆罪で逮捕されたときに生じるデメリット
- 自殺教唆罪で刑事訴追されるときに弁護士へ相談するメリット
当サイトでは刑事事件の経験豊富な弁護士を多数掲載しています。各法律事務所のHPを確認すれば受任実績や専門分野が分かるので、信頼に値する弁護士までご相談ください。
目次
自殺教唆とは?罪になる理由と問われる罪状について
自殺した本人は罪に問われませんが、自殺を唆した者は自殺教唆罪で逮捕されます。
まずは、自殺教唆罪の法的性質などについて解説します。
自殺教唆罪の構成要件と法定刑
自殺教唆罪とは、「人を教唆して自殺させたとき」に成立する犯罪類型です(刑法第202条前段)。自殺教唆罪の法定刑は「6カ月以上7年以下の懲役刑・禁錮刑」です。
自殺教唆罪の構成要件は以下2点です。
- 人を教唆すること
- 生命の主体による有効な自殺意思が存在すること
人を教唆すること
自殺教唆罪の実行行為は「教唆」です。教唆の読み方は「きょうさ」です。
教唆とは、「人に犯罪遂行の意思(自殺の意思)を生じさせて実行させること」を意味します。
たとえば、スマホやDMで執拗に「死んで欲しい」「自殺すると楽になるから死んだ方が良い」という趣旨のメッセージを送り続けたり、対面で自殺するように説得したりして、本人を自殺に追い込む行為が挙げられます。
生命の主体による有効な自殺意思が存在すること
自殺教唆罪が成立する前提として、「生命の主体による有効な自殺意思が存在すること」が求められます。
第1に、「有効な自殺意思」と認められるには、「死ぬことの意思を理解し得るだけの精神能力」が必要です。たとえば、自殺の意味を理解していない幼児や、意思能力を欠く精神障害者などについては、有効な自殺意思を有し得ないと考えられます(大判昭和9年8月27日、最決昭和27年2月21日)。
第2に、自殺意思の形成は本人の自由意思に基づいて行われる必要があります。たとえば、強制的な意思抑圧の結果や暴力などによる恐怖心など、意思決定の自由が存在しないケースでは、「有効な自殺意思」があったとは認められません(福岡高宮崎支判平成元年3月24日)。
第3に、「有効な自殺意思」であるためには、本人が「死ぬことを具体的に認識し受容していること」が必要です。たとえば、「一時的に仮死状態に陥るかもしれないが蘇生するはずだ」と誤認していたときには、「有効な自殺意思」は存在しないと考えられます(大判昭和8年4月19日)。
第4に、欺罔によって自殺意思を生じさせたときにも、「有効な自殺意思」は存在しないと扱われます。たとえば、判例では、追死する意思がないのに追死するものと誤信させて毒物を飲ませて中毒死させた事案において、「『真意に添わない重大な瑕疵ある意思』は『有効な自殺意思』ではない」ことを理由に、自殺関与罪を否定して殺人罪の成立を肯定しています(最判昭和33年11月21日)。
自殺教唆罪は未遂犯も処罰される
自殺教唆罪は未遂犯も処罰対象です(刑法第203条、第202条)。
自殺教唆未遂罪が成立するのは「実行の着手」があった段階です(同法第43条本文)。
自殺教唆未遂罪の「実行の着手」は、「生命に対する現実的な危険の発生=自殺行為への着手によって危険が発生したとき」とされます。
なお、自殺教唆未遂罪の法定刑は既遂犯と同じ「6カ月以上7年以下の懲役刑・禁錮刑」です。ただし、未遂犯については「刑の任意的減軽」というメリットが得られる場合があるので、既遂犯よりも執行猶予付き判決を獲得しやすいでしょう。
自殺教唆が逮捕される理由
そもそも、自殺した本人が処罰されることはありません。なぜなら、自殺者の生命は、本人自身との関係性において刑事罰による保護の対象にはならないからです。
これに対して、他人との関係では、自殺者の意思に合致した生命の侵害は違法です。というのも、生命には絶対的な価値があるので、自殺者本人の意思に反してでも保護する必要性があるからです(パターナリズムな要請)。そのため、自殺教唆行為は例外的に違法なものと扱われます。
ただし、本人の意思に反して生命を侵害する行為(殺人行為)と比べると、本人の意思に合致した死の惹起は法益侵害の程度が軽微なのも事実です。
そのため、自殺教唆罪は殺人罪よりも軽い範囲の法定刑が定められていると考えられます。
自殺教唆罪の公訴時効
自殺教唆事件を起こしたとしても、生涯逮捕リスクに晒されるわけではありません。
なぜなら、他の犯罪類型と同じように、自殺教唆罪にも「公訴時効」が適用されるからです。
公訴時効制度とは、「犯罪行為が終わったときから一定の公訴時効期間が経過することによって検察官の公訴提起権が消滅する制度」のことです(刑事訴訟法第253条第1項)。検察官の公訴提起権が消滅すると刑事裁判にかけられることはなくなるので、結果として、警察に逮捕される可能性も事実上消滅します。
自殺教唆罪の公訴時効期間は「10年」です(同法第250条第1項第3号)。つまり、自殺教唆をしてから10年が経過すると”時効逃げ切り”を達成できるということです。
自殺教唆罪と自殺関与罪・同意殺人罪の関係
刑法第202条に規定されている犯罪は、「自殺関与罪」と「同意殺人罪」です。そして、自殺関与罪は、「自殺教唆罪」と「自殺幇助罪」に区別されるという関係に立ちます。
- 自殺教唆罪:人を教唆して自殺させたとき
- 自殺幇助罪:人を幇助して自殺させたとき
- 同意殺人罪:嘱託を受けたり承諾を得て人を殺したとき
自殺関与罪と同意殺人罪の区別は、「『自殺者・被殺者の意思に合致した生命侵害』に対する”教唆・幇助的関与(自殺関与)”か”共同正犯的関与(同意殺人)”か」という違いしかありません。
また、自殺関与罪も同意殺人罪も同じ「6カ月以上7年以下の懲役刑・禁錮刑」という法定刑の範囲で処断されることに変わりはないので、自殺教唆罪・自殺幇助罪・自殺関与罪・同意殺人罪の違いを細かく考える必要はないでしょう。
自殺教唆と殺人教唆の違い
自殺教唆は「人を教唆して自殺させること」を処罰対象とするものです。
これに対して、殺人教唆は「人を教唆して殺人をさせること」を意味します(刑法第199条、同法第61条第1項)。
また、「殺人をさせるように教唆をしたが殺人結果が生じなかったとき」には、殺人未遂罪の教唆の容疑で逮捕されます。
自殺教唆で問われる可能性があるその他の犯罪類型
他人に対して自殺するように唆したとしても、自殺教唆罪以外の容疑で逮捕される可能性があります。
殺人罪の間接正犯
上述の通り、自殺教唆罪が成立するには「生命の主体による有効な自殺意思が存在すること」という要件を満たす必要があります。
つまり、自殺するように唆した結果、相手が自殺をしたとしても、そこに「有効な自殺意思」が存在しないときには、自殺教唆罪ではなく「殺人罪の間接正犯」が成立するということです。
殺人罪とは「人を殺したとき」に成立する犯罪類型のことです(刑法第199条)。殺人罪の法定刑は「死刑または無期懲役もしくは5年以上の懲役刑」です。
たとえば、自殺することの性格な意味を理解できない幼児や精神障害者を唆して自殺させたとき、執拗な暴行や脅迫を繰り返して自殺について正常に判断できない状態に追い込んで自死を選択させたとき、「後追い自殺をするから」と嘘をついて先に自殺をさせたときなどでは、自殺教唆罪ではなく殺人罪の間接正犯の容疑で逮捕されます。
脅迫罪
脅迫罪とは、「生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫したとき」「親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫したとき」に成立する犯罪類型のことです(刑法第222条第1項第2項)。脅迫罪の法定刑は、「2年以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑」です。
たとえば、「自殺をしないと殺すぞ」と伝えたとき、脅迫罪の容疑で逮捕される可能性があります。
強要未遂罪
強要罪とは、「生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知して脅迫したり、暴行を用いたりすることによって、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害したとき」「親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知して脅迫したり、暴行を用いたりすることによって、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害したとき」に成立する犯罪類型のことです(刑法第223条第1項第2項)。強要罪の法定刑は、「3年以下の懲役刑」です。
そして、強要罪は未遂犯も処罰対象にされています(同法第223条第3項)。
たとえば、暴力を振るって自殺をさせようとしたとき、電話で「自殺しないと家に火をつけるぞ」と伝えたとき、その時点で強要未遂罪の容疑をかけられます。
自殺教唆罪で逮捕されるときの刑事手続きの流れ
自殺教唆が警察に発覚すると、以下の刑事手続きの流れを経ることが多いです。
- 自殺教唆の容疑で警察に逮捕される
- 自殺教唆について警察段階の取調べが実施される
- 自殺教唆事件が送検される
- 自殺教唆について検察段階の取調べが実施される
- 検察官が自殺教唆事件を公訴提起するか判断する
- 自殺教唆事件が公開の刑事裁判にかけられる
自殺教唆罪の容疑で警察に逮捕される
自殺を教唆した事実が発覚すると警察に逮捕されます。
犯罪の性質上、自殺教唆罪で立件されるケースの大半は「通常逮捕手続き」の対象です。
通常逮捕とは、「裁判官の事前審査を経て発付される逮捕令状に基づいて実施される身柄拘束処分」のことです(刑事訴訟法第199条第1項)。
そして、逮捕状が発付されるのは、「逮捕の理由」「逮捕の必要性」の2つの要件を満たすときです(犯罪捜査規範第118条、同規範第122条)。
たとえば、自殺教唆事件が以下の要素を有するとき、逮捕状が発付されて通常逮捕手続きに移行するでしょう。
- 住所不定・無職・職業不詳で逃亡するおそれがある場合
- 過去に前科・前歴がある場合
- 自殺教唆について余罪への関与が疑われる場合
- 複数人で自殺教唆行為に及ぶなど、共犯の存在が疑われる場合
- 自殺教唆をしたときの証拠を隠滅するおそれがある場合
- 自殺教唆の結果、本人が死亡した場合
- 自殺教唆に関する任意の出頭要請を拒否したり事情聴取で黙秘・否認をした場合
- 自殺教唆の結果亡くなった本人家族の処罰感情が強い場合
- 自殺教唆ではなく殺人罪の成否が疑われる場合
逮捕状が執行されると、その時点で被疑者の身体・行動の自由は制限されます。「仕事が忙しいから別の日に出頭したい」「警察に連行される前に会社に電話をしたい」などの要望は一切聞き入れられず、そのまま警察署に連行されて取調べを受けなければいけません。
自殺教唆罪について警察段階の取調べが実施される
自殺教唆事件を起こして逮捕されると、警察段階の取調べが実施されます。
警察段階の取調べの制限時間は「48時間以内」です(刑事訴訟法第203条第1項)。
警察段階で実施される取調べには受忍義務があるので拒絶することはできません。また、取調べがない時間帯は留置場・拘置所に身柄が留められるので、日常生活からは完全に隔離されます。さらに、接見禁止処分が下されることが多いので、家族などとの面会も不可能です。
自殺教唆罪について警察から検察官に送致される
警察段階の取調べが終了すると、自殺教唆事件が検察官に送致されます(刑事訴訟法第246条本文)。
なお、刑事手続きには「微罪処分(警察限りの判断で刑事手続きを終了させる処分)」という処分類型が存在しますが、自殺教唆事件では微罪処分を獲得するのは現実的には厳しいでしょう。なぜなら、微罪処分の対象になるのは検察官があらかじめ指定した極めて軽微な犯罪類型に限られるところ、自殺教唆罪は微罪処分の対象に挙げられていないからです。
したがって、自殺教唆罪の容疑で逮捕されたときには、警察段階・検察段階それぞれで実施される取調べへの対応方法を熟慮したうえで「不起訴処分獲得」を目指すのが防御目標になると言えるでしょう。
自殺教唆罪について検察段階の取調べが実施される
逮捕後、警察段階の取調べが終了して送検されると、検察官による取調べが実施されます。
検察段階の取調べには「原則24時間以内」という制限時間が設けられています(刑事訴訟法第205条第1項)。「警察段階48時間と検察段階24時間を合わせた合計72時間」で得られた証拠や供述内容を前提として、検察官が自殺教唆事件を公訴提起するか判断します。
ただし、自殺教唆事件は慎重な捜査を必要とするケースが多いです。「身柄拘束付きの取調べは72時間以内に限られる」というルールを貫くと、検察官が正確な情報を前提に公訴提起判断できません。
そこで、「やむを得ない理由」があるときに限って、検察官による勾留請求が認められています(同法第206条第1項)。勾留請求が認められて裁判所が勾留状を発付すると、被疑者の身柄拘束期間は例外的に「10日間~20日間」の範囲で延長されます(同法第208条各項)。
自殺教唆罪の容疑で勾留請求される可能性がある「やむを得ない理由」として以下の事由が挙げられます。
- 自殺現場の状況について慎重に鑑定・実況見分をする必要がある場合
- 被害者が自殺ではなく他の死因で亡くなった可能性がある場合
- 被害者が自殺するに至った経緯や教唆・幇助の具体的内容について慎重な捜査活動を要する場合
- 複数の自殺教唆事件に関与した疑いがある場合
- 複数人の教唆行為によって被害者が自殺に追い込まれて、共犯関係を洗い出す必要がある場合
- 自殺教唆事件について被疑者が黙秘・否認している場合、供述内容に矛盾点がある場合
以上を踏まえると、自殺教唆罪の容疑で逮捕・勾留されると、身柄拘束期間が最長23日間に及ぶ危険性があるということです。これでは、仮に不起訴処分の獲得によって前科なしで刑事手続きを終結できたとしても、長期の身柄拘束期間が生じただけで社会生活にさまざまなデメリットが生じかねません。
したがって、自殺教唆罪の容疑で逮捕されたときには「勾留阻止活動」にも留意する必要があります。刑事弁護の取扱い実績豊富な弁護士へご相談のうえ、公訴提起判断までの期間の短縮化を目指した防御活動に専念してもらいましょう。
自殺教唆罪について検察官が公訴提起するか否かを判断する
検察段階の取調べが終了すると、自殺教唆事件を刑事裁判にかけるか否か(起訴か不起訴か)が判断されます。
- 起訴処分:自殺教唆事件を公開の刑事裁判にかける旨の訴訟行為
- 不起訴処分:下着泥棒事件を公開の刑事裁判にかけず、検察限りの判断で刑事手続きを終結させる旨の意思表示
日本の刑事裁判の有罪率は約99%とも言われています。つまり、刑事裁判にかけられた時点で、有罪になって前科がつくことがほぼ確定的になるということです。
したがって、「実刑判決だけは避けたい」「前科者になりたくない」と希望するなら「不起訴処分の獲得」は不可欠だと言えるでしょう。各法律事務所のHPを確認すれば過去の実績を確認できるので、不起訴処分の実績豊富な私選弁護人までご依頼ください。
自殺教唆罪について公開の刑事裁判にかけられる
自殺教唆罪の容疑で逮捕・起訴された後は、公開の刑事裁判が待っています。
まず、刑事裁判が開廷される時期は「起訴処分から1カ月~2カ月後」が目安です。起訴後の保釈手続きがスムーズに進めば、起訴処分から公判期日の間は自宅などに戻ることができます。これに対して、保釈請求が認められず起訴後勾留が続くと、公判期日や判決確定に至るまでの数カ月間日常生活に復帰できずに過ごさなければいけません。社会生活への支障を避けるなら、早期の保釈請求が不可欠でしょう。
次に、公判期日の回数は被疑者・被告人の認否に影響されます。たとえば、公訴事実に争いがなければ第1回公判期日で結審するのが通例です。これに対して、教唆行為自体を争うなどの否認事件では複数の公判期日を経て弁論手続き・証拠調べ手続きが行われます。
自殺教唆罪の法定刑が「6カ月以上7年以下の懲役刑・禁錮刑」であることを踏まえると、自殺教唆罪の容疑で逮捕・起訴されたときには「執行猶予付き判決を獲得できるか」がポイントになります。実刑判決が確定すると社会復帰が極めて困難になるので、刑事裁判経験豊富な弁護士までご相談のうえ、酌量減軽などの防御方法を尽くしてもらいましょう。
自殺教唆で逮捕されたときに生じるデメリット5つ
自殺教唆罪で逮捕されると、以下5点のデメリットが生じる可能性があります。
- 自殺教唆罪で逮捕されると実名報道リスクに晒される
- 自殺教唆罪で逮捕されると長期間身柄拘束されかねない
- 自殺教唆罪で逮捕・起訴されたことが勤務先にバレると懲戒処分が下される
- 自殺教唆罪で逮捕・起訴されたことが学校にバレると何かしらの処分が下される
- 自殺教唆罪で逮捕・起訴されると前科によるデメリットが生じる
自殺教唆罪で逮捕されると実名報道される可能性がある
自殺教唆罪の容疑で逮捕された段階で顔写真付きで実名報道される危険性に晒されます。
そもそも、すべての刑事事件が報道されるわけではありません。話題性を集めるトピックや重大犯罪などを起こして逮捕されたときに報道番組やネットニュースで配信されるのが実情です。
そして、自殺教唆事件は世間的な関心が高いニュースに位置付けられるので、自殺教唆罪の容疑で逮捕されたときには全国またはローカルニュースで報道される可能性が高いです。
顔写真付きで実名報道されるとインターネット上に自殺教唆事件のことが未来永劫残り続けます。たとえば、学生時代の同級生や転職活動先の企業に名前をネット検索されただけで、過去に自殺教唆事件を起こしたこと(逮捕されたこと)がバレてしまいます。これでは、自殺教唆事件について刑事責任を果たし終わったとしても社会復帰が難しくなりかねないでしょう。
実名報道リスクを避けるには、「自殺教唆事件を起こしたことがバレたとしても逮捕されないこと」が重要です。自殺教唆事件が警察に発覚する前なら、事前に弁護士へ相談することで在宅事件処理を目指すことも可能なので、出来るだけ早いタイミングで刑事事件実績豊富な弁護士までお問い合わせください。
自殺教唆罪で逮捕されると長期間身柄拘束される可能性がある
自殺教唆事件を起こしたことが警察に発覚すると、逮捕・勾留によって長期間身柄拘束される危険性に晒されます。
逮捕段階だけでも72時間、勾留請求されると最長23日間の身柄拘束期間が生じかねません。しかも、逮捕・勾留中はスマートフォンなどの所持品がすべて取り上げられるので被疑者本人は外部と一切連絡をとることが禁止されます。さらに、逮捕・勾留中に接見禁止処分が下されると、弁護士以外の第三者はたとえ家族であったとしても面会することができません。
たとえば、数日~数週間拘置所に収監されると、その期間は会社に理由を説明できないまま欠勤が続きます。無断欠勤がこれだけの期間に及ぶと、それだけで懲戒処分の対象になりかねないでしょう。また、身柄拘束期間中は厳しい拘置所生活を強いられるので、心身に過度のストレスが発生します。
逮捕・勾留によって生じる身柄拘束期間への対策としては、「自殺教唆事件を在宅事件処理の対象にする」「逮捕されたとしても勾留阻止活動に専念する」ことが近道になります。弁護士へ相談するタイミングが早いほど身柄拘束処分回避の可能性が高まるので、すみやかにお問い合わせください。
自殺教唆罪で逮捕されたことが会社にバレると懲戒処分が下される可能性がある
自殺教唆罪の容疑で逮捕されたことが会社にバレると、就業規則の懲戒規定に基づいて懲戒処分が下されます。
懲戒処分の種類は、「戒告・譴責・訓告・減給・出勤停止・降格・諭旨解雇・懲戒解雇」です。
たとえば、斟酌に値するやむを得ない理由によて自殺教唆罪に及んでしまったときには比較的軽い懲戒処分で済む可能性があります。これに対して、犯罪に対して厳しい懲戒規定を定めている企業の場合には、自殺教唆罪で有罪になったことを理由に懲戒解雇処分が下されることもあるでしょう。
会社からの懲戒処分を避けるには、「自殺教唆事件を起こした事実を会社に隠し通すこと」が重要な防御方針になります。在宅事件処理になれば身柄拘束をきっかけに会社バレする自体を回避できるので、出来るだけ早いタイミングで刑事事件実績豊富な弁護士までご相談ください。
自殺教唆罪で逮捕されたことが学校にバレると何かしらの処分が下される可能性がある
学生が自殺教唆罪の容疑で逮捕された場合、学校にバレて何かしらの処分が下される可能性があります。
学校から下される処分内容は学則・校則のルールに沿って決定されます。
たとえば、学生の犯罪に対して厳しい考え方をもつ学校の場合には、自殺教唆罪で逮捕・起訴されただけでも退学処分を下されることもあるでしょう。これに対して、当該学生の普段の様子などを総合的に考慮した結果、更生教育の余地があると判断されたときには、出席停止・有期の停学処分・厳重注意などの軽い処分で済む可能性もあり得ます。
今後の人生を考えて学歴にキズが付くことを避けたいのなら、「学校バレを防ぐこと=身柄拘束処分を回避すること=在宅事件化を目指すこと」が重要です。出来るだけ早いタイミングで弁護士へ相談のうえ、自首などの幅広い選択肢について検討してもらいましょう。
自殺教唆罪で逮捕・起訴されると前科がつく可能性がある
自殺教唆罪の容疑で逮捕・起訴されると有罪判決が確定する可能性が高いです。
そして、自殺教唆罪について判決が確定したときには、刑事罰だけではなく「前科」が付く点に注意しなければいけません。
前科者になると、今後の社会生活に以下のデメリットが生じます。
- 前科情報は履歴書の賞罰欄への記載義務が生じるので、自殺教唆罪で有罪になると今後の就職活動・転職活動が困難になる
- 自殺教唆罪の容疑で有罪になると、前科を理由に就業制限が生じる職業・資格がある(士業・警備員・金融業など)
- 自殺教唆罪で逮捕・有罪になったことを理由に配偶者から離婚を求められると拒絶できない(法定離婚事由に該当するため)
- 自殺教唆での前科を理由にビザ・パスポートの発給制限を受けると、自由に海外旅行・海外出張できなくなる
- 前科者が再犯に及ぶと、刑事処分が厳しくなる危険性が高い
前科によるデメリットを避けるには、「不起訴処分を獲得すること」が何より重要です。刑事裁判で反論を主張しても受け入れられる可能性は低いので、自殺教唆罪の容疑で逮捕された時点ですみやかに刑事事件経験豊富な弁護士までお問い合わせください。
自殺教唆罪の容疑をかけられたときに弁護士へ相談するメリット3つ
自殺教唆事件を起こしたときや、自殺教唆罪の容疑で逮捕されたときには、私選弁護人への相談をおすすめします。
なぜなら、刑事事件に強い弁護士への相談によって以下3点のメリットを得られるからです。
- 被害者家族との間での示談交渉を検討してくれる
- 少しでも軽い刑事処分獲得を目指してくれる
- 弁護士接見をフル活用して身柄拘束中の被疑者に対してさまざまなメリットをもたらしてくれる
被害者家族との間で示談交渉を進めてくれる
自殺教唆事件には直接の被害者は存在しません。そのため、「被害者との示談交渉」という方法が直接的に軽い刑事処罰に繋がることは考えにくいでしょう。
ただし、自殺教唆事件の経緯次第では、自殺して亡くなった本人の家族との間で何かしらの民事的な合意を取り付けることが可能です。形式上は「参考人」という位置付けではありますが、「ご遺族の同意を得ていること」が斟酌された結果、不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得可能性が高まることもあります。
弁護士は、感情的になっている遺族との間でも冷静に話し合いを進めて、常識的な範囲の示談条件で和解契約締結を目指してくれるでしょう。
少しでも軽い刑事処分獲得を目指してくれる
自殺教唆事件で刑事訴追されるおそれがあるときや逮捕されたときにはすみやかに私選弁護人までご依頼ください。
というのも、以下のように、弁護士は刑事手続きの段階ごとに適切な防御目標を設定して軽い刑事処分獲得を目指してくれるからです。
- 自殺教唆罪の容疑で逮捕される前:自首、在宅事件処理
- 自殺教唆罪の容疑で逮捕された後:勾留阻止活動、不起訴処分の獲得
- 自殺教唆罪の容疑で起訴された後:保釈請求
- 自殺教唆罪の容疑について刑事裁判にかけられた後:執行猶予付き判決獲得
自首
過去に起こした自殺教唆事件が警察にバレていない段階なら、「自首」という選択肢が防御活動上の効果を発することもあります。
自首とは「まだ捜査機関に発覚しない前に、犯人自ら進んで自殺教唆行為に及んだ事実を申告し、刑事処罰を求める意思表示」のことです(刑法第42条第1項)。自首が有効に成立すれば「刑の任意的減軽」というメリットを得られます。
たとえば、自殺教唆罪の容疑で逮捕・起訴されたとしても、「自首減軽」の結果、執行猶予付き判決を獲得しやすくなるでしょう。また、自首をした態度が評価されて、逮捕処分ではなく在宅事件として刑事手続きが進められる可能性も高まります。
警察から連絡がない段階で弁護士へ相談すれば、「そもそも自首するべき事案なのか」「自首をした後にどのような取調べが想定されるのか」「自首をした後の事情聴取でどのような供述をするべきなのか」について判断してくれるので、有利な刑事処分を獲得しやすくなるでしょう。
在宅事件
過去に起こした自殺教唆事件が警察にバレていないときや、警察に発覚したとしても逮捕・勾留という身柄拘束処分が実施されていない段階なら、「在宅事件」を目指すのも選択肢のひとつです。
在宅事件とは、「逮捕・勾留という身柄拘束処分を付することなく任意捜査の対象として取り扱う事件類型」のことです。捜査対象者には取調べの受忍義務が課されないので、比較的柔軟な形で捜査活動に強力することができます。
たとえば、事情聴取の日程について捜査機関側とスケジューリングできますし、事情聴取を途中で切り上げて自由に帰宅することも可能です。
自殺教唆事件が在宅事件の対象になるのケースとして、以下のものが挙げられます。
- 氏名・住所・職業が明らかで逃亡のおそれがない場合
- 捜査機関の要請に応じて出頭し、事情聴取で犯行を自供している場合
- 自殺した本人の家族との間で民事的な解決方法について和解が成立している場合
- 自殺教唆の経緯について疑わしい点がなく、殺人罪(殺人罪の間接正犯)の成否が問題になることはない場合
- 自殺教唆に及んだときの証拠物(スマートフォンなど)を隠蔽するおそれがない場合、捜査機関に提出している場合
- 自殺教唆行為が組織的に行われたわけではなく、単独犯として実行された場合
- 捜査対象者に前科・前歴がない場合
在宅事件の対象になるには、「逃亡・証拠隠滅のおそれがないこと」を捜査機関側に丁寧に伝えなければいけません。
適宜私選弁護人と相談のうえ、在宅事件処理が継続するような供述内容についてアドバイスを提供してもらいましょう。
勾留阻止
自殺教唆罪の容疑で逮捕された後は、「勾留されないこと」が重要です。
なぜなら、勾留請求されると身柄拘束期間が数週間延長されてしまうからです。
自殺教唆罪の容疑で逮捕されたときには、「不起訴処分を獲得すること」だけではなく、「身柄拘束処分を短期間で済ませること」も同時並行的に考慮しなければいけません。
取調べに対して協力的な姿勢を見せたり、誠実に自殺教唆行為に至った情状要素を丁寧に回答するなど、勾留阻止に向けた防御活動に専念してください。
不起訴処分
自殺教唆罪の容疑で逮捕されたときには、「不起訴処分の獲得」が最大の防御活動になります。
そもそも、「自殺教唆事件を起こした以上、刑事裁判は覚悟しなければいけない」というのは間違いです。なぜなら、不起訴処分は以下3種類に分類されるので、誤認逮捕や証拠不十分以外のケースでも起訴処分回避の道は残されているからです。
- 嫌疑なし:自殺教唆事件に関与した証拠がない場合、誤認逮捕・冤罪の場合
- 嫌疑不十分:自殺教唆罪を立証する証拠が不足している場合
- 起訴猶予:自殺教唆事件に関与したことに間違いはないが、諸般の事情を総合的に考慮すると刑事裁判にかける必要がない場合
自殺教唆事件に関与した事実に疑いがないケースでは、「起訴猶予処分」獲得が防御目標になります。
起訴猶予に付するか否かを判断するときには、「犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況」などの諸般の事情が総合的に考慮されます(刑事訴訟法第248条)。
起訴処分は「事実上の有罪」と同義です。今後の社会復帰の可能性を高めるには起訴猶予処分の獲得が不可欠なので、限られた時間のなかで、弁護士に効率的な防御活動を展開してもらいましょう。
保釈請求
自殺教唆罪の容疑で逮捕・起訴された後は、すみやかに「保釈手続き」を進める必要があります。
なぜなら、起訴された段階で保釈請求が通らなければ「起訴後勾留」によって刑事裁判の期日まで身柄を拘束され続けるからです(刑事訴訟法第60条第1項、第2項)。たとえば、仮に刑事裁判で執行猶予付き判決を獲得できたとしても、起訴後勾留によって数カ月の欠勤期間が生じただけで懲戒処分が下されかねません。
保釈請求は以下3種類に大別されます。刑事手続きの状況を踏まえて適切な保釈手続きを履践してもらいましょう。
- 権利保釈(保釈除外事由に該当しない限り認められる保釈)
- 裁量保釈(裁判官の裁量によって認められる保釈)
- 義務的保釈(身柄拘束期間が不当に長期化している場合に認められる保釈)
執行猶予付き判決
自殺教唆罪の容疑で起訴された後は、「執行猶予付き判決の獲得」が防御目標になります。
なぜなら、実刑判決が下されると刑期を満了するまで服役を強いられるからです。自殺教唆罪の法定刑は「6カ月以上7年以下の懲役刑・禁錮刑」と定められているので、実刑判決が確定すると今後の社会復帰が困難になります。
執行猶予付き判決とは、「被告人の犯情や事件の諸般の事情を考慮して刑の執行を一定期間猶予できる制度」のことです。執行猶予期間中にトラブルがなければ、実刑が下されることなく刑事責任を果たしたことになります。また、猶予期間中は今まで通りの日常生活を送ることもできます。
ただし、執行猶予付き判決を獲得するには、「3年以下の懲役刑・禁錮刑・50万円以下の罰金刑の言渡しを受けたとき」という要件を満たさなければいけません(刑法第25条第1項)。つまり、自殺教唆罪の容疑で逮捕・起訴されたときには、「3年以下の懲役刑・禁錮刑」というラインまで量刑を引き下げるための防御活動が不可欠だということです。
したがって、自殺教唆罪の容疑で起訴されたときには、刑事裁判実績豊富な私選弁護人に依頼をして、酌量減軽などを目指して防御活動を展開してもらうべきだと言えるでしょう。
身柄拘束中の被疑者に弁護士接見を通じてアドバイスを提供してくれる
自殺教唆罪の容疑で逮捕・勾留されると、接見禁止処分が下されることが多いため、被疑者は家族・知人などの第三者と一切面会することはできません。
これに対して、被疑者には「接見交通権」が認められているので、弁護士とはいつでも自由に面会でき、また、書類・物の授受をすることも許されます(刑事訴訟法第39条第1項)。
厳しい取調べが継続するなか、被疑者にとって唯一の味方である弁護士と接見することによって、以下のメリットが生じるでしょう。
- 身柄拘束によって厳しい生活を強いられている被疑者を励ましてくれる
- 「被疑者ノート」を手渡して違法な捜査活動を牽制してくれる
- 取調べでの供述方針を明確化してくれる
- 供述調書に署名・押印するときの注意点や確認点を教えてくれる
自殺教唆罪に問われたときはすみやかに弁護士へ相談しよう
どのような経緯があったとしても、他人の自殺を教唆することは犯罪です。自殺教唆罪の容疑をかけられた時点で厳しい刑事手続きに巻き込まれることを覚悟しなければいけません。
当サイトでは、自殺教唆罪などの取扱い実績豊富な弁護士を多数掲載しています。
「身柄拘束処分を回避するため」「不起訴処分・執行猶予付き判決を獲得するため」には刑事事件を専門とする弁護士のサポートが不可欠なので、お心当たりの方は出来るだけ早いタイミングで信頼できそうな法律事務所までお問い合わせください。